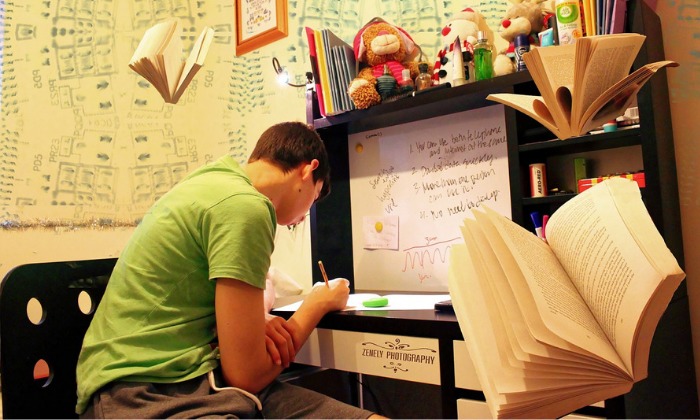今回は【進学校を目指せるかどうかの分岐点は小学3年生】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小3が学力の分岐点になる理由は様々ありますが、大都市圏の事情と地方でも少数派ながら中学受験組の存在は無視できません。
地方でも中学受験組の子は小学3年生の2月、小4頃から塾通いを始める子が多いこともあり、中学受験に向けた動きが本格化する直前期の小3までに【受験塾に入って勉強についていけるをするかどうか】の判断がされるケースが多いです。
そのため、小学3年生でしっかり基礎学力を仕上げるために家庭学習で鍛えている子もいれば、まだまだ小学校生活は長いと捉えている親子もいたり、小学生時代は勉強は宿題をやっていれば良いという考えの家庭もあったりと、小学校2年生以上に学力差や授業で学ぶ単元の理解力の違いが出てきます。
それでも、親世代にとっては【自分たちの時は低学年と呼ばれていた小学3年生】ですから、あまり学力差に対する危機感を持ちにくいです。
親の教育に対する温度差が子どもに影響するのは周知の事実ですが、その差が出始めるのが小学校3年生であり、この時点で【高校受験で進学校を目指せるかどうか】がおおよそ見えてきます。
小学3年と聞いて早いと思う方もいるはずです。
一般的に学力差が出るのは小学4年生位と言われています。
私も小学生の時は学力差がそんなにハッキリするとは思っていませんでした。
塾で働いていなければ子育てをしていても【まさか小学3年生で進学校に進めそうかどうか分かるの?】と半信半疑になっていたことでしょう。
小学3年生は、【勉強のやり方】や【学びに対する子どもの気持ちもだいぶ異なる】ということが目立ち始めてきて、抽象的思考や読解力も少しずつ必要になってきます。
ですから、小学3年生の学力、勉強との向き合い方はその後の学力形成に大きな影響を与える分岐点となります。
そこで今回は、なぜ、小学3年生で進学校に入れるかどうか見えてくるのかを考えていきます。
学習習慣の差が学力差に直結する
まず、小3の時点で家庭学習の習慣や基礎学力に差がつきはじめ、4年生以降の吸収力に直結します。
子どもによって【学習習慣】があるかどうか決まる時期であり、毎日の宿題や家庭学習の有無で、基礎学力に差がつきやすくなります。
家庭学習の習慣がついていないと当然ながら学校で学んだ内容がすんなり理解できなくなります。
十分に理解するには復習をする必要があります。
その復習もサラッと勉強したら済むものではなく、子どもによっては何度も教科書を読みながら基礎問題を解いていき、ようやく何も見ずに問題が解けるようになるという努力が不可欠だったりもします。
ただ、家で勉強する習慣というのは一部のごく少数の子を除くと、親のサポート、下準備が不可欠です。
親が就学前後から【家で宿題と家庭で準備した教材を勉強する子に育てる】【自分から進んで勉強する子になるように】という明確な目標を掲げて、家庭学習の定着を誘導していきます。
こうした誘導をせず、【子どもが成長したら勝手に勉強するはず】と考えている親の子は、ほぼ例外なく学習習慣が定着しなかったり、勉強と言えば宿題のみという子が多いです。
もちろん、そういう子の中にも学校の授業だけを聞いてテストで満点、高得点連発する子も少数ながらいます。
とはいえ、家庭学習を全くしないという状態が続いていれば遅かれ早かれどこかで学力が頭打ちします。
この場合の頭打ちというのは、テストで点数が取れないという意味になります。
【2年生の頃はそこそこ良い点数も取っていたのに80点台ばかりが増えた】
【満点が全く取れなくなった】
こんな風になかなか点数が取れなくなってくる子は小学3年生のクラスでチラホラ出てきます。
特に差が出るのは漢字、算数の三桁の計算や表とグラフなどの単元です。
【いつもよりも難しい】という単元のテストでは70点台の子もかなり多くなります。
思考力や抽象的な学びを理解する力の差が出始める
さて、親としては小学校3年生はまだまだ子どもという感覚で接しますが、学校の勉強を見てみると【具体から抽象】への思考力を問うような問題も少しずつ学ぶ時期になります。
算数で言えば図形問題や文章題の理解力に影響が出てきます。
子ども③が算数の宿題で文章題を解いていた時に、問題の計算自体は簡単なのですが、公立小の宿題にしては文章が長いと感じて、【この問題文、1回でどんな意味なのか分からな子もいるのでは?】と聞いたところ、【いるよ。長くて何が言いたいのか分からないんだって】と教えてくれました。
思考力や抽象的な学びが本格化するのは4年生になってからですが、3年生でも【視覚で判断がつきにくい学び】や【比喩】【立体のイメージ】などが理解できる子と、よく分からに子に二分されてきます。
算数の図形や、理科の実験の理解に大きく関わってくるということに、子どもが小学3年生の時点で気がつく、というのはなかなか難しい面はあります。
しかし、小学3年生での学びは確実に難化していきます。
小学校1年生や2年生の感覚で勉強をしていると、つまりは学習不足が積み重なると小学4年生の勉強を十分理解できなくなります。
そして、3年生では理科と社会が本格的に始まり、授業で勉強する教科数が増えることでテストの回数も増えますし、国語、算数、理科と社会と教科ごとに異なる学習方法、内容に適応する必要が出てきます。
【理科は好きだけど国語は苦手】という好き嫌いの意識が芽生え始めてきます。
理科も社会も【何となく】で答えが出る学問ではなく、データを見て考察をしたり、地形の特徴からどんな農産物を育てるのに適しているのかといった【条件を見て考えて答えを出す学び】です。
低学年の頃に学んだ基礎学力を土台に、【こうなったらどうなるのか】と頭の中で考える勉強の色が少しずつ濃くなってくるのが小学校3年生です。
この学年で勉強に躓き、学習意欲が低下してくると【進学校への道】というのはかなり厳しいものになってきます。
学びへのモチベーションやの違いが目立ってくる
ところで、勉強が【できる】【わかる】と感じられるかどうかが、学びへのモチベーションに直結します。
ここでつまずくと、【自分は勉強が苦手】という意識を持ちやすくなります。
私も塾で仕事をしている時に感じましたが、学業不振の子ほど【自分は勉強したって成績が上がるわけない】とマイナス思考が強い子が多かったです。
勉強に対する心理というのは小学校3年生から4年生頃に個人個人異なる印象を持つようになります。
自分から勉強に向かう姿勢ができている子は小学校3年生以降の勉強にも乗りやすくなり、小4の壁も乗り越えられる力を蓄えることができます。
反対に、勉強に対して嫌な感情を抱いている子は小3の勉強で躓くことが多くなり、小4の壁にぶつかってしまい、【自分は勉強はダメな子】と固定観念を強めていきます。
さらに、やる気がないように見えるので親から【怠けてる】と誤解されやすくなり、叱られることでますます勉強から心が離れていきます。
また、心の成長に伴い同級生の出来不出来を気にし、自分と比べる子もいます。
【劣等感を抱きやすくなる年齢に突入する】というタイミングでもあるので、親としては子どもの学習面の不安がどんどん増して来ると思いますが、子どもの気持ちも理解しましょう。
【どうしたら前向きに勉強に取り組んでくれるのか】という視点を持って家庭学習のプランを考えてみたり、少しでも学校のテストで【勉強したら久しぶりに高得点が取れた】となるにはどういうことに取り組めば良いのか子どもと話し合ってみてください。
小学校3年生時点で【遅れている】と感じても、まだまだ挽回は可能です。
小学校2年分を復習しつつ、現在学んでいる小学校3年生の内容をしっかりと、子どもに合ったペースで地道に学習習慣と基礎力をつけていくことで、進学校を目指せる軌道に乗れるようになります。