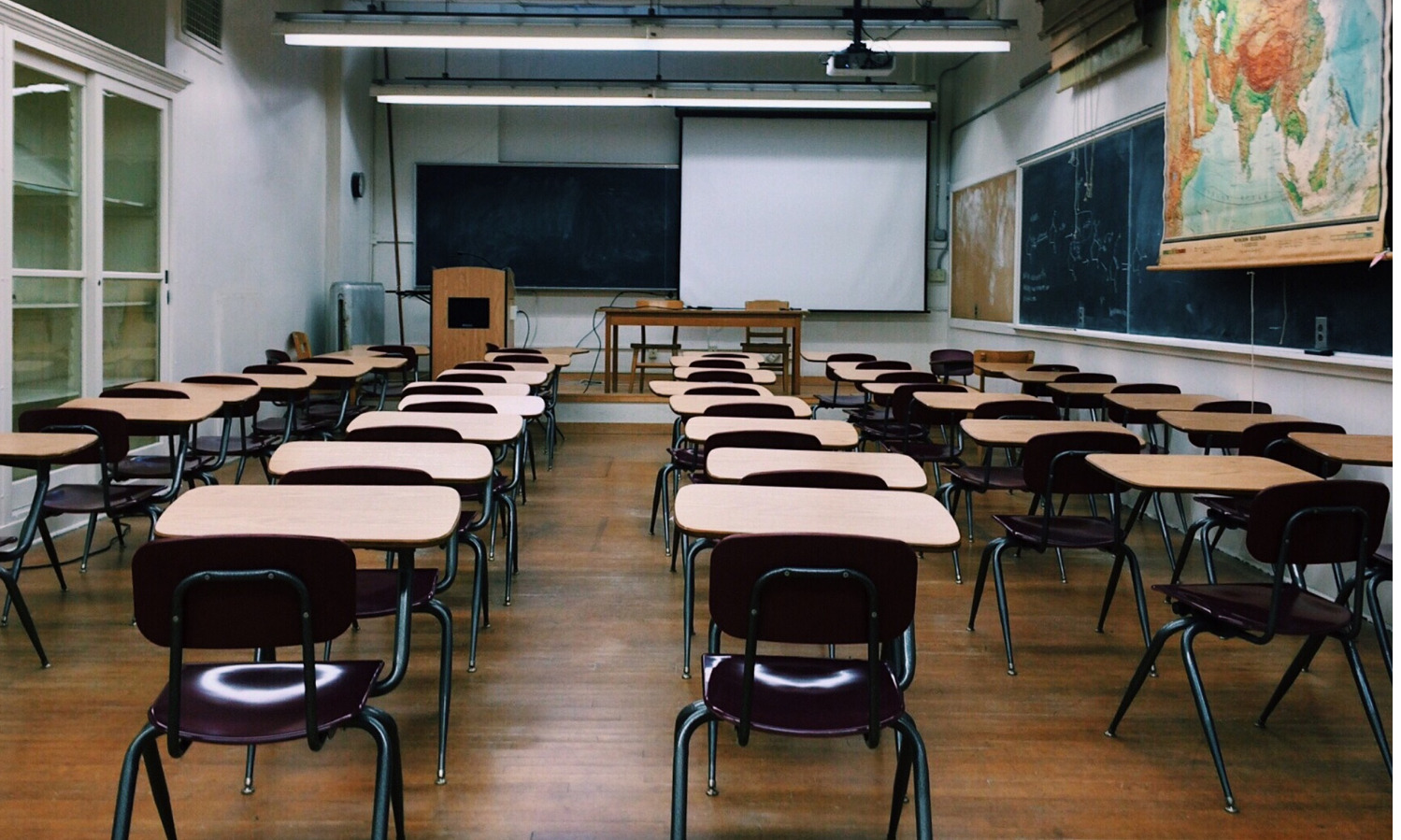今回は【子どもが勝手に勉強する子に育つ親の特徴】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子どもの自主性や学びに対する興味を自然に引き出すための関わり方が上手、という親はいます。
「あんな風に我が子も育って欲しいな」と思い、その人の真似しようにも、どうすればよいか分からなかったり、「自分にはできるか?」と自信が持てない方もいることでしょう。
私が塾で出会った賢い子、自分から勉強する子の親というのは、子どもが小学生時代に圧力をかける雰囲気ではなく、どんな態度で勉強しているかを観察している、というのを感じました。
【何となく様子を見る】なので、子どもの方はジロジロ観察されている、監視されているという感覚ゼロです。
我が家の子ども②③もそうですが、子どもの性格によっては勉強中にジロジロ見られるのを極端に嫌がる子はいます。
親としては気になるから近づいたり、【どう?】と声がけをしてしまうのですが、子ども的にはそうした親の行動というのは集中力をブツリと切ってしまうことなので、子どもの性格を踏まえて【うちの子が勝手に勉強する子に育つ道】を探すことが必要です。
【勝手に勉強する子】を育てる親は、子どもの自主性を尊重し、学びを楽しむ環境を整えることに長けています。
例えば、親自身が学ぶ姿勢を見せることで、子どもにとって【学ぶこと】が自然な行動として映ります。
また、親が過度に干渉せず、子どもが自分で選択し、試行錯誤できる自由を与えることも重要です。
さらに、努力の過程を褒めることで、結果だけでなくプロセスを大切にする価値観を育てます。
こうした接し方を心がけて子育てをしていると、子どもは失敗を恐れず挑戦する心を持つようになります。
親の関わり方次第で、子どもが自発的に学ぶ力を身につけることができるという認識をまずは持ってください。
【元からあの子は頭が良い】ではなく、その子の親が自然と、または色々と考えた上で【自発的に勉強する子に育つような下地作り】をしてきているのです。
それでは、具体的にどのような特徴があるのかご紹介していきます。
子どものリアルな課題を把握している
まず、勝手に勉強する子に育ててしまう親は【子どものリアルな課題】を把握しています。
子どもの勉強面でのリアルな課題を把握するためには、子どもの様子、何か困っていることはないかという心理面の変化を感じ取れるような親子のコミュニケーションや、テストの点数の変化に気がついているかが鍵となります。
普段とちょっと違う様子、元気がないことに気がつき、子どもから【何が難しいと思っているのか】【授業でわからないと感じていることはあるか】を聞くことで、直接的に課題を知ることができます。
【どの教科が一番好き?】や【最近だとどの宿題が大変だった?】など、ざっくばらんな質問をすることでただ、ストレートに聞いて素直に答えるというのはそれだけ親子関係がしっかりしているともいえます。
そこに至るまでには小さい頃から子どもの話を聞いて、適切なアドバイスを送ってきたという実績、積み重ねがあってのことです。
ダイレクトに勉強のことを聞くと子どもが【うるさい】と一蹴するのは、いつもガミガミ叱ってくるからなので、リアルな課題を子どもから聞き出したいのであれば親子関係を良いものにするよう努力する必要があります。
また、子どもが勉強に対して苦手意識やプレッシャーがある場合、それをすぐにキャッチし課題克服につながるサポートが瞬時にできる親だと、子どもは安心して勉強に打ち込むことができます。
学校の授業中の理解度について子どもと話をし、得意不得意な教科や単元を把握しています。
カラーテストが戻ってきたら確認するのが面倒になってくる親もいるので、宿題やテストの答案を注意深く見てみましょう。
ミスが多い部分やどのタイプの問題に苦戦しているのかが課題のヒントとなります。
明らかに成績が下がってきている時は、子どもでも分かりやすいよう科目ごとに理解度や取り組みやすさについて簡単なチェックリストを作り、一緒に記入してみてください。
これにより課題が明確になるだけでなく、子どもが親に対して【頼りがいがある】【困った時はすぐに親に相談しよう】と思うようになります。
定期的に勉強の大切さや将来の話をしている
さて、自発的に勉強する子の親というのは子どもに勉強の大切さを伝え、将来の話をしています。
ただ単に【やらないといけない】とか【この世の中は学歴が大切】というものではなく、現実的な具体例を示し、実際にその努力が報われるまでの道筋を示すことで、子どもの将来の夢を叶えるための道のりを考えるきっかけをつくり、学びの重要性を納得させることができます。
子どもはどうしても時の流れがゆっくりで、まだまだ子ども時代が続くと勘違いしてしまうところがありますが、確実に大人への道を歩いていきます。
しかも、【あと何年後には中学進学】【高校受験までに残されているのはあと何年】というのがハッキリしています。
小学生時代や中学生時代は自分がなりたい道に進むための選択肢を広げられるか、それとも狭めてしまうのかという極めて重要な時期になります。
親もそのことを理解し、【今から親として子どもに伝えられることはないか】と考え、子どものためを思って勉強の大切さ、将来のことを考えることを促す会話を心がけています。
また、勉強だけでなく、子どもが興味を持っていることや夢を中心に話をすることで、勉強がただの義務ではなく、目標達成のための手段であると理解させることができます。
そして、【子どもが自分から勉強する子】に育ったという親は子どもの考えを尊重します。
子どもの考えを尊重するというのは、わがままな子になるという意見もありますが、子どもが自分の考えを踏まえて【こうしたい】と決めたことを尊重し、だけれど宣言したからには最後まで頑張るようにくぎを刺せる人です。
受験で言えば、志望校を決める時に子どもの考えを尊重してこの学校に決めるというものが一番わかりやすいでしょうか。
ただ、親の思惑で受験校を決めるという家庭もいますが、そういう家庭の子は親の言われるがままに勉強している分、自発的に勉強しようという意欲がどうしても出てきません。
受験期の【あともう踏ん張り】が期待できません。
これでは自分から勉強する子には育たないでしょう。
今から声がけを変えていくには、勉強や将来に関する話をする際、叱るような口調や否定的な意見は避け、励ましや肯定的なコメントを多く含めるよう心がけましょう。
勉強や将来の話を特別な場で行うよりも、日常の会話の中でさりげなく触れることで、子どもにプレッシャーを与えずに意識を育むことができます。
親がゲームや動画視聴三昧をしていない
そして、子どもが勝手に勉強するようになるには【親がゲームや動画視聴三昧】ではない、ということが大きなポイントになります。
親がゲームや動画視聴に費やしてばかりだと子どもと過ごす時間は減るだけでなく、【勉強しなさい】という言葉が子どもの心に響かず、【親もやっているのに】という不満が募るなど子どもに悪影響を及ぼします。
どうしても、ゲームや動画視聴をしていると周囲のことを気にしなくなり、大人であっても【もう少しだけ】とズルズルと続けてしまいます。
これでは親としての示しがつきません。
ゲームや動画視聴を控えることで 親が子どもと会話する時間を設けることができますし、そもそも子どもの様子に気を配ることにもつながります。
子どもの方も親と過ごす時間が増えることで安心感や信頼感を感じやすくなり、親子関係が深まります。
ゲームであればカードゲームやボードゲームといった親子で楽しめる、会話が弾むゲームをすると親子関係の安定につながります。
親が家庭内でバランスの取れた生活スタイルを示すことで、子どもも自然と健全な習慣を学ぶことができます。
一方で、親の趣味や娯楽を完全に排除する必要はありません。
重要なのはバランスを取ることです。
親が自分の時間を大切にすることで、子どもにメリハリをつけて過ごすことのメリットやリラックスの大切さを伝えることもできます。
仕事に関する勉強もするけれど、趣味も大切にする姿を子どもはみているので、それを参考に【自分もこういう風になりたい】と思い、しっかり勉強しようという気持ちを持ち、成長していきます。