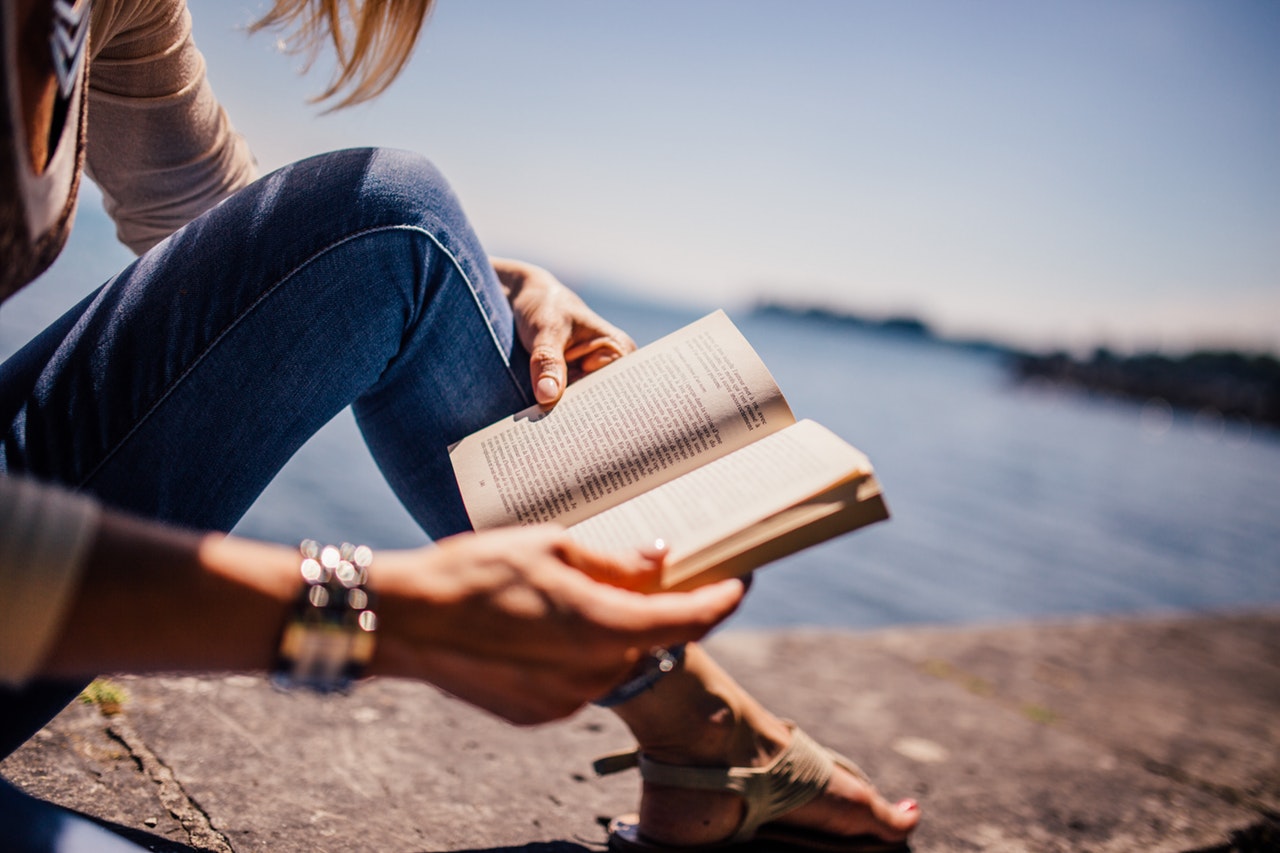教育改革が迫っていることもあり、家庭教育本の世界もそれに向けた本が多く出版されてきています。
何か得たいが知れないものが迫ってくると、不安を煽って購買力を高める商法ですね・笑。
さて、今回は、乱売されている家庭教育本のなかから【読んでおいた方が良い】本を紹介したいと思います。
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
今、読んでおくべき本とは?
個人的に、たくさんの家庭教育本を読んできました。
今、親が読むべき本はどれか?と考えたときに選ぶポイントが4つあります。
- 国語に関する本
- 算数・数学に関する本
- AIに関する本
- 世界に通用する系の本
サクッと書きましたが、こんな感じです。
子供たちが社会に出て役に立つ力をつけさせて欲しい!!、と産業界からの圧力もあって今回の教育改革が断行される背景があります。
つまり、社会人としてスキル高め人間にさせる準備をしといたほうが得策、ということになりますよね。
得策と言うと、浅い感じがありますが、さらに【生きる力】を身につけさせることが重要視されてくると推測しています。
流れに乗るのではなく、自分が流れを作る、という人間ですね。
それでは、順を追ってそれぞれ説明していきましょう!
1. 求められる国語能力が変わる

2020年度の大学入試(国公立の1次)はセンター試験に替わり新入試制度がスタートします。
まだ手探り状態ですが、行われたプレトではとくに国語が大幅に変更した印象があります。
文部科学省のHPから問題を入手することができますが、読みにくいので、ここでは読みやすい高校生新聞のサイトリンクを貼っておきます。
まぁ、親世代とは違う形式を導入していますね。
この問題を時間内にキレイに書ける子はそう多くいないのです。
書く力=社会に出て超重要視される力、とも言えます。
資料を読み込む力がない、プレゼン準備の原稿が書けない人が大量発生していることの裏返しなのでしょうね。
たしかに、学校では【文章作成】を教えてくれません。
自力でやるしかないのです。
新しい入試は記述系が多いから、学校でも習うのでは?と思いたくなります。
しかしカリキュラムがきつい現状をみると、時間を割くことは不可能。
つまり、家庭や通信、個人の作文や論文教室を受講するるしかないのです。
では、どうやって国語能力を上げていけばいいのか、違くなるといってもどの程度変わるのか分からないですよね。
そういった疑問を解消してくれるのが出口汪先生の国語が変わる 答えは「探す」から「創る」へ わが子の学力を伸ばす方法です。
[amazonjs asin=”4864700400″ locale=”JP” title=”国語が変わる 答えは「探す」から「創る」へ わが子の学力を伸ばす方法”]
大学入試の現代国語のカリスマ先生として有名ですが、最近は小学生向けの問題集も多数出版しています。
先生的に、論理的な思考を鍛えるのは子供の頃から行う必要がある、とお考えなのでしょう。
求められる国語スキルと、スキル向上の方法が語られています。
2. 文系理系関係なく数的な力は必要
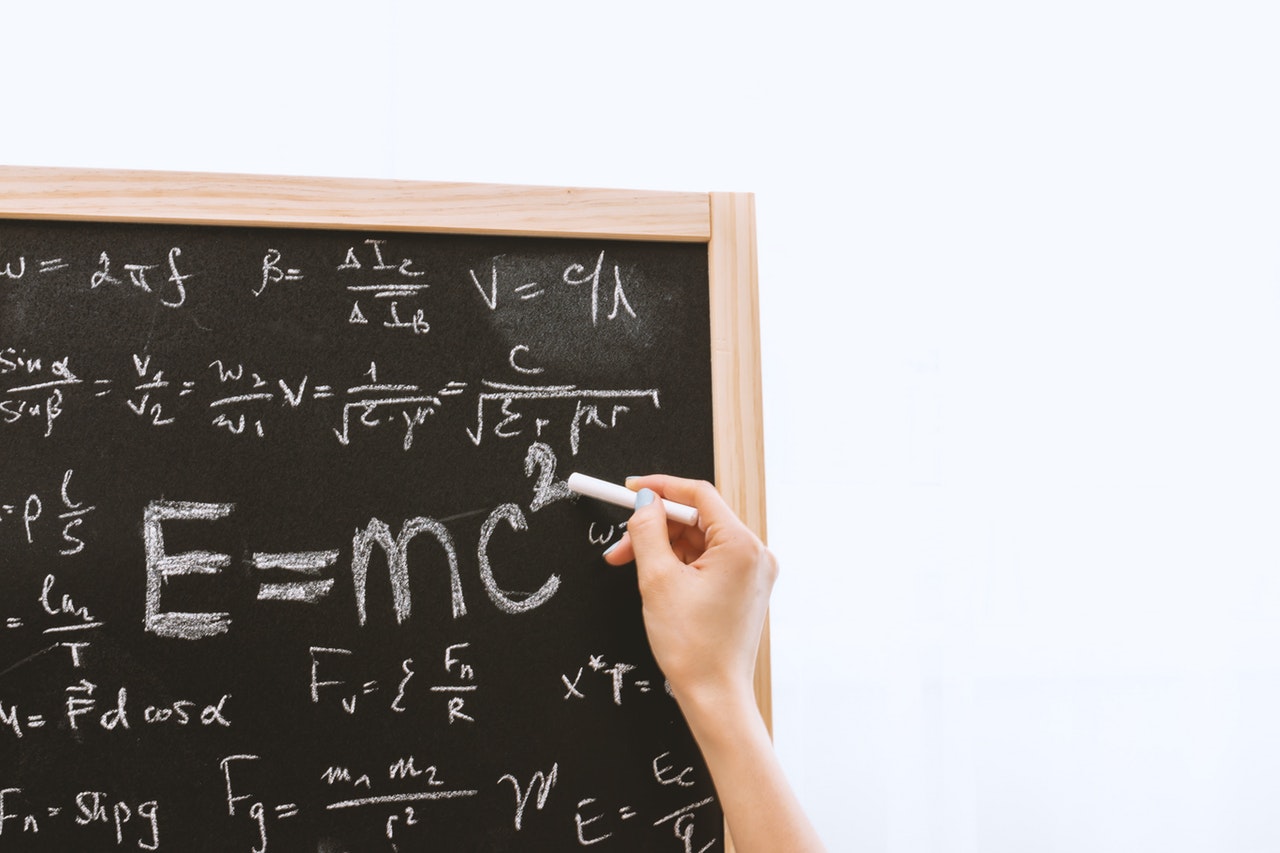
私立文系を狙う子は、早々に理系科目を捨てていました。
けれど時代は変わり、ITを大活用したビックデーターを基に商品開発など行っていきます。
そういったとき、データを読めるかどうか=数的なセンスがあるかどうかが必要になってくるのです。
会議などでも、どの年代をターゲットにして年間の想定売上など、全て【数・数値】が登場してきます。
本屋さんに行くと、社会人向けコーナーに統計学の本がズラ~と並んでいますが、それだけニーズがある証拠。
話を小学生に変えてみますが、子供①は3年生辺りからたまにグラフの宿題を渡されたりしています。
グラフを書いたり、そこから読み取ってみたり。
う~ん、自分の時よりグラフ系の問題が多い気がします。
でも、グータラ小学生だったので記憶が抜けていますが・笑。
[amazonjs asin=”4093974624″ locale=”JP” title=”細野真宏の数学嫌いでも「数学的思考力」が飛躍的に身に付く本!”]
私は文系なので、論理的思考で会話をするのが苦手なのはしかたがない、と思い込んでいました。
が、旦那さん(文系)に「理系文系関係なく、起承転結を考えて話をしないと相手に伝わらない」と注意され続けてきました。
子どもと接する時間は、どうしても母親の方が長くなります。
脈絡もなく自分が会話していたら、そのまま子供に真似されると思い、論理的思考の本を読むようになりました。
おかげで様で少しはまともになりました・・・。
子供に数学的思考を身につけさせたければ、親がお手本にならないといけないと感じています。
これは、上記の国語スキルと同じですね。
数学と国語は両端に位置してそうで、実は同じ場所に同居している不思議さがあります。
数値は読み取れるけれど、それを分かりやすく伝えるには語彙力や作文能力が高くなければいけませんしね。
3.AIに関する本
子供たちが社会に出る頃、AIが事務処理などを一手に担っている可能性が高いです。
レジはセルフレジが拡大傾向ですし、郵便局や銀行の簡単な業務は取り替わっていくのではないでしょうか。
2015年頃から、AIに関する書籍数が増えてきている気がします。
最初は、人工知能対人間、というテイストの本ばかりですたが、最近は子供や保護者向けの啓蒙本が目立ってきています。
その代表的な1冊が【2019年ビジネス書大賞 大賞】AI vs. 教科書が読めない子どもたちです。
[amazonjs asin=”4492762396″ locale=”JP” title=”【2019年ビジネス書大賞 大賞】AI vs. 教科書が読めない子どもたち”]
公立学校の教科書を正しく読めない子が増えてきている、という衝撃的な内容となっています。
ただ、教科書うんぬんの話は後半に出てきて、前半は正しいAIを伝えるためにページを割いています。
ですから、読めない子が増えてきているのか!?と期待して読むと肩透かしを食らいます。
出版社のタイトル策略にはまったとしても、一読の価値はあります。
自分で考える力がないと置いてかれる時代がやってきます。
裏を返せば、自分で考えて自分で行動する子にとっては飛躍できる時代とも言えるのです。
4.世界に通用する系の本

超難関高校でボチボチ欧米の名門大学に入学する子が増えてきています。
そういった、グローバル志向の強い保護者&子供向けの本が最近出版が相次いでいます。
どれも興味深く面白いのですが、国内の大学でいい、とお考えの保護者にも読んでいただきたいです。
なぜかというと、会社に入り取引先がインドの会社、とかマレーシアの会社の視察に行く、とか普通になってきていますよね。
世界のエリートとやり取りすることもあり得るのです。
その時、無知だと恥をかくのは子供。親としては、下準備をして相手を知っておく必要があります。
世界では○○なんだよ、と家庭の会話で自然と出てくるようなスタイルでかまいません。
実行してみましょう。
入門編としてオススメなのは一流の育て方―――ビジネスでも勉強でもズバ抜けて活躍できる子を育てるです。
[amazonjs asin=”4478061467″ locale=”JP” title=”一流の育て方―――ビジネスでも勉強でもズバ抜けて活躍できる子を育てる”]
私のお気に入りの1冊。
悩める親御さん向けです。本棚に常備しております。
さて、我が家ではとんでもなく中途半端な英語教育を行っていますが、英語は関心度が高いです。
2020年度から科目化決定し、2018年度から前倒しで少し授業している学校もあります。
子ども①も教科書を使いましたが、完全に会話オンリーです。
そこは徹底していますね。文法は一切触れていない様子。
一方、英語系の本も沢山出ています。
読み応えもあり、実践方法も記載されているのは【ほんとうに頭がよくなる 世界最高の子ども英語――わが子の語学力のために親ができること全て!】です。
[amazonjs asin=”4478102376″ locale=”JP” title=”ほんとうに頭がよくなる 世界最高の子ども英語――わが子の語学力のために親ができること全て!”]
2020年の英語科目化問題にも触れています。
「実践的な英語を早めに触れさせておいた方が後々便利」というニュアンスの記載があります。
それにしても、英語を家庭で行う場合は、ルーティン化できるかどうかが勝負ですね~。
習慣化、日常生活に落とし込むのは難しい、と最近感じております・・・・苦笑。
結論 子供に勉強だけさせずに親も学びましょう
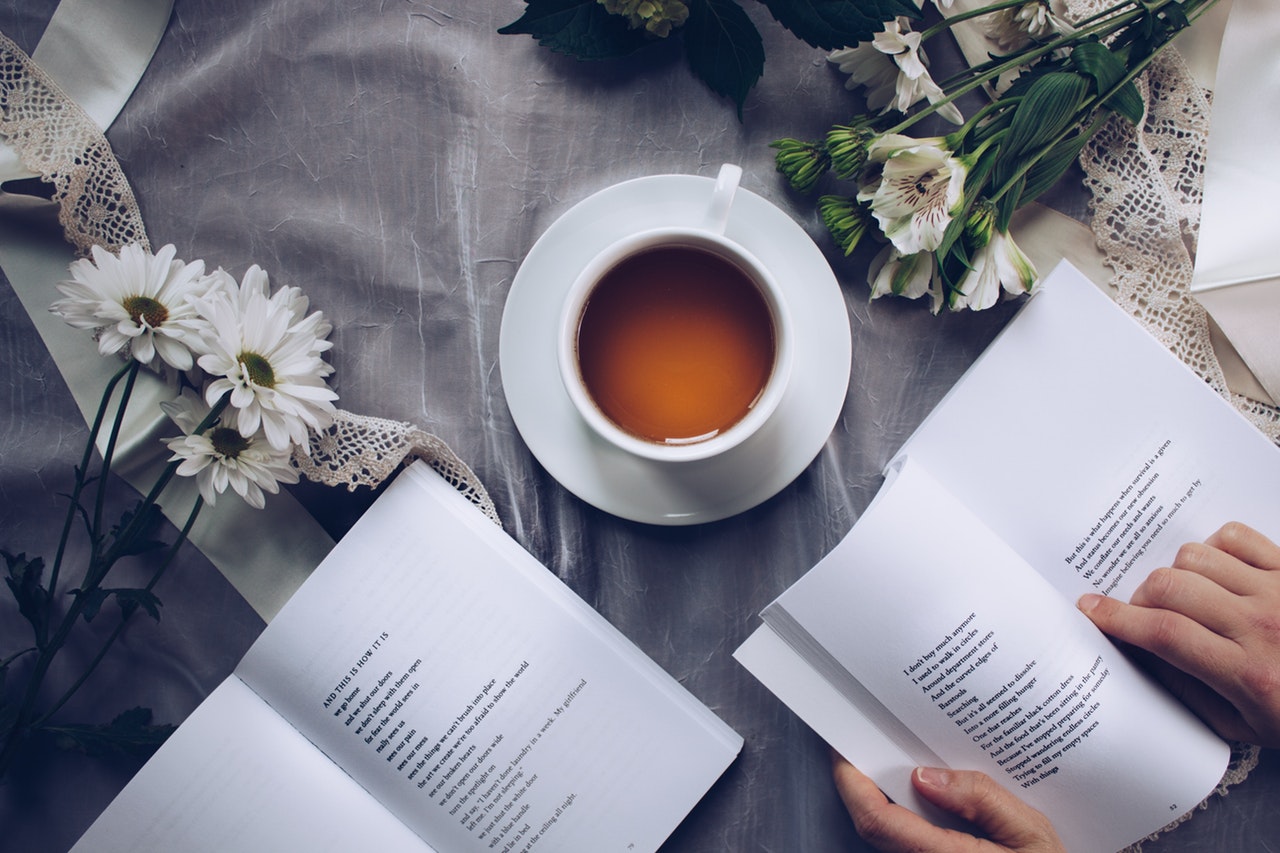
この記事を読んでいると、またアマゾンサーフィンしたくなります。
最近、子供の本ばかり借りてきたり買ったりしていたので、また本探しの旅に出たいです。
家庭教育のジャンルは、子を思う親をターゲットにしているので、タイトル倒れのものもあるのでご注意くださいね。
親が本を読んでいると、子供も自然と本は読むもの、と勘違いしてくれるので一石二鳥。
是非、読んでみてください。
番外編
家庭教育系で大人気の「○歳系」本。
私も、大量に読んでいます・笑。
何冊かを記事にしていますので、興味のある方は読んでみてください。