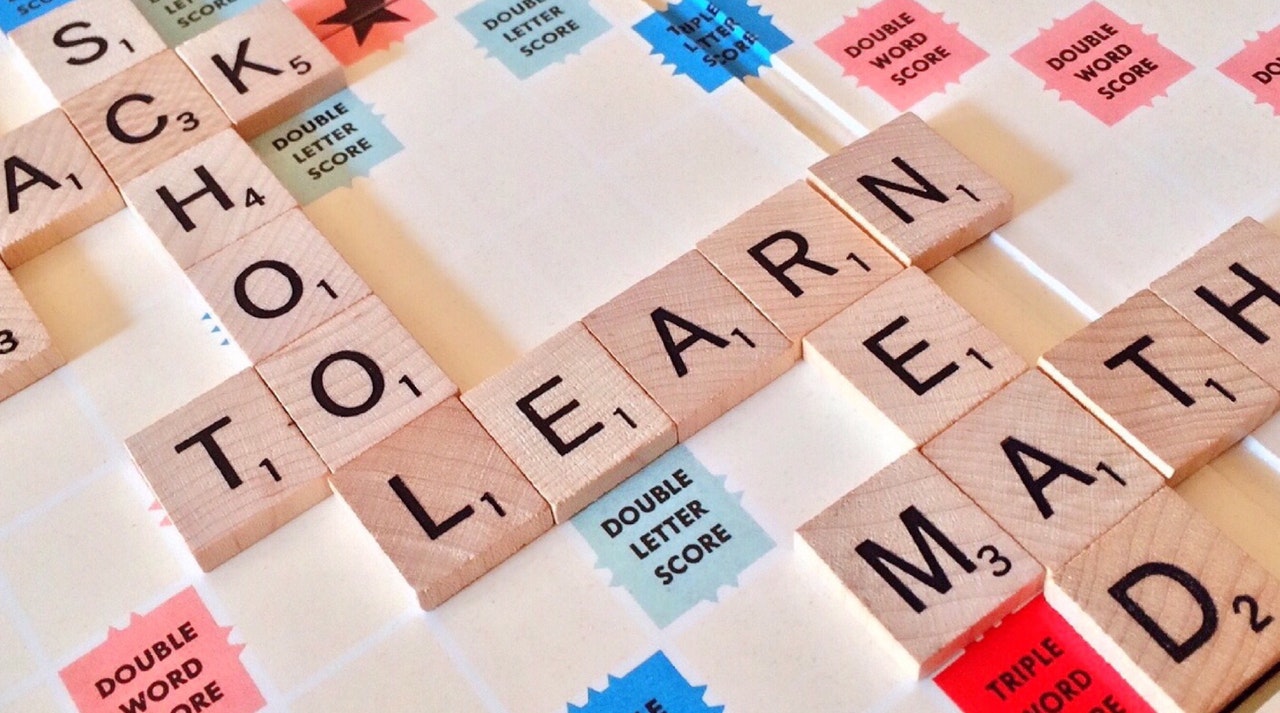今回は【トップ高校を目指しても子どもを息切れさせない工夫】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
新年度がスタートする春は、進級進学など新しいクラスメイト、環境で学校生活が始まることもあり、期待よりも不安を感じる子の方が多いと思います。
新たに受験学年となる子どもたちにとっては勝負の一年が始まるわけですが、4月の時点で考えると高校受験であれば残り8ヶ月、9ヶ月と思う以上に時間は限られています。
こうした中で、進学校、トップ高校を目指すとなると【ライバルたちに競り勝つ学力】を鍛えつつ、苦手克服も頑張らないといけません。
私も中学3年生の時は同じ高校を受験する同級生の全員が塾通いをしていて、とんでもなく焦ってしまい、受験直前期の秋の終わりに自律神経失調症となるなど精神的に追い込まれてしまった苦い思い出があります。
大人になれば高校受験も長い人生の中での大きなイベントの一つ、色々と学ぶこともあった出来事なのですが、リアル受験生の子どもにとっては人生の分岐点、失敗してしまえばそれは自分にとっては敗北だと思い、とてつもないショッキングな出来事だと捉えています。
とくに進路進学の選択肢が少ない地方では第一志望に不合格となると、同級生と連絡を断つ子も少なからずいます。
子どもが受験学年となると親の方は【合格すること】ばかりに目が向いてしまいますが、【不合格となった場合でも立ち直れるようなサポートをしつつ寄り添い励ます】をしていく必要があります。
トップ高校を目指す場合は子どもも他の子に負けられないという気持ちで全力で勉強をしていきます。
心が不安定になる時もあることを考慮しつつ、息切れせずに受験を乗り越えていくにはどのようなことに気をつければよいのでしょうか。
受験生は悩みながら勉強していると話す
まず、受験生は悩みながら勉強しています。
これは、どの高校を目指す場合でも、そしてトップ高校に余裕で受かりそうな子でも【大丈夫か】と不安を感じながら勉強する瞬間があります。
傍から見ると、【余裕で入りそうだから良いよね】と思っていても、当の本人はそうではなく【もっと頑張らないと】と気合を入れて勉強しています。
同じくトップ高校を目指す子からすると【そんなに勉強しないで欲しい】と思ってしまいますが、上位で受かる子は不安を搔き消すためにさらに勉強するという傾向が強いというのは私の中学生時代、塾で出会った生徒達、そして子ども①の同級生の話を聞いていても感じています。
子ども①の同級生の神童さん達も【受かるために猛烈な追い込みをしていた】というタイプでしたが、子ども①からすると【あの学力で追い込みするのはずるい】と苦笑いを浮かべながら文句を口にしていました。
とはいえ、猛烈に勉強することが彼ら彼女たちにとっては不安を消す行為です。
そういう話をしながら、【どんな子でも受験というのは子どもの心を不安にさせる】【不安と向き合いながらみんな過ごす】【自分らしく不安と向き合うにはどうすれば良いか】と語り合ってみましょう。
我が家でも、子ども②の中学受験の時、そして子ども①の高校受験の時に不安を取り除くことに力を入れていきました。
子ども①の受験はちょうどコロナ禍の初年度だったこともあり、受験の緊張感というよりは感染予防の方に集中していたことや、世間のドタバタ感もあり【気がついたら受験がやってきて受けた】というちょっと不思議な受験学年でした。
子ども②の時は不安を増大させるタイプなので、余計なことは親の方から言わず、子ども②が何か不安を言ってきたら受け止めることを徹底しました。
子ども①もさすがに高校受験の時は夏休み明けからどんどん緊張感MAX状態となり、色々と愚痴、不安、これまでの勉強への取り組みの甘さの後悔をただ静かに聞いていました。
子ども①②のどちらも、最後まで話を聞いた上で励ましの言葉をかけていました。
親もイライラしたりどうなるか気を揉むことばかりですが、子どもがかなりの不安を抱えている以上、【もっと勉強しろ】という言葉は極力控えるようにしてください。
勉強ばかりさせるのは悪手
さて、トップ高校を目指す場合は【子どもがしっかり勉強する】というのは不可欠です。
まれに、本当にまれにサクッと勉強して軽々と受かる神童さんもいますが、そういう子は滅多にいないのでインターネットなどでそういう話を見ても、絶対に真似しないでください。
地方でもトップ高校は偏差値65以上の子達の戦いです。
世間的に賢い子と言える偏差値65の子でも負けてしまうような世界ですから、【合格に少しでも近づくには勉強を頑張るしかない】です。
とはいえ、四六時中勉強ばかりしていては心も疲弊してしまいます。
メリハリのある受験学年を過ごすためには、しっかり勉強しつつ、時には休憩タイム、リラックスタイムを設けるようにしてください。
子ども①の周囲には【この模試が終わったら外食に行く】【スターバックスで新作メニューを飲む】といったご褒美を作っている人もいました。
我が家の場合、外でキャッチボールをする、一般に開放している公的な体育館でバトミントンや卓球をして勉強疲れ、ストレス発散をしていました。
親からガミガミ言われ、勉強ばかりさせられる受験生は全国津々浦々にいますが、塾で出会った子ども達を見ていると必ずしも良い結果となるわけではありません。
息抜きができずに親の視線を感じながら勉強をするというのは、何かと不安を感じる時期に大きなストレスとなります。
親からのプレッシャーがかなりある受験学年の生徒の中には、授業中にボーっとして集中力が途切れたり、イライラしていたりと他の受験生とは明らかに落ち着きのない様子だったこともあります。
これでは追い上げの時期に周囲から取り残されてしまいます。
親の方は良かれと思って勉強させるけれど、実はあまり良い方向に動いていないということも珍しくありません。
とにかく勉強させるというのは親も心に余裕がない証拠です。
子どもの受験は1年間、家庭の雰囲気が重苦しいものになりがちですから、親もストレス発散して子どもにキツイ言葉を言い過ぎないよう気をつけてください。
子どもの立ち位置を模試で確認する
受験学年では子どもの精神面のサポートというのは親の仕事の中でも大切なものですが、やはり現実を見ると子どもが受かるかどうかを確認することも必要です。
受験では全国各地自治体の入試問題に似た作りの模試が開催され、多くの中学生が受けています。
この結果で合格圏、可能圏となったら100%大丈夫、というわけではありませんが、模試を受けている人数も多いことからかなり信ぴょう性の高いテストと言えます。
第一志望の志望校判定も重要ですが、【第一志望の受験生の中で自分は何位くらいなのか】を確認することも大切です。
もちろん、子どもも親も安全圏、可能圏、努力圏、またはA判定、B判定、C判定の方に目がいきます。
しかし、立ち位置を知らないと【自分はどのように模試ごとに変動しているのか】が見えてきません。
トップ高校を第一志望にしていると、超余裕で入る子やかなり余裕で入る子は模試自体をほとんど受けていないということがあります。
子ども①②の周りでもそういう類の模試をほぼ受けていないという神童さん、もの凄く賢い子はいました。
そういう子達は自治体の中で大量にいるわけではありませんが、模試の結果をそのまますんなりと受け止めることはせず、【自分の順位の上に数十人いるかもしれない】と考えてみるようにしてください。
我が家も、第一志望の高校の募集定員の中で何番くらいになるかを【受けていない超優秀な同級生達】を加味した上で計算しています。
子ども①の高校受験の時は志望校判定よりも【ちゃんと募集定員の中には入れそうか】というのを模試の結果が出るたびに確認をしていました。
成績の乱高下が激しい子ども①でしたが、一応【なんとか滑り込めそうな順位】をキープしていました。
ただ、そのことを子ども①に伝えると気が緩むので受験が終わるまで口にはしませんでした。
トップ高校を目指すというのは地方でもそう簡単なことではないので、長い道のりを息切れしないよう、子どもを息切れさせないよう、そして確実に近づけるよう親子で頑張って走りぬきましょう。