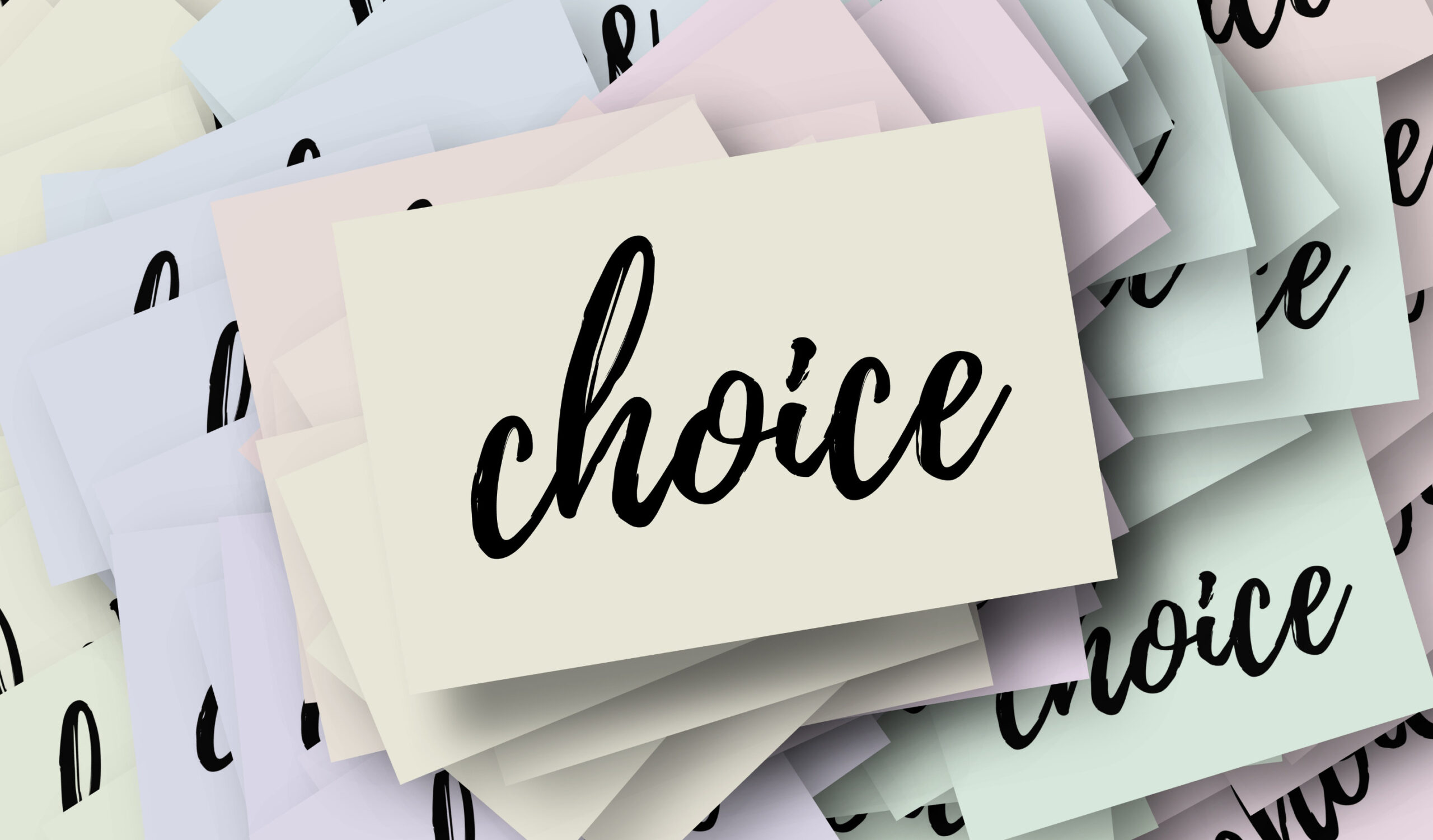今回は【子どもの学力 先取り学習をする? しない?】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
教育に関心のある保護者なら、幼児期から小学校入学に向けて先取り学習をしようかと考える方もいるでしょう。
実際に私の周りでも年中さんや年長さん頃から小学校内容を勉強している子はいました。
呑み込みの早い子は小学校2年生くらいの内容まで理解できているので、そういう子を見ると周囲のお母さんたちは【すごいですね】【賢いですね】【羨ましい】といった称賛の言葉を口にします。
足し算や引き算も小学1年生の躓きやすい単元である繰り上がり、繰り下がりもできて、2年生で学ぶ九九の暗記もできている。
1年生や2年生の漢字の読み書きができている。
そういう子はちょっと探せば周りにけっこういたりします。
私も自分の子ども時代、そして子ども①②③の子育てを通じてそういうタイプの子に出会ってきました。
子どもが学校より先のことを学ぶことで、小学校のテストで満点を連発しやすくなりますし、子どもも【自分は他の子より勉強ができる】という自信を感じるようになります。
ただ、先取り学習をしている子の誰もが小学校6年間でずっと学力上位層にいて、中学受験では難関校や倍率の高い学校には入れたり、公立中学進学組なら学校でトップを維持してトップ高校に楽々合格するかと言えば、現実はそうではありません。
親としては、先取り学習をしていて成績が良い我が子を見ていると【この調子で中学受験とかトップ高校に入れるかも】と期待してしまいたいところですが、そんなに甘くはないです。
たしかに、神童さんぶりを発揮して幼児期からずば抜けている子もいますが、親の期待とは裏腹に途中で伸び悩む子の方が意外と多いという印象があります。
今回は、教育に興味関心のある親なら気になる先取り学習について取り上げていきます。
先取り学習は意外と簡単にできる
まず、先取り学習は思う以上に簡単にできます。
代表的なものが、公文です。
公文に入れば、子どもの学力スキルによって進み具合は多少なりとも異なりますが、小学校に入る前に小学校内容を勉強することは可能です。
この他にも学研でも幼児期から通うことで小学校内容を先に勉強することができます。
学習系の習い事に入ることで、家庭で個別に取り組まないといけない先取り学習を容易に進めることができます。
子ども①②③の学校、塾でもこうした習い事に幼児期から通い、とくに計算力などで圧倒的な力を見せつけている子がいました。
授業も復習になることが多く、カラーテストも低学年の頃は満点を連発しているので【スゴイ賢い子】となります。
ただ、先取り学習の差による学力差というものは学年が上がると見えなくなってきます。
子ども①②③ともに口を揃えていたのが【小学校3年生の頃から差が少し縮まってくる】ということでした。
学校の学びが抽象的なものが増えるにつれて、幼児期からの先取り学習の優位性がなくなってきて、小学4年生、そして5年生頃には【みんなと同じくらい】になっていくようです。
もちろん、神童さんタイプの子は幼児期から先取り学習をし、ずっと圧倒的な学力差を見せていますが、そんなタイプの子は滅多にいません。
多くの子は追いかけてきた子達の集団にのみ込まれていきます。
我が家の子ども①②の周囲にいる、幼児期から先取り学習をしてきた子の多くはそんな形で同化していきました。
ですから、先取り学習をしていても結局は小学校に入ってから本格的に勉強をスタートした子と10歳前後には優位性が消滅し、団子状態になると考えてよいでしょう。
全てを理解していないとデメリットになることも
さて、教育熱心な親からすると先取り学習をしてたくさんの知識を増やして同級生を圧倒する学力を身につけて欲しい、と期待してしまいますが、幼児期に九九の暗記、かけ算や割り算ができるようになっても安心できないことがあります。
それは、四則計算のシステムを理解しているかどうか、が幼児期ではまだ怪しいところがあるからです。
呑み込みの早い子はスイスイ計算問題を解ける、九九をスラスラ唱えることができますが、それではかけ算はどういう計算なのか、割り算はどう意味があるのかを理解しているというのは別問題です。
今の小学校では思考力重視の学びとなっているため、たとえ算数の計算問題でも【この計算式はどういう意味があるのか】と意見を言い合ったりしています。
割り算なら割る、割られるという考えなども、言葉が悪いですが【しつこいくらい勉強する】という授業が行われています。
何となく計算ができる、ではなく【この式はどんなことを表現しているのか】を問う学びへと変化しているので、ただ計算が速いだけでは算数が得意な子にはなれない時代になっています。
感覚で問題を解いていると、高学年で抽象的な内容がどんどん増えていくと【何となく分かるけれど、どういう意味なのか?】と感じるようになり、中学に入ってからさらに考えさせる学問へとなっていく中で先取り学習の優位性が消えてしまう子もいます。
または、先取り学習によって成績が良い状態を続けてきたことで、小学校4年や5年生の学びで躓いてしまい成績が低下していくことに耐えきれず、心が勉強から離れていく子もいます。
こうなると、親が思い描いていたような進路進学は難しくなります。
幼児期や小学校低学年のキラリとした学力とは程遠い進学先となった子を知っている、という方もいると思います。
幼児期や小学校低学年での先取り学習は【何となくのノリでできる】というのが一番恐ろしいです。
もし、我が子がそういうタイプだと感じたら、行き過ぎた先取りを求めず、セーブするようにしてください。
高校進学後は先取り命になる
ところが、高校進学後は大学受験を考えている場合は先取り学習をしているかどうかが合否を決めるくらい重要なものに変わります。
地方の学力上位層の中には、高校受験の勉強をしつつ高校数学の勉強をしている子もいます。
そのくらい、高校受験組にとっては先取りをしているかどうかが重要になります。
子ども①が通う高校でも、とくに英語と数学は予習を前提として授業が進められていきます。
現役で最難関大学に受かる子がいる学校では【受験学年である高校3年生で受験勉強に時間を作れるかどうか】がポイントとなるため、進みが早いです。
子ども①の周囲にいる子の中には、高校1年生までに数ⅢCまで一通り青チャートで自主的に予習し終わっている、という子が複数人います。
いずれも、東大、医学部医学科を目指しているような子達です。
学校の授業通りに勉強していると大学受験に遅れをとってしまうので、可能な限り学校の授業が復習の場になるようどんどん先を急いでいるわけです。
教育情報はインターネットの浸透で住んでいる地域による差というものがなくなってきていますが、親の経験や地域の教育熱の高い低いによって先取り学習の考え方も異なります。
特に地方では志望校に合格すると、大学受験に目を向けることよりも【合格した!万歳!】という気持ちが強くなり、なかなか次の受験に焦点を合わせることができない親子もいます。
そして、大学受験は高校2年生の夏休み前後から本腰を入れれば間に合うと考えている子もいます。
そうなると、全国を相手にした大学受験で厳しい戦いを強いられることになります。
どちらかというと、幼児期や小学校低学年での先取り学習を重視している人の方が多いのですが、【実は高校進学後の方が大切だよ】という考えが広まって欲しいなと個人的には感じていますし、小学校の授業で学びつつ、その前後の単元の予習復習をしっかりしていくことで十分な学力は身につきます。
子どもの理解度を踏まえて親が焦って先取りに熱心にならず、冷静になって家庭学習を進めていきたいですね。