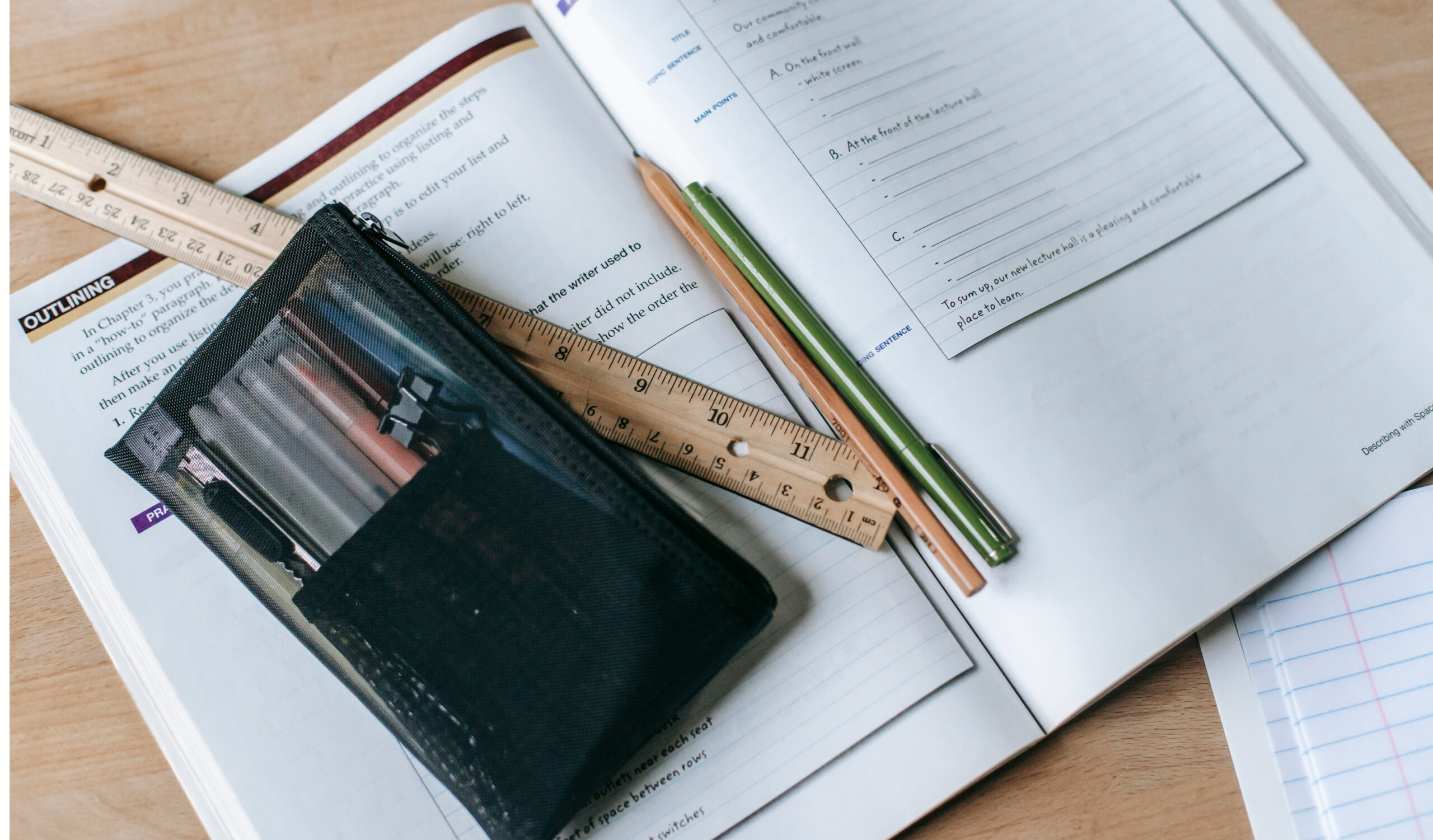子ども①の小学4年が、もうそろそろ終わりを迎えようとしています。
教育都市伝説的な【10歳の壁または小4の壁】もとりあえずとりあえず通過したことになりました。
そこで今回は、多くの家庭教育本で謳われている、10歳の壁について独断と偏見で考察してみようと思います。
実際の10歳の壁を、地方都市の公立小に通っている子ども①を通して色々考えてきたので、その謎を知りたい方のご参考になれば、と願っています。
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
10歳の壁の特徴とは
早速ですが、気がついたことは以下の3つになります。
- とくに算数での差が明確化する
- 勉強への意欲が固定化される
- 精神面が大きく変わっていく
世間には、10歳の壁をテーマにした本はたくさん出版されていますよね。
しかし、リアルな声をお届けすることは大切だ、と感じてこの1年で気がついたことや、驚いたことをご紹介していきます。
1.とくに算数での差が明確化する

小学4年になると、分かり切った問題から小数や分数など、瞬時に掴み取れない数を扱うようになります。
この、抽象的な勉強がポイントです。
10歳の壁の話では、算数の話がよく出されますが、子供①の話を聞いていても、痛感しました。
簡単に言うと、出来る子は高得点を維持し、勉強する習慣のない子は坂道を転げ落ちるように点数が悪くなるのです。
算数以外でも、その差は出始めていますが、算数では特に顕著でした。
ある程度、予想していた私も怖さを感じたくらいです。
子供①も「先生が、小学4年になると算数が難しくなるからついていくのが難しくなるよ!と口にしている」と常々言っていました。
まとめテストの時は、基準点以下の子は再テストが行われるようになっています。
ちなみに小学3年生の時は、再テストは漢字テストのみ。
学校の先生も、点数の悪い子向けに補習プリントなどを出しているようですが、やはり元々勉強する習慣がほとんどない子ばかりなので、定着は難しいようです。
理科も、小学3年よりも問われる知識量が増えるので4年生の時点で音を上げている子がいる、という事実があります。
中学に入ると、さらに突っ込んんだ内容を学んでいくので、小学4年生で理科につまずくと立て直すのがとても難しくなります。
グータラ小学生だった私もそうでした・・・苦笑。
2.勉強への意欲が固定化される

勉強への意欲、というと大げさですが、【将来への意欲】の有無を起因とする差が固定化されていきます。
勉強への意欲は、子供が勝手に身につけるものではありません。
親や周囲の影響などから、【将来、こういった仕事をしたいから今から勉強しておこう】、という考えを持っているかどうか、です。
私自身の経験上、親から世の中の仕事に関して教えてもらわずに育ってきたので、身近な職業=学校の先生、農家、知っている職業=新聞記者、アナウンサー、小説家、くらいでした。
小さい頃から、色々な世界を知っていると、将来の夢が広がり勉強へ向かう心構えが変わります。
そのことは、子供①を通じて肌で感じましたね~。
子供①は園児時代から宇宙やロボットなどに興味があるものの、「食べ物関係の仕事がしたいな~」と口にしていました。
親としては、1人で料理をしようともしない&食べることだけ大好きな子供①に、プロの料理人の適性がないのは分かっていたので、2018年の夏に大勝負に出たのです。
火星接近と誕生日プレゼントで、大奮発して天体望遠鏡を購入。
土星の環を見て、大興奮した子供①は案の定「宇宙関連の仕事に就きたい」と夢を軌道修正し、以前よりも真面目に勉強に取り組むようになりました。
10歳になると、視野を広げるためにも様々な仕事があることをさり気なく伝えるようにすることが大切です。
3.精神面が大きく変わっていく

学習内容以上に、親が対応に苦慮しそうなのが精神面での成長です。
同い年の中では、幼い雰囲気の子供①でも、ぶつかる回数や反抗的な言動が増えてきました。
また、他の子との違いや苦手なことへの劣等感が大きくなってきます。
子供①を例にすると、幼稚園から小学2年までは自分が足が遅いことにハッキリと気がついていませんでした。
かつては、瞬足やバネのちからを履いていれば速く走れる、と勘違いしていました。
しかし今では、体力テストの短距離走が近づくと「やだな~」とため息をつくなど自分の運動神経のなさに気がつき絶望感に苛まれています。
その姿を見るたびに、「私に似たね。運動ではなく勉強で勝負だ!」と声をかけています。
まぁ、小学生時代は足が速い子はとくに花形なので何の慰めにもならない言葉ですけどね・・・。
自分の苦手分野を自覚し始めるのも10歳前後からです。
何でも話をしてくれた時代は過ぎ、思春期や反抗期への階段を登り始めていきます。
男女での差や、個々人によって時期や症状は異なるものの、親の言うことを素直に聞いてくれた時代とサヨナラする時期です。
子供子供から卒業し、自我が芽生えてきた1人の人間として親と向き合うようになっていきます。
子供①は、小学4年の夏頃から少しずつ心の変化が見えてきているので、親としてはちょっと寂しいですね・・・。
それでも、まだ色々話はしてくれますけどね。
10歳の壁をなんなく乗り越えるポイント

10歳の壁は、勉強面や精神面で大きく変化をし始める頃にやってくる試練?のようなものです。
ここでは、その壁を乗り越えるポイントを説明していきます。
まず大切なことは、自立しようともがき始めた子供、という前提で接することがベースにあります。
明確にチェンジすることはないので、子供に寄り添いつつ成長を促していく姿勢が大切です。
ポイント1.【飛躍の年頃】とポジティブに考える

10歳の壁を上手く利用して、子供の自立を促そう!、と考えても、正直難しいです・笑。
子供①がぶつかってくると、イラっとします。
朝の忙しい時間帯とかに、「おかずこれだけ?」と言われた日には、とくに・・・。
まぁ、私が同じ年頃はもっと親に反抗していたので、何も言えない自分がいますけどね。
親に文句タラタラは、それだけ忖度なくものを言えるから、と考えるようになってきました。
いっちょ前になってきた、です。
ここでガミガミ連発だと、口数が減るだけなので、とりあえず言い分は聞いたふりをしています。
で、自己責任を覚えさせました。
勉強しない→テストの成績悪い→テスト勉強しない自分が悪い、という感じですね。
明日の準備をしない→先生に叱られる→嫌な思いをする→自分が悪い、と同じです。
これを、2018年の夏休みに経験させておき、冬休み頃から心入れ替えて勉強するようになりました。
子供①の黒歴史・夏休み編、と私の中では呼んでいます。
失敗を経験させ、そうならないための思考回路を作る時期でもあります。
長い目で見て、一度痛い目を遭わせておくか~、とのんびり構えてみましょう。
ポイント2.【勉強は大切】という意識を定着化させる
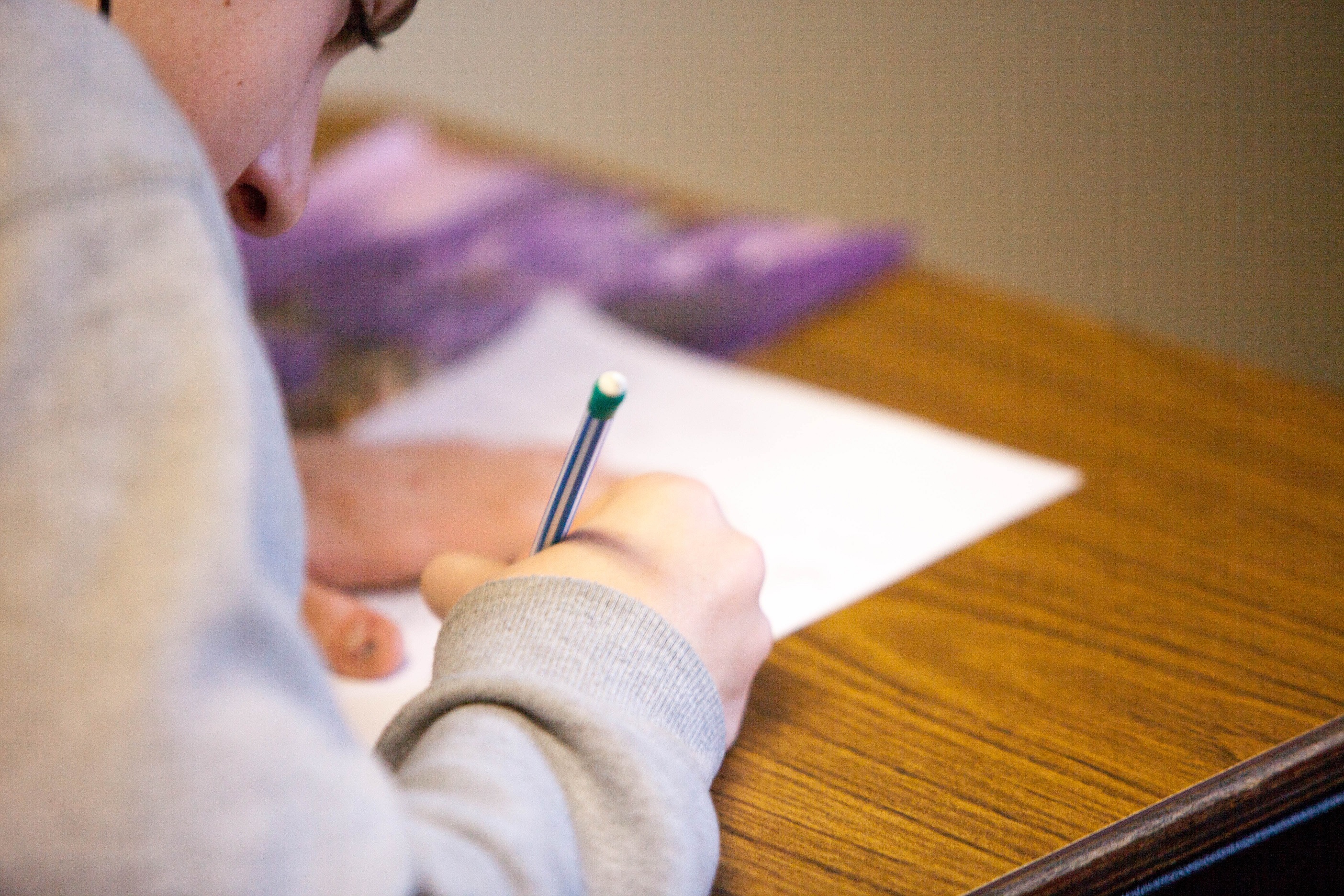
子供①の学校生活を見聞していても、勉強への意識差が拡大&固定化されていきます。
自我が芽生えてくるので、親の勉強しなさい攻撃は受け入れ拒否になってくるので、重要なポイントです。
10歳までに何が何でも【勉強をしておくと将来の選択肢が増える】という意識を植え付けてください。
ただし、ガンガン勉強はNGです。
学校の宿題&家庭学習の習慣をしっかり身につけ、将来の受験に備えておきましょう。
子供①は、学校と塾の同級生の違いに悩んだ時期がありました。
塾のお友達は将来の目標を明確に持っている子ばかりと気がつき、自分も夢に向かって勉強するようになってきています
通塾の有無に関係なく、【将来への明るい希望】はやる気を出す魔法の薬です。
将来なりたい職業を一緒に探していくことをおすすめします。
ちなみに、子供②は探偵や忍者が好きなので、どうにか職業に結び付けたいと考えています。
しかし子供②、刑事系は嫌のようです・・・。
まとめ
今回は、10歳の壁を経験してみて感じたことを書いてきました。
新年度からは、子供②が小学3年になり、10歳の壁の前の9歳の坂道を歩いていくことになります。
兄弟姉妹でも、個々人性格や資質が異なるので、その子に合わせた家庭学習方法を探して行かないといけません。
子供①に合ったものが、子供②には合わないこともありますからね。
10歳前後の変化を上手く利用し、さらに子供を成長させていく姿勢が一番大切だと思います。
10歳の壁に関する他の記事はこちらをご覧ください。