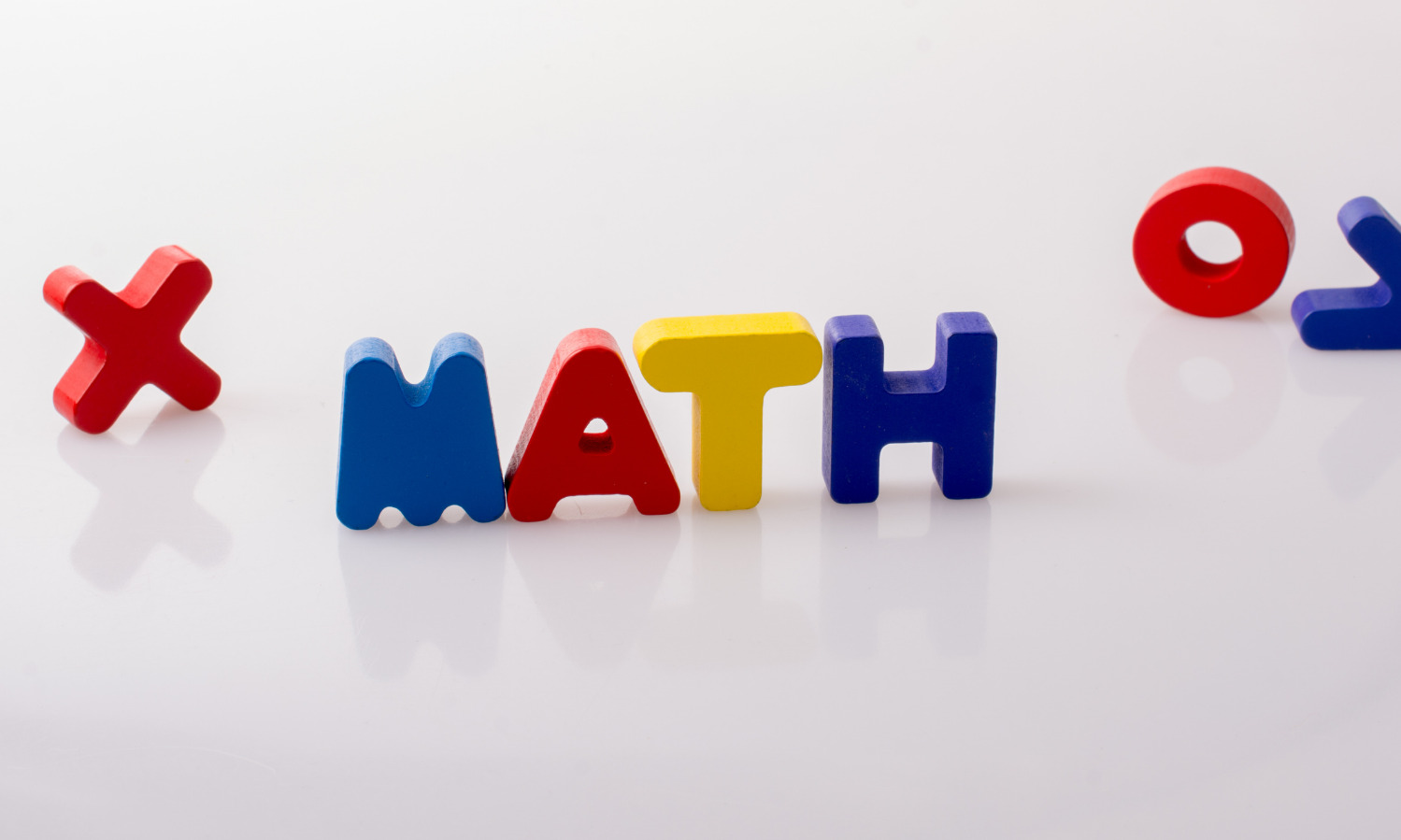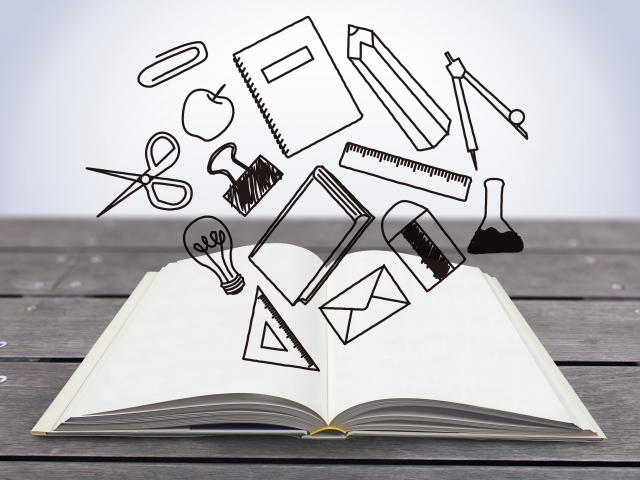今回は【後悔しないために! 学力差がつく前に親ができること】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校生活のスタート時点では、子どもたちの学力に大きな差は見られません。
【うちの子もちゃんと授業についていってるし、テストもそこそこ取れているから大丈夫】と安心している方も多いでしょう。
正直、1年生での難所は算数の繰り上がりの足し算と繰り下がりの引き算、と明確なので対策しやすいですし、2年生でも九九の暗記をしっかりすれば学校の授業を聞いて宿題をして、家庭学習でドリルなどの教材で勉強するという習慣が定着していれば困ることはほぼないです。
しかし、学年が進むにつれて、徐々に【できる子】と【つまずく子】の差が目に見えて広がっていきます。
とくに、小学校中学年から高学年に差しかかるころ、学力差は一気に表面化します。
算数では抽象的な概念や複雑な文章題が増え、国語では長文読解や表現力が問われるようになります。
この段階になると、家庭でのサポートがないままでは、理解が追いつかない子も出てきます。
【最近、宿題に時間がかかるようになった】【授業の内容をあまり話さなくなった】などの小さな変化は、子どもが密かに学びの波に乗り切れていないサインかもしれません。
周囲の子が次々と新しい内容を吸収し、テストでも高得点をキープしているのを見れば、【うちの子だけ取り残されていないだろうか】【このまま中学に進んで大丈夫だろうか】と不安になるのも当然です。
けれど、心配するだけでなく、今だからこそできる対策があります。
学力差が開く前に、親が少し視点を変えて関わることで、子どもの学びの土台をしっかり築くことができます。
そこで今回は、学力差がどのように広がっていくのか、成績上位をキープできる子の家庭に共通するポイント、そして、今日からでも家庭で実践できる具体的な対策について考えていきます。
【もっと早く知っておけばよかった】と後悔しないために、子どもの学力差がどう生まれていくのか、その仕組みから一緒に見ていきましょう。
学力差が広がっていく過程
まず、【学力差が出始めるのは中学生になってから】と思っている方はけっこういますが、現実はもっと早くから差が出ています。
確かに中学校に入ると、定期テストや通知表などで成績が明確に数値化されるため、差がよりハッキリと目に見えて分かるようになります。
しかし、実際に学力の差が生まれているのはもっと早い段階、小学校中学年生からだと言われていますし、我が家の子ども①②③の学校生活を見聞きしていても、その通りだと感じています。
では、なぜこの時期から差がつき始めるのでしょうか。
小学校低学年のうちは、国語ではひらがな・カタカナの読み書き、簡単な文章の読解。
算数では足し算・引き算・九九など、いわば【スキル系】の学習が中心です。
これらは暗記や繰り返しで何とかなりやすく、親の目にも【順調そう】に映ります。
しかし3年生になると、状況は変わります。
文章題や図形問題、理科や社会などの導入が始まり、【言葉で考え、整理し、表現する力】が求められる学習にシフトしていきます。
ここで、表面的な理解だけで進んできた子は、一気に壁にぶつかることになります。
正直、中で仕事をしている時は【小学4年生、5年生で差が出る】と思っていたのですが、いざ子育てをして子どもたちの勉強を見ている、クラスの様子やママ友の話を聞いて【小3でかなり差が出てきている】というのを痛感しました。
たとえば、算数の文章題では【なにを聞かれているか】を読み取る読解力、問題を整理する論理力が必要です。
理科や社会でも、単に【知っている】だけではなく、【なぜそうなるのか】を考える力が問われます。
この時期に、【ただ覚える】だけの勉強に慣れてしまっている子は、なぜ間違ったのかを自分で分析するのが難しくなり、次第に勉強に対する自信を失い、苦手意識を持ち始めます。
一方で、普段から【なぜそうなるの?】【他に方法はある?】と自分で考える癖がついている子は、ここで一気に伸びていきます。
この【自分で考える力】の差こそが、学力差の本当の正体なのです。
さらに、もうひとつ大きな分岐点が訪れるのが小学校高学年ですし、対策をしなければその後の進路進学を決定するくらいの重要な分岐点です。
小学校5年生、6年生になると授業内容は一段と難しくなり、特に算数では比・割合・速さなど抽象度の高い単元が登場します。
ここでの理解度が、そのまま中学数学の土台になります。
この時期、学力差はますます広がりやすくなります。
なぜなら、つまずきを放置したまま次の単元に進むスピードが上がり、遅れを取り戻すチャンスが限られてくるからです。
また、自信を失った子どもは勉強への意欲を失いやすく、【やらない→ますますわからない→もっとやらない】という悪循環に陥りがちです。
その一方で、上位層の子は【わからない】と感じた時点で質問したり、自分で調べたりする自走力を備えているため、つまずきに直面したとしても最小限に食い止め、乗り越えることができます。
このように、学力差はある日突然生まれるわけではありません。
【自分の頭で考える力の差】【学ぶ姿勢の差】【家庭の関わり方の差】が、じわじわと積み重なり、気づけば大きな開きとなって現れてくるのです。
だからこそ、差が見えてくる前の今の段階で、子どもの学びの姿勢や家庭での関わり方を見直すことが、後悔しないための第一歩になります。
成績上位の子に共通する【家庭環境と親の関わり方】
さて、学力差が広がる背景には、学校での授業だけでなく、家庭での環境や親の関わり方が大きく影響しています。
同じ学校、同じ先生、同じ教科書を使っていても、子どもの理解度や学力が大きく異なるのは、その【家庭の力】が違うからです。
実際に、成績上位を安定して維持している子どもたちの家庭を観察してみると、いくつかの共通点が見えてきます。ここでは、特に効果の大きい3つのポイントを紹介します。
-
日常の中に学びがある家庭
成績上位層の家庭では、【勉強は机の上だけのもの】ではありません。
買い物に行ったときの計算や、お風呂での理科的な会話、ニュースを見ながらの社会的な話題など、日常の中に自然と学びを取り入れているのが特徴です。
たとえば、【このリンゴ、1個120円だけど3つでいくら?】【今日の天気はなぜ急に変わったのかな?】【今のニュース、どう思った?】
こうした問いかけを通じて、子どもは自分の頭で考える癖を身につけます。
しかもこれは、無理やり【勉強しなさい】と言わなくても、楽しく、自然と思考力が育つ環境です。
このように、日常会話の中で【考える→表現する→深める】プロセスを経験している子は、教科書の内容もより深く理解し、応用力を高めやすくなります。
-
自学力を育てる見守る姿勢
もう一つ、上位層の家庭に共通するのが、【教えすぎない親】の存在です。
子どもが【わからない】と言ったときに、すぐに答えを教えてしまうのではなく、
【どこまでわかってる?】【もう一度問題を読んでみよう】【どうやって考えた?】というように、ヒントや問いかけで考えを促すことを重視しています。
これは時間も手間もかかりますが、このプロセスこそが、子どもに【自分で考えて解決する力(=自学力)】を育てることにつながります。
一方で、すぐに答えを与えてしまう家庭では、【わからなかったら聞けばいい】という依存的な姿勢が定着し、自分から問題に向き合う力が育ちにくくなってしまいます。
また、【結果】よりも【過程】を重視する声かけをすることも大切です。
テストで良い点を取ったときに、【頑張ったね、どうやって勉強したの?】と過程に関心を持つことが、努力することの意味を理解させ、継続的な成績向上につながります。
-
読書や対話の習慣が根付いている
読解力はすべての教科の土台です。
国語はもちろん、算数の文章題、理科や社会の記述問題でも、【読み取る力】【考えを言語化する力】が求められます。
成績上位の子は、幼い頃から読書の習慣があるケースが非常に多いです。
そして、それに加えて、親子で本の内容について感想を語り合ったり、【どうしてそう思ったの?】と意見を聞く機会がある家庭ほど、子どもの言語能力は格段に伸びていきます。
また、読書だけでなく、親子の対話の質も重要です。
【今日、学校で何があったの?】という質問に対し、【うん、楽しかった】で終わらせず、【どんなところが楽しかったの?】【そのときどう思った?】と一歩踏み込んで聞くことで、子どもは言葉を使って思考を整理する習慣が育ちます。
このような会話が普段から行き交う家庭で育つ子は、学校で習ったことがより深く定着し、自分の意見としてアウトプットする力が強くなります。
成績上位を維持している子どもたちの家庭は、特別なことをしているわけではありません。
しかし、日々の関わり方や家庭の中に、【考える】【話す】【自分でやってみる】チャンスが豊富に存在しています。
親として気をつけたいことは、【勉強しなさい】と言うよりも、【一緒に考えよう】【教えてくれる?】と、子どもを尊重する関わり方です。
これらの積み重ねが、確実に子どもの思考力・読解力・自立心を育て、結果として成績上位に導いていく上で、大きな力となります。
学力差を乗り越えるための家庭の工夫3選
ところで、これから学年が進むにつれて、子どもたちの学力差はますます目に見えるようになっていきます。
テストの点数、成績表、通知表、偏差値。
そんな数字や言葉で評価される場面が増え、不安になる方も多いのではないでしょうか。
しかし、焦る必要はありません。
学力の土台となる力は、家庭の中でコツコツと育てることができます。
ここでは、忙しいご家庭でも今日から実践できる【家庭での工夫】を3つ紹介します。
対策①:【勉強をやらせる前に、話をする時間を増やす】
子どもの学力を伸ばすうえで、最も基本的で効果的なのは、親子の会話です。
【今日、学校どうだった?】
【何を習ったの? それってどんな内容だったの?】
【それ、面白そうだね!もっと詳しく教えてくれる?】
こうした何気ない問いかけが、子どもにとっては学びの再確認になります。
自分の言葉で説明することで、理解が整理され、記憶も定着しやすくなります。
また、【話す→聞かれる→考える→答える】というプロセスを繰り返すことで、論理的思考力や表現力も育まれていくのです。
とくに、【できた・できなかった】に一喜一憂するのではなく、【どうやって考えた?】【どこが難しかった?】とプロセスに目を向ける声かけをすると、子どもは自分の学びを内省しやすくなります。
私も、結果が気になるものの、そうしたところはあまり見えないように気をつけて【今回のテストを一言で総括すると?】と質問し、そこから具体的に各教科の点数や問題点などを話し合うように心がけています。
最初に点数を聞くと、子どもも【やっぱり点数だけにしか興味がない】と思うので、テストの結果に関する会話をどうするかと戦略を練ることは重要です。
学力の土台には、思考力があります。
思考力は、テストに関することだけでなく会話の中で育てることができます。
対策②:【毎日の読書を習慣化する】
学力の根幹を支えるもの。
それが読解力です。
読解力は国語のためだけの力ではありません。
算数の文章題、理科の実験説明、社会の資料読み取り、すべてにおいて【読む力】【理解する力】が求められます。
子ども①②③も学校生活で【小学校3年生4年生頃から語彙力の差を感じるシーンが出てくる】と口にしていました。
小学5年生になると【話をしても語彙力の差で会話のキャッチボールが上手くできない子】【問題文の意味が分からない】【教科書に書かれている内容が理解できない】という子がクラス内でも一定数いるようです。
この読解力は、家庭での読書習慣によって自然と伸ばすことができます。
絵本でも図鑑でも、本人が興味を持つ内容ならOKです。
大切なのは【毎日読む】ことです。
そして、できれば親子で感想を共有してください。
【この登場人物、どう思った?】
【この場面、もし自分だったらどうする?】
こうした対話が、読解力と同時に考察力や表現力も伸ばしてくれます。
読み聞かせも効果的です。
我が家でも長年、読み聞かせを続けてきていますが、子どもが高学年になっても、親が読んであげる時間を持つことで、親子の距離も縮まり、安心感のある学びの環境が生まれます。
対策③:【勉強はやる気ではなく習慣で動かす】
【うちの子、やる気がなくて…】と悩む声はよく聞かれますが、実は成績上位の子どもたちは、やる気ではなく習慣で動いていることが多いのです。
やる気は日によって波があります。
モチベーションに頼った学習は、どうしても不安定になりがちです。
だからこそ、学習習慣を【当たり前の行動】にしてしまうことがポイントです。
たとえば、【夕食後の30分は勉強タイム】【宿題が終わったら好きなことをしてOK】【朝の10分は読書の時間】と、学びの時間を生活の中に組み込んでしまうことで、抵抗感は自然と減っていきます。
最初は5分でも構いません。
【机に向かう習慣】がつくだけで、学びに向かうハードルは格段に下がります。
親は【やったかどうか】だけを確認し、細かく口出ししすぎないことも大切です。
勉強を特別なことにせず、日常の一部に変えていくことで、学力差に負けない土台が育っていきます。
以上、ご紹介した3つの工夫は、どれも派手な方法ではありません。
しかし、こうした【小さな習慣の積み重ね】が、やがて大きな学力差を埋めていく力になります。
学年が上がるにつれて勉強は難しくなりますが、家庭の中に【話す・読む・続ける】というシンプルな学びの基盤があれば、子どもは自信を持ってその波を越えていくことができます。
繰り返しになりますが、学力差はある日突然生まれるものではありません。
実際には、日々のちょっとした【理解のズレ】や【学習習慣の差】が、気づかないうちに積み重なり、やがて大きな差となって表れてくるのです。
だからこそ、今このタイミングで親ができることには、大きな意味があります。
・学校での出来事を丁寧に聞いてあげる会話の時間
・親子で楽しむ読書や、ニュースを一緒に見る習慣
・毎日決まった時間に机に向かう学習のリズム
こうした習慣は、どれも塾や高額な教材に頼らず、家庭で自然にできることばかりです。
【もう遅いかも…】と感じる必要はまったくありません。
むしろ、気づいた今が、チャンスです。
これから先、子どもがどんな学びの壁に直面しても、自分の力で考え、乗り越えていけるように。
親としてできるサポートは、今からでも十分に始められます。
まずは、今日からできる小さな一歩を。
その積み重ねが、未来の大きな差を生まない【強い学びの土台】になります。