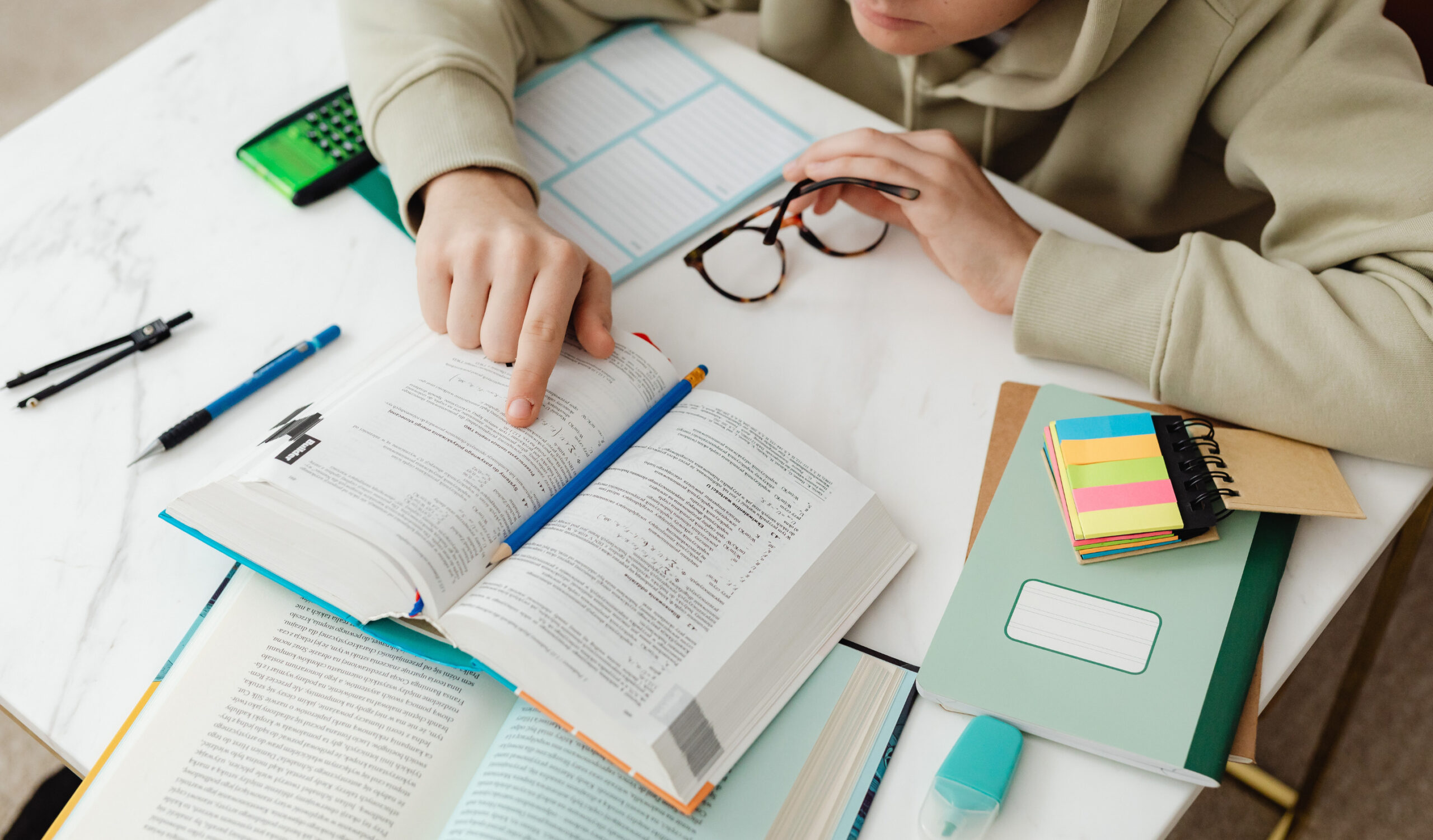今回は【進路は小学生でほぼ決まる? 親が知らない『学力の分かれ道』】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
地方に住んでいると、どうしても子どもの教育は中学になってから本格的に考えれば良いとする空気が漂っています。
私の周囲でも小学生の頃から色々と手を打っている所がある家庭は、教育に関心の強い家庭に限定されていました。
確かに、進学や受験という言葉が現実味を帯びてくるのは中学生以降です。
しかし実際には、子どもの進路に大きな影響を与える【学力の分かれ道】は、小学生のうちにすでに始まっています。
小学3年生までは勉強に躓きもなく、「うちの子は普通にできている」と感じていたのに、4年生以降から少しずつ授業についていけなくなったり、勉強への意欲が低下したりするケースは少なくありません。
それは単なる気の緩みではなく、学習内容が一気に抽象化・複雑化し、思考力や読解力といった“応用力”が求められるタイミングに入っているからです。
しかも、学習指導要領が変わってからは【わからない】というタイミングが幾分早まっているというのは一人の親という立場でも感じています。
つまり、以前なら小学3年生で躓いているような学力の子が小学2年生で、小学4年生で躓いていた子が3年生で学校の勉強で困ることが増えるという具合にです。
こうした小学生で進路の明暗が分かれる現実を知っていれば、中学進学の勉強面での悩みを軽減することができます。
学力差が出始める小学3年生から4年生という時期に、家庭での学習習慣がしっかり身についているか、自分で考える力が育っているかどうかが、やがて中学進学後に大きな差となって表れてきます。
しかも、学力差は、ただのテストの点数の差ではありません。
【自学自習ができる子】と【指示待ちの子】、【応用問題に挑む子】と【わからないとすぐ諦める子】など、将来の進路や可能性に直結する学び方の差として定着していくのです。
塾でも、入会した時点で同じ学力であっても、自分の課題を把握して対処できる子と出来ない子とでは、成績が伸びるのは前者のタイプの子でした。
リアルタイムで子育てをしていると、【果たして我が子は伸びるのか】というのがハッキリとは見えてこないもどかしさがあります。
ただ、小学生の時期は進路の分かれ道であるということは間違いありません。
そして家庭でどのように子どもの学びを支えるべきなのかは教育に関心のある親なら気になるテーマだと思います。
そこで今回は、将来の進路を他人任せにせず、今できることを知る第一歩を考えるためには、小学生で決まってしまう学力の分かれ道をご紹介していきます。
すでに始まっている「見えない進路レース」
まず、小学生の頃からハッキリとは見えない進路レースが始まっています。
小学生のうちは、まだ進路について深く考えなくてもよい、そう感じている親も多いかもしれません。
しかし、実際には小3〜小4の段階で、すでに進路レースのスタートは切られています。
見えにくいだけで、周囲は確実に動いています。
地方でも中学受験、地方の中学受験の王道は公立中高一貫校になりますが、中学受験を視野に入れた家庭では、小3頃から塾に通い始め、小4には本格的な受験カリキュラムが始まるのが一般的です。
また、受験をしない家庭でも、学習系の習い事や家庭学習教材で早期から地道に学力を積み上げているケースもあります。
一方で、学校の授業はすべての子どもに社会に出てから困らない【最低限の学力】を保障するものです。
つまり、できる子にとっては物足りず、つまずいている子にとっては物足りないまま進んでいくのが現実です。
その結果、学校の授業だけでなんとなくやっている子と、家庭や塾でプラスαの学びをしている子との間に、見えない大きな差が生まれます。
この差は、保護者から見えにくいために放置されがちです。
【うちの子は学校では特に問題ない】【テストで80点くらいは取れているから大丈夫】と安心しているうちに、知らない間に受験のスタートラインに立っている子との差、受験はしないけれどコツコツと学力を鍛えている子との差が生まれ、後れを取ってしまうことも少なくありません。
さらに深刻なのは、【普通に過ごしているだけ】では、どんどん取り残されてしまうリスクが高まっているということです。
公立小学校では【そこそこできる】ことが評価されがちですが、それが通用するのは学校内だけです。
たとえ学区の公立中学に進んでも、中学の勉強は小学生時代とはガラリと変わりますし、思考力を問う中学の内容や高校の入試問題には、応用力、読解力、試行錯誤する力が不可欠で、平均点前後の力では太刀打ちできません。
この現実をさらに加速させるのが、地域や家庭ごとの教育への温度差です。
同じ学区に通っていても、親の学習への関心度や情報収集力によって、子どもの学力差は広がっていきます。
例えば、子どもの教育に力を入れている親は当然ながら塾情報や進学実績にも敏感です。
一方、教育に無関心な家庭では、【まだ小学生なのに勉強させるなんてかわいそう】と捉えてしまい、結果として進路選択の幅を狭めてしまうのです。
子どもにとって、こうした【家庭環境の差】はそのまま学力の差になり、将来の選択肢そのものを左右する土台になります。
子ども自身には選ぶ力がまだなく、どんな道に進むかは、大人の判断と環境づくりに大きく依存しているということを、親は意識しなければなりません。
【うちの子にはまだ早い】と思っているうちに、進路レースの大きな差は静かに、でも確実に開き始めているのです。
学力の土台は小4〜小5でほぼ決まる
さて、基本的に学力の土台や子どもの勉強への向き合い方は小学4年生から5年生頃にほぼ決まってしまいます。
親は、なぜこのタイミングが分かれ道なのかと親も考えることが重要です。
子育てをしていると耳にする言葉に、【小4の壁】というものがあります。
これは単に学年が上がるという意味ではなく、学習内容が抽象的・論理的になり、子どもの【学びに向かう力】が試され始める時期であることを指します。
小学3年生までは、日々の授業をこなしていればある程度の理解ができていた子も、4年生になると【文章題が読み解けない】【問題の意図がつかめない】と感じることが増えてきます。
これは、文章読解や論理的な思考を必要とする課題が一気に増えるためで、ここに対応できるかどうかで、子どもたちの学力はハッキリと二極化し始めます。
さらにこの時期は、心の成長も大きな変化を見せる頃です。
自我が育ち、友達との比較や周囲の目を意識し始める中で、【勉強がわからない】と素直に言えなくなる子が出てきます。
理解できていないのに、わかったふりをしてやり過ごす。
それが続くと、学習の抜けや弱点が積み重なり、気づけば【どこでつまずいたのか分からない】状態になります。
学校の先生がすべての子どものつまずきに気づくのは難しく、家庭でのフォローがないと、そのまま取り残されてしまうことも少なくありません。
そして、この小4〜小5の時期についた差は、簡単には埋まりません。
思考力や読解力といった力は、短期間の詰め込み学習では育たないからです。
日々の学習を通じて、じっくり時間をかけて積み上げていく必要があります。
加えて、学習習慣や自己管理能力もこの時期に定着しやすく、勉強の取り組み方が子どもによって大きく差が出ます。
例えば、【宿題を自分で計画的に進める子】と【親に言われないと手をつけない子】では、同じ学習量でも成果に大きな差が出ます。
学ぶ姿勢や集中力、継続力といった【見えにくい力】が、実はこの頃に大きく形作られるのです。
こうして迎える小6では、すでに基礎が固まっている子と、まだ学びの土台が不安定な子とで、学力面の見えない格差が明確に表れてきます。
そしてそれは中学進学後、テストの成績や授業理解度として一気に可視化され、【伸びる子】と【伸びない子】の分岐点となってしまうのです。
進路の明暗は家庭環境で決まる
ところで、学力の差は、生まれ持った才能だけではありません。
むしろ小学生のうちは、親の教育に対する価値観や勉強するよう促す声かけやサポート、教育情報へのアンテナの張り方が、子どもの進路に大きく影響していきます。
【進路の明暗】は、学校や塾だけでなく、日常の家庭環境に大きく左右されます。
よく【塾に通わせれば安心】と考える家庭もありますが、それ以上に大切なのは、家庭での学びの空気がどうなのか、です。
家に帰ってきたとき、自然に勉強に向かう雰囲気があるか。
親が本やニュースに関心を持ち、学びを日常会話に取り入れているか。
そうした積み重ねが、子どもにとっての【学びは当たり前】という感覚を育てていきます。
また、子どもの学び方は一人ひとり違います。
性格や集中力、学ぶスピード、得意・不得意も様々です。
それを無視して【みんなと同じようにやればいい】と考えてしまうと、子どもは苦しさを感じやすくなります。
大切なのは、親が子どもの個性を見極め、その子に合った学び方を一緒に作っていく姿勢です。
すでに差がついてしまったとしても、巻き返しは家庭での取り組み次第で可能です。
【進路格差】を埋めるために、今すぐ始められることをしていきましょう。
一つ目は家庭学習の質と習慣を育てることです。
教科書ワークなどを活用して基本の復習を徹底しつつ、読解力や思考力を養うドリルを取り入れる。
難しい問題を解かせるより、【理解して進める】という学びを丁寧に行うことが重要です。
二つ目が*親子で教育情報にアンテナを立てることです。
進路や入試の基礎知識を知るだけでも、学びの方向性が変わります。
小学生の頃から志望校があるかどうかに関わらず、【高校によって合格できそうな偏差値というものがある】【卒業後はどんな進路をしている人が多いのか】を子どもと一緒に把握することで、必要な学びに自然と導くことができます。
そして三つ目が【学び=楽しい】と思える体験を積み重ねることです。
子どもにとって学びが【やらされるもの】ではなく、【知ることが面白い】と感じられるように、日々の会話や読書、体験活動などを通して、自発的な学びのきっかけを作ることが大切です。
進路は突然決まるものではありません。
日々の家庭環境、親の姿勢、関わり方が、子どもの未来を少しずつ形作っていくのです。
【小学生から考える】と、できることから始めてみましょう。
家庭こそが、子どもの進路の第一歩を支える、最も大きな力となります。