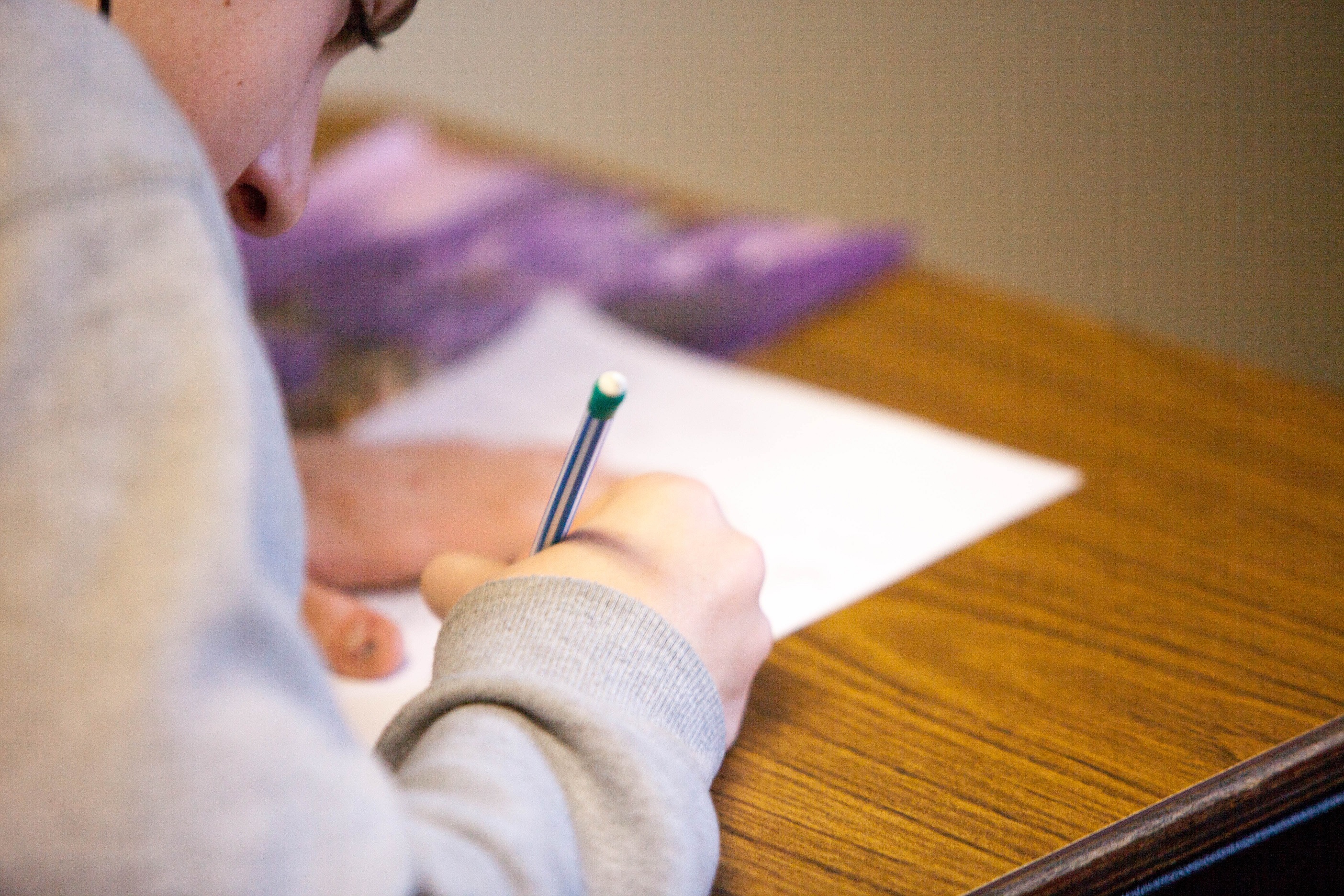今回は【軽視厳禁 小4の壁を乗り越えた後のこと】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
親が小学生の頃、一部の優等生を除くと【なんだか学校の授業が難しくなってきた】【テストで満点を取ることがなくなってきた】と感じることが増えてくるのが小学校4年生です。
私も3人の子どもの小学4年生を経験してきましたが、主に算数で【苦戦するな】という単元が増えてきて、その都度家庭学習でフォローをしたりしてきました。
小4の壁を乗り越えると、親は【ひと安心】と思いがちですが、実は本当の勝負はその先にあります。
小学校5年生以降は学習内容が一気に抽象的かつ複雑になり、応用力や思考力が求められるため、表面的な理解ではついていけなくなります。
さらに、中学では教科数が増え、スピードも速くなり、自学自習力や時間管理力が欠かせません。
小4の壁はあくまで入り口であり、【学ぶ土台】ができたかどうかを確認する段階にすぎません。
その先の継続的な学びに耐えうる習慣や姿勢を育てることこそが、本当に重要なのです。
親は、安心するのではなく、【今が次の段階への準備期間】と考え、学習習慣の定着や思考力の育成に意識を向ける必要があります。
小4の壁を乗り越えたとしても、決して楽観視してはいけない理由は、【壁の先にも、さらに大きな成長のハードルや学力差が待っている】からです。
確かに、小4の壁はとても重要です。
子ども①②③の学年でも学力差がハッキリしてきた、算数の授業で【すぐ分かる子】【まぁまぁ分かっている子】【よく分からない子】がザックリと分類され、理科や社会でも徐々にこうした学力グループが構築されていきました。
小4の壁、10歳の壁という言葉は浸透しており、【小4の勉強をしっかり見よう】と意気込む親も少なくありませんが、あくまで最初の大きな転換点であり、学力、思考力そして学習習慣や生活リズムなどが【中学以降に対応できるか】を左右するスタート地点にすぎません。
小4の壁を越えた段階で満足せず、次の成長段階、つまりは小学校高学年や中学生になり自分から学べる力、時間管理力、思考力、ストレス対処力などをどう育てていくかも意識する必要があります。
目の前の成績よりも、その先で自力で学び続けられる力があるかどうかに目を向けておくべきです。
そこで今回は、小4の壁を乗り越えた後のことを考える重要性をご紹介していきます。
学習内容の複雑さは加速する
まず、学習内容の複雑さ、難化が加速します。
ですから、小4の壁を気にする親は多いですが、それを乗り越えたからといって安心してしまうのは危険です。
実際には、本当の勝負は小学校高学年から始まると言っても過言ではありません。
小4は学習内容の「質」が変化し始める時期ですが、小学校5年生、6年生、そして中学にかけては、その複雑さ、学びがますます抽象化していきます。
小学校高学年になると、単なる知識の暗記では太刀打ちできない内容が増えてきます。
たとえば、算数では【割合】【速さ】【立体図形】など、複数の考え方を組み合わせて問題を解く力が求められます。
国語では、文章の要点を捉えたり、筆者の主張を読み取ったりと、読み解く力の深さと広がりが問われるようになります。
今までなじみのなかった古文の勉強もスタートします。
理科や社会も記憶中心の学習から、【なぜそうなるのか】【どうしてそう考えるのか】といった思考型の学びへと移行していきます。
資料を見て意見を書かせる問題もカラーテストで出題されるようになるので、理科と社会でもハッキリとした点数差が出てくるのも小学校5年生からになります。
さらに中学に進学すると、英語や数学といった単元の積み上げ型教科が本格化し、授業スピードも格段に早くなります。
定期テストの成績が内申点に直結するため、計画的な学習、提出物管理、部活動との両立など、子ども一人一人の【学習+生活管理】の総合力が問われます。
ある意味、牧歌的な生活から自分の実力が様々な角度から評価される社会人の世界に足を踏み入れるようになるのです。
学校生活など全てにおいて大きく変わる未来が目前に迫ってくるので、小学生の頃から中学生になってからの生活を説明し、テストや模試の存在と役割や、今からできることとして日々の学習結果をもとに【何ができて、何が苦手か】を親子で確認する機会を設けていきましょう。
中学では自己管理力が求められるため、小学生のうちからその感覚を持たせることが大切です。
中学進学後の対応力はレベルが違う
さて、小学生時代の最大の難所ともいえる小4の壁を乗り越えても、その先に待ち構える中学進学後の世界は小学生の感覚でいくと痛い目にあいます。
勉強、部活などの対応力もレベルアップするからです。
親が小4の壁を気にして見守り、無事に乗り越えたことに安堵するのは自然なことですが、そこで安心しきってしまうのはとても危険です。
実際のところ、本当の勝負は中学進学後から本格的に始まります。
中学校では、授業内容、スピード、評価方法、一日の生活リズムのすべてが小学校とはレベルが違い、対応できるかどうかで学力差が一気に広がります。
その現実に備えるためには、小学校高学年からの【移行期間】をどう過ごすかがカギを握ります。
中学校では、教科担任制によって一人の先生が一教科を専門的に教えるため、授業の進度は早く、説明も抽象的になります。
また、提出物・定期テスト・内申点などが成績に大きく関わり、自分で計画を立てて取り組む力、つまりは自己管理力が不可欠になります。
小学校では先生や親が自然にフォローしてくれていた部分が、中学では【自分でやるのが当たり前】に変わるので、小4の壁の後は中学進学に向けた準備をしていくことを怠らないでください。
小4の壁を越えた段階では、まだ基礎力の確認が終わったにすぎせん。
ここから先に育てたいのは、【学習習慣の定着】【振り返りと自己修正力】【メリハリある時間の過ごし方】を子ども自身ができるようになることです。
教育方針がしっかりしている、子どもの教育に関心のある親は小学生時代に毎日一定時間、机に向かう習慣を作り、学びを当たり前にしています。
しかし、中学でさらに学力をつけていくには宿題以外にも自分で復習や問題演習をする時間を持つことが重要になります。
そして、【できた】【できなかった】を確認し、次の対策を自分で考える習慣をつけます。
親は【何がうまくいった?】【どこが難しかった?】と問いかける形でサポートをするのが理想的です。
勉強と部活、塾通いをする子も増える中学生になると自由時間が激減します。
遊び・勉強・休憩をバランスよく管理できる力、テスト前に計画的に準備できる感覚を、小学生のうちから少しずつ育てておくと中学での対応力が高まります。
小4の壁を乗り越えたからといって油断は禁物です。
むしろそこから先が本番であり、中学では“学力の深さ”と“生活力”が試されるステージが始まります。
そのためには、小学校高学年のうちに、ただ勉強ができるだけでなく、【自分で考えて、動ける力】を少しずつ育てることが必要です。
親もその変化に合わせてサポートの形を調整し、子どもが安心して挑戦できる環境を整えていきましょう。それが、中学での飛躍につながる土台となります。
成長とともに精神面の変化も訪れる
ところで、小学校高学年から中学生にかけての時期は、学力の差が広がるだけでなく、反抗期や思春期といった精神面での大きな変化が訪れます。
親としては、小4の壁を無事に過ぎてほっとしたのも束の間、精神面の変化と直面することになります。
小学校高学年になると、身体的な変化だけでなく、精神的にも自立心が芽生えてきます。
【自分の考えを持ちたい】【親に干渉されたくない】という気持ちが強まり、親に対して反発的な態度をとるようになることも珍しくありません。
これは自然な成長の一環であり、心が成熟していく過程です。
しかし、親がそれを理解せずに【言うことを聞かない】【生意気になった】と否定的に受け止めると、子どもとの信頼関係が崩れ、学習意欲や自己肯定感の低下につながる恐れがあります。
そして、思春期には、友人関係や自分の将来について悩む機会も増え、集中力が下がったり、成績が不安定になったりすることがあります。
中学生になると、部活動や定期テスト、内申点といったプレッシャーも加わり、心の不安が学業に直結しやすい時期です。
状況を改善しようと【勉強しなさい】と言うだけでは通用しません。
まずは、心の安定が学びの土台であることを親が理解し、精神面のサポートを重視することが求められます。
対処法として家庭でできることは、子どもが不安やイライラを抱えているとき、すぐに正論で諭すのではなく、まずは気持ちを受け止めることが大切です。
【そう思うのも無理ないね】【つらかったんだね】といった共感の言葉は、子どもにとって安心材料になります。
信頼関係が築かれていれば、勉強の話も前向きに聞き入れやすくなります。
高学年以降は、子ども自身が【選ぶ経験】を通して、判断力や責任感を育てる時期です。
勉強方法や生活のルールも、一方的に決めるのではなく、【どうしたい?】【どうすればうまくいくと思う?】と問いかけながら、本人の意思を尊重する姿勢が、精神的な自立を促します。
感情的に注意するよりも、集中できる学習環境や、安心して話せる家庭の雰囲気を整えることが効果的です。
あえてリビングに勉強スペースを作る、短時間でも一緒に勉強する、親も読書や学びに取り組むなど、家庭全体が【学びに前向きな空気】に包まれることが、子どものモチベーションを支えます。
小4の壁を超えた先には、学力だけでなく精神面の成長という新たな課題が訪れます。
反抗期に入り、思春期の入り口にいる子どもたちは、揺れる心を抱えながらも、自分なりに前へ進もうとしています。
その時に親が【管理する者】ではなく【理解する者】として寄り添うことで、子どもは安心して自立し、学びにも前向きになれます。
親の見守り方が、これからの成長を大きく左右するカギとなることを意識してください。