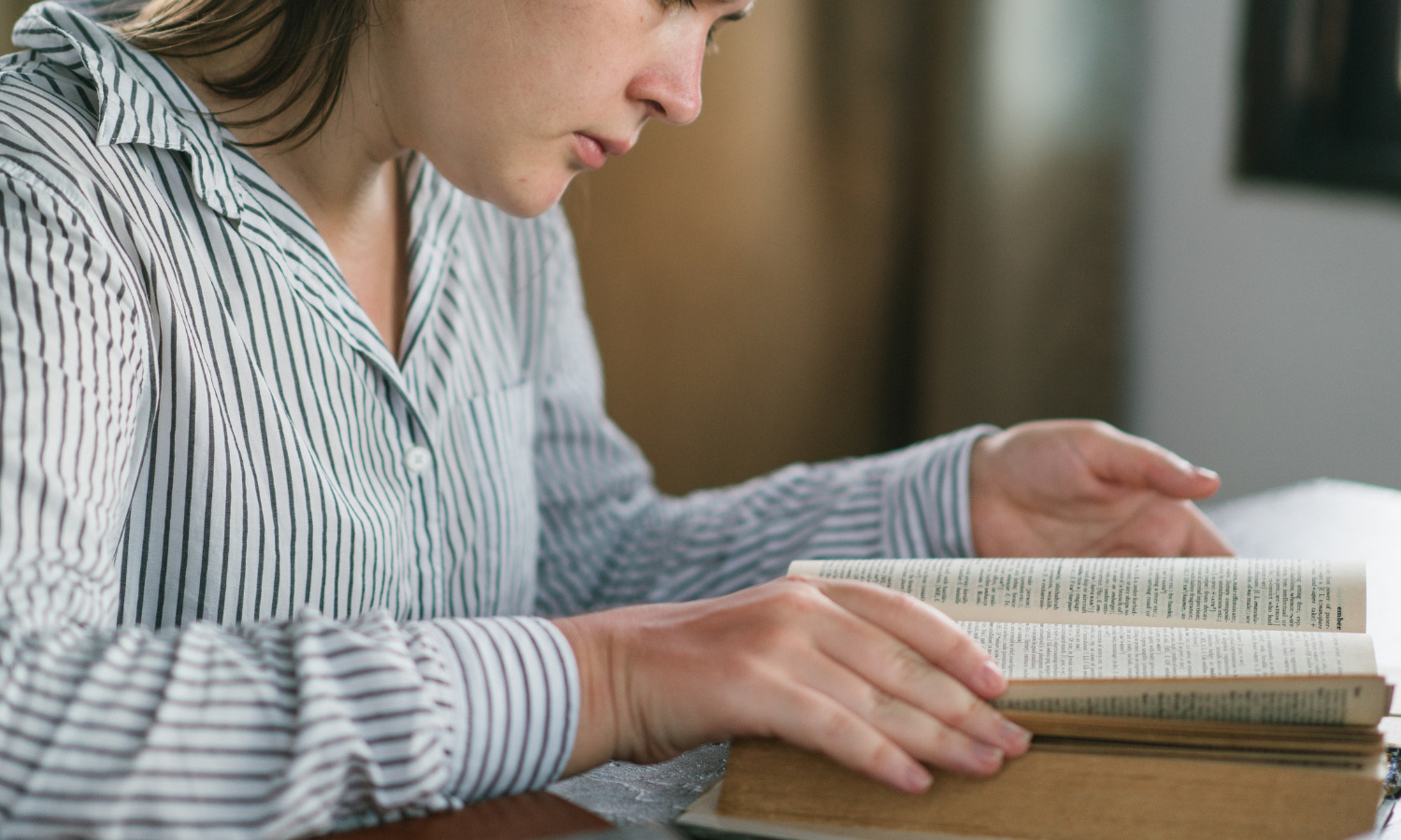今回は【テストで満点でも危険 優等生が陥りがちな【抽象概念】理解の落とし穴】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学生や中学生でテストの点数が良く、いわゆる【優等生】と言われてきた子でも、学力の伸び悩みに直面することがあります。
とくに中学後半から高校レベルの学習に入ると、【なんでこんなに頑張ってるのに成績が伸びないの?】という壁にぶつかることが少なくありません。
その原因のひとつが、【抽象概念の理解不足】です。
計算問題や暗記中心のテストでは満点を取れる子でも、文章題や応用問題になると急に点数が下がる。
これは、単なる努力不足ではなく、概念を意味として理解する経験が少ないことに起因しています。
そこで今回は、テストでは優秀なのに抽象概念でつまずく子の特徴と、そこから脱却するための改善策、さらに考え方の意識改革について3つのパートに分けてお伝えします。
テストの点だけでは見えない学力の本質を、親子で見直すきっかけになれば幸いです。
満点でも危険?抽象概念が苦手な優等生の3つの特徴
まず、小学校のテストでいつも高得点を取っている優等生。
親としては【この子は安心】と思ってしまいがちです。
しかし、実はその満点が、中学から必要になる学びの本質的な理解を妨げている場合もあります。
とくに危険なのが【抽象概念の理解が不十分なまま、高得点を維持している子ども】です。
たとえば、公式や語句を覚えるのは得意なのに、なぜそうなるのかを説明できない。
応用問題になると手が止まる。文章題になると途端に正答率が下がる。
そんな傾向があるなら、すでに表面的な理解にとどまっている可能性があります。
これは決して本人の能力が低いわけではなく、小学校や中学初期の学習が【正確に覚えれば点が取れる構造】になっていることが大きく影響しています。
そのため、深く考える癖や抽象的なものを自分の言葉で理解する力が育たないまま、表面だけで乗り切ってしまうのです。
ですが、当然ながら学年が進むにつれ、応用力・思考力・表現力が問われる問題が増えていきます。
高校入試でも大学入試でも、【公式だけ知っていても解けない】問題は確実に増えています。
今、表面だけの理解に甘んじていると、必ずどこかで壁にぶつかります。
ここでは、そうした抽象概念の理解が苦手な優等生に見られる特徴を3つに分けて解説していきます。
早い段階で気づくことができれば、十分に軌道修正は可能です。
特徴①表面的な暗記が得意で意味理解が浅い
多くの優等生は記憶力に優れており、テストで高得点を取るのも難しくありません。
語句の意味、歴史の年号、数学の公式、理科の用語など、いわゆる【知識系】の問題は、短期間の集中学習でも対応できます。
その結果、【テスト=覚えたら勝ち】という学習パターンが自然と定着してしまいます。
しかしこの習慣には、大きな落とし穴があります。
それは【意味理解が伴わない】まま知識が積み重なっていくことです。
たとえば、【速さ=距離÷時間】という公式を暗記していても、【なぜこの式になるのか】【単位がどう変化するのか】といった背景まで理解していないことが多いのです。
こうした子どもは、暗記の範囲ならスラスラ解けても、公式の使い方が少しでも変わると混乱します。
応用問題やグラフを含む出題に対して、【意味を考える】ことに慣れていないため、問題文を読み取る力も育っていません。
一見、学力が高いように見える子どもが、学年が進むにつれて伸び悩むのはこのためです。
【暗記=理解】という誤解のまま中学・高校の学習に進むと、理解型の問題に対応できず、点数が伸びなくなる傾向が強まります。
だからこそ、早い段階で【覚えるだけでなく、意味を理解しているか】に目を向けることが重要なのです。
特徴②応用問題や文章題に極端に弱い
優等生であっても、応用問題や文章題になると一気に苦手意識を持つ子がいます。
とくに小学校や中学初期では、基礎的な計算問題や知識問題で点を稼げるため、応用や記述のトレーニングが不足しているまま高得点を取り続けてしまうことがよくあります。
応用問題とは複数の情報を組み合わせたり、自分の考えを論理的に整理したりする力が求められる問題です。
文章題は、その情報を文章から読み取る読解力と、問題にどう対応するかを判断する力の両方が必要になります。
このような問題で力を発揮するには、【抽象概念を理解し、それを具体的に使いこなす力】が求められます。
小学校の算数の山場でもある割合や比の問題では、【何と何を比べているのか】【全体に対してどれだけか】を読み取る力が必要です。
理科や社会でも、【なぜそうなるのか】を考えさせる問題が増えており、単なる用語の暗記では太刀打ちできません。
また、応用力はそう簡単に身につくものではなく、考える経験の積み重ねがものを言います。
そのため、基本問題ばかり解いていると、応用力が育たないまま学年が進んでしまうことになります。
テストで高得点を取れていても、応用問題に歯が立たないなら、それは学力の危険信号のひとつと言えるでしょう。
特徴③説明させると【言葉が出ない】
優等生の中には、テストの問題はスラスラ解けるのに、解き方や理由を口頭で説明させると急に言葉が詰まる子がいます。
【どうしてそうなるの?】【なぜその答えになったの?】と質問しても、【えっと…たぶんこうだから】と曖昧な返答しかできないのです。
これは、問題の解法をなんとなく覚えていても、頭の中で整理されておらず、言語化できていない状態です。
つまり、理解が浅いことを意味しています。
特に抽象概念は、言葉で説明するプロセスを通して初めて本当の理解につながります。
説明できないということは、自分でも本質的に分かっていない可能性が高いのです。
【説明する力】は、思考力・表現力と密接に関係しており、最近の入試でも重視されています。
文章で説明させる問題や、論述・記述型の問題は、表面的な理解では対応できません。
【考えを言葉にする】訓練を日頃から行っておかないと、対応できなくなります。
家庭での学習でも、子どもに【どうやって考えたの?】と質問する習慣をつけることで、思考の整理や表現の訓練になるので、紙の上だけで完結せず、言葉としてアウトプットさせることが、真の理解を深める第一歩になります。
抽象概念を育てるための3つの改善策
さて、先ほどは優等生であっても抽象的な概念をうまく理解できていないケースがあること、そしてそのような子どもたちに見られる3つの特徴を紹介しました。
では、どうすればこの【抽象概念への弱さ】を克服できるのでしょうか?
それには、毎日の学習におけるちょっとした工夫が非常に大きな効果をもたらします。
特別な教材や塾に頼らなくても、家庭の中でできる改善策は数多くあります。
意識すべきは【理解の深さ】に着目して取り組み方を変えることです。
これまでのように、暗記やパターン化された学習だけに頼っていては、思考力や応用力を伸ばすことは難しくなります。
そして、子ども自身に【考える】体験を与えることも大切です。
自分で疑問を持ち、納得しながら理解していく学習プロセスを通じて、抽象概念は着実に頭の中に定着していきます。
そのためには、親の関わり方や声かけも大きなカギとなります。
ここでは、抽象的な考え方を育てるための3つの具体的な改善策を紹介します。
【今すぐ実践できること】ばかりなので、毎日の家庭学習の中に自然に取り入れてみてください。
点数だけにとらわれない本質的な学力を育てることができるはずです。
改善策①【なぜ?】と問い返す家庭の会話を習慣に
抽象概念を理解する力は、ただ教科書を読むだけでは育ちません。
ポイントは、子ども自身が【なぜそうなるのか】【どうしてこう考えたのか】と、自分の頭で理由を探すことにあります。
これを日常の会話の中に取り入れるのが、もっともシンプルで効果的な方法です。
子どもが問題を解いて【できた!】と言ったとき、そのまま褒めるだけでなく、【どうしてその答えになったの?】【なぜそう考えたの?】と問い返してみましょう。
こうした質問を通じて、子どもは自分の思考過程を言葉にする練習ができます。
これが、思考の整理や論理力の土台をつくるのです。
また、この問い返しの習慣は、子どもにとって【ただ答えること】以上に、【考えを深めること】の大切さを教えてくれます。
はじめはうまく言葉にできなくても、繰り返すうちに自然と自分の考えを組み立てる力がついてきます。
注意したいのは、問い返しが詰問にならないこと。
子どもを責める口調ではなく、【知りたいから教えて】という姿勢で聞くことが大切です。
親が答えを出させるのではなく、一緒に考えるという雰囲気を作ることで、子どもも安心して思考を言葉にできるようになります。
改善策②図解や具体例で視覚的に理解させる
抽象概念を学ぶとき、言葉だけの説明では子どもにとって難解になりがちです。
とくに小学生〜中学生の段階では、頭の中でイメージする力がまだ発展途上にあるため、【見て理解する】工夫が欠かせません。
そこで効果的なのが、図や具体例を使って視覚的に理解を助ける方法です。
たとえば、割合の学習で【30%オフ】と言われても、数式で理解するだけではピンとこない子もいます。
そんなときは、実際に買い物の例や金額を使って、【この商品が1,000円で30%オフなら、どうなる?】と具体的に考えさせると、数式と現実が結びつき、理解が深まります。
また、理科の変化や社会の構造なども、絵や図にして整理すると頭に入りやすくなります。
言葉で覚えさせるのではなく、【目で見て納得させる】ことで、知識がイメージとして記憶され、長く残りやすくなります。
学校の教科書にも図や表はありますが、家庭ではさらにそれを活用し、子どもと一緒に簡単な図を描きながら考えるのがおすすめです。
手を動かして自分で図解することで、頭の中が整理されていきます。
抽象的な学びを【見える形】に変えること。
それが、子どもの理解力を一段階引き上げる重要なステップとなります。
改善策③異なる教科をつなげて考える力を養う
抽象概念の理解を深めるには、【教科を超えて考える力】を育てることがとても効果的です。
これはいわゆる教科横断型の学習と呼ばれ、実際の生活や入試問題でもますます重視されるようになっています。
たとえば、理科で【水の状態変化(気体・液体・固体)】を学ぶとき、ただ実験結果を覚えるだけではなく、【これって国語の説明文でも出てきたよね】【算数で習った温度のグラフと同じ考え方が使えるね】といった具合に、他教科とのつながりを意識させるようにしていきましょう。
このように、学んだ知識を別の文脈で再活用する経験が増えると、子どもは意味のある学びとして知識を捉えるようになります。
これは単なる暗記とは異なり、【使える知識】へと変化していきます。
家庭でも、【これは他の教科にも出てくるね】【このニュース、社会で習ったことと関係あるね】といった一言を添えるだけで、子どもの思考の幅が大きく広がります。
抽象的な内容ほど、他の事例との関連づけが理解を助けてくれます。
抽象概念をしっかりと定着させたいなら、教科を分断せず【すべてはつながっている】という視点を持つことがカギになります。
このような学び方ができる子は、応用力も非常に強くなります。
抽象概念に強くなるための3つの意識改革
ところで、ここまで抽象概念の理解に苦しむ優等生の特徴と、それに対する具体的な改善策をお伝えしました。
テストの点数では見えにくい【理解の深さ】を育てるには、思考を言語化させたり、図解でイメージさせたりといった、日々の積み重ねがとても大切です。
しかし、これらの方法を実践する前提として、もっと根本的な部分、つまり【考え方】や【価値観】の部分を変えていく必要があります。
優等生として小学校時代を過ごしてきた子どもほど、【早く正解することが正義】【ミスをしないのが優秀】といった思い込みを抱いていることが多く、それが抽象的な学びの成長を妨げてしまうことになります。
また、子どもだけでなく親の意識も大きく影響します。
【点数だけで評価していないか】【すぐに答えを教えてしまっていないか】など、親子の関係の中にある見えない壁が、実は学びの質を左右していることも少なくありません。
ここでは、抽象概念に強くなるために、子どもと親の両方に必要な3つの意識改革を紹介します。
これは日々の学習態度や声かけの中で変えていけるものであり、大きな環境を変える必要はありません。【すぐに成果は出なくても、確実に力になる】意識の土台作りを、一緒に考えていきましょう。
意識改革①【できた・わかった】より【説明できる】を目指す
多くの子どもは、問題を解いたときに【できた!】【わかった!】と口にします。
しかし、その理解がどのレベルの理解なのか、親や先生が確認してみると、意外と曖昧なことが少なくありません。
勉強する単元が抽象的な内容ほど、表面ではわかっているつもりでも、深い理解には至っていないケースが多いです。
こうした状況を改善するために、ぜひ意識してほしいのが【説明できることを目指す】学び方です。
つまり、【答えを出せた】だけで満足せず、【その理由を言葉で説明できるか】を確認していくスタイルに切り替えることです。
説明することで、頭の中の知識が整理され、自分の理解の浅さにも気づけるようになります。
最初はうまく言葉が出なくても、それが当たり前です。
大切なのは、【答えを出す】ことではなく、【どうしてそう思ったのかを考える】プロセスに目を向けること。
たとえば、家庭での学習中に【この答えになった理由を教えて】と聞くだけで、子どもの思考はグッと深くなります。
説明しようとする中で、自分でも気づかなかった理解の穴を見つけることができるからです。
【説明できる】ことを目標にすることで、単なる暗記型の学習から、思考力と表現力をともなった本物の理解へとシフトしていきます。
意識改革②【すぐに正解を出すこと】が学力の証とは限らない
多くの優等生が【正解を早く出すことこそ優秀】と信じています。
確かに、小学校では早く正解できる子が褒められ、テストでも高得点につながるので、そのような価値観を持つのは自然な流れかもしれません。
しかし、抽象的な学びにおいては、【時間をかけてじっくり考える力】の方が圧倒的に重要になります。
抽象概念は、すぐにはピンと来ないものが多く、見た目はシンプルでも裏には複雑な関係性が隠れています。
それを理解するためには、【わからない時間】に耐えて、何度も考え直す粘り強さが求められます。
逆に、すぐに正解を求めすぎる子は、少しでも難しいと感じると投げ出してしまう傾向が強いです。
このような傾向を防ぐためにも、家庭では【考える時間を尊重する】空気を作ってあげましょう。
問題を解くときに時間がかかっていても、【ゆっくりでいいよ】【考えられていて偉いね】と声をかけることで、子どもは正解の速さより考える過程を大事にするようになります。
また、親自身も【答えを早く出してほしい】という期待を手放すことが重要です。
すぐに答えを教えてしまわず、【どう思う?】と子どもに問い返すことで、自分の頭で考える力が自然と育ちます。
スピードよりプロセス。
これは、将来の本物の学力を育てるために欠かせない視点です。
意識改革③【間違えた=失敗】ではなく【気づき=成長】ととらえる
優等生ほど【間違えること=悪いこと】【失敗=恥ずかしいこと】と感じやすい傾向があります。
これは、常に高い評価を受けてきたことや、周囲の期待を感じ取っていることが背景にあります。
しかし、この間違いを恐れる姿勢こそが、学びの最大のブレーキになります。
抽象概念を理解しようとする過程では、最初から正しく理解できる方が珍しく、試行錯誤しながら少しずつ整理されていくものです。
むしろ、間違いを通して【なぜ間違えたのか】【どこを勘違いしていたのか】に気づくことが、学びの最も重要なステップになります。
そのためには、家庭でも【間違えたことを叱らない】【間違えたことを前向きにとらえる】雰囲気づくりが欠かせません。
たとえば、【ここで間違えておいてよかったね】【間違いから大事なことに気づけたね】と声をかけることで、子どもは徐々に間違いを恐れなくなります。
また、親自身が【完璧じゃなくても大丈夫】という姿勢を見せることも効果的です。
大人でも間違えるし、そこから学べるというメッセージを伝えることで、子どもも安心して挑戦できるようになります。
【間違えたらダメ】ではなく、【間違えてこそ成長できる】。
この価値観の転換こそが、抽象概念をしっかりと身につけるための土台になります。
【満点】の奥にある本当の理解力を育てるために
一見すると安心できる【満点のテスト】や【常に上位の成績】。
しかしその裏に潜む抽象概念への理解不足という落とし穴に、気づいているご家庭は意外と少ないものです。
今回通してお伝えしたのは、【高得点=深い理解】とは限らないという現実。
そして、これからの学力に必要なのは、【なぜそうなるのか】【どうしてそう考えたのか】を自分の言葉で説明できる力である、ということです。
まず、抽象概念が苦手な優等生の3つの特徴として、【表面的な暗記学習】【応用・文章題への弱さ】【説明できない理解の浅さ】を紹介しました。
どれも、点数では見抜けない学力のひずみです。
続いて、その課題を克服するための3つの改善策を提示しました。【家庭での問いかけ】【視覚的な理解の補助】【教科をまたいだ学びの連携】。これらは、特別な教材や環境がなくても、親子の日常の中で実践できるものばかりです。
そして最後により根本的な部分、子どもと親の意識のあり方を見直すことの重要性を伝えました。
【説明する力を意識する】【スピードより過程を大切にする】【間違いを受け入れ、学びに変える】
こうした意識の変化が、学力の質そのものを変えていきます。
今、満点が取れているからといって、それが将来まで通用する本物の学力とは限りません。
見えない落とし穴に気づき、早めに手を打つことが、伸び悩みを防ぎ、真のトップ層へと成長するカギとなります。
ぜひこの機会に、お子さんの理解の深さに目を向け、点数の裏にある【思考力】や【抽象的な理解力】を育てていきましょう。