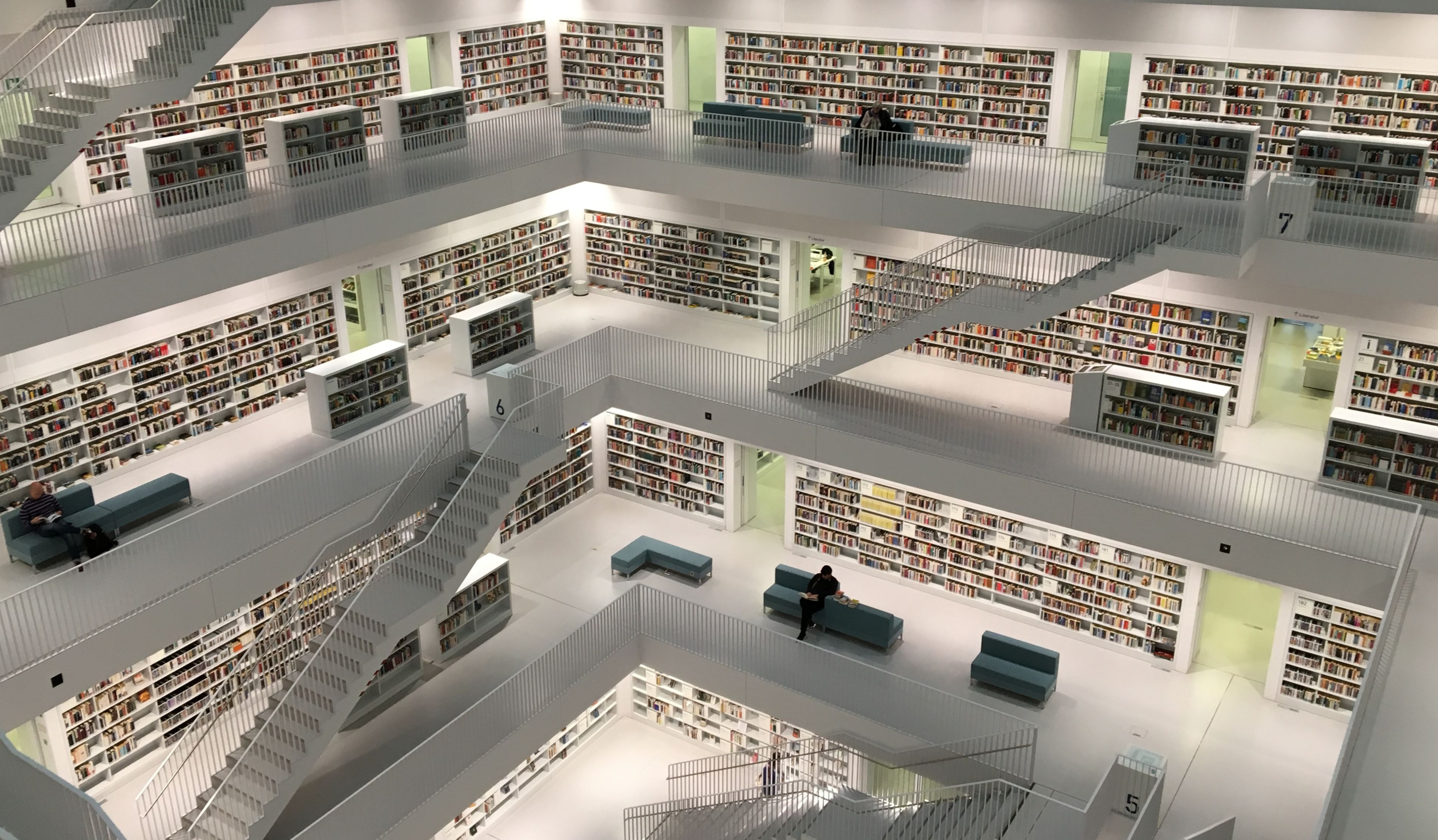今回は【中学生になって転落 高校受験で偏差値55未満に進学する元優等生】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校時代、テストでは常に90点以上、先生からも【しっかり者】と評価されていた子が、中学生になった途端、成績が伸び悩み、最終的に偏差値55未満の高校へ進学する。
このようなケースは決して珍しくありません。
私も、【小学生時代は優等生だった】という子に、自分の小中学生、そして塾で仕事をしている時にも出会っています。
中学に行っても安泰と思われるような【小学校の優等生】こそ、成績の転落リスクを抱えていると言っても過言ではないです。
中学の学習内容は急に難易度が上がり、定期テストの結果や提出物、内申点が進路に直結する世界に変わります。
ところが、小学校での成功体験を引きずっていたり、自分だけが先行していたりすると、変化に対応できず、周囲との差が一気に開いてしまうことがあります。
そこで今回は、【元優等生】がなぜ転落してしまうのか、その背景となる3つの特徴を分析し、続いてそのようなタイプの子たちに対して小学生のうちに取るべき3つの具体的な改善策を紹介し、最後に学力回復のために必要な親子の意識改革についてお伝えします。
失速を防ぎ、再び自信を取り戻すためにも小学生時代の成功に安住せず、今こそ地に足をつけた学び直しが必要です。
なぜ優等生が中学で転落するのか?
まず、小学生のときに【よくできる子】と言われていた子どもが、中学生になったとたんに成績が急落し、最終的に偏差値55未満の高校に進学するというようなケースは、決して稀なことではありません。
むしろ、小学校時代に高く評価されていた子どもほど、つまずきやすい傾向があります。
その理由は、中学校の学習や評価の仕組みが、小学校とは大きく異なるからです。
たとえば、学習内容が抽象的・論理的になり、覚えるだけでは解けない問題が増えます。
また、定期テストによる点数化、内申点への影響など、子どもにとって新しいプレッシャーも加わります。
しかし、多くの親や本人はこの変化に気づくのが遅れ、【なんでできないの?】と自信やモチベーションを失ってしまうことが少なくありません。
小学校でうまくいっていたことが、そのまま中学では通用しないという現実に、早めに気づき、対応を考えることが大切です。
ここでは、中学で成績が下がりやすい元・優等生の子どもに共通する3つの特徴を解説します。
当てはまる点があれば、それは改善へのヒントでもあります。
まずは現状を正しく知るところから、立て直しが始まります。
特徴①【理解力でなんとかなる】が通用しなくなる
小学生時代に成績が良かった子どもには、【とくに勉強しなくてもわかる】というタイプが少なくありません。
授業を聞いているだけで大体理解できるし、少し見れば問題が解ける。
そうした地頭の良さや直感的な理解力に頼って成績を取っていた子も多いでしょう。
しかし、中学に入ると状況は一変します。
学習内容が抽象化・複雑化し、単なる理解だけでは解けない問題が増えてきます。
とくに数学や英語では、順を追って基礎から積み上げないと理解できない単元が続きます。
そのため、表面的に理解しただけでは応用問題に太刀打ちできなくなり、【今まで通りではダメだ】と気づいたときにはすでに遅れているケースもあります。
また、小学校では説明されればすぐ分かるという自信が、逆に復習や演習の習慣をつけることを妨げていた可能性もあります。
その結果、反復学習に慣れておらず、時間をかけて勉強する姿勢が身についていないのです。
こうした子は、【わかる】と【できる】の違いに気づき、初めて本当の学習のスタート地点に立つことになります。
特徴②【テスト勉強】の経験不足で結果が出せない
小学校では、単元ごとの確認テストが中心で、いわゆる定期テストのような大がかりな試験はあまり行われません。
ところが中学に入ると、年に数回の中間・期末テストがあり、5教科を一気に勉強する必要が出てきます。この大きな変化に戸惑うのが、元優等生の子どもたちです。
とくに、これまで【自然にわかる】ことで成績を取っていた子どもは、【何をどれだけ勉強すればよいのか】【どうやって復習すれば定着するのか】といった戦略的な勉強の仕方を知りません。
その結果、テスト前に慌ててノートやワークを見直しても、十分な準備ができずに低得点を取り、自信を失ってしまうのです。
さらに、提出物や課題も評価対象になる中学の内申制度に対し、小学生のときにその重要性をあまり実感していなかった子は、【提出を忘れる】【質が雑】といったミスを繰り返し、成績に影響していきます。
テスト勉強とは単なる暗記ではなく、【計画】【実行】【振り返り】を含むスキルです。
ここに早く気づき、適切な学習習慣を身につけることが、元優等生の再浮上には不可欠です。
特徴③【相対評価】の部分で初めて挫折感を味わう
小学校では、絶対評価を基本とする指導が多く、周囲との比較よりも【自分がどれだけ理解できたか】が重視されてきました。
通知表の評価も、がんばり次第で多くの子が高評価を得られるように設計されています。
そのため、優等生だった子どもは、【自分は勉強ができる】と自然に思い込みやすい側面があります。
しかし、中学校ではテストの順位や偏差値、内申点といった相対評価の部分が影響してきます。
学年順位が掲示されたり、模試の結果が数字で返ってきたりする中で、初めて【自分より上がいる】という現実を突きつけられることになります。
小学校時代に【常に一番】【先生に褒められる】ことが当たり前だった子にとっては、この変化が大きな挫折となります。
自信が揺らぎ、やる気を失い、勉強へのモチベーションも下がっていくのです。
この【自信喪失のサイクル】を断ち切るには、他人との比較から離れ、【昨日の自分よりできたか】に視点を変える意識が必要です。
そうした心の持ち方が、安定した学習姿勢と再成長の基盤になります。
成績転落を止めるには【勉強のやり方】そのものを変えるべき
さて、中学で思うように成績が取れなくなった元優等生に必要なのは、【もっと頑張れ!】という根性論ではありません。
小学校の成功体験に頼っていた勉強法を、中学仕様にアップデートする必要があるのです。
多くの子どもが【なぜ勉強しても点が取れないのか分からない】と感じていますが、それは本人の能力の問題ではなく、勉強の仕方や準備の方向性がズレているからです。
たとえば、テスト勉強の方法が場当たり的であったり、苦手を放置したまま先に進んでしまっていたり、提出物や授業態度の重要性を軽視しているといった学習習慣の隙が、内申点や定期テストの結果に表れてきます。
しかし逆に言えば、やり方を変えれば結果も変わります。
必要なのは、【小学生のときと違うステージにいる】という意識と、それに合わせた具体的な対策です。
ここでは、転落を止め、再浮上するために必要な3つの改善策をご紹介します。
どれも今日から家庭で取り組める内容です。
改善策①【勉強の計画】と【振り返り】を習慣化する
多くの中学生がつまずくのは、【勉強の中身】ではなく【勉強の進め方】です。
テスト前に一気に詰め込むだけのやり方では、中学の定期テストには通用しません。
まずは1〜2週間前から逆算して、教科ごとに何をするべきかをリスト化する計画力が必要です。
その際、【この日に理科のワーク3ページ】【この日は社会の用語暗記】といった具体的な行動に落とし込むことがポイント。
さらに、計画を立てて終わりにせず、実行後に【どこができたか】【まだ覚えていない部分はどこか】といった振り返りを入れることで、学習の質がぐっと高まります。
この【PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)】は、勉強に限らず将来的な自己管理力の基礎にもなります。
最初は親が一緒にスケジュールを立てたり、振り返りの時間を一緒に設けたりすると、子どもは自然と自分の勉強を自分ごととして捉えるようになります。
学習内容に追われる前に、【どう学ぶか】を見直すことが、成績回復の第一歩です。
改善策②【苦手教科】は小単元に分けて戻り学習
中学で成績が伸びない子どもに共通するのは、苦手教科を放置してしまう傾向です。
しかも、【どこからわからなくなったか】が自分で把握できていないため、勉強のスタート地点が見えず、やる気も起きなくなってしまいます。
このような時は、苦手教科を一気に克服しようとするのではなく、まずは【小単元ごと】に分けて、ピンポイントで戻り学習をすることが大切です。
たとえば数学なら【正負の数だけ復習する】、英語なら【be動詞と一般動詞の違いだけに絞る】といったように、範囲を限定して取り組むことで、達成感が得られやすくなります。
また、理解できた箇所から順に前に進んでいくことで、自信が少しずつ回復していきます。
【わからない】をそのままにせず、一度立ち止まって丁寧に見直す姿勢は、学力の土台を作り直す上で不可欠です。
元優等生だった子は【できない自分を認めたくない】というプライドから、苦手を放置しがちです。
しかし、できないことを認める勇気こそが、学力回復のスタート地点です。
小さな【できた】を積み重ねることが再浮上の鍵となります。
改善策③提出物・授業態度の評価ポイントを見直す
中学では、定期テストだけでなく、授業中の態度や提出物の状況が内申点に大きく関わってきます。
ところが、元優等生だった子ほど【点数さえ良ければ大丈夫】と思い込んでしまいがちで、これが大きな落とし穴になります。
提出物を雑に仕上げたり、ギリギリに出したりしていると、先生からの印象も悪くなり、評価が下がります。
また、授業中の姿勢も重要で、【ノートを取っているか】【質問に対してリアクションしているか】【発言や発表に前向きか】など、細かな行動が観察されています。
特別なことをする必要はありませんが、例えば【提出物は2日前までに出す】【ノートは先生の板書+自分の気づきを書き足す】【授業の最初に姿勢を正す】といった、当たり前の行動を徹底するだけで評価は大きく変わります。
また、家庭でも【提出物出せた?】【授業、発言できた?】と声をかけて関心を持つことで、子どもの意識は確実に変わります。
テスト以外の部分を丁寧に整えることで、総合評価としての内申点も着実に上がっていくのです。
心の壁を越えることで勉強は再び動き出す
ところで、中学で成績が落ち込んでしまった子どもに必要なのは、勉強方法の見直しや計画力だけではありません。
実はそれ以上に大きな鍵を握るのが【意識の持ち方】です。
とくに小学校時代に優等生だった子どもは、自分の成績が落ちたことをなかなか受け入れられず、プライドや自信喪失から立ち直れないまま、勉強に身が入らなくなるケースも多いです。
親としても、つい【前はできてたのに、どうしたの?】【もっと本気を出しなさい】と言ってしまいがちですが、こうした言葉は子どものプレッシャーを強めるだけで逆効果になることも少なくありません。
まずは、子ども自身が今の状況を客観的に見つめ、過去の自分と決別し、少しずつでも前に進むための意識の転換が必要です。
ここでは、勉強への意欲を取り戻すために効果的な3つの意識改革をご紹介します。
これらは特別なスキルではなく、親の関わり方や子どもの心の持ち方を少し変えるだけで実践できる内容です。焦らず、着実に【心の回復】から学力再生を目指しましょう。
意識改革①【過去の栄光】を手放して、今の自分を受け入れる
かつて優等生だった子どもほど、【昔の自分】に強くとらわれています。
小学校で常に高得点を取っていた、先生から褒められていた、クラスの中でも一目置かれていた。
そんな成功体験が強い分、今の自分とのギャップに苦しみやすいのです。
このような子は、今の自分を否定されたように感じ、【どうせやっても無駄】【自分はもうできない】と投げやりになる傾向があります。
しかし、本当に必要なのは過去の自分にしがみつくことではなく、今の自分を正しく見つめ直すことです。
テストの点が落ちた理由、提出物を忘れた理由、計画が崩れた原因。
すべてを冷静に振り返り、現実を直視することでようやく、次の行動が生まれます。
親としても、【昔はできていたのに】と過去を引き合いに出すのではなく、【今はどこが難しい?】【一緒に整理してみよう】と寄り添う姿勢が求められます。
過去を誇るのではなく、今を受け入れて、未来に向けて動き出す。
そこから本当の意味での学び直しが始まります。
意識改革②【間違い=悪】ではなく、【ミスから学ぶ】姿勢に
元優等生だった子は、間違いを極端に嫌う傾向があります。
【できる子】という評価を守ろうとするあまり、間違えることを恐れ、挑戦を避けるようになることもあります。
たとえば、難しい問題には手を出さない、間違えたノートを破ってしまう、間違いを指摘されると機嫌が悪くなる。
こうした行動は、完璧主義の裏返しとも言えます。
しかし、勉強とはそもそも【分からない】【できない】ことを理解し、それを乗り越えるプロセスです。
間違いは決して悪ではなく、成長のきっかけです。
むしろ、どこで間違えたのかを振り返ることで、理解はより深まります。
この意識を育てるには、家庭での声かけが重要です。
子どもがミスをしたときに、【どうして間違えたの?】と責めるのではなく、【よく気づけたね】【次はどうすればいいと思う?】と問いかけることで、失敗を前向きにとらえる習慣がつきます。
【間違えることを恐れない】【挑戦を楽しむ】
この姿勢こそが、学びを止めないための最大の武器です。
【意識改革③】他人との比較より【昨日の自分】と比べよう
中学校では、テストの順位や偏差値、成績の評価など、周囲との比較が一気に増えます。
その結果、【○○ちゃんより下だった】【あの子はいつも90点なのに】と、他人と自分を比べて落ち込む子が多くなります。
プライドの高い元優等生ほど、他人より劣っていると感じた瞬間に強く傷つき、自信を失いやすくなります。
この他人基準の思考は、成績だけでなく、心の健康にも悪影響を及ぼしかねません。
そこで必要なのは、視点の転換です。
他人と比べるのではなく、【昨日の自分】【一週間前の自分】と比較して、小さな成長を喜べるようになること。
それはたとえば、【前は5問中2問しか解けなかったけど、今日は3問できた】といったわずかな変化でかまいません。
家庭では、テストの点数だけでなく、【前より計画的に勉強できたね】【ワークを最後までやり切ったね】といった行動や努力に目を向け、具体的に褒めるようにしましょう。
自分比で前に進む習慣は、成績以上に強い心を育ててくれます。
長い受験期を乗り越えるためにも、この考え方を親子で共有していくことが大切です。
【元・優等生】からの逆転は気づきと行動から始まる
小学校時代に優等生だった子が中学で成績を落とす背景には、【勉強の方法】【環境の変化】【意識の持ち方】のズレがあります。
直感的な理解力や暗記力だけで何とかなっていた小学生時代とは異なり、中学の学習では計画的な学習習慣、論理的思考、反復練習、提出物の管理といった総合的な学びの力が求められます。
今回はまず最初に優等生の子がつまずく典型的な3つの特徴、理解力頼みの勉強法、テスト勉強の未経験、そして相対評価に対するメンタルの脆さを紹介しました。
これは決して個人だけの問題ではなく、環境の変化に適応できなかった結果です。
次に、立て直しに必要な3つの改善策として、【計画と振り返りの習慣化】【苦手単元への戻り学習】【提出物や授業態度の見直し】を挙げました。
どれも小さな実践の積み重ねで、確実に成果が出てきます。
さらに最後に再び勉強に向き合うために必要な意識改革として、過去への執着を手放すこと、間違いを成長のきっかけととらえること、そして他人ではなく昨日の自分と比べる視点の転換が重要であることを伝えました。
成績の転落は、一時的な停滞に過ぎません。
必要なのは、現実を正しく見つめ、柔軟に行動を変え、そして【変わっていける自分】を信じる力です。
元優等生の子どもたちは、もともと努力ができる素地を持っています。
だからこそ、正しい方向に導いてあげることで、再び自信と結果を取り戻すことができます。
本当の学力を取り戻すための第一歩を、今日から踏み出しましょう。