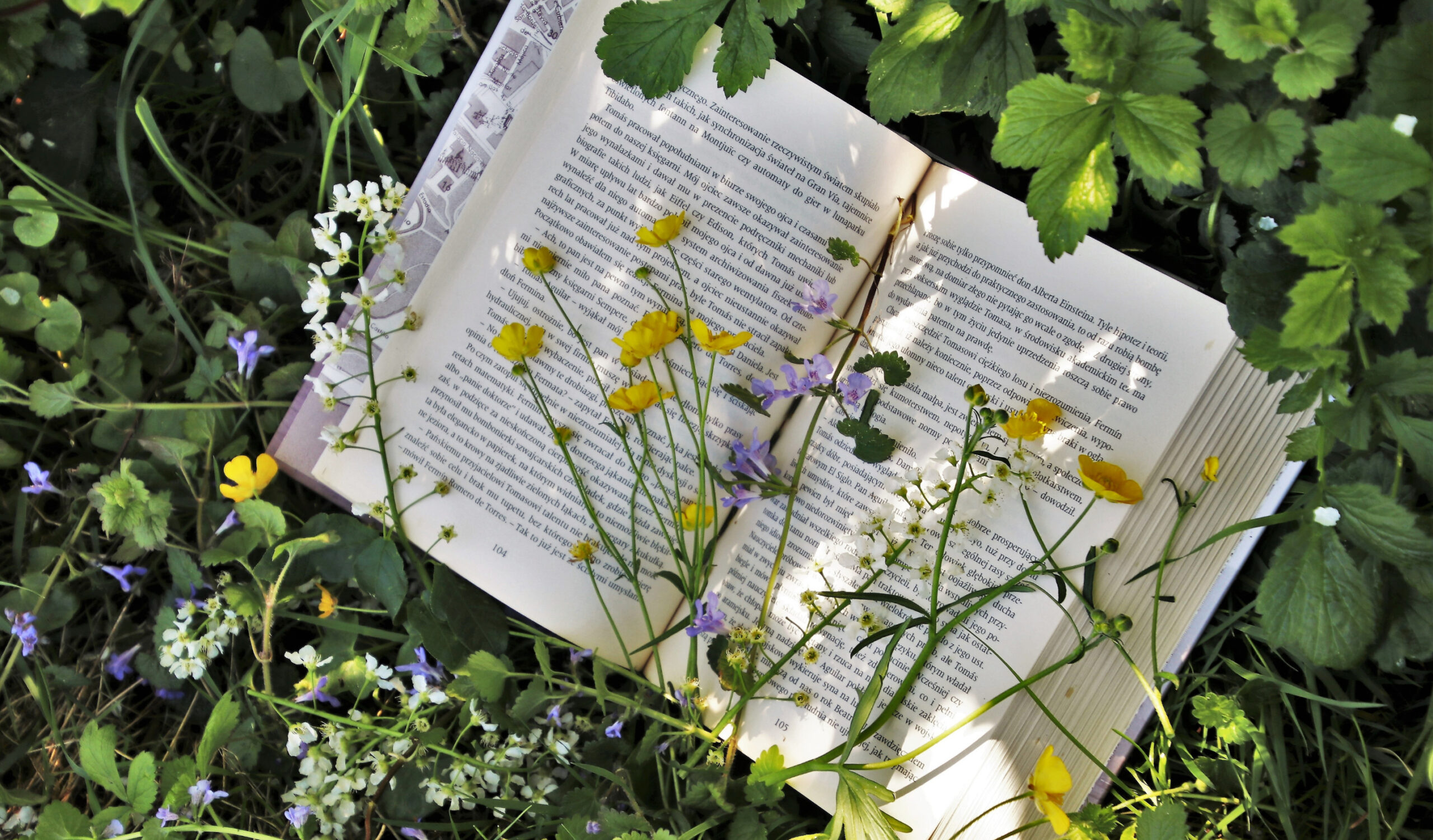今回は【学力一発勝負とはサヨナラ? 多様化する大学入試の下準備】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子どもが成長すると遅かれ早かれ【受験】と対峙することになります。
小学校受験、中学受験そして高校受験とありますが、子育ての集大成ともいえるのが大学受験です。
近年の大学入試は、【学力テストの点数だけで合否が決まる時代】という親世代の頃の常識から大きく変化しています。
特に私立大学では、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜(指定校推薦・公募推薦)による入学者が半数を超える大学も珍しくありません。
実際、2024年度の全国の私立大学での入学者のうち、推薦や総合型選抜を経て入学した新入生は59%を占めています。
今や、入試は学力一発勝負ではなく、【人物評価】や【経験】【将来のビジョン】などを含む多様な入試対策を考えることが求められているのです。
その一方で、こうした入試方式は【準備が早いほど有利】とも言われています。
高校に入ってから慌てて対応するのではなく、小学生や中学生の段階から【どんな力が求められるのか】を意識しておくことが、将来の選択肢を大きく広げるカギになります。
実際、子ども①の同級生たちの中でこうした入試制度の利用を検討している子たちは中学生の頃から色々と考え、高校1年生になってからより積極的に動いています。
そこで今回は、大学入試の多様化をふまえ、推薦や総合型選抜に向いている子の特徴、突破するための具体的な準備、そして家庭でできる学習のコツを3つのパートに分けてご紹介します。
まだ早いと思われがちな小中学生の時期こそ、将来に差がつく下準備を始める絶好のタイミングです。
推薦・総合型に向いている子の3つの特徴
まず、大学入試の現場では、年々【推薦型】や【総合型選抜】の比率が高まっています。
私立大学では、これらの方式で入学する生徒が半数以上を占めることも珍しくなく、今や主流とさえ言える状況です。
こうした入試は、一般選抜のように学力試験の点数で一律に評価するのではなく、その人がどんな経験をし、どのような意欲を持ち、何を学びたいのかを多面的に見て合否が決まります。
このため、単に【成績が良い】だけでは通用しない部分もあり、【どんなタイプの子が向いているのか?】という疑問を持つ親の方も多いでしょう。
推薦や総合型選抜で求められるのは、学力以上に【人間性】【主体性】【表現力】など、これまで見えづらかった力です。
ここでは、そうした推薦・総合型に向いている子どもの特徴を3つ取り上げて解説していきます。
これらの特徴は生まれ持った才能ではなく、小中学生のうちからの意識や環境づくりによって育てることができます。
お子さんの可能性を広げるためにも、今からできる小さな取り組みをぜひ意識してみてください。
特徴①好きなことに熱中できる
推薦や総合型選抜では、【どんなことに興味があり、どんなふうに取り組んできたか】が大きな評価材料になります。
そのため、好きなことに夢中になれる子は、この入試方式に向いていると言えます。
たとえ学業の成績がトップレベルでなくても、自分の好きなテーマを持ち、それを深めてきた経験がある子は強いアピールが可能です。
たとえば、昆虫が好きで観察日記をつけていた、図鑑を集めて研究していた、というようなことでも、それが継続されていれば立派な探究活動になります。
ポイントは、【やらされる勉強】ではなく【自ら取り組む学び】ができているかどうかです。
また、熱中できることを持つ子どもは、自分なりの視点や疑問を持つようになります。
これが将来的に志望理由書や面接での発言に深みを与えることにもつながります。
もちろん、すぐに【これだ】と決まった興味を持つ子ばかりではありません。
大切なのは、日々の中で興味の芽を見逃さず、親がそれを【面白いね】【もっと調べてみようか】と広げてあげることです。
小さな好奇心の積み重ねが、やがて推薦入試で通用する個性へと育っていきます。
特徴②自分の考えを言葉にできる
総合型選抜や推薦入試では、【思っていることをどう表現するか】が極めて重要です。
面接、小論文、志望理由書など、どの形式でも共通して求められるのが、自分の考えを言葉でわかりやすく伝える力です。
ですから、普段から【何を考えたか】【なぜそう思ったか】を言語化する習慣がある子は、このような入試に強い傾向があります。
表現力というと難しく感じるかもしれませんが、特別なトレーニングが必要なわけではありません。
家庭の中で、【今日、学校でどんなことがあった?】【それをどう思ったの?】といった問いかけを日常的に行うことで、考えをまとめる力は自然と育っていきます。
また、読書感想文や作文を書く経験も、表現力を鍛えるうえで非常に有効です。
自分の感じたことを文章にするという行為は、思考を整理し、他者に伝える訓練にもなります。
さらに、言葉での表現力は、将来の就職活動や社会に出てからも必ず必要になるスキルです。
今のうちからこの力を育てておくことは、入試対策にとどまらず、長い目で見ても大きな財産になります。
特徴③コツコツ取り組みを継続できる
推薦や総合型選抜では、【継続して努力した経験】が大きく評価されます。
大会での優勝や表彰歴などの華やかな実績がなくても、一つのことに地道に取り組み続けた記録や姿勢は、しっかりとアピールポイントになります。
そのため、コツコツ努力を積み重ねられる子どもは、推薦型入試にとても向いています。
たとえば、3年間同じ部活動を続けてきた、検定に挑戦して合格を積み重ねたといった、見た目には地味でも継続の裏にある努力は確実に評価されます。
大学側は、【この子は入学後も真面目に学び続けられるか】を見ているため、日々の取り組みの積み重ねこそが信頼につながるのです。
また、継続力は高校生活にも良い影響を与えます。
定期テストに向けて計画的に学習する力や、課題に丁寧に取り組む姿勢は、高校での内申点や先生からの推薦にも直結します。
一方で、途中でやめた経験が多い子でも、なぜやめたのか、そこから何を学んだのかをきちんと説明できれば、それもまた強みになります。
大切なのは、表面上の結果よりも、取り組みに対する姿勢や意識です。
多様な入試を突破する3つの準備法
さて、大学入試が【一発勝負の学力テスト】だけでは決まらない時代になった今、子どもたちはそれぞれの個性や強みを生かせる選抜方式を選べるようになりました。
とくに総合型選抜や学校推薦型選抜では、学力以外にも、人柄や活動実績、志望理由、将来の目標など多面的な要素が評価の対象になります。
しかし、こうした入試方式で合格を勝ち取るには、それ相応の準備が必要です。
何となく高校生活を過ごしていては、【語れる実績】が不足してしまうからです。
逆に、小・中学生のうちから入試の多様化を意識し、早めに動き出しておけば、それだけで他の受験生に大きな差をつけることができます。
ここでは、推薦や総合型選抜など、多様な入試を突破するために今からできる3つの重要な準備ポイントを紹介します。
ポイントは、特別な才能や実績を求めるのではなく、日常の中でどう行動するか、どんな経験を積むかにあります。
大切なのは、入試直前に慌てるのではなく、時間を味方につけて、コツコツと選ばれる準備を重ねていくことです。
準備①戦略的な高校選び
多様な大学入試を見据えるなら、中学卒業後に進学する高校の選び方は非常に重要な一手になります。
とくに指定校推薦を希望する場合は、どの大学と推薦枠の提携があるかを事前に調べておくことが必要です。
推薦枠は高校ごとに異なるため、【どんな大学とつながっているか】は進路に大きく影響します。
また、高校の学習スタイルや校風も大きなポイントです。
探究学習やプレゼンテーション活動が盛んな高校、英語やICTに力を入れている高校など、学校ごとの特色を見比べることで、自分の目指す進路に合った環境を選ぶことができます。
探究型の授業や課題研究に力を入れている学校では、推薦入試で必要な探究実績を自然に積むことも可能です。
さらに、内申点を重視するかどうか、課題提出や日々の授業への評価がどれくらい影響するのかも、見落とせない要素です。
高校に入ってからの努力が評価につながる環境かを見極めることが、後悔のない選択につながります。
中学生のうちから、偏差値だけでなく【将来につながる学びができる高校かどうか】という視点で学校選びを考えることが、推薦・総合型に強い土台づくりの第一歩になります。
準備②課外活動や経験の蓄積
推薦・総合型入試では、学力だけでなく【これまでどんなことに取り組んできたか】という経験や実績が非常に重視されます。
そのため、部活動、ボランティア、地域活動、留学、検定試験など、学校の外でどんな活動に参加したかが、そのまま入試でのアピール材料になります。
たとえば、3年間同じ部活動を続けてきた経験、地域のイベントや子ども会でのリーダー経験、短期でも海外研修に参加した経験などは、継続性・主体性・協調性など、多様な力の証明になります。
成績や受賞歴がなくても、【どんな思いで取り組んだか】【何を学んだか】を語れることが大切です。
また、英検・漢検・数検などの検定試験への挑戦も、自己成長の証として評価される要素になります。
とくに英語に関する資格は、志望大学によっては出願要件を満たすために必要なこともあるので、早めの取得をおすすめします。
これらの経験は、一朝一夕では得られません。
だからこそ、中学生のうちから【挑戦してみる】【人前で発表してみる】といった一歩を踏み出す機会を家庭でも応援してあげましょう。
蓄積された経験が、志望理由書や面接の場で強力な武器になります。
準備③自分をアピールする力を鍛える
総合型や推薦入試において、経験や学びがいくら豊富でも、それをうまく伝えられなければ評価されません。
そのために必要なのが、【自分をアピールする力】=表現力・説得力・自己分析力です。
志望理由書、小論文、面接など、どの形式でも【自分の言葉で、自分の考えを伝えること】が合格への決め手になります。
たとえば、志望理由書では【なぜその大学なのか】【何を学びたいのか】【将来どう活かしたいのか】を、論理的かつ熱意を持って伝える必要があります。
これは作文とは違い、自分の人生をどう考えているかを言語化する作業です。
小中学生のうちから、考えたことや学んだことを自分の言葉で話す習慣を持つことが、最終的なアピール力の差につながります。
また、面接では受け答えの内容だけでなく、話し方や表情、態度も重要な評価対象となります。
普段から親子で対話する時間をつくり、【なぜ?】【どう思う?】と問いかけることが、自然と話す力・考える力の育成につながります。
【自分をどう見せるか】【どう語るか】は、今後の人生にも役立つスキルです。
勉強だけでなく、自分の思いや経験を伝える練習も、今から大切にしていきましょう。
家庭でできる3つの学習サポート
ところで、大学入試における多様な選抜方式が進む中で、学校や塾だけでなく、家庭での関わり方が子どもの進路に与える影響はますます大きくなっています。
まだ早いと思われる思われる小学生・中学生の段階で動くことも大切です。
家庭でどのように学習に取り組み、どんな習慣を築けるかが、高校以降の進路選択や入試対策の【土台】となります。
【推薦や総合型選抜を目指す】と言うと親からすると特別な準備が必要な印象を持つかもしれませんが、実はその基盤になるのはごく基本的な学習の姿勢や、日々の積み重ねです。
家庭での学習習慣、思考力の育成、苦手意識の克服など、小さなことの積み重ねが、将来のアピール材料や自信へとつながっていきます。
ここでは、親が日常の中で意識しておきたい、家庭での学びを支える3つのコツをご紹介します。
難しいテクニックや指導法ではなく、誰でも今日から始められるシンプルな習慣ばかりです。
入試対策に直結するだけでなく、子どもの学びへの姿勢を変えるきっかけにもなるはずです。
将来に向けて【学び方の力】を育てるために、まずは家庭でできることから一歩踏み出してみましょう。
コツ①基礎学力の定着を大切にする
どれほど推薦や総合型選抜が普及しても、やはり【学力ゼロ】では通用しません。
むしろ、学力以外の力が求められる入試方式だからこそ、盤石な基礎学力の定着が信頼につながります。
大学側も、【しっかりと基本的な学力を身につけたうえで、どんな力を伸ばしてきたのか】を見ています。
家庭での学習では、まずは国語・算数(数学)・英語といった基本科目を着実に押さえることが大切です。
とくに国語はすべての教科の土台であり、語彙力や読解力が弱いと、小論文や面接でも不利になります。
算数や数学では、計算力や論理的思考を鍛えることで、他教科への応用力も自然と高まります。
基礎を定着させるには、【毎日短時間でも学習する習慣】をつけることが効果的です。
朝の10分、夜の15分といった時間でも構いません。
継続することで知識が定着し、学ぶことに対する抵抗感が減っていきます。
また、丸暗記ではなく【なぜそうなるのか?】を考えながら学ぶことで、思考力も鍛えられます。
日々の学習を通して、【わかる喜び】【できる楽しさ】を感じられるようになると、学力の土台はより強固なものになります。
コツ②思考力・表現力を育てる対話習慣
推薦・総合型選抜では、【考える力】【伝える力】が評価の軸になります。
これは試験の場だけでなく、日常的に自分の考えを持ち、それを言語化する経験の積み重ねが必要だということです。
家庭では、親子の対話がそのトレーニングの場として最適です。
普段の生活で行うのが一番敷居が低く、食事中やお風呂での会話の中で、【今日、学校でどんなことを学んだ?】【それを聞いてどう思った?】といった問いかけをすることで、自然と子どもは自分の考えをまとめ、言葉にする練習ができます。
最初は答えが浅くても問題ありません。繰り返すことで、自分の中に思考の軸ができていきます。
また、読書感想文や日記、自由研究のまとめなど、書く経験も表現力の育成に大きく貢献します。
作文や文章を書くのが苦手な子でも、【自分の言葉で書く】ことを意識させることで、徐々に自信をつけていくことができます。
親が【正しい答え】を求めすぎず、【あなたはどう思うの?】と問いかける姿勢を持つことで、子どもは安心して自分の意見を話せるようになります。
考えを深めて伝える力は、将来どの進路でも必ず武器になります。
その芽を育てるのは、日常のささいな対話からです。
コツ③苦手科目を放置しない工夫
どんなに他の力が優れていても、推薦や総合型入試では大きな苦手科目があると不利になるケースがあります。
高校の内申点に響いたり、課題提出の評価に影響したりと、弱点が目立ってしまうからです。
だからこそ、小・中学生の段階で【苦手をそのままにしない】姿勢を身につけておくことがとても大切です。
苦手な教科を克服するには、まず【できないこと】を責めないことが第一歩です。
子どもがミスをしたとき、つい叱ってしまうと、自信を失ってしまい、余計に苦手意識が強くなります。
むしろ、【どこがわからなかったのか、一緒に見てみよう】と寄り添う姿勢が、前向きな学習意欲を引き出します。
また、苦手な科目ほど【小さな成功体験】が重要です。
たとえば、1問だけでも正解できた、昨日よりも早く解けた、というような達成感を積み重ねることで、子どもは【やればできる】という実感を持てるようになります。
さらに、親子で【つまずきを早く見つける習慣】をつけることも効果的です。
学校の授業や宿題での間違いを見逃さず、その場で一緒に解き直すことで、理解が深まります。
苦手科目の放置を防ぐには、【早期対応】【小さな成功】【親の寄り添い】がカギになるのです。
今こそ【自分らしさ】で未来を切り拓く準備を
大学入試が【点数重視の一発勝負】から、【人物評価を重視した総合評価型】へと大きくシフトする中で、私たち親ができることもまた変わってきています。
これからの時代に求められるのは、単に成績の良い子ではなく、自分の考えを持ち、それを言葉で伝え、行動に移す力を持った子です。
今回はまず最初に推薦入試や総合型選抜に向いている子の特徴として、【好きなことに熱中できる】【自分の考えを言葉にできる】【継続的に努力できる】という3つのポイントをご紹介しました。
こうした特徴は天性の資質ではなく、日々の生活や親の関わりの中で育てていけるものです。
続いて高校選びや課外活動の経験、自己表現の力といった、将来の進路につながる実践的な準備を取り上げました。
早い段階から視野を広げ、経験の蓄積を意識することで、入試本番で確かな武器を手に入れることができます。
そして最後に、家庭でできる学習のサポートとして、基礎学力の定着、表現力を育てる対話、苦手科目への丁寧な向き合い方をお伝えしました。
どれも、家庭の中で今日からできる小さな一歩です。
子どもの未来を決めるのは、誰かと比べる偏差値ではなく、自分の人生を自分の力で歩もうとする主体性です。
総合型選抜や推薦入試の広がりは、その可能性を多くの子どもに開いてくれています。
だからこそ、親の私たちも【今できること】を積み重ね、子どもたちが、【自分らしさ】で未来を切り拓けるよう、そっと後押ししていきたいものです。