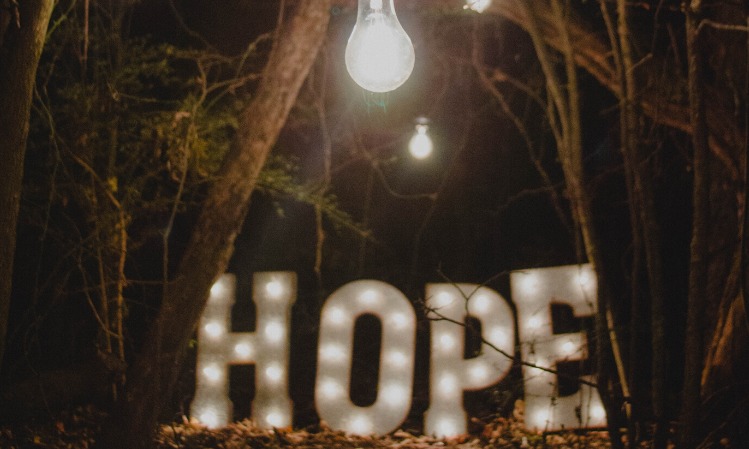今回は【小学5年生で決まる学力の差!親が見逃せない黄金期の過ごし方】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学5年生は、学力の分かれ目となる非常に重要な時期です。
この学年になると、算数では割合や図形、国語では読解力の強化など、これまでとは一段と難易度の高い内容が増えてきます。
また、単なる暗記中心の学習から、自分で考え、問題を解決する力が求められるようになるため、思考力や応用力の育成が本格化します。
この変化に対応できるかどうかで、今後の成績の伸びや将来の進路が大きく左右されます。
地方の子は高校受験する子が多数派ですが、親子で地元のトップ高校合格を目指す場合、中学校3年間でいかに頑張るか、と同じくらい小学5年生の過ごし方がカギとなります。
ここでしっかり基礎を固め、学習習慣を確立できれば、中学での勉強もスムーズに進み、成績が安定した上位層への道が開けます。
逆に、この時期に躓くと、その後の学習に大きな影響を及ぼし、巻き返しが難しくなることも少なくありません。
子ども①②が小学5年生の時に、クラス内で恐ろしい位の学力差が出てきました。
算数がお手上げの子が増えたり、理科社会の用語を覚えられない子もいる一方で、中学受験する子や学区の公立中学でトップに君臨するような子はどの教科も満点連発と同じ授業を受けているけれど、挽回が不可能なくらいの差が生まれていました。
現在、小学5年生となった我が家の子ども③に話を聞くと、【算数はもちろんのことだけれど社会の出来不出来がドン引きするくらいスゴイ】と口にしていました。
とにかく、小学5年生が子どもの勉強面での大きな分かれ道になります。
そこで今回は、まず【小学5年生で学力差がつく理由】を解説し、次に【家庭学習の見直しポイント】、そして【親ができる効果的な関わり方】の3つの章に分けてご紹介します。
これらを実践することで、子どもの未来をしっかりと支える土台を築くことができるでしょう。
小学5年生の学力差がつく理由
まず、小学5年生は、学力の分かれ目となる重要な時期です。
この時期になると、算数では割合や図形といった難易度の高い単元が登場し、国語でも読解力や表現力が一段と求められるようになります。
これまでの【覚える】学習から【考える】学習へとシフトし、思考力や応用力を伸ばすことが必要になるため、子どもの理解度や取り組み方によって成績に大きな差が生まれやすいです。
さらに、小学5年生は学習習慣や自分で計画を立てる力が育ち始めるタイミングでもあります。
ここで自立した学習態度が身につくかどうかが、中学以降の成績安定やトップ高校合格の可能性を左右します。
つまり、小学5年生のうちに学力の土台をしっかり築くことが、その後の学びをスムーズにし、成績の伸びにつながっていくのです。
ここでは、小学5年生で学力差がつく具体的な理由と、その背景にある学習内容や心構えの変化について詳しく解説します。
①カリキュラムの難易度が一気に上がる
小学5年生になると、学校のカリキュラムはこれまでよりも一段と難しくなります。
学力の差が明確に表れ始めます。
算数では【割合】【比】や【図形】といった単元が登場し、単なる計算力だけでなく、問題の背景や仕組みを理解しながら解く力が必要になります。
割合の問題では、全体の何パーセントかを計算するだけでなく、具体的な場面に当てはめて考える思考力が求められます。
また、図形では形の性質を理解し、面積や角度の関係性を論理的に考える力が重要です。
そして、公式も覚えないといけません。
国語では、長文の読解が増え、物語や説明文の内容を正確に読み取り、筆者の意図や登場人物の気持ちを考えることが求められます。
これらの単元はつまずきやすく、小学5年生の段階で理解が不十分だと、中学での勉強にも大きな影響が出てしまいます。
だからこそ、この時期までに基礎力をしっかり固め、じっくり取り組むことが重要になります。
②思考力・応用力が必要になる学習への切り替え
小学5年生になると、勉強の内容が単なる暗記から【考える力】を求められる問題解決型の学習へと大きく変わっていきます。
これまでは公式や暗記した知識を使うことが中心でしたが、この時期からは【なぜそうなるのか】【どうしてこの方法で解けるのか】を自分で考え、答えにたどり着く力が必要です。
苦手な子が急激に増える算数では、単純な計算力だけでなく【条件を整理し、複数の要素を組み合わせて考える力】が試されます。
また、国語でも大きな変化が現れます。
語彙力のない子は書かれていることがよく分からないと感じるくらい、それまでの学年よりも教科書に出てくる作品がレベルアップします。
単なるあらすじ理解ではなく、筆者の主張や登場人物の心情、構成の意図などを深く読み取る力がしっかりなければ、テスト問題を解く時にも悩みながら、分からないなと考えながら解くことになります。
さらに、これまでの実生活では触れる機会のなかった【古文】にも初めて触れるようになり、言葉の意味や表現の違いに戸惑う子も少なくありません。
こうした内容は、まさに中学国語への助走であり、思考力・理解力の転換点でもあります。
この変化に対応できるかどうかが、成績の伸びを大きく左右します。
日頃の勉強の質がとても大切で、ただ問題を繰り返すだけでなく、【なぜその答えになるのか】を子ども自身が考える時間を設けることが成績アップのカギとなります。
親も、答えの正誤より過程を重視した声かけを心がけ、子どもの思考力を育てるサポートをしていくことを心がけましょう。
③学習スタイルの自立を目指す
小学5年生は、学習内容が難しくなるだけでなく、自分で学習を管理し、計画を立てる力が求められる時期でもあります。
これまで低学年までは親や先生の指示で勉強を進めてきた子どもたちも、この段階では自分で【いつ、何を、どのくらい勉強するか】を考える必要が出てきます。
自立した学習スタイルを身につけることが、成績の安定や向上に直結します。
しかし、急に自分で全てをこなすのは難しく、多くの子どもが戸惑いや不安を感じることもあります。
そこで親のサポート方法も変わってきます。
具体的には、細かく管理するのではなく、子どもが自分で計画を立てる過程を見守り、適宜アドバイスや助言を行うことを意識してください。
また、計画通りに進まなかったときに責めるのではなく、【どうしたら上手くいくか】を一緒に考え、励まして、改善していくようにしましょう。
このように、小学5年生は【学習の自立】を促す重要な時期であり、親もサポートの仕方を工夫しながら、子どもの主体生を伸ばす環境づくりを心がけることが必要です。
これができれば、子どもは自信を持って中学以降の学習に臨むことができ、志望校合格に向けて一歩近づくでしょう。
黄金期の家庭学習の見直し
さて、小学5年生は、学習内容が難しくなるだけでなく、学力の土台を固める【黄金期】とも言える大切な時期です。
この時期にしっかり基礎を見直し、考える力を伸ばす家庭学習の習慣をつけることが、その後の成績の安定や伸びにつながります。
低学年で学んだ基本の理解が不十分なままだと、難しくなる内容に対応できず、学力の差が広がってしまいます。
家庭では、まずこれまでの学習内容を丁寧に復習し、基礎を確実に固めることが重要です。
そのうえで、ただ問題を解くのではなく【なぜこうなるのか】を子ども自身が考えられる問題演習を取り入れ、思考力や応用力を育てる工夫も必要です。
また、集中できる環境づくりも大切で、勉強時間や場所の確保、スマホやゲームとの付き合い方を見直すことも必要に応じてしていきましょう。
ここでは、こうした家庭学習の見直しポイントを詳しく解説していきます。
【対策1】基本の復習を丁寧に小学1~4年の基礎を固め直す
小学5年生の学力を安定させ、今後の成績の伸びにつなげるために、まず取り組むべきは【1年生から4年生までの基礎の見直し】です。
この時期、子どもたちは応用問題に触れる機会が増えますが、応用ができない原因の多くは、実は基本の理解があいまいなまま進んでしまっていることにあります。
たとえば算数では、かけ算・わり算の概念があやふやなまま割合や速さに進んでしまうと、式の立て方でつまずきます。
国語では、語彙や文章の構造理解ができていないと、長文読解に太刀打ちできません。
ですから、5年生のうちに一度立ち止まり、教科書レベルの基本問題を解き直し、理解が不十分な単元を洗い出すことが大切です。
復習は、一気に詰め込むのではなく、日々の学習に少しずつ取り入れるのがコツです。
1日1単元でも【できた】を積み重ねることで、自信と理解の両立ができます。
【対策2】思考力を伸ばす問題演習を取り入れる
小学5年生は、単なる計算や暗記の学習から、思考力や応用力が求められる学習へと本格的に移行するタイミングです。
ここで成績を安定させるには、【ただ正解を出す】のではなく、【なぜそうなるのか】を考えながら解く習慣を育てることが重要です。
つまり、答えにたどり着くまでの【思考のプロセス】を大切にする学びに変える必要があります。
そのためには、ドリルや問題集の選び方がカギとなります。
難易度の高い応用問題ばかりではなく、基礎から標準レベルの中で【考える力】を引き出す工夫がされた教材を選びましょう。
具体的には、解説が丁寧で、自分で理解を深められるような構成になっているものが理想です。
教科書内容も怪しい時は教科書ワークなどを使い、基礎を徹底復習しましょう。
解いた後に、【どうしてその答えになったのか】を親子で確認する時間をつくるのもおすすめです。
また、間違えた問題は【やり直し】よりも【考え直し】を重視しましょう。
すぐに正解を教えるのではなく、【何が違っていたのか】【どう考えればよかったか】を自分で振り返る機会が、深い理解と応用力を育てます。
【対策3】学習環境の整備
学力を安定して伸ばすためには、【どこで、いつ、どう学ぶか】という学習環境の整備が欠かせません。
小学5年生は、自分で学習習慣をつくっていく時期です。
集中できる環境が整っているかどうかが、日々の勉強の質に大きく影響します。
まず見直したいのは【学習する場所】です。
テレビやおもちゃ、スマホなどの誘惑が少ない静かなスペースを確保することで、集中力を維持しやすくなります。
また、【学習する時間帯】も重要です。
できれば毎日同じ時間に勉強する習慣をつけると、自然と気持ちの切り替えができるようになります。
さらに、スマホやゲームとの付き合い方も大切です。
完全に禁止するより、【勉強が終わったら30分】などのルールを家庭で話し合って決めると、子ども自身が時間管理の意識を持つようになります。
快適で集中しやすい学習環境を整えることは、子どもの努力を無駄にしないための土台です。
親が環境づくりを意識するだけで、子どもの勉強効率は大きく変わってきます。
親ができる効果的な関わり方
ところで、小学5年生になると、学習内容の難易度が一気に上がるだけでなく、自立した学びが求められるようになります。
これまでのように親が細かく勉強を管理するのではなく、子ども自身が【どうやって勉強するか】を考え始める時期です。
そのため、親の関わり方も変化させていく必要があります。
ただし、【手を離す】のではなく、【手の添え方】を工夫するのがポイントです。
子どもが学びの中で自分の頭で考え、試行錯誤しながら成長していくためには、親の励ましと信頼が大きな力になります。
正解や点数に一喜一憂するのではなく、【考えた過程】に目を向けて子どもの努力を認めることが、子どものやる気を育て、勉強に向き合う本気の姿勢を作っていきます。
ここでは、成績が安定して伸びている子の家庭で実践されている、親の効果的な関わり方を3つの視点から紹介します。
子どもの主体性を育みつつ、確実に成長を支えるヒントをお伝えしていきます。
【関わり方1】結果ではなく【考えた過程】を褒める
成績を安定して伸ばしている子どもの多くは、親から【結果】よりも【考えた過程】を認められて育っています。
テストで良い点を取ったときに【すごいね!】と褒めるのは当然ですが、それ以上に子どもの心に響くのは、【どう考えてこの答えを出したの?】【自分で工夫して取り組んだんだね】という声かけです。
たとえ間違っていても、【ここまで自分で考えたのは立派だったよ】と伝えることで、子どもは自分の努力を認められたと感じ、自信につながります。
逆に【どうしてこんなミスをしたの?】という否定的な言葉は、子どもの挑戦する気持ちを削いでしまいます。
勉強は、すぐに成果が見えにくいことも多いため、プロセスに目を向けることで、継続的な学びへの意欲を引き出せます。
【点数】や【できたかどうか】だけに注目するのではなく、【自分で考えたこと】【工夫した部分】を拾い上げて褒める。
これが、学びの土台を育てる親の大切な姿勢です。
【関わり方2】自立を促す【任せる】サポート
小学5年生は、勉強との向き合い方において【自立】を促す絶好のタイミングです。
親がすべてを管理するのではなく、少しずつ【任せる】姿勢が求められます。
たとえば、1週間の勉強計画を子ども自身に立てさせたり、宿題に取り組む時間を自分で決めさせるなど、小さなことから始めるのが効果的です。
もちろん最初から完璧にできるわけではありません。
計画通りにいかないこともあるでしょう。
そんな時に【だから言ったでしょう】ではなく、【どうすれば次は上手くいくかな?】と一緒に振り返ることで、子どもは試行錯誤しながら成長していきます。
失敗を責めず、次へのヒントに変える経験が、自分で考える力を育てます。
任せるというのは、放任とは違います。
あくまで【見守りながら、必要なときにサポートする】という関係性が大切です。
子どもが自分の意思で勉強に取り組み、【自分の努力で伸びている】と実感できることが、成績の安定と将来の自信につながっていくのです。
【関わり方3】親子で振り返りタイムを設ける
学力が安定して伸びている家庭には、定期的に【振り返る時間】があるのが特徴です。
おすすめなのは、週に1回、親子で10〜15分程度の【振り返りタイム】を設けること。
1週間の勉強の中で【できたこと】【頑張ったこと】【難しかったこと】などを一緒に振り返り、次の目標を子ども自身に考えさせる機会をつくります。
この時間は、親が評価する場ではなく、子どもの気持ちを聞き出し、前向きに次へつなげる場です。
【先週よりも自分から机に向かえてたね】【ここは難しかったけど諦めなかったね】といった声かけが、子どもの自己肯定感を高めます。
また、この時間を通じて、親子のコミュニケーションも深まります。
学校での様子や友だち関係、気持ちの変化など、普段の会話では出てこない話題も自然に出てくることがあります。
勉強だけでなく、心の状態も整えるために、この振り返りの時間はとても大切です。
親子で学びを振り返りながら進むことが、長期的な成長を支える大きな力になっていきます。
小学5年生は、学力の伸び方に大きな差が出始める【分かれ道】の時期です。
学習内容の難易度が増し、自分で考える力や学習への主体性が求められ始めるこのタイミングで、家庭での関わり方が今後の学力を大きく左右します。
まずは低学年までの基礎を見直し、思考力を育てる学びにシフトすること。
そして、子どもが自立して学べるよう、親は【支配】ではなく【支援】の立場に立ち、考える姿勢や努力の過程に目を向けて声かけをしていくことが大切です。
この大切な時期に親子で一緒に学ぶ姿勢を育てることで、成績が安定し、精神も安定し、中学・高校でも伸び続ける力を育むことができます。