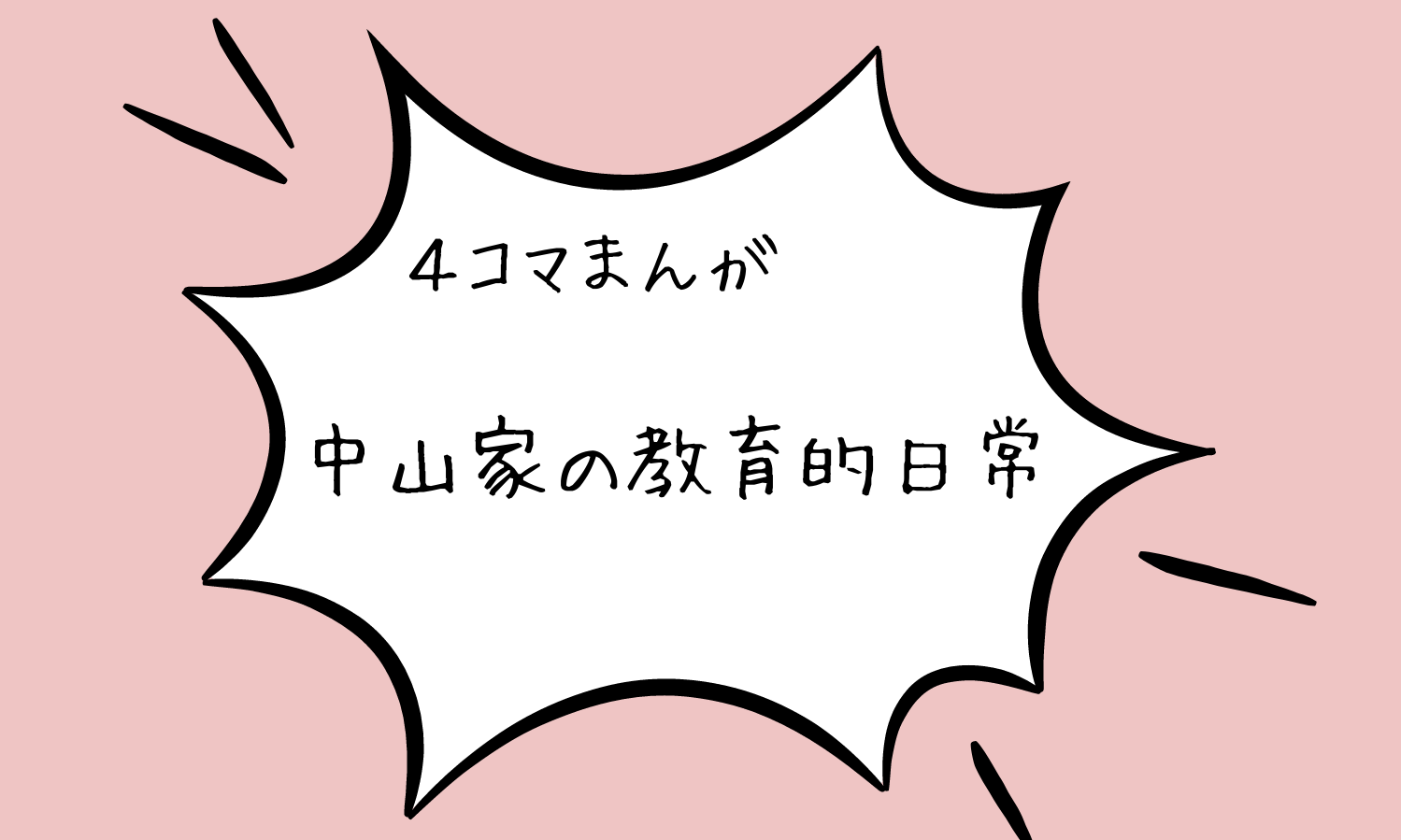今回は【文武両道ができる子の共通点とは 進学校での【忙しいのに成績がいい】理由】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
【進学校って、勉強ばかりじゃないの?】
【部活に力を入れると、学力が落ちるんじゃないかと心配です】
このように感じている方は、多いと思います。
中学生の生活は想像以上に忙しく、授業、宿題、定期テスト、そして部活動と、毎日やることが山のようにあります。
私も中学生になってから、あまりの忙しさに驚きましたし、小学生時代がのんびりと過ごせたことが恋しくなったこともありました。
ただ、成績が良い子ほど忙しい中でも部活と勉強を両立していたり、学校の部活でも忙しい部に入っていている子も多く、【文武両道を実践する子がいるんだ】と感心しました。
かくいう私も、吹奏楽部でしたし、活発ではない運動部以上に忙しい部に入ってなんとか勉強と両立できるようもがいた記憶もあります。
ただ、進学校を目指すとなると、【部活を続けながら受験勉強をするなんて、本当に可能なのか?】という疑問を持つのは当然のことです。
ところが、実際の進学校では、文武両道を実現している生徒が多くいます。
彼ら彼女たちは運動部や文化部に真剣に取り組みながら、成績も上位をキープしているのです。
しかもそれは、ほんの一部の特別な子に限られた話ではありません。
多くの進学校では、【文武両道】が理想ではなく前提として定着しています。
とくに、地方の公立トップ高校では【部活も勉強も頑張る】という校風のところも珍しくありません。
私も高校時代の同級生や先輩後輩で【部活に入らず勉強だけ頑張って最難関大を目指す】という子はいませんでしたし、我が家の子ども①が通う高校でも最上位層や上位層の子ほど運動部率が高かったり部活をしっかりやっている子の割合が高いです。
では、なぜそんなことが可能なのでしょうか?
不思議だなと感じている人は多いことでしょう。
そこで今回は、文武両道を可能にしている子の共通点や進学校の【忙しいのに成績がいい】という子が多くいる理由をご紹介していきます。
文武両道は本当に可能?進学校の実態
まず、文武両道をしている子は本当にいるのでしょうか。
【進学校は勉強漬け】【部活なんてやっている暇はない】、というイメージを持っている方も少なくないかもしれません。
ところが、進学校では両立している子が多くいます。
【文武両道】が当たり前の世界で、【忙しいのにどうしたらあんなに成績がよくなれるのか】と思わず声を上げてしまうような、そんな存在の子もいます。
地方のトップ校でも、多くの生徒が何らかの部活に所属しており、平日はもちろん土日も活動しているケースが珍しくありません。
しかも驚くのは、その【忙しさ】の中でも、定期テストで上位を取り、模試でも高得点を出している生徒が多数いるということです。
子ども①の周囲にいる【旧帝大の医学部医学科に入れそうな子】や【最難関大学に入れるレベルの子】達も平日、土日の練習、遠征などに参加しつつ、高い学力をキープしています。
【どうせ帰宅部の子が成績いいんでしょ?】と思われるかもしれませんが、実際にはバリバリの運動部の子が成績上位に名を連ねることも珍しくありません。
文武両道を理想ではなく、【そういう子が普通にいる】と、日常として体現しているのが、進学校のリアルな姿です。
それでは、なぜそんな両立が可能なのでしょうか?
最大の理由は、彼ら彼女たちが時間の価値と使い方を早いうちから自覚していることです。
進学校に通う子ども達は、【時間は限られているもの】という前提を理解しています。
たとえば、【部活の後に家に帰る】で残された勉強時間は多くて2〜3時間程度です。
部活の後に塾の自習室で勉強してから帰宅するというパターンでも、同じように確保できる時間はMAX2時間から3時間くらいです。
残された時間の中でどうやって課題をこなすか、どうやって苦手を克服するかを、自分で考え、工夫する力が育っています。
時間を無駄にせず、電車での移動時間に英単語を確認したり、休み時間に予習復習をしたり、授業を100%集中して自習時間のように使ってしまう生徒もいます。
こうした姿勢が習慣化しているため、長時間勉強することよりも、【短時間で成果を出す】ことに長けているのです。
また、学校側もそうした生徒の努力を支えるように、部活動と学業が両立しやすい時間割や、部活ができる時間の設定、教育相談などを整備しています。
学校全体で【文武両道はできる】という共通認識があるからこそ、無理なく継続できるのです。
そして、文武両道ができる子とそうでない子の違いは、単純な忙しさではありません。
本質的な差は、時間に対する意識と、学習に向き合う姿勢にあります。
【部活で忙しいから勉強できない】と考える子もいれば、【部活で時間がないからこそ、集中して勉強しよう】と考える子もいます。
両者の違いは、1日ではなく、数ヶ月、数年で大きな差となって現れます。
私自身も経験しましたし、塾で出会った子や子ども①の周囲の友達の話を見聞きしていても、進学校で成績上位にいる生徒の多くは、部活があるからこそ【やるべきときはやる】というメリハリの習慣を大切にしています。
彼ら彼女らは【あとでやる】ではなく、【今やれることを今やる】という行動パターンを自然に身につけています。
また、失敗や挫折を通して、うまく時間を使えなかった経験を持っている子も多く、そこから学んでやり方を自分で見つけています。
つまり、文武両道は【持って生まれた才能】ではなく、経験と意識によって身につけられる力だということです。
こういう話を聞くと、【本当にうちの子にそんなことできるの?】と不安に思うかもしれません。
けれど実際は、文武両道は才能ではなく【習慣】と【意識】で成り立っているものです。
もちろん、最初から完璧にできる子はいません。
しかし、部活と勉強の両立に挑戦する中で、時間の大切さに気づき、努力の仕方を学び、自分で改善できる子が育っていきます。
文武両道できる子の共通点5つ
さて、【部活も頑張っているのに、なんでこの子は成績も落ちないんだろう?】と不思議に感じた子に出会ったことはないでしょうか。
文武両道を実現している子には、ただ頑張っているだけでなく、効率的で戦略的な学び方の共通点があります。
ここでは、進学校で文武両道を成し遂げている子に共通する5つの特徴をご紹介します。
1. 時間の使い方がうまい(タイムマネジメント力)
文武両道の子に最も強く見られる特徴は、【時間をどう使うか】を常に意識している点です。
彼らは、たとえ部活で毎日帰宅が遅くても、【今できることは何か】を考えて行動しています。
たとえば、【朝の10分を漢字練習に使う】【通学中に英単語アプリで暗記する】【学校の授業で理解しきるつもりで集中する】など、スキマ時間の積み重ねを最大限に活用しています。
時間が限られているからこそ、【この30分で何を終わらせるか】という集中力と判断力が身についているのです。
逆に、時間がたっぷりあるときのほうが、集中できないというのは良くある話です。
部活に入らずに自由に放課後の時間を過ごす子の方が勉強時間がたっぷりあるのに、ダラダラ過ごしてしまい、結局学力向上に至らないというケースは、私も塾で見てきました。
2. やるべきことの優先順位をつけられる
文武両道を実現している子は、【全部を完璧にやろう】とは考えません。
その代わり、【今やるべきことは何か?】という優先順位を冷静に見極めています。
たとえば、翌日に提出がある課題と、2週間後の定期テストを比べる。
どちらも大切ですが、まずやるべきは明日の提出物。
その判断が自然にできるのです。
また、複数のタスクが重なっても、【全部は無理だから、これは少し後に回そう】と落ち着いて対処できます。
このように、自分の頭でスケジュールを組み立てられることが、精神的な余裕にもつながっています。
3.【やるときはやる】というメリハリ思考
集中力を長時間持続させるのは難しいものがあります。
それでも文武両道の子は、【やると決めた時間は全力で集中する】というメリハリのつけ方が上手です。
たとえば、【夜の1時間だけは机に向かって集中する】【朝は必ず10分だけ復習する】など、短時間でもやる時間と休む時間を明確に区切っています。
また、【疲れたから今日はやらない】となるのではなく、【疲れてるからこそ、10分だけでもやって終わらせよう】と考えられるのもポイントです。
部活の疲れを言い訳にせず、自分のやるべきことに向き合う習慣が根づいています。
4. 成長を楽しめるマインド
文武両道をしている子どもたちは、【やらされている感覚】で勉強や部活をしているわけではありません。
彼らに共通するのは、【自分の成長を楽しむ姿勢】です。
【前はできなかった問題が解けるようになった】【参加した大会で前より記録が少し伸びた】【練習の成果が試合で出せた】
こうしたできるようになったという経験を、小さな喜びとして積み重ねています。
それが【次も頑張ろう】というモチベーションになり、どちらも前向きに取り組めるのです。
文武両道の子は、負けず嫌いで粘り強い一方、自分自身と前向きに向き合う力を持っています。
自分の弱さを受け止め、改善する気持ちを持って勉強や部活動に対して同じ熱量で臨むことができるという特徴もあります。
5.周囲の良い影響を受けている
進学校にいる生徒たちは、日々高い意識を持った仲間に囲まれています。
周囲が当たり前のように文武両道をしていることで、自分自身の基準も自然と引き上げられていきます。
たとえば、【同じ部活の仲間が帰宅後にしっかり勉強している】【授業中に積極的に発言するクラスメートが多い】【みんなテスト前に計画的に動いている】という、そんな空気感の中にいると、【自分も頑張ろう】と思えるのです。
これは家庭の中だけでは得られにくい刺激です。
環境は人格をつくると言われますが、進学校の子たちは、【頑張るのが当たり前】という文化の中で、自然と文武両道を身につけているとも言えるでしょう。
文武両道をしている子は、決して特別な才能を持っているわけではありません。
その多くが、日々の中で【どうすれば時間をうまく使えるか】【どうすればもっと成長できるか】を考え、自分なりの方法を身につけていったのです。
時間管理、優先順位、メリハリ、成長への意識、周囲からの刺激。
どれもすぐに完璧にできるものではありませんが、家庭でも少しずつ育てていくことが可能です。
家庭でできる!文武両道を支える関わり方
ところで、文武両道を実現するために大切なのは、子ども自身の意識や習慣だけではありません。
やはり、家庭での関わり方が、文武両道の成否を大きく左右します。
ここでは、親としてどのように子どもを支えればよいか、4つの視点から具体的にご紹介します。
1.部活を【敵】にしない
【部活も大事だけど、勉強が一番なんだからね】
そんな何気ない一言が、子どものやる気を削いでしまうことがあります。
とくに真面目で一生懸命な子ほど、【勉強も部活も頑張りたい】と思っているもの。
それなのに、部活が否定されると、【自分の頑張りを理解してもらえない】と感じ、ストレスや反発を生みやすくなります。
部活で味わう達成感、悔しさ、仲間とのつながりは、精神面の成長においてとても大きな意味があります。
それは結果的に、勉強への集中力や粘り強さ、自己管理能力にもつながります。
親としては、【部活を頑張っているね】→【じゃあ、その勢いで勉強もいこう!】というように、プラスの流れをつくる声かけが効果的です。
2.忙しさを言い訳にさせない声かけ
【部活で疲れてるから、今日は勉強しなくていいよ】
つい優しさからかけてしまいがちなこの言葉ですが、これが繰り返されると、子どもにとってやらない理由を与えてしまうことになります。
確かに部活後は疲れているでしょう。
でも、【疲れていても、少しだけやってみよう】【5分でもいいから机に向かってみよう】と小さな行動を促すことで、子どもは【やる習慣】を身につけていきます。
大切なのは、【疲れていても、自分で区切ってやり遂げる経験】を重ねることです。
それが自己肯定感や自信につながり、文武両道の土台になります。
3.【頑張り方】を教える
子どもに【もっと頑張りなさい】と言うのは簡単ですが、頑張り方を知らなければ空回りしてしまうこともあります。
文武両道を実現するには、【限られた時間でどう成果を出すか】を考えた努力が必要です。
たとえば、次のような工夫を家庭でサポートできます。
【一週間単位の簡単な予定表を一緒に立てる】【勉強が終わったらチェックを入れる仕組みをつくる】【やる内容を絞って集中する】ことの大切さを伝える。
また、部活と勉強の切り替えがうまくいかないときは、【5分だけタイマーをセットしてやってみよう】など、行動に移しやすい仕掛けを作るのも効果的です。
努力を根性論で乗り切るのではなく、【工夫して成果を出す】経験を積ませていくことで、子ども自身が成長の手ごたえを感じるようになります。
4.感情面のサポートが、継続のカギ
両立がうまくいかず、悩んだり落ち込んだりすることも当然あります。
そんなときに、【どうしてちゃんとできないの!】と叱ってしまうと、子どもは余計に自信を失い、やる気をなくしてしまいます。
大切なのは、【失敗してもまた立て直せる】【自分を信じて応援してくれる人がいる】と子どもが感じられる関わりです。
【ここまでよく頑張ったね】【うまくいかなくても、またやり直せばいいよ】【疲れてるのに、自分で時間作ったのはすごいね】といった声かけが、自分にはできるという感覚を育てることにつながります。
また、【結果】ではなく【取り組む姿勢】や【行動】を認めることも重要です。
テストの点が上がったときだけ褒めるのではなく、【毎日机に向かっているね】とプロセスを褒める姿勢が、長く続ける力を支えていきます。
文武両道は、子ども自身の力だけでは難しいことも多いものです。
でも、家庭でのちょっとした声かけや姿勢が、大きな後押しになります。
・部活を肯定しながら、勉強にもつなげる
・忙しさを理由にせず、小さな行動に導く
・頑張り方を一緒に考える
・成果よりも努力や継続を認める
これらを意識するだけで、子どもは【自分もできるかもしれない】と感じ始めます。
文武両道は才能ではなく、習慣と環境によって育てられる力です。
ぜひ、家庭からその土台を築いていきましょう。
【忙しいから無理】ではなく、【忙しい中でもやれる工夫をする】
そんな小さな意識の変化から、文武両道の力は少しずつ育っていきます。
焦らず、でも着実に、子どもの可能性を信じてサポートしていきましょう。