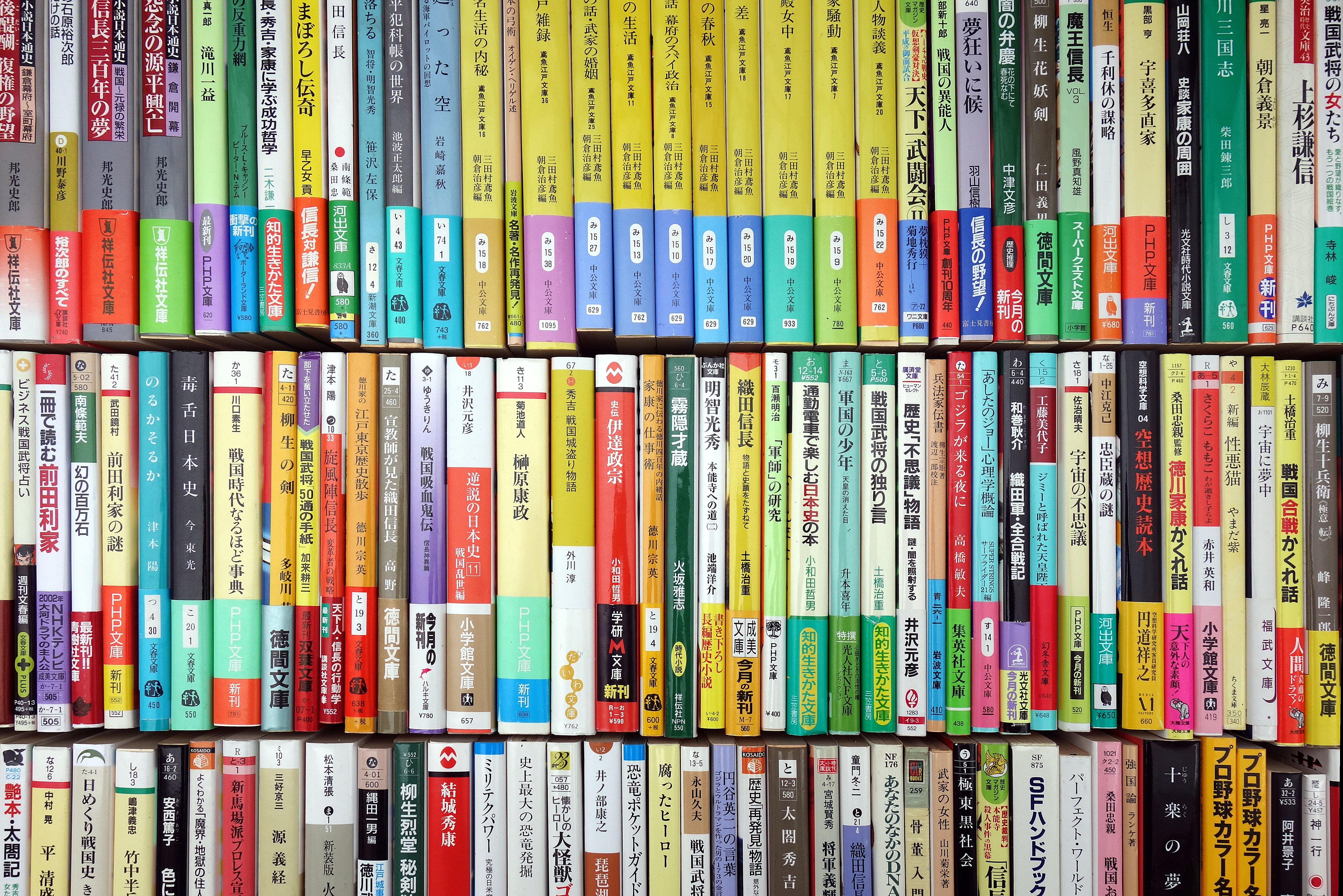今回は【小学生から塾に通うなら仕上げるべき学力とは】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
中学受験をする家庭なら塾通いをするのは当たり前という考えが浸透しています。
そして、中学受験はしないけれど塾通いをする小学生もいます。
塾という存在は子育てをしているなかで概ね高校受験、大学受験までという割と限定されている期間に存在感が強まります。
子どもが塾に関わる期間は一番長くて9歳10歳頃から18歳と最長9年間、8年間になります。
塾で出会った先生は子どもたちの思い出の中で残ることもあったりするので、子育てをする中でも親が思う以上に重要な場所になることもあります。
塾に通う目的は【受験のため】というのがオーソドックスな理由ですし、その他にも勉強させるため、勉強方法を学ぶためということもあります。
一口に塾と言っても、通う子の学力層が違ったり、地方でも【この塾はこの学校に強い】など特色がハッキリとしていています。
そして、地方の塾でも進学校に合格すると昔よりも高校入学後も塾に残る、通い続ける子が増えている印象はあります。
大都市圏では中学受験、中高一貫校に入ったら違う塾に通うなど進学によって塾を変えることも多いですが、地方ではずっと同じ塾に通う子もいます。
住んでいる地域で塾事情も異なりますが、塾に通わせるとなると親は色々とリサーチをしていきます。
授業料、教材費、施設維持費などの費用や合格者の多い学校がどこなのか、どこの小学校や中学校の生徒が通っているのか、授業の雰囲気や通いやすさなど【お金を出すからしっかり調べる】ということはすると思いますし、それが当然だと思います。
個人的には塾の費用などと同時に忘れてはいけない、いや気にして欲しいポイントが【通っている子どもたちの学力レベル】です。
そこで今回は、小学生から塾に通うとなるとどのくらいの学力に仕上げるべきなのかなどをご紹介していきます。
通塾前に家庭で仕上げておくべき学力の目安
まず、小学生が塾に通うとなると、【中学受験するため】という理由が多いと思います。
大都市圏では小学生を対象にした、幅広いニーズに応える塾はたくさんありますが、地方では塾に来る小学生というと【中高一貫校を受ける子】が通うというイメージが強く、私の周りでも公文や学研でなく中学受験をするわけではないけれど塾に通う子というのはかなりレアな存在でした。
ただ、受験をしない場合は【学校内容の定着】【勉強する習慣を身につける】と考えて通わせる家庭も珍しくありません。
実際にそういう考えで入会した小学生を教える機会もありましたし、
ちなみに、子ども①②③の小学校で4年生以上で塾に通う子というのは学年全体で5%弱程度ですし、【中学受験しないけれど通う】という子はその中でも1人〜2人くらいですが、小学校6年生の12月くらいから中学進学に向けて地元の塾に通い始める子は増えていきます。
小学生向けの塾であれば中学受験組の子が多く通う塾、学区の中学に通う予定で学力上位層の子が割と多く来る塾、地元密着型の学校の内容を定着させる塾、の3つにザクっと分類されます。
中受向けの塾は地方であれば公立中高一貫校を狙う各小学校のトップ層の子が集い、テストの点数でクラス分けされる実力主義の世界です。
高い学力、気合を入れて勉強できる子が集結しますし、【常に勉強できる子】であり【受験学年になれば遊びなどを犠牲にして勉強できる子】でないとそうした塾に通いきるのは難しいです。
学区に進学予定の子などはそこまで気合を入れて勉強しなくても日々を過ごすことができますが、塾に通うということは宿題が出されるわけなので、【今までよりも家庭学習の時間が増える】ということになります。
【家庭でどの程度の学力まで仕上げておくべきか】は、どんな目的か、または子どもの学力レベルによって違ってきます。
中受向けの塾なら【小学校のカラーテストで満点や90点台しかとらない】という子ばかりになるので、そこが一つの目安になりますし、塾の勉強特有の応用問題を解くことも嫌がらない、解ける学力がないと塾の授業を受けるのは厳しいでしょう。
そして、どの塾でも共通して必要な【目安】があります。
大手塾であれば、大都市圏や地方問わずに入塾前に子どもの学力レベルをチェックするテストを受けます。
場合によっては断られることもあるので、希望の塾に入るためにはこのテストを突破することが第一関門になります。
ただ、こうした事前のテストがない塾であっても【自学自習できる子】【出された宿題をちゃんとやる】ということは求められますし、塾側も想定している授業の進み方というのは生徒が家で勉強をすることを大前提にしています。
ですから、どのレベルの塾に通う場合でも【家で勉強する習慣がある】に仕上げておくことが望ましいですし、そうしていないと月謝をドブ川に捨てていることになってしまいます。
中学受験する子向けの教材を使用する塾な最上位層の子が集まる
さて、近畿圏、首都圏問わず中学受験用の教材を使用している塾は、学習内容が小学校の範囲を大きく超えており、【こんな問題を小学生の頃から解かないといけないの?】というレベルです。
有名どころですと、受験算数などが上がりますが、国語の読解問題や理科社会も【小学校のカラーテストと比較できないくらい難しい】といえます。
そのため、こうした教材を使って授業が進められる塾では【各小学校の最上位層】の子が集まる場となっています。
中学受験をする子がゴロゴロいるエリアでは中学受験をする子が集まる塾の中にも学力による厳格なクラス分け、6年生になれば志望校に沿ったクラス編成がされることもあり、中学受験をする子向けの教材でも難易度が異なります。
一方、地方で中学受験をする子が集まる塾は受験する子自体の母数が限られているので、それなりに生徒数の多い校舎でMAXで3クラス編成、通常は2クラス編成に落ち着くと考えていいでしょう。
面白いことに、地方では中学受験向けの教材を使う塾の上位クラスに非中学受験組がかなりいることがあります。
これは私が高校生時代の国立大学附属中出身の子達も【小学生から受験向けの塾に通っていた】という話をしていましたし、我が家の子ども①②が通う塾でも、小学生のクラスで国立小学校や地域でも教育熱の高いエリアの小学校に通う中学受験をしない小学生が通っていたりと【受験しないけれど中受の勉強をする】という子がいます。
そういう子達は【高校受験に向けて】【大学受験に向けて】という家庭の教育方針で通っているというところもありますし、小学校以上のことを学びたいという子どもの知的好奇心を満たすため、という部分もあります。
ですから、地方に住んでいて高校受験でトップ高校を目指しているという場合は【小学生から受験する子が勉強することを学んでいる受験しない子達】の存在を意識することも必要ですし、家庭学習でも子どもの学力レベルが高いのであれば受験算数や難易度の高い教材を取り入れつつ、小学6年生の冬から中学進学に向けて塾に入って差が出ていない状態に仕上げる対策をしていくことも大切なポイントになります。
塾に通って成績が伸びる子は確かにいる
ところで、子どもが仕上がりそうな学力に注目するだけでなく【勉強姿勢】も重要です。
塾の先生は生徒の伸びしろ、授業への取り組み方を注意深く見ていますし、【どのくらい伸びそうか】というのもある程度予測できます。
伸びそうな子というのは【集中して15〜30分勉強できる】【 間違い直しを嫌がらない】【できるようになりたいという意欲がある】という特徴があります。
塾というのは教育の場であるものの、お金を払って成績を上げていく、受験で志望校合格することをサポートするサービス業です。
しかし、サービス業とはいえ生徒本人のやる気がなければ期待するような結果を掴み取ることはできません。
しっかり成績を上げる、期待する結果を残すには【塾で学んだことを復習し定着させる】ということは必須です。
私の経験上、成績が上がらない子は全員【塾だけで完結する】でした。
つまり、勉強するのは塾だけで家庭では何もしないという勉強スタイルを貫いていたので、宿題もやってこないことがザラで、全く知識が定着できないまま、ただ時間が過ぎ去っていきました。
反対に成績が上がる子は【分からない】を放置せず、すぐに先生に質問したり自分で調べるクセがありましたし、学業不振の子は【分かった風】で先生の説教をスルーしていました。
そして、なぜわざわざ塾に行っているのかを理解し、【中学に進学しても成績上位者になりたい】【難しい問題も解けるようになりたい】など明確な目標がありました。
親に言われたから通ってるだけの子とは伸び方は、本当に驚くくらいの違いがありましたし、【なんとなく聞いている子】と【しっかり考えて授業を受ける子】の吸収力は全く違いました。
塾はできる子をもっと伸ばす場所でもありますが、【自分から学ぼうとする姿勢】がない子は塾に通わせても効果が出にくいです。
そして、塾のレベルやクラスのレベルによっては【当たり前のように勉強する子】でないとついていけないので、塾に入る前に【基礎学力を鍛えて宿題を嫌がらず、応用問題を避けようとしない子】に仕上げておくのがベターです。