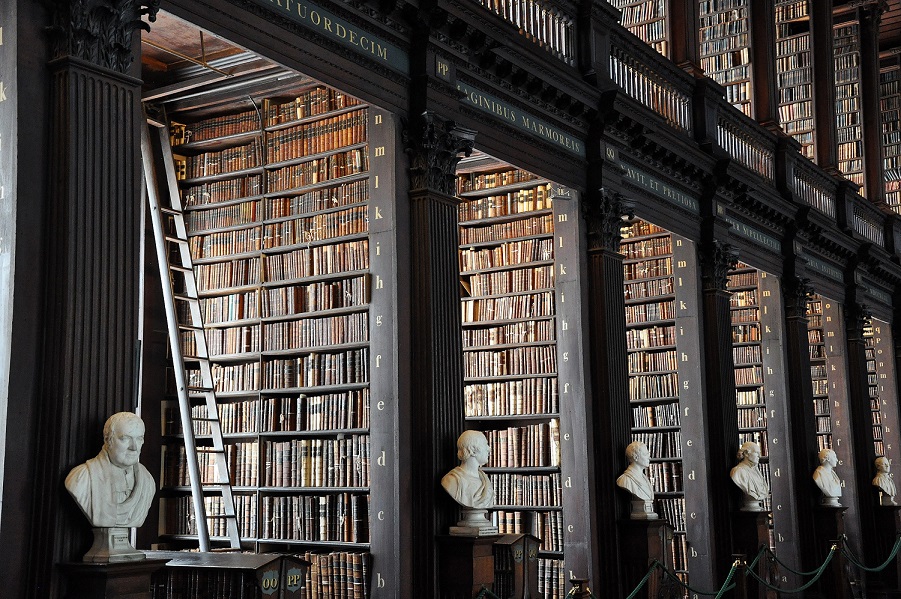今回は【中学生になって心強い 小学生の間に身につけたい3つの力】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
中学生になると学校の定期テストで校内順位がハッキリと出ます。
塾に入れば、所属するクラスも成績によって決まります。
牧歌的な小学生時代からガラリと変わり、実力主義の世界に子どもは身を置くことになります。
どうしても、地方に住んでいると【子どもは小学生時代はのびのびと過ごすもの】【勉強は中学生になってからでも大丈夫】と考えている親、周囲の雰囲気があったりします。
我が家の周囲でも、教育方針の違いというのは各家庭でかなりバラツキがあるというのは子育てを通じて感じることもありました。
やはり、【小学生時代はのんびりと】や【小学校のカラーテストは良い点数が取れているし】と考えている方が圧倒的多数派でした。
ただ、中学生になれば子どもの実力が判明してしまい、校内順位で【この位の高校に行ける】というのも見えてきます。
その時点で【思っていたよりも低い!】と慌てても、上位層の子はしっかり勉強しているので同じレベルになろうとしても、並大抵の努力では追いつくことも叶いません。
子どもへの負担を軽減しつつ、中学生になってからの勉強で苦労しないようにするには、小学生時代から将来を見据えて動き出すことが不可欠です。
それでは、勉強をガンガンさせていけばいいのかと言えば、話はそんなに単純なものではありません。
子育てを通じて色々と見聞する中で【幼児期や小学校低学年の頃はあんなに出来ていた子が、結局小学校高学年や中学生になってから伸びなくなった】というケースは案外多いです。
一人の親として色々と考えさせられることもありました。
そこで今回は、改めて小学生の間に子どもが身につけておくと心強い3つの力をご紹介していきます。
読み書きソロバンの弱点がないか
まず、中学生になるとどの教科も単なる知識を問う問題、用語を暗記すればそれでOK、という学びではなく、知識を学び、それを応用する勉強になります。
ただ、住んでいる地域の教育レベルによって変わりはしますが、とりあえず学習指導要領が改訂された影響で、テストも【文章を読み取る力がないと太刀打ちできない】が増えます。
読解力がないと問題の意味や条件を取り違えやすくなりますし、中学生になれば高校受験に向けた準備もしなければならないので、
それでは、中学生になったらいきなり勉強の質が変わるのかと言うと、そうではありません。
小学生の時から変化は起きています。
小学校4年生頃からすんなり1回で理解できない単元が増えてきますし、小学校5年生ではとくに算数の割合、図形、最小公倍数や最大公約数で苦戦する子はかなりいます。
基礎学力が不足気味という子はもちろんのこと、【ちょっとだけ読み書きソロバンのどこかに弱点がある】という子も小学校高学年の勉強では理解できない単元が出てくる事態になります。
高学年の勉強で躓くことが多くなったり、テストで80点台ばかりを取ることがあるとそれは黄色信号です。
この状態を改善させないと、間違いなく中学での勉強に苦労します。
例えば、中学の数学は、小学校で学んだ算数の計算力が弱いと途端に点数が取れにくくなります。
入学したばかりの頃に学ぶのは一応、計算分野なのですが、【目で見てすぐに答えられる問題】ではありません。
【正の数・負の数】【文字式】は計算力が盤石でないとスラスラ解けないです。
また、教科書の文章も専門的になり【何を言っているのかよく分からない】と感じる子もいます。
これは読解力とは無縁だと考えている子もいる数学でも【整数の性質ってなに?】と戸惑い、テストで苦戦することになります。
そして、他の教科も用語や公式を暗記しつつ、考えながら解く力、つまり論理的思考力も中学以降で重要性がかなり増してきます。
小学校6年間の間で、読み書きソロバンを盤石すぎるほど鍛えつつ、じっくり考えることに慣れさせる、文章を正確に読み取れる力を鍛えていきましょう。
自分で勝手に勉強する子になれるか
さて、小学生の間に身につけておきたい3つの力のうち、2つ目は【自分で勝手に勉強する子】になれる力、です。
中学受験界隈で最近取り上げられる【自走力のある子】です。
塾で出会った勉強しない子の特徴は、スバリ【受け身な子】でした。
指示待ちで受け身な子になると勉強をすることが自分事にはならず、成績が上がらないのも親のせいにしたりと、責任回避するようになります。
そういう子にならないようにするには、【自発的に行動できる子】に育てるというのが近道です。
自分から考えて動くというのは簡単そうで意外とできない子が多いので、最初は親が声がけをしたりとサポート、誘導をして【自分で考える経験】を積ませていくことが望ましいです。
親子の会話で【どういう意味?】【どうしてそう思うの?】という、子どもが考える回数を増やすような会話を増やしていくようにしましょう。
受け身な子は【どっちでもいい】【先生がやりたい問題を決めて】と全てにおいて他人任せなところがあります。
こうなると、受験期に突入しても自分が今やるべき勉強を自分自身で把握していない、合格に向けてどこを克服していけばいいのか分からず、迷走状態で受験に挑むことになります。
こうした未来は親としては絶対に避けたいところですから、小学生の間に【自分で勝手に勉強する子】に育てるというのは親にとっては子育てにおける大きなミッションの一つと言えるでしょう。
親がノータッチで自分から勉強する子になることはほぼないので、親が誘導して【自分から勉強するのは当たり前だよね】という感覚が身につくようにしないといけません。
ポイントになるのが【勉強に対する嫌悪感を排除する】【勉強することはプラスになることだと気づかせる】【勉強して分かることの喜びを経験させる】です。
塾で子ども達と接していて感じたのが【勉強するかしないかは子どもの気分次第】ということでした。
やる気がない子に勉強させるのは本当に大変でしたが、やる気のある子は勝手にサクサク勉強して手がかかりませんでした。
そして、勉強することの意味をあーだこーだと文句を言う子と、【こういう仕事に就きたい】【家を出て一人暮らしをしたいから親が納得してくれる大学に入れるよう頑張る】と明確な目標を持って勉強しつつ、自分の人生にプラスなると理解している子の学習量、成績は雲泥の差がありました。
また、分からない問題ばかりで学習意欲がどんどん低下する子もいれば、しっかり理解できるまで勉強をして【解けた!】という経験を増やしていき、勝手に勉強する子に変身した子もいました。
自走力のある子になると親も楽になるので、小学生の間に親がサポートをしつつ力をつけるようにしていきたいですね。
抽象的な学びに耐えうる思考力
ところで、小学生の頃から中学、高校につながる【抽象的な学び】に対応できる思考力を育てるには【知識の詰め込み】【知識の暗記】ではなく、自分で考える癖と文章内容を整理する力を育てていく必要があります。
普段の生活で【どうしてこうなったのだろうか】と話をしたり、昔話などのお話でも【このあと皆はどうなったと思う?】と自分の考えを口にする、自分の言葉で説明する機会を家庭で作ることが、徐々に抽象的な学びが増えても適応できることにつながります。
考える力は小学校低学年の頃に個人差が目立つという、割と早い段階から【考えるのが得意な子と苦手な子】が区別されます。
一度、【考えるのが苦手】と思い込んでしまうと、そこから抜け出すのは難しくなります。
親がアレコレ指示するのではなく【どう思う?】【どっちがいい?】と色々な場面で考えさせる機会を与えてください。
そして、抽象的な学びというのは考えさせること、とは言い切れない面もあります。
例えば、算数や数学での図形や規則性の分野にはルールがあります。
そのルールに基づいて頭の中で考えて問題を解いていきます。
パターンを見つける力、それを応用する力も抽象的な学びになります。
こうした学びは小学校の勉強より中学受験の勉強で多いです。
可能であれば、無理のない範囲で中学受験をする予定はなくても少し受験算数の問題を解いてみたり、小学校で学ぶ以上の勉強を家庭学習に取り入れていくのもおすすめです。