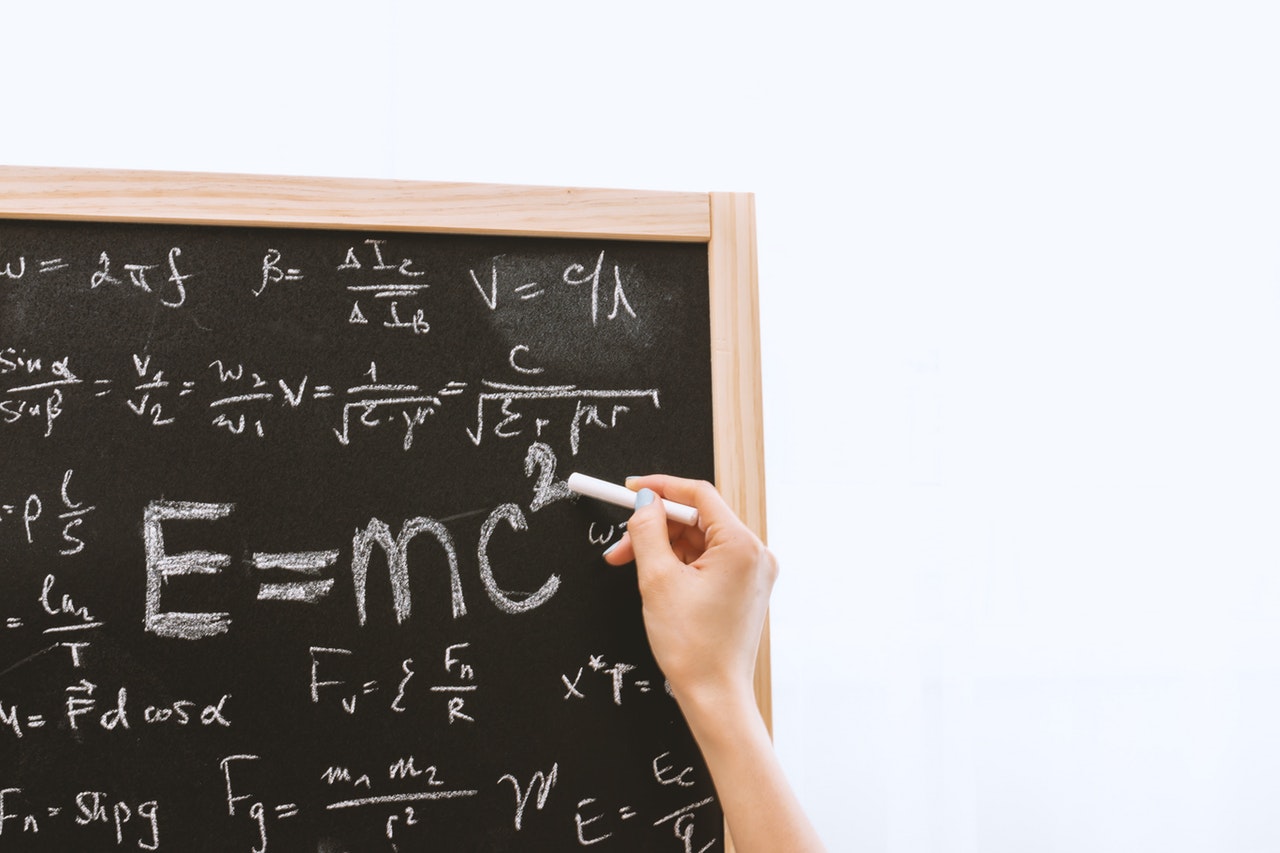小4の壁とか10歳の壁という言葉があります。
一般的に、学力差が拡大すると言われています。
しか~し、ただ単に勉強だけを頑張ればOKというものではありません。
高学年に向けて、さらに中学進学に向けて「学力の土台つくり」にもなるやっておくべきことをご紹介していきます。
YouTubeでも発信しています。こちらはテキスト版です。
ブログで取り扱っていないテーマ、YouTubeオリジナルの内容も発信していますので、興味がありましたらどうぞ。
第3位スマートな話し方ができるようにする
スマートな話し方というとちょっと難しそうですが、まずは言葉を省略しない話し方です。
・主語述語を使う
日本語は言葉を省略できるので、意味が通じてしまう。
会話が成り立ってしまうわけです。
主語と述語を理解していると、英語学習の時にもプラスになります。
日本語と英語というと全く別のものです。
しかし、主語と述語や形容詞、副詞と語句の品詞を理解していた方が断然、英語の理解度が早いです。
家庭での会話でも、親の方も主語と述語をハッキリ言って喋るように意識してください。
日頃から文法を鍛え、主語述語をちゃんと言って話すと【ハッキリしてている話し方】に近づきます。
・理由を述べる
論理的思考、自分の意見をいう学びが浸透しています。
自分の考えを述べる、というのは成長するにつれてそういう機会が増えていきます。
なぜ、そう思うのか
なぜ、それが欲しいのか
理屈っぽいと煙たがられるかもしれません。
しかし、自分の感情そのまま喋ってしまうと後で後悔することもあります。
理由を述べることで言葉を口にする時にワンクッションおけます。
SNSでの炎上問題もあります。
喋りながらも感情的にならず【考えながら発信する】という力を伸ばせます。
第2位 正しい漢字を書けるようにする
今の子ども達は、完全なるデジタルネイティブ世代です。
生涯を通して、字を書く機会も親世代に比べれば減ります。
そのため、逆に小学生の頃から習った漢字を「しっかり書ける」状態にしておくことが大切です。
字を書く機会が減ったと言われていますが、入試では筆記ですし就職試験でも書く機会があります。
人生の岐路では「書く」というのがつきもの。
そういう大切な場面で、小学生で習う漢字が書けない、というのは致命的です。
この前、我が家の末っ子子ども③が学校のテストで出た「正門を通る」を生活の生と書いて間違えていました。
同じ音訓読みなので、知っている漢字をあてはめたわけです。
漢字の、熟語の持つ意味を考えないで読み方だけで漢字を選んで書いたんですよね。
見直しをするとき、「立派なもんだから正しい門。それを正門というんだよ」と説明。
生だと、生きている門になるよね、と声をかける。
子ども③も「そんなわけないね」とミスを理解して正しい漢字を覚えさせる、という流れが一番効果的です。
間違えている漢字が多ければ多いほど、訂正作業が必要になってきます。
そのため、小学校4年生になるまでに習った漢字をしっかり覚える。
熟語の組み合わせも間違えないようにする、がとても大切です。
第1位 確かな計算力を身につける
計算の基本である四則計算は小学校3年生までに全て学びます。
小学校3年生から四則計算を利用して、分数の基本や小数を勉強することになります。
徐々に算数の内容もむずかしくなるので、確実に計算ミスを減らす。
計算が苦手だと、すなわち算数嫌い、数学嫌いに拍車をかけてしまいます。
算数は計算だけでなく、図形や単位換算もありますが花形は計算。
計算力が足りていないと、「自分は算数が苦手」と思い込んでしまうことにもなりかねません。
ですから、計算力を鍛えることはかなり重要です。
ご存知の通り、数学は大学進路の際に理系文系の選択に大きくかかわってきます。
本当は理系分野に興味があるけれど、数学が壊滅的で無理、と諦めることもあり得ます。
そういった事態を防ぐためにも、計算力を小学4年生までに身につける、鍛えておくことが必要です。
まとめ
今回は、『【小4の壁対策】小学校4年生までにやっておくべきことTOP3』について紹介していきました。
学力差が顕著になってくる小学3年生、4年生までに、
・主語述語を意識したスマートな話し方ができる
・正しい漢字を書けるようにする
・計算力を身につけ
を鍛えておくと、高学年や中学生以降の学びにプラスになりますので、是非実践してみてください。