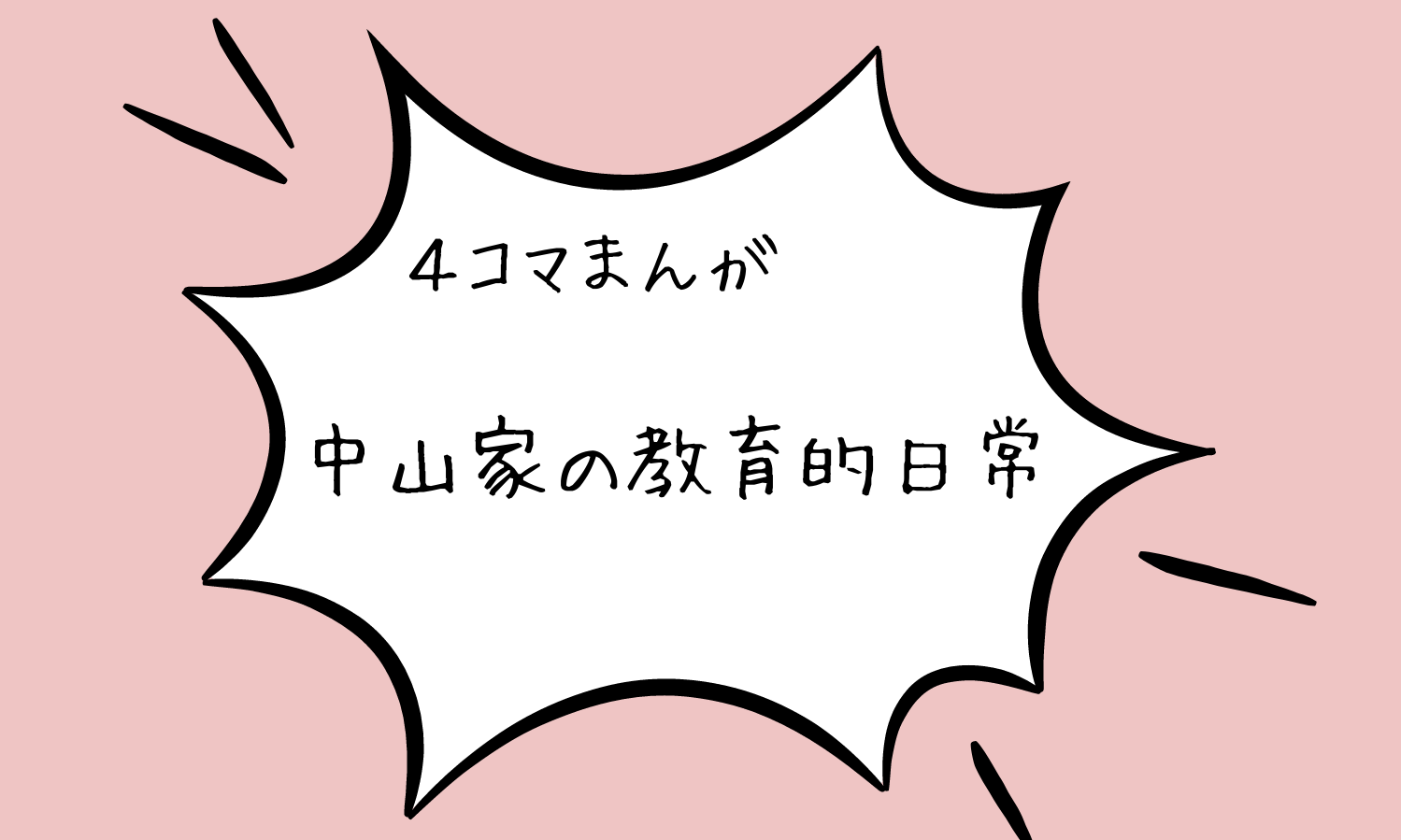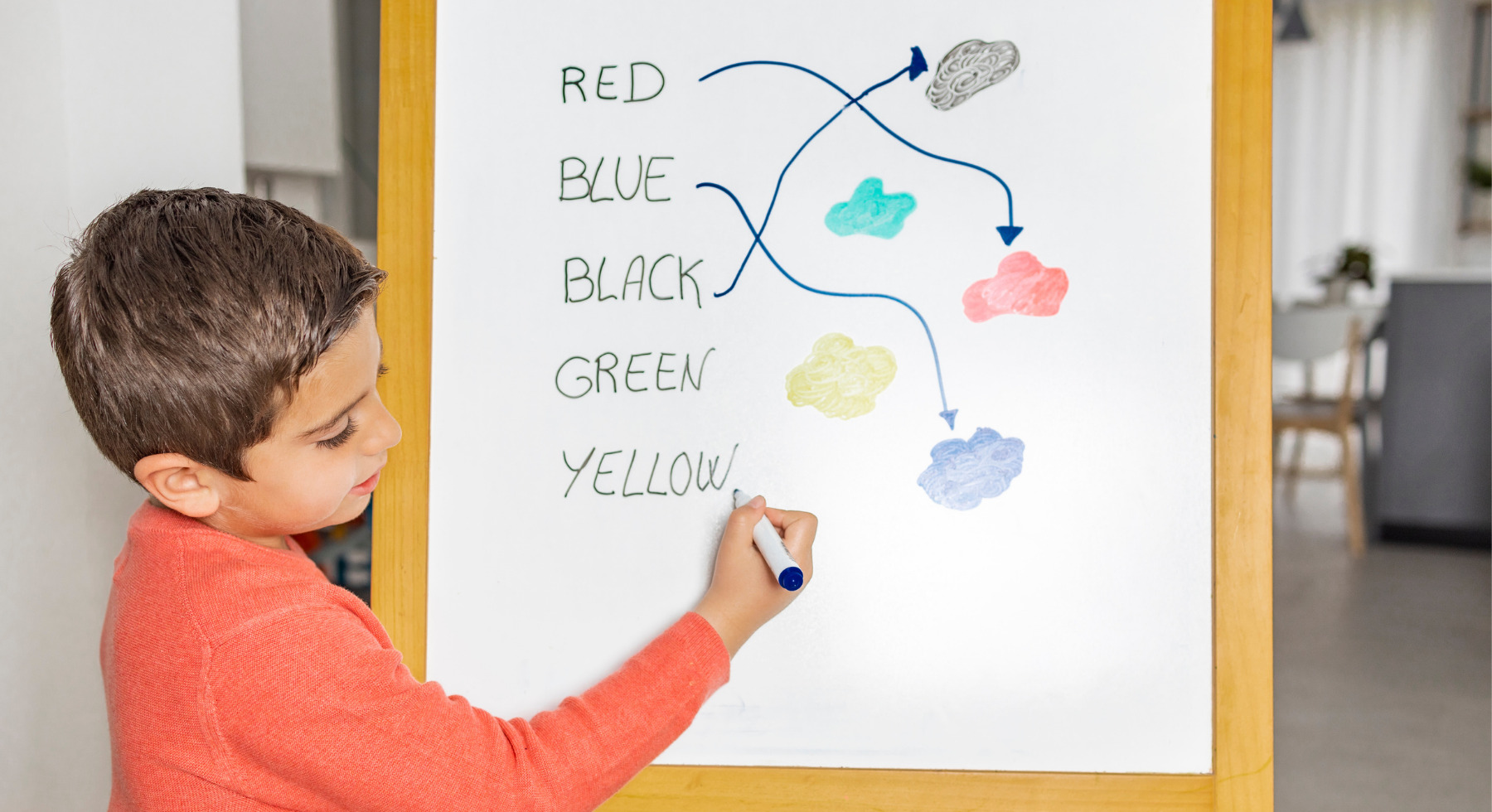新型コロナウイルスの蔓延により、世界中の生活様式や働き方なの大きく覆されました。
まだ現在進行形のコロナ禍。
以前の世界には戻ることはないのかな、と個人的に思っています。
さてさて、先日ネットニュースにて気になる記事が目に留まりました。
コロナ禍による学力格差や学習不足、授業スピードの速さなどが昨年から問題視されていました。
具体的な数値が、しかも小中高で出ているのはおそらく初めてのことかもしれません。
ただ、学習指導要領が変わったからと言って極端に難しくなったわけではありません。
(中1の英語のレベルは以前よりも高いですが・・・)
元々一定数いた「難しい」という子が臨時休校を起点にし増えたのかどうか。
もう少し詳しく調査しないと結論は下せませんが、学力格差がより顕在化したのではないかと個人的に感じています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
キンドルとは違う読み心地かなと思います。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
[amazonjs asin=”B0CK8RTW7Y” locale=”JP” title=”ブログに載せたまま放置編 透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ”]
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonですので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
[amazonjs asin=”B0CKPLNTJT” locale=”JP” title=”賢い子は何が違う? 伸びる子の分岐点 (edumother books)”]
[amazonjs asin=”B0CGZGCBF2″ locale=”JP” title=”親に知って欲しい 個別指導塾のあんなこと・こんなこと: 月謝 進学実績 通いやすいさ それだけで判断するのは時代錯誤なのでやめてください (edumother books)”]
[amazonjs asin=”B0CFDJQ1FL” locale=”JP” title=”子どもの「好き」を見つけないのは損!: 隠れた才能を見つける秘訣 (edumother books)”]
[amazonjs asin=”B0C8YC77D3″ locale=”JP” title=”難化する学校英語: 親の経験が通用しない 中学英語への段差に気をつけて (edumother books)”]
[amazonjs asin=”B0C3TTNV47″ locale=”JP” title=”夫婦の教育方針の違い: なぜずれる? どう決める? (edumother books)”]
[amazonjs asin=”B0BW34XRV7″ locale=”JP” title=”自分から勉強する子になる秘密: 本当は内緒にしたい (edumother books)”]
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
[amazonjs asin=”B0BTNYDVCS” locale=”JP” title=”小3が学力の分岐点: 小4の壁はもう古い 小3の坂道に気をつけて (edumother-books)”]
[amazonjs asin=”B0C2FJQRGQ” locale=”JP” title=”小1プロブレム 対応策を考える: 就学で起きる変化に立ち向かう (edumother books)”]
[amazonjs asin=”B0BZ8X3BV4″ locale=”JP” title=”子育ての鬼門 小4の壁の乗り越え方: 小4の壁を飛躍の時に (edumother books)”]
[amazonjs asin=”B0C7BHJ8M4″ locale=”JP” title=”子どもの自己肯定感: 低いとどんな人になるか考えたことありますか? (edumother-books)”]
パンドラの箱は開けられたのか

学力格差に関しては、4コマ漫画でも軽くお伝えしていますが最近の問題では決してないです。
アムラー世代である(これっぽちもアムラー的な服装はしたことありませんが)私の時代でも、地方トップ高校の保護者の学歴や職業は偏っていました。
一番多い組み合わせは「大卒のお父さん・大卒or短大卒のお母さん」。
私たちの親世代は、昭和10年代後半から昭和20年代に生まれた人たちがほとんど。
1990年代半ば、トップ高校の同級生の親の大半が「短大以上」という事実に、両親高卒の私はかなりショックを受けました。
すでに、1990年代半ばから学力層の固定化は進んでいたのです。
学歴は受け継がれていく・・・
その世代が今、親となっています。
祖父母&親が大卒や短大以上の学歴だと、その子には大卒を求めます。
というか、何か特別なことがない限り(高校野球で大活躍・かなり勉強が苦手など)は大卒が当たり前という空気感。
で、親戚一同や近隣で大卒の人が身近にいないと、大卒というのはものすごく遠い存在に映ります。
そうなると大学にいかないので、大学進学者が少ない高校に進学することになります。
簡単にいうと、義務教育である小中の時点で「大学行くのが当たり前と思っている子」と「別に大学に行くつもりはない子」にザクっと二分化するわけです。
戦後から現在を振り返ると、祖父母⇒親⇒子どもの3世代がスッポリとはまる時間です。
祖父母の学歴が、今の子ども達に影響を及ぼしていることは間違いないでしょう。
私の場合、両親ともに進学希望を出していたのに家の事情(まぁ、ベタな経済的事情)で断念。
自分達のようにはなって欲しくないということで、(基本的に放置プレーで教育熱心でもないけれど)子どもに進学を熱望していました。
さて、こうした学力の固定化が進んでいるため、臨時休校中の対応も各家庭で異なります。
親ガチャという、言葉もありますがやはり家庭の考えで教育方針は決められる面はありますよね・・・。
コロナ禍でさらに加速する学力格差

コロナ禍によって学力格差が進んでいるという話、論調が出てきています。
これは、事実でしょう。
なぜなら、大まかに2つのグループに分けられるからです。
・臨時休校期間でも家庭学習をしっかりやって学習時間を確保していた子
・TV・動画視聴やゲームに時間を費やしていた子
これ以外にも、2020年春の緊急事態宣言では各自治体の図書館や大型ショッピングセンターがお休みに。
本を借りたい、本を買いに行くのも難しく、既存の蔵書量の違いで読書タイムも差が出たと推測されます。
電子書籍もありますが、子どもには紙ベースが最適(アプリでゲーム始めたりするので)。
学校があればそれなりに確保できる、生活リズムと「学習時間+読書時間」が各家庭にゆだねられた状態でした。
短期間で戻すのは困難
国や学校への批判云々の前に、親がどのくらい教育に関心があるかどうかで大きく左右されたと思います。
生活リズムが崩れると、一気に勉強する時間も減ります。
私もそうならないよう、あの時期は試行錯誤を繰り返して生活リズムをキープしていました。
そして、コロナ禍で学び遅れや授業進度への対応として以下のことに当てはまるかどうかで、子どもの学力差がドカンと出てしまっている感があります。
・タブレット端末の通信教材を受講する
・オンライン形式の授業を行う塾に入る
・もともと入っていた塾でオンライン形式や通塾スタイルを選択し学びを継続
家庭学習プラスアルファの学習機会があったか、ということです。
これで苦手克服や先取りを進めた子はけっこういたと思います。
それがガッツリ3月から5月末までの3ヶ月間(地域によりますが)続いたわけです。
3ヶ月丸々グータラしていた子が、1日3,4時間勉強してい子に追いつくのはほぼ不可能。
前年度の授業スピードに追い付けず、はたまた先取りをしている子もいる。
それが1年間を経て出てきているのではないかと危惧しています。
習熟別を本気で考える時期が来た

日本の義務教育では、学力差があるものの、一つのクラスで一同が授業を受ける形式がスタンダード。
算数などでは習熟別などでの授業が行われるケースもありますが、一般的ではありません。
国語や算数など柱となる教科で、習熟別クラスを設けて【全く分からない】子を生み出さない授業スタイルを本気で考える時期が来つつあると感じています。
子ども②が2021年度小学5年生ですが、やはり約分を上手くできない子も一定数いるとのこと。
丁寧に教えたいけれど授業を進めないといけない。
そして宿題プリントは現状は全員統一の問題です。
ただし、生徒の理解度に合わせることで、一部の親から反対意見が出たりクレームの電話が鳴り響く可能性も否定できません・・・。
面倒な問題を生み出すので、そう簡単には導入できないかもしれませんが、コロナ禍で学力格差が現在進行形で進んでいます。
可能な限り、1人1人に合った教育が実現できれる日がくると良いのですが、時間は待ってくれません。
やはり、家庭でコツコツと遅れを取り戻すことが最善手なのです・・・。