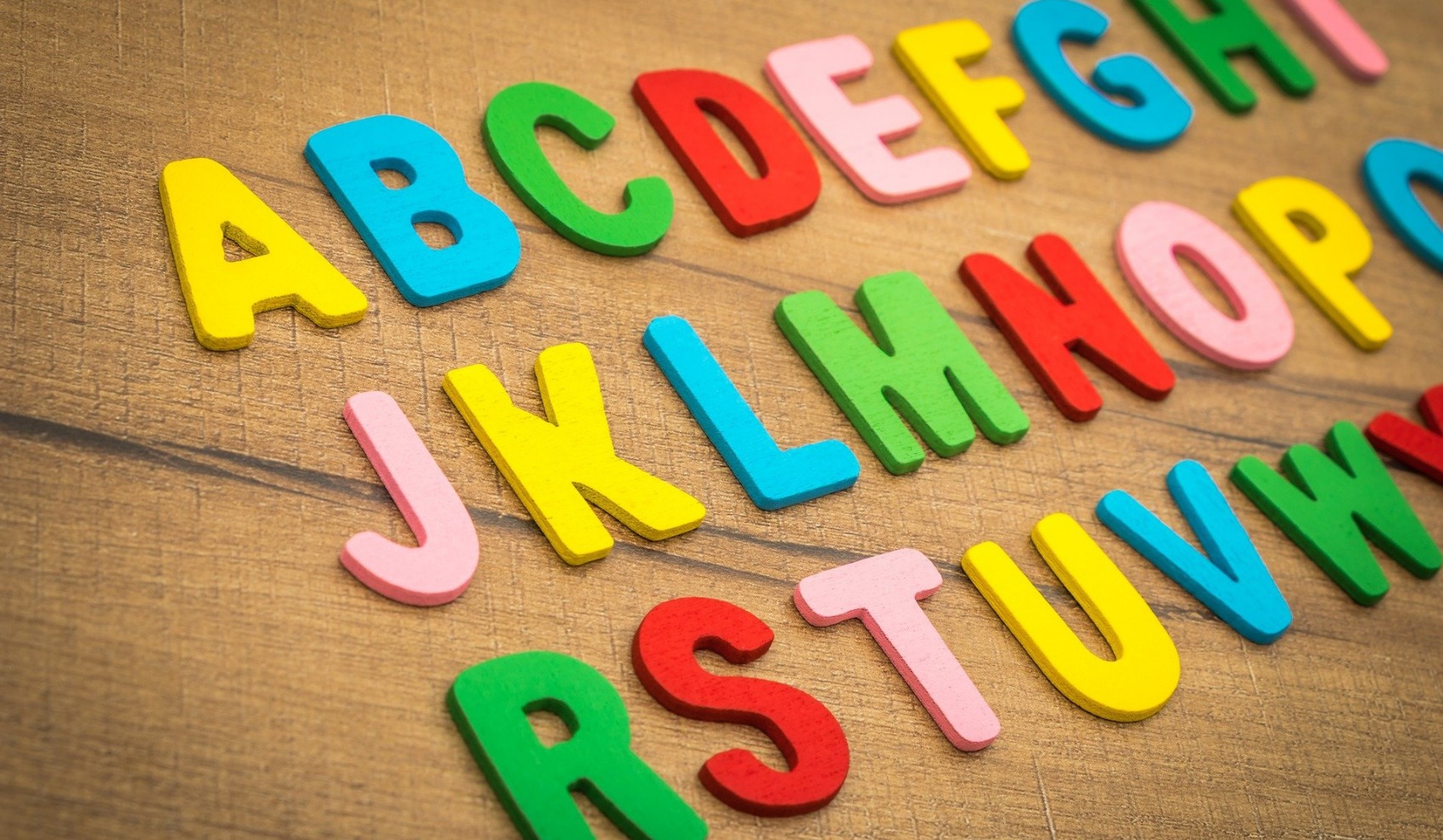「うちの子、いつになったら勉強してくれるのかしら」
そうお悩みの親はたくさんいます。
結論から申し上げますと、「子どもが勝手に勉強することはまれ」です。
【成長すれば勝手に勉強する】は期待しても無駄。
勉強しない子を勉強する子に変身させる大変さを語っていきます。
そして、少しでも勉強する子にさせるにはどうすればよいのでしょうか。
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
勉強しないのは楽です
子どもが成長とともに自発的に勉強すると思い、ずっと期待して待つのは無謀です。
ハッキリ言って、勉強する習慣が全くない子が自分から目覚めるのは500人に1人というレベルだと思います。
もう少し和らげると、300人に1人でしょうか。
私は小学生の頃、グータラでした。同じようにグータラ仲間の子が中学で確変したのは皆無。
経験上、【小学生時代まったく勉強せずも心根を入れ替えた子は300人~400人に1人ならいるかも】です。
勉強していない子にとって、勉強は苦行のようなもの。
【日本は勉強して偉くならなくても生活できる】と思っているのでしょう。
理由1.親に反抗する時期に入ったらお手上げ
勉強する習慣ゼロ⇒自分からガンガンする子に変身、は夢幻です。
書籍物の中に、【自分から勉強する子に云々】というものもありますが、それはレアケースだから。
ビリギャルもそうですよね、レアケース⇒興味関心で本を買う、というパターン。
「親は東大でのエリート官僚で御三家に合格した記録」なんて題名の本があったとしたら、どちらがより多くの人の心に届くか、です。
「いつかは勉強する子に」を夢見ても、行動しない限り改善しません。
そして、子供が成長すれば成長するほど難しくなります。
なにせ、小学4年生前後から反抗期に突入し始めます。
子どもの性格によって突入時期はバラバラですが、【素直に何でも聞く】をやめて自立の第一歩を踏む出すわけです。
このタイミングの前に学習習慣をつけておかないと、サァ大変。
よほどのことがない限り、勉強する子に変身しません。
理由2.勉強を教えてケンカに発展する

それでは、親がつきっきりで勉強を教えるべきかというと、可能な限り自分でやらせるのがベター。
私も経験していますが、親が教えるとケンカに発展することがよく起きます。
職歴を知っているママさんから「教えられていいよね」と言われることもありましたが、塾講師だろうが何だろうが、子どもにとっては「お母さん」。
中には親が教えて上手くいっている家庭もあるとは思いますが、普通は難しいです。
勉強しない
↓
親が教える
↓
お互いがイライラ
↓
ケンカ
↓
勉強しない
の繰り返しです。
理由3.家庭内が不穏でやる気が下降
【お前がちゃんと見ていないからこんなことになった】
父親が子どもの成績が悪いことを母親のせいにする。
これ、よくあることです。
夫婦のイザコザ、子どもにとって良いことゼロ。
【自分のせいでケンカしている】と思います。
そして、【勉強だけしている私・僕が好きなのかな】と子どもなりに考えるように。
子どもにとって良くない状態です。
家庭の雰囲気が悪いと落ち着いて勉強に励めませんよね。
これは、職場に置き換えれば分かりやすいかと思います。
会社の雰囲気が最悪。パート先が人間関係がギスギスしている。
【今日も1日頑張るぞ!】というやる気はなかなか出ませんよね。
勝負の時期は就学前から低学年まで

個人的に、後の面倒くささを考えれば【就学前から低学年の頃に家庭学習を身につける】がおすすめです。
ちょっと早すぎる、という意見もあるかもしれません。
しかし、私が考える【椅子に座って机に向かい1日5分程度勉強系に取り組む】は成長するにつれ威力を発揮します。
ここでは、その理由も考えていきます。
理由1.勉強への抵抗感をあまり感じない
年長時代から椅子に座って机の上で文字を書いたりするのに慣れていると、小学校の授業や宿題に戸惑うことはほぼありません。
行き過ぎた早期教育は考えものですが、就学前から勉強っぽい要素を取り入れることは後で楽です。
我が家の場合、幼児期から椅子に座って机で折り紙やお絵かき、工作をしていました。
年長の冬に文字や足し算のドリル(100均のもの)、Z会や進研ゼミの就学前ドリルを一通り取り組ませました。
コツコツと短時間を積み重ねていくと親がガミガミ言わなくても小学3,4年生以降に自分から勉強する子になっていきます。
理由2.勉強することがルーティーン化
勉強しない子が勉強する気になれないのは、【普段やっていないから】です。
この期間が長くなればなるほど、やる気を起こすのに苦労します。
で、親もイライラしケンカに発展。
習慣化するには、やはり就学前から低学年が適しています。
それ以降になると、子どもは成長し自我が芽生えて親に反抗。
これは自然なことですが、やはり【鉄は熱いうちに打て】です。
ただし、欲張って5分、10分、30分とガンガン勉強させるのはNG。
勉強のさせ過ぎは、勉強嫌いにさせる原因になるので注意が必要です。
理由3.自分の未来を掴むために勉強する
人間、楽したいです。
ただ、子どもの中でも明確な夢がある子は努力しますよね。
だいたい、スポーツ面が取り上げられることが多いですが、勉強も同じです。
【プロ野球選手になりたい】から素振りやランニングをして体を鍛える。
【多くの人を病気から救く医者になりたい】から医学部を目指して勉強する。
【世界中で演奏会をひらくピアニストになりたい】から毎日ピアノの練習をする。
みんな、目標に向かって頑張ります。
将来の夢が勉強しないと叶うのが難しい場合、家で宿題以外の勉強をする気になります。
毎日遊んでいる子が、簡単に医学部に入ったり国家医師免許に合格することはムリ。
勉強がルーティーン化していると、夢に向かって勉学に励みます。
もちろん、息抜きするときもありますが基本は【なりたい自分になるため】に努力するようになります。
【それでは我が子はもう手遅れ・・・】という訳ではありません。
自我が芽生えて反抗期の子どもにも、勉強する気にさせる下準備はあります。
学ぶ姿勢の大切さを伝える

思春期を迎え、反抗期な子どもに【勉強しなさい】と言ってもぬかに釘。
こういう時は、以下のことをして子どものやる気を少しずつ上げていきましょう。
- 将来のことを語り合う
- 社会情勢を話し合う
- 人生の選択肢を話す
1.将来のことを語り合う
親だからと上から目線ではなく、将来やりたいことを聞いてあげましょう。
家&地元を出るのか。どこで生活したいか。
と一番遠い未来から聞いていくのがベスト。
【都会に出たい】と言われたら、どうすれば都会に行けるのか考えてみましょう。
【東京で就職するにはどうすればいいのか】【生活費がかかるから給料の良い職種は何か】【大学は東京の方が有利になるか】等々。
遠い未来に到達するには、今何をすべきか浮かんでくるはずです。
2.社会情勢を話し合う
2020年は新型コロナウイルスによって全世界が混乱&今までの日常が根底から覆されました。
大企業でも一寸闇。
先行き不透明な社会を生き抜くにはどんなスキルを磨くべきか考えましょう。
雇用不安は、親世代も当事者であります。
これまでの景気の波(バブル⇒バブル崩壊⇒就職氷河期など)を経験していたら、当時の思い出を話すのも親として、人生の先輩としての役割です。
ちなみに、私の場合はバブル時代が実家の暗黒時代でした。
そう、日本の歴史上最高に景気の良い時代を全く体感できなかったのです・・笑。
不安定な時代でも、欲しがられる人材の基本は【やる気があり受け身ではない人】【素直な人】【向上心がある人】。
簡単な話、楽なことに逃げる人は相手にもされません。
そういった現実を伝えるのも親の務めです。
3.人生の選択肢を話す
長い人生、必ず大きな選択の時がやってきます。
進学先、就職先、結婚相手・・・・。
簡単にいうと、勉強していないと選択肢は狭まります。
これは事実です。
進学先が選べず、就職先も不本意だったけどここしかなかった。という人生を送りたいのか。
子どもは時間が無限になると思っています。
無限が有限であると気がつくのは、20代、30代を過ぎた頃でしょうか。
私も40を過ぎて色々と考えるようになってきました。
実りある人生を送って欲しいという我が子を思う親の気持ち。
なかなか、子ども分かってくれません。
ついガミガミ言ってしまいますが、冷静になって人生を話し合って勉強の大切さを気づかせてあげたいですね。