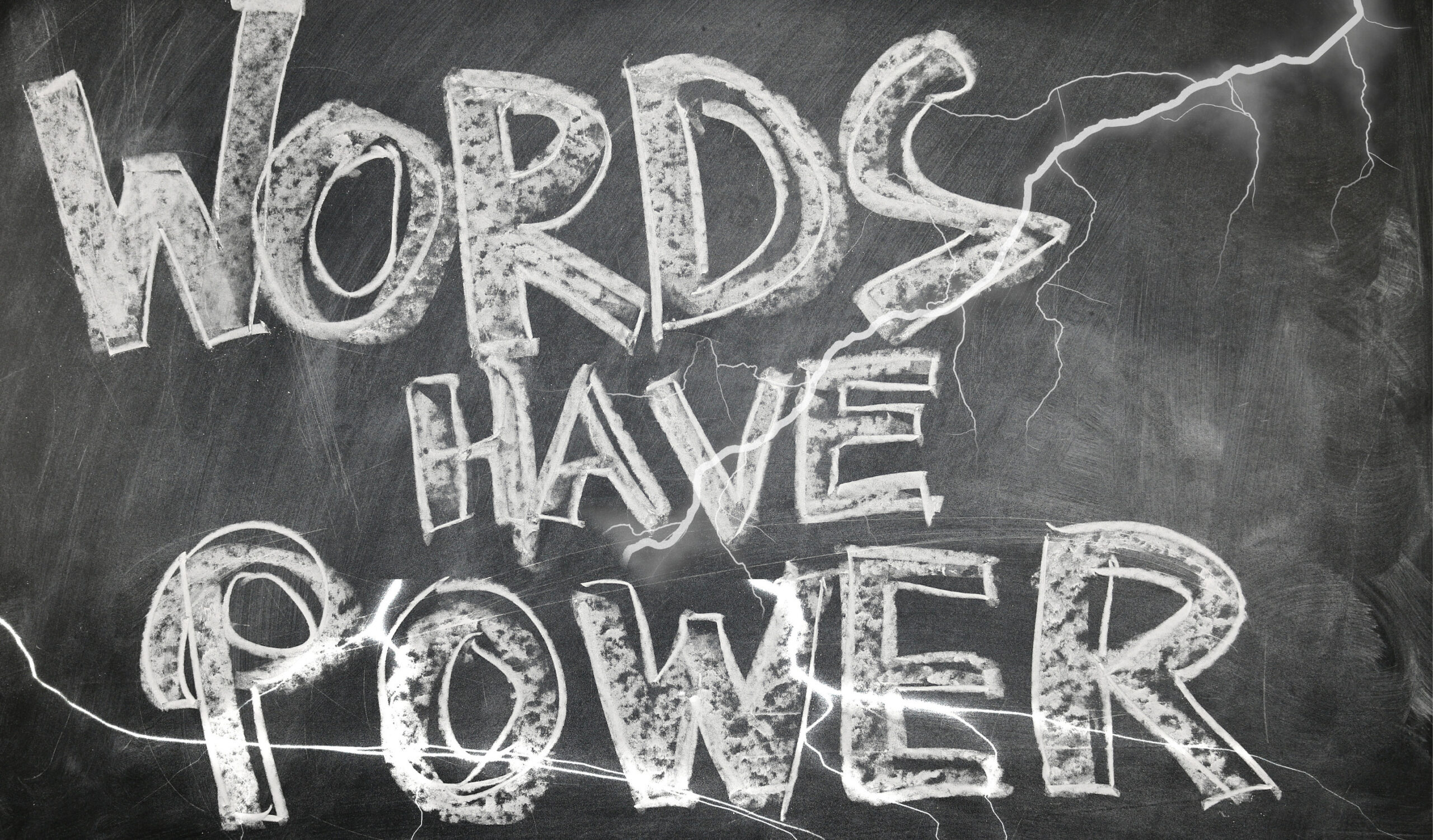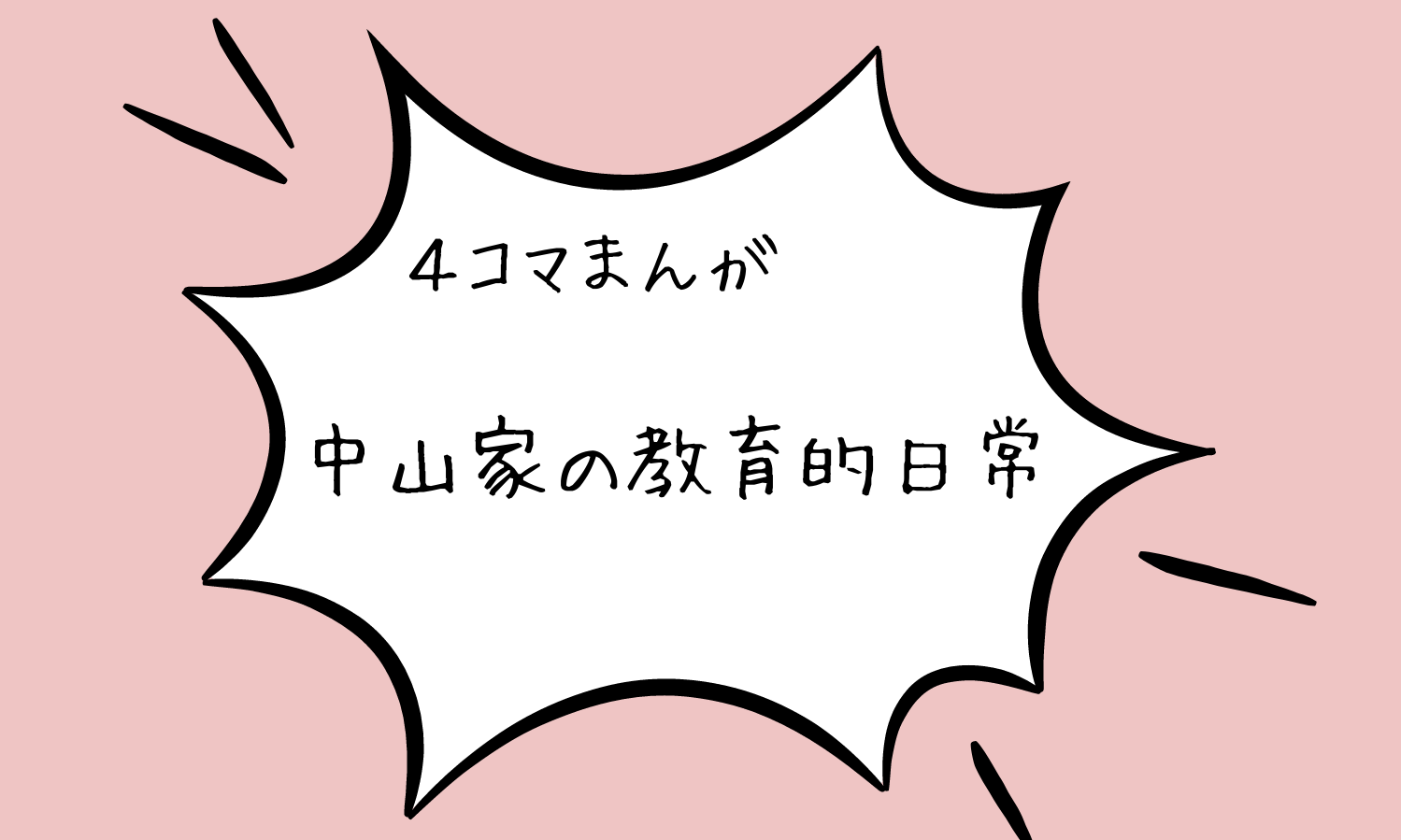今回は【【基礎はできるのに】の壁 上位層に食い込むための攻略法】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
【基礎はできているのに、応用になると急に解けなくなる】【授業では理解しているのに、テストで点が伸びない】
多くの子がぶつかるのが、応用の壁です。
我が家の子どもたちも、基礎はそれなりにできるけれど応用問題には苦戦するということが度々あります。
基礎力はあるのに結果につながらないと、親としては【あと何が足りないの?】【勉強量の問題?】と悩みがちですが、実はこの壁には明確な原因があります。
応用問題は【難しい問題】ではなく、【知識を使い分ける問題】です。
つまり、応用問題が解けるかどうかは思考の質 の問題であり、【知っている量】よりも、【知識をどう扱うか】で差がつきます。
そしてこの扱う力は、生まれつきの才能ではありません。
正しい学び方と環境さえあれば、どの子でも必ず伸ばせる力です。
むしろ、基礎ができている子ほど、伸びしろは大きいと言えるでしょう。
そこで今回は、最初に、なぜ【基礎はできるのに応用が解けない】のか、続いて上位層の【思考回路】を盗め!応用問題を解く3つのスキル、そして家庭で実践する応用力を鍛える3つのステップ、という流れで、応用の壁を突破するための実践的な思考法を解説します。
【基礎→応用】がつながらないのは、その間の橋がないだけです。
その橋さえ架けてしまえば、子どもは一気に上位層へ食い込みます。
そのための道筋を、ここから丁寧にお伝えします。
なぜ【基礎はできるのに応用が解けない】のか
まず、【計算はできるのに文章題になると止まる】【公式は覚えているのに応用に使えない】。
多くの子どもがぶつかる応用の壁は、決して能力不足ではありません。
むしろ、基礎力がついてきたからこそ浮き彫りになる次の課題といえます。
基礎問題は、公式を覚え、それをそのまま当てはめれば点が取れる仕組みです。
しかし応用問題は、知識よりも思考の扱い方が試されるステージ。
つまり、勉強の質が問われる段階に入ったということです。
応用問題は、子どもにとって見たことのないタイプの問題に感じられることが多く、そこで思考が止まります。
しかし、上位層は同じ問題を見ても【どの考え方が使えるか】を探しながら読み、自然に道筋を作っていきます。
この差が、学力差、点数差となって表れます。
ここでは、基礎ができているのに応用が解けない理由を、①知識が点のままつながらない、②問題文を読み取る力が弱い、③思考の手順(プロセス)が身についていない、という3つに分けて深掘りします。
原因さえ分かれば、対策は明確になります。
応用力とは、生まれつきの才能ではなく伸ばせる力です。
まずは、この壁の正体を正しく理解するところから始めましょう。
原因①知識が【点】のままの状態
基礎問題は、学んだ公式や手順をそのまま使えば解くことができます。
そのため、知識が点のままでも対応できてしまい、ある程度の成績は取れてしまいます。
ところが応用問題は、【複数の知識を同時に使う】【別単元の内容と組み合わせる】といった思考が求められます。
すなわち、知識が線になっていなければ太刀打ちできないのです。
たとえば算数で、割合と比の混合問題が出ると手が止まる子がいます。
これは【割合=割合の公式】【比=比の公式】という別々の箱で覚えているため、問題に合わせて取り出して組み合わせる力が弱いからです。
また、国語で文章題が苦手な子は【語彙】【文脈】【主語述語】などがバラバラになっており、文章全体の流れとして処理できていません。
知識を点で覚えている子は、見たことがある問題は解ける一方、少しひねっただけで【知らない問題】と誤認してしまいます。
ところが上位層は、知識がネットワーク化されているため、未知の問題でも【何かヒントがあるはず】と考えて突破口を探せます。
応用力とは知識の扱い方であり、ただ覚えるだけでは育ちません。
点を線に、線を面に広げる学び方に変えることが、応用問題の攻略には不可欠なのです。
原因②問題文の【読み取り力】が不足している
応用問題が解けない最も典型的な理由のひとつが、読み取り力の不足です。
これは単に【読むのが遅い】という話ではなく、問題文の情報を整理し、どこが重要かを判別する力 が弱いという意味です。
基礎問題では、問題文が短く、必要な情報も明確で、問いが単純です。
しかし応用問題になると、条件が複数あり、問題文が長くなり、時には余計な情報も混ざります。
ここで読み取り力がない子は、【どこから手をつければいいかわからない】状態に陥り、解き始める前に混乱してしまうのです。
算数で例を挙げるとすると、文章題では【条件を図にする】【数字の関係を整理する】といった前処理が欠かせません。
しかし読み取りが弱い子は、文章のまま処理しようとするため、頭の中がごちゃつき、正しいアプローチを選べなくなります。
また国語でも、問いの意図を読み違えたり、重要な語句を見落としたりすることで、正しい答えにたどり着けません。
一方、応用問題が得意な子ほど、問題文を読むときに構造を意識します。
・登場人物
・条件のつながり
・主語と述語
・時間の流れ
などを自然に整理しながら読み進めるため、問題の全体像が把握できます。
応用問題が解けるかどうかは【読む力=情報処理力】の差です。
読み取り力を鍛えることが、応用突破への最短ルートなのです。
原因③思考のプロセスが身についていない
基礎問題は、あらかじめ決められた型に沿って解けば正解できます。
そのため普段の学習が基礎中心の子は、【考えるプロセス】を省略したままでも点が取れてしまいます。
しかし応用問題には、型がありません。
自分で考え方の道筋を作れなければ、手が止まってしまいます。
算数の応用問題では、①情報整理、②必要な公式の選択、③解法の組み立て、④検算、といった段階的な思考が必要です。
しかし思考手順が身についていない子は、【とりあえず公式を当てはめる】癖が強く、問題の構造を理解しないまま突っ込んでしまいます。
国語でも同様です。
・本文の要点整理
・問いの意図の理解
・根拠の選択
というプロセスを踏まず、【なんとなく】で選ぶため正答率が安定しません。
上位層の子どもは、問題を解くとき必ず思考の手順があります。
これは特別な才能ではなく、日頃から【どう考えたの?】と問われ、考える過程を言語化する習慣があるからです。
プロセス思考があるからこそ、応用問題という初見の問題にも対応できます。
応用力とは、【考える才能】ではなく【考える習慣】。
この習慣がなければ、どれだけ基礎を固めても応用問題には太刀打ちできません。
応用の壁を越えるには、思考プロセスを育てることが不可欠なのです。
上位層の【思考回路】を盗め!応用問題を解く3つのスキル
さて、応用問題が解けるかどうかは、【頭の良さ】ではなく【思考回路の違い】です。
実際、上位層の子、彼ら彼女たちは応用問題を解くときに特別速いわけでも、特別な閃きを持っているわけでもない、ということがあります。
ただ、考え方が一貫しており、問題の構造を瞬時に把握するパワーを持っています。
多くの子が応用問題でつまずくのは、【知識が足りない】のではなく、【どう考えればいいのか】がわからないからです。
基礎問題とは異なり、応用問題は自分でルールを選ぶ思考が必要です。
だからこそ、思考の型を持っている子は強く、型を持たない子は迷子になります。
ここでは、応用問題を解くために最も重要な3つのスキルを紹介します。
それは、①情報を整理して【見える化】する力、②知識をつなげて使う力、③仮説と検証を繰り返す思考の柔軟性です。
これらは、どれも才能ではありません。
意識すれば誰でも確実に習得でき、身につくほど応用問題が解けやすくなります。
応用力の核心とは【考え方を整える力】です。
ここでは、その具体的な中身を掘り下げていきます。
スキル①情報を整理して【見える化】する力
応用問題が解ける子は、読んだ情報をそのまま頭に放り込まないという共通点があります。
長い文章や複数の条件が提示されたとき、それをそのまま記憶しようとすると負荷が大きすぎて、思考が混乱します。
そこで彼ら彼女たちが自然に行っているのが情報の可視化 です。
例えば算数では、
・図で関係を整理する
・表にまとめる
・線分図に書く
といった方法で、文章を【目で見て理解できる形】に変換します。
こうすることで、複雑に見えた条件が一気に整理され、どこに注目すべきかが明確になります。
国語でも同じです。
・段落ごとの要点を書き出す
・人物の関係を線でつなぐ
・問いに関わる部分にしるしをつける
といった作業によって、文章の構造がつかみやすくなります。
可視化ができない子は、問題文の情報を頭の中で処理しようとするため、情報がごちゃつき、何をすればよいかわからない状態に陥りがちです。
一方、可視化が得意な子は正解までの道筋がはっきり見えるため、迷わず取り組めます。
応用問題は情報量との勝負です。
情報整理ができるかどうかで難易度が大きく変わります。
【見える化】は応用問題を解く第一歩であり、最も強力な武器です。
スキル②知識を【つなげて使う】力
応用問題とは【複数の知識を同時に使う問題】です。
ところが、多くの子は学校で学んだ内容を単元ごとの箱にしまい込んでしまい、必要なときに取り出して組み合わせることができません。
例えば算数では、
・割合 × 比
・速さ × 図形
・小数 × 分数
など、複数単元を組み合わせることでしか解けない問題が増えていきます。
このとき【割合の公式だけ】【比の公式だけ】のように単品で知識を扱う子は、応用問題が急に難しく感じます。
国語でも同じで、語彙・文法・文脈理解・論理構造などが複合的に求められます。
【単語は知っているけど文章の意味がとれない】という現象は、知識が結びついていないことが原因です。
上位層の子は、知識を【道具】として扱っています。
道具箱から必要なものを自由に取り出すように、【この問題は割合と比の両方が必要だな】【この文章は接続語に注目すれば流れが読める】と考えられます。
知識をつなげる力は、才能ではありません。
・復習の仕方
・考え方の整理
・解き直しの工夫
これによって、誰でも後天的に鍛えられます。
応用力とは、知識の量ではなく知識の扱い方。
このスキルが身につくと、応用問題が一気に解けやすくなります。
スキル③仮説と検証を繰り返す【試行錯誤の力】
応用問題で最も大切なのが、 仮説・検証型の思考 です。
応用問題は、初見で完璧に解けるよう設計されていません。
むしろ、【まずはこうかな?】【違う、じゃあこっちか】という試行錯誤そのものが正しい道筋です。
ところが、基礎問題ばかり取り組んできた子は【一発で正解できるもの】と思い込みがちで、少し複雑な問題に当たると【分からない】【無理】とすぐに考えることを止めてしまいます。
上位層の子は違います。
彼ら彼女たちは最初から【応用問題は試すもの】という前提で取り組みます。
だからこそ、
・途中で書き直す
・別の考え方をためす
・条件を入れ替えてみる
といった柔軟な思考が自然とできるのです。
この思考法は、数学・国語・理科・社会すべてで有効です。
とくに中学以降の内容は、【仮説→検証→修正】のくり返しが前提となるため、この力を小学生のうちから、早い段階で育てるほど伸び方が変わります。
仮説思考は【粘り強さ】そのものでもあります。
粘れる子は伸びるし、粘れない子は伸びません。
だから、応用問題を解く力とは【性格】ではなく、【思考習慣】なのです。
家庭で実践!【応用力】を鍛える3つのステップ
ところで、応用問題を解く力は、一部の子だけが持つ特別な才能ではありません。
むしろ 家庭での学び方の工夫 によって、誰でも後天的に鍛えることができます。
応用問題が苦手な子の多くは、【考え方の型】が身についていないだけで、その型は家庭でも十分に形成できます。
大切なのは、【正解させること】【量をこなすこと】ではありません。
応用問題を解ける子に育てるには、どう考えたかに親が関心を向ける必要があります。
つまり、答えではなく【考え方】を中心に会話する家庭ほど、応用力は確実に伸びていくのです。
ここでは、家庭で応用力を育てるための具体的なステップとして、①考え方を言語化して【見える化】する
②解き直しを習慣化して思考を改善する、③段階式に【少しむずかしい】問題で成功体験を積む、という3つの方法を紹介します。
どれも今日から実践でき、しかも効果が出やすいものばかりです。
応用力は、環境次第で飛躍的に伸びます。
家庭での関わり方を少し変えるだけで、【基礎はできるけど応用が苦手】という状態から脱却し、確実に上位層へ近づくことができます。
ステップ①考え方を【見える化】して整理する習慣をつくる
応用力を伸ばすうえで最も効果が高いのが、思考の見える化です。
子どもの頭の中で起きていることは、外からは見えません。
しかし、応用問題が解けるかどうかは、この頭の中の考えの道筋がどれだけ整理されているかで決まります。
そこで家庭でできる最初のステップが、【言語化】と【図式化】を習慣にすることです。
例えば、
・どう考えたの?
・どこで迷った?
・その公式を使おうと思った理由は?
など、親が【答え】ではなく【考え方】を聞くことで、子どもは自分の思考を外側に出す練習ができます。
これだけで、頭の中が整理され、応用問題へのアプローチが改善していきます。
また、算数や理科の問題では、
・線分図
・表
・図解メモ
といった見える化ツールが強力に役立ちます。
問題文をそのまま頭の中で処理しようとすると混乱しますが、図にすることで【どこがわからないのか】【何を使えばいいか】がはっきり見えるようになります。
応用問題は【情報整理】の戦いです。
親が【考えを外に出す習慣づくり】をサポートしてあげることで、子どもの思考力は驚くほど早く伸びていきます。
これは家庭だからこそできる、最強の応用力トレーニングです。
ステップ②【解き直し】を習慣化し思考を改善する
応用力が伸びる子は、例外なく【解き直しがうまい】です。
ところが、多くの子は間違えたときに【答えを見て終わり】にしてしまい、思考が改善されないため、同じ間違いを繰り返します。
応用力が身につかない最大の理由はここにあります。
家庭でできる最も効果的な練習は、解き直しに【理由】をセットにすること
です。
具体的には、
・なぜ間違えたのか
・どの部分の思考がズレていたのか
・次は何に気をつければいいのか
これらを言語化させます。
重要なのは、【知識がなかった】ではなく、【思考のどこに問題があったか】を特定することです。
例えば、
・読み取り不足
・早とちり
・情報整理の欠落
・公式を選ぶプロセスの誤認
など、思考のズレが明らかになるほど、次は確実に改善できます。
また、解き直しは 1度で終わらせない のがポイントです。
【次の日】【1週間後】など、時間を空けて再チャレンジさせることで、知識が使える形として定着します。
上位層は、間違えた問題が【宝物】だと理解しています。
家庭でその価値を共有できれば、応用力の伸び方も変わっていきます。
ステップ③段階的に【少し難しい問題】で成功体験を積む
応用力を伸ばすうえで必ず必要なのが、【少し難しい問題を解けた】という成功体験です。
いきなり高度な応用問題を解かせると挫折し、逆に基礎ばかりだと力が伸びません。
最適なのは、基礎より少しだけレベルを上げた問題に継続的に取り組むことです。
これは、筋トレで言えば適正負荷になります。
軽すぎても意味がなく、重すぎても続かない。
応用力も同じで、子どもが【自分の力で解けた!】と感じられる難度の問題が最も成長を促します。
段階式の問題選びで大切なのは、①基礎の変形問題、②単元融合のライト応用、③本格的な応用問題、といった順番を踏むことです。
とくにおすすめなのは、
・塾のような応用問題の一部を取り組む
・学校より少し難しい問題を混ぜる
・時間を区切り、思考の集中タイミングを作る
といった家庭での工夫です。
また、解けたときには【なぜ解けたのか】を振り返ることで、成功体験が再現できる方法として記憶に残ります。
これは本番のテストで確実に活きるスキルです。
応用力は、いきなり高い壁を登るのではなく、階段を一段ずつ上がることで身につきます。
家庭が適切な段差をつくってあげるだけで、子どもは確かな実力を積み上げていきます。
応用力は【才能】ではなく【思考の育て方】で決まる
【基礎はできているのに応用が解けない】という壁は、多くの子どもが必ず通るものです。
しかしその原因は、決して能力不足ではありません。
今回見てきたように、応用の壁は 知識の問題ではなく思考の構造の問題 です。
最初に応用問題が解けない理由として、①知識が点のまま、②読み取り力不足、③思考プロセスの欠如、という3つの原因を解説しました。
これは、覚える勉強から考える勉強に切り替わるタイミングで、誰もが直面する課題です。
続いて、上位層が持つ応用問題の思考回路として、①情報の見える化、②知識の接続、③仮説・検証の試行錯誤、という3つのスキルを紹介しました。
これは特別な能力ではなく、身につければ誰でも応用問題がクリアに見えるようになる再現可能な技術です。
最後に、その思考力を家庭で育てるための実践ステップとして、①考え方の見える化、②理由を伴う解き直し、③少し難しい問題での成功体験、という3つを示しました。
これらは家庭でもすぐに始められ、継続すれば確実に応用力を育てることができます。
応用問題は、才能やセンスではなく 【思考の習慣】 で決まります。
家庭で考える過程を大切にする学び方を続けるだけで、子どもは着実に応用の壁を乗り越え、上位層へ一歩ずつ近づいていきます。
基礎はできている。
それは、応用力を飛躍的に伸ばす準備がすでに整っているということを意味しています。
これからの伸びしろは無限大です。
我が子の応用力を育てる一歩を、今日からぜひ始めてみてください。