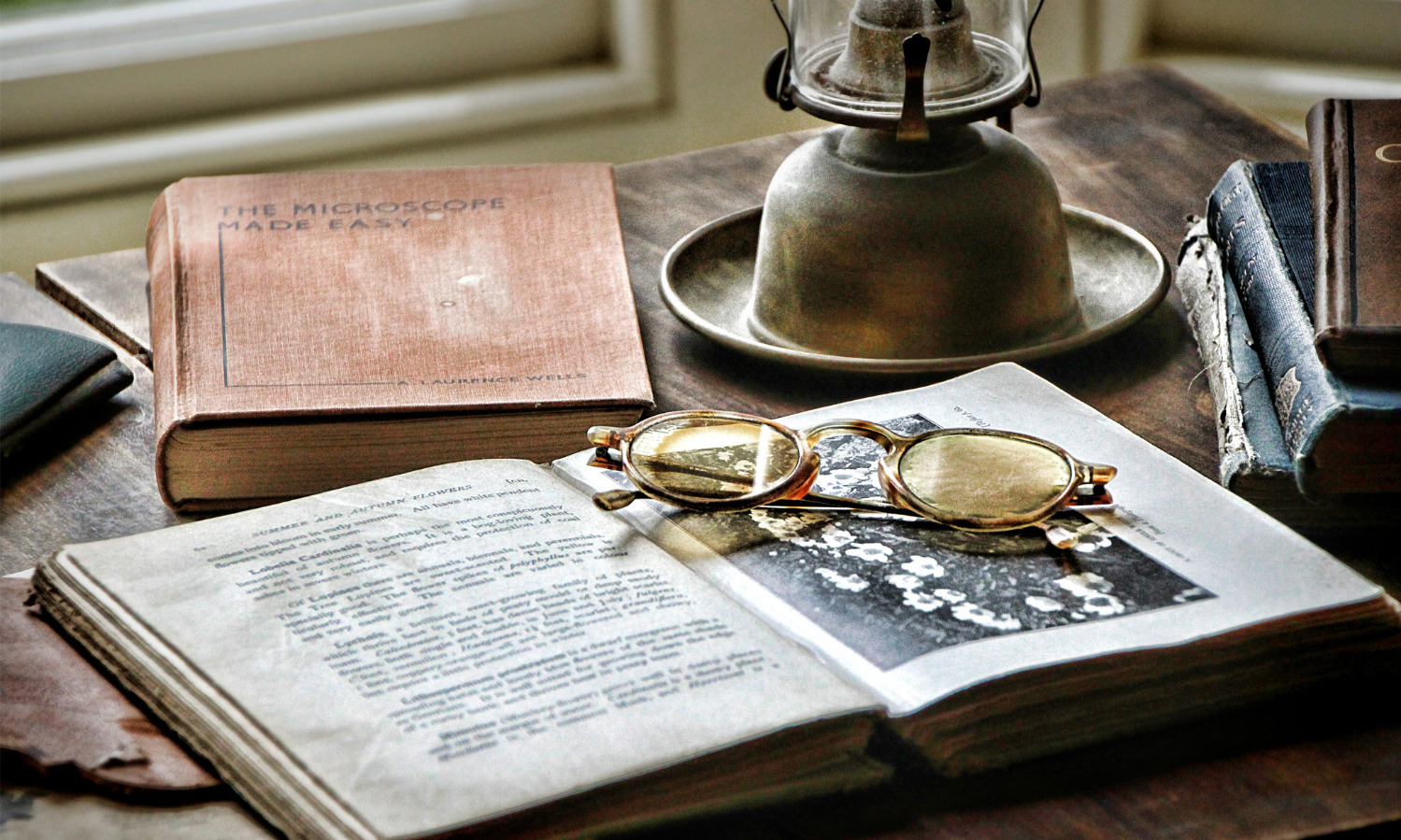今回は【小学生時代に苦手になると挽回しにくい教科はどれか】と題し、お話をしていきます。+
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校では1年生と2年生では国語、算数そして生活科を勉強し、3年生になると生活科に代わり理科と社会の2教科が加わります。
そして、5年生になると英語を教科として学ぶようになり、中学生と同じように5教科を勉強するようになります。
小学校では高学年になると算数や理科、英語を教える専任の先生がいる学校もありますが、一応担任の先生が全教科を担当するという仕組みが出来上がっています。
一方、中学生になると各教科に【この教科を教える先生】がいて、授業内容のレベルも上がります。
小学生から中学生に進学すると、学力格差が一段と進んでいきますが、これも学びの質の専門性が濃くなり、それについていける子と理解ができずに苦戦する子が鮮明になるからだといえます。
そして、勉強は螺旋階段のように学んだことを一つ一つ積み重ねていくため、どこかの知識が抜けていると、その階段が脆いものになってしまいます。
つまり、小学生時代に苦手教科や単元を放置すると、中学進学後に深刻な学習の遅れを招く可能性があるのです。
中学校の授業は小学校の内容を基に進むため、基礎が理解できていないと授業についていけず、さらに苦手意識が強まります。
周囲にスラスラできている同級生がいると、思春期特有の心の不安定さも相まって【自分はできない】と悪い方に考えてしまう、または【どうでもいいや】と開き直ってしまうこともあります。
このような学習の躓きは、成績低下だけでなく、自己肯定感の低下や学校生活全体への不安にもつながります。
最初は小さな躓きであっても、一度遅れが生じると挽回が難しくなり、学習へのモチベーションも失われがちです。
私も塾で、高校受験が迫ってきている子ども達のなかで、小学生時代の理解不足がドッサリある子達はやるべきことがあまりにも多すぎて、現実逃避をして、結局ほとんど改善することができないまま受験期に突入したというケースもありました。
小学生のうちに苦手を克服し、基礎を固めておくことが、中学以降の学習の安定と自信、そして高校受験にむけた確かな力を身につけることにつながります。
そこで今回は、小学生時代に苦手になると挽回しにくい教科をご紹介していきます。
好き嫌いがハッキリする算数
まず、小学生時代に苦手になると挽回しにくい教科の代名詞が【算数】です。
小学校6年間で早い段階から苦手な子も出てくるだけでなく、子ども同士の学力差が顕著になるきっかけにもなる教科です。
一般的に、算数で【よく分からない】と感じる子が増えるのは小学4年生頃ですが、子どもによっては小学1年生の繰り上がりの足し算や繰り下がりの引き算でスラスラ解けない子もいます。
九九の暗記も、定着するまでの期間というのも個人差があります。
親自身も【算数は差が出やすい】というのを理解しているので、小学校に入る前から対策をして学校の勉強で躓くことのないように準備をする家庭もあります。
その一方で、特段サポートもせずに学校の算数を乗り越えていこうとする家庭もあります。
子どもの生まれ持った学力スキルと親の教育方針も相まって、算数の理解力の差が生まれてしまうのは否めません。
算数は基本的な計算力や概念を理解することから始まりますが、学年が上がると学んだことを応用し、さらに高度な問題に取り組んでいきます。
例えば、四則計算で躓いていると分数での仮分数を帯分数にする単元でも苦戦することになります。
一つひとつの概念を理解し、次のステップに進むためには、【すでに学んだ知識】をしっかりと身につけていることが求められます。
算数は積み重ねの学問であるため、小学校低学年で学んだことの理解が不十分だと、小学校中学年、そして高学年で深刻化していく傾向があります。
算数を得意教科にするためには、何度も繰り返し練習し、基本知識を定着させることが重要です。
しかし、理解できていない部分があると、反復練習をしてもなかなか身につきません。
この時に、算数に対する苦手意識を抱えてしまうと、【どうせわからない】と勉強に対して消極的になりがちです。
消極的な姿勢が続くと、テストの点数も停滞、下降していくので自信を失い、さらに挽回が難しくなります。
こういう状況から脱するためには、まず【できることから始める】ことがポイントです。
全ての問題を一度に解こうとするのではなく、基礎的な部分から段階的に取り組むことで、自信をつけることができます。
今の学年の学びに固執するのではなく、足し算や引き算の基本をしっかりと理解し、できる問題を繰り返し解くことで、少しずつ自信がついていきます。
図形が苦手な子も多くいますが、実際に図を描いたり、折り紙や積み木を使って形を作るなど、手を動かして学ぶ方法が効果的です。
形を視覚や触覚で理解することで空間認識力が高まり、イメージがつかみやすくなります。
簡単な問題から取り組み、自信をつけながら段階的に難易度を上げると挽回しやすくなります。
さらに、積極的に質問をすることも重要です。
分からないことがあれば、早めに先生や親に聞いて、解決することが挽回のカギとなります。
大人からサポートを受けることで、理解が深まり、苦手意識を克服しやすくなります。
苦手と自覚する時には問題山積の国語
さて、国語は算数のように【正解不正解】がはっきりしていないことが多く、苦手意識を自覚しにくい科目です。
しかし、読解問題で何を聞かれているのか分からなかったり、文章の意味を正確に読み取れなかったりする状況が続くと、【なぜできないのか】が自分でも分からないまま、苦手意識だけが膨らんでいきます。
そしてある時点で、【どんな文章を読んでもよくわからない】と感じるようになると、その時にはすでに基礎力が抜け落ち、挽回が困難になってしまいます。
国語が難しく感じる主な理由の一つは【語彙力の不足】です。
語彙が少ないと、文章の内容や言葉の意味を正しく理解できず、文章全体の構造や作者の意図も読み取れません。
また、文章の内容に関する背景知識がないと、読み解くのがさらに難しくなります。
小学校の教科書には物語文や論説文は学年に合ったレベルの文章が掲載されています。
しかし、読解力や語彙力が学年に相応しい力が身についていなければ理解できなくなっていきます。
とくに古文なども登場してくる小学校5年以降の国語は【こんなに難しかった?】と感じるようになる子もいます。
しかも、国語の学びに必要な読解力、語彙力などの力は一夜で身につくものではなく、日常的な読書や会話を通じてゆっくりと積み上げられるものです。
ですから、【うわ、国語が苦手かも】と子どもが自覚した時点でかなりやるべきことが山積みになっていると思っていいでしょう。
そもそも、国語の読解力が弱いと、全教科の文章問題や指示の理解が困難になります。
国語の記述問題が苦手な場合、他の教科の記述問題も苦戦することを意味します。
社会や理科の記述式の問題では資料を踏まえて自分の考えを適切な言葉で表現する必要があります。
自分の感じたことや考えたことを言語化する力が弱いと、作文や意見文などでも思うように書けず、ますます国語への苦手意識が強まります。
挽回するためには、まずは読む量を増やすことが欠かせません。
物語、説明文、詩など、様々なジャンルの本を読むことで語彙力が自然と高まり、表現の幅も広がります。手始めに短くてわかりやすい本から始め、子どもが興味を持てる内容を選ぶことで、読書習慣を無理なく身につけられます。
次に、音読を取り入れることも有効です。
声に出して読むことで、文章のリズムや構成、語彙の使い方に敏感になり、理解力が向上します。
また、親子で一緒に文章を読んで感想を言い合うなど、日常の中で言葉のやりとりを増やすことも、言語感覚の向上につながります。
読解力を高めるには、【なぜその答えになるのか】を考える習慣をつけることが重要です。
問題を解くだけでなく、【どうしてこの選択肢が正しいのか】【なぜ他の選択肢ではないのか】を話し合ったり書いたりすることで、理解が深まります。
国語は挽回するのに時間がかかる教科であり、その性質上、苦手を自覚した時には多くの力不足が山積みになっているので、苦手克服が大変になります。
だからこそ、日々の積み重ねが何より大切です。
焦らず、子どものペースで【読む・書く・話す・聞く】の基本を少しずつ磨いていくことが、国語力の挽回への確かな道となります。
中学で難易度がアップする英語
ところで、小学校で英語が教科として扱われるようになったのが2020年度でした。
この年は、学習指導要領改訂の話題が全て吹っ飛んでしまうような波乱の年となりましたが、ちょうど小学6年生だった我が家の子ども①は小学英語の1期生になります。
そして、2021年度に中学でも学習指導要領が改訂となりましたが、小学英語と中学英語は別物です。
そして、小学生から英語を勉強している今の子どもたちは、ザクっと言えば親世代が中学1年生の夏休み前後までに習っていた内容を前倒しに学んでいるということを意味します。
つまり、小学校5年生と6年生で習っているという前提なので、かつての中学生のように【アルファベット練習】【簡単な英単語練習】からスタートすることはありません。
中学に入学したら、最初からしっかりと英文法の勉強をすると思ってください。
私も子どもたちを通じて見聞きしていますが、小学校の英語は、主に【聞く】【話す】を中心とした活動的な学習が多く、ゲームや歌を通じて英語に親しむことが目的です。
この段階では文法の細かい説明や読み書きの力はあまり重視されず、英語に慣れるために【楽しく触れる】ことが中心です。
しかし中学に進学すると、親世代の頃と同じように【書く】【読む】【聞く】が重視され、文法や単語の暗記、英文の構造理解、英作文といった抽象的な学習が本格化します。
しかも、小学校で学ぶ英単語数は600語から700語、中学校3年間では1600語から1800語と親世代の頃よりも格段に多く、それに伴い覚えないといけない語彙も増えます。
【基本は小学校の頃に学んだ】という前提で中学英語はスタートするので、和気あいあいとした雰囲気の小学英語とのギャップに戸惑い、急に難しくなったと感じてしまう子が多く、苦手意識につながりやすくなります。
そして、小学生の時点で英語に対して苦手意識を持ってしまうと、さらに中学英語についていけず、中学1年生の最初から【分からない】【英単語が覚えきれない】になります。
こうした状況にならないためにも、小学生の頃から英単語の暗記、英文の音読などを家庭学習で取り入れるのが無難です。毎日5〜10分の音読や英文を読むだけでも、英語の語感や語順に自然と慣れていくことができます。
文法の理解には【使って覚える】ことが有効です。
例えば、混乱する子も多い【be動詞】と【一般動詞】といった基本文法は、例文を何度も書いたり、似た文を自分で作ってみたりして、繰り返し使うことで理解が深まります。
また、動画やアプリなどの現代的な教材を使って、感覚的に英語に親しむのも効果的です。
そして、苦手意識を克服するためには成功体験を積み重ねることが欠かせません。
自分が知っている単語で短い文章が作れた、聞いた英語が少しわかった、という小さな達成感を意識して学習を続けることで、【英語は難しい】から【英語は自分でも理解できる】に気持ちが変化していきます。