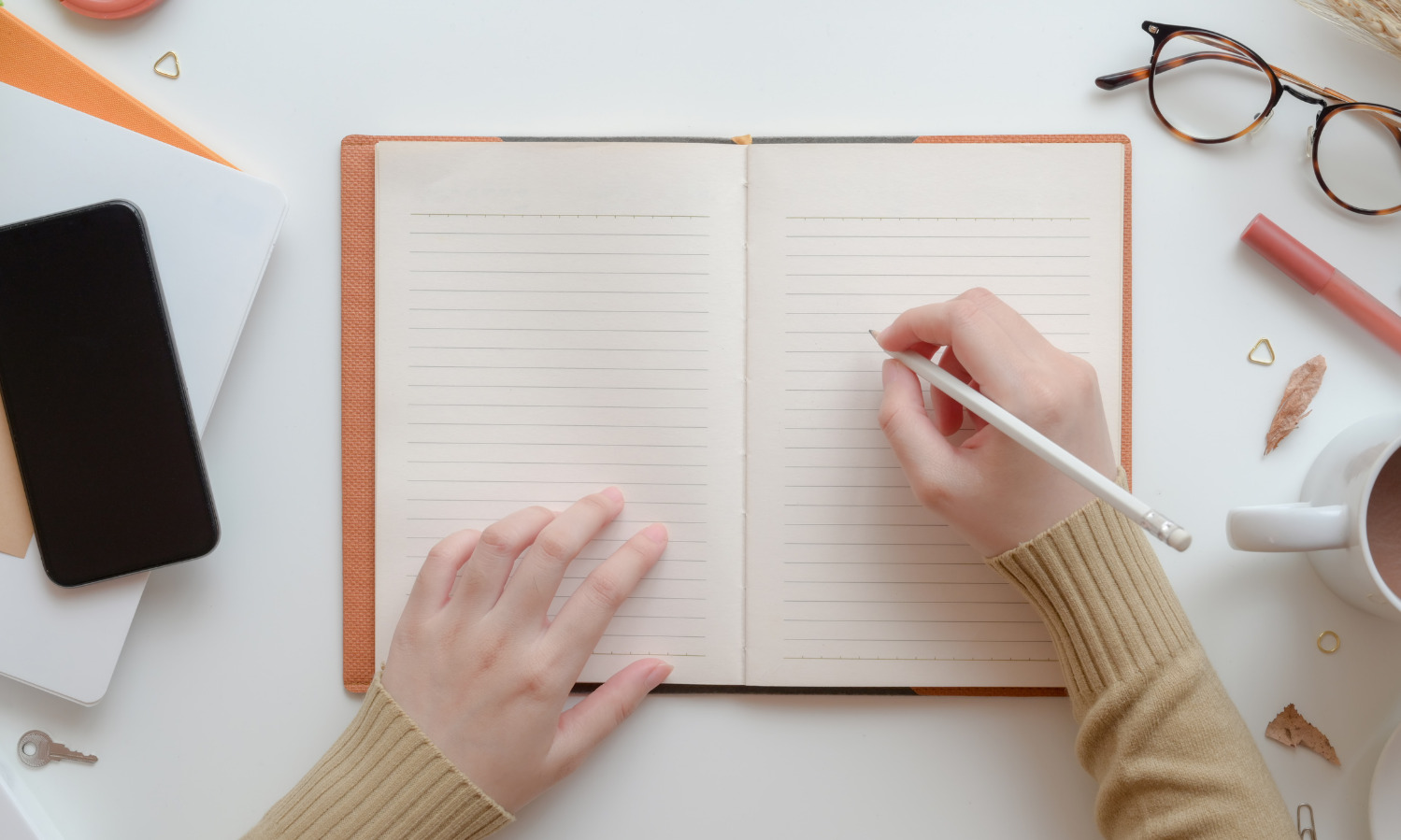今回は【学力グループ上位をキープ 学力の分岐点を乗り越えるには】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子育てをしていると、子どもの勉強面では【そろそろ学力差が出始めるから気をつけないと】と感じる学年に直面したり、学力グループが構成されているなかで上位グループにいられるように家庭学習でもサポートをしたり、場合によっては通信教材などを活用するようになります。
そもそも、学力上位をキープできるかどうかの分岐点は、家庭環境や子ども個人の資質にもよりますが、一般的には小学校3から4年生、いわゆる中学年と呼ばれる年が一つの大きな節目とされています。
小学校低学年では、基本的な読み書きや計算といった学習の土台が築かれます。
これは言わば、学力の基礎工事期間のようなものです。
この時期は、親の方も【算数の繰り上がりと繰り下がりがスラスラ解けるようにしないと】とか【意外とカタカナの練習期間が短いから家庭でやらせないと】と考えて積極的にサポートをします。
まだ授業内容も比較的簡単なことや反抗期に突入する前であることともあり親が家庭学習で誘導しやすい立場でいられます。
そして、子ども同士の学力差はそれほど顕著ではないので、【勉強を頑張らせないと】という焦りを感じる親はそう多くはありません。
とくに地方では【小学生時代はのびのびと過ごさせる】と考えている家庭も多いですし、教育熱の高い地域に住んでいないけれど、しっかり勉強させる教育方針だと住んでいるエリアで少し浮いてしまうこともあります。
こうした教育方針のズレも学力グループを形作る中で少なからず影響を与えていきますが、子どもの学力差、学力グループの固定化というのは親が思うよりも早い段階で進んでいきます。
そう言っても、なかなか信じてくれない人もいますが、小学校3〜4年生は9歳、10歳という年齢で、子どもは少し背伸びをしたがるけれど、まだまだ子どもらしく過ごしている時期です。
この年頃で学力差が出る原因としてあげられるのは、徐々に学習内容が抽象化し、理解力、思考力といった【学習スキルの差】が如実に表れ始めるからです。
これまでスムーズに学校の勉強に対応してきた子の中でも【すぐに分からない単元が増えてきた】【表やグラフを読み取るのが面倒】と感じてきて、勉強に対して微妙な感情を抱くようになってきたりもします。
学力グループが形成されていくなかで、どういう点に気をつければ上位グループをキープすることができるかを考えていきます。
学習内容の難化に立ち向かう
まず、子どもの学力グループが形成される過程で、学力上位をキープするためには、小学校中学年以降に訪れる学習内容の難化にどう立ち向かうかが分かれ道になります。
学力の分岐点を乗り越えるためには親子が協力して【これからの勉強をどうしていくか】と考え、実際に家庭学習の進め方を見直すことも必要になってきます。
まず絶対条件といえるのが学習習慣がしっかり身についているかどうかです。
学習内容が難しくなると、宿題だけでは理解が追いつかない場合も出てきます。
このときに【毎日一定時間机に向かう習慣】があれば、学びのリズムを崩さず、積み重ねによって理解を深めることができます。
学習習慣は低学年の間に仕上がっていることが理想です。
次に難しい学習内容に立ち向かうために必要となってくるのが、【わかる楽しさ】や【問題が解けた喜び】を体験させることです。
学習内容が難しくなっても、成功体験を少しずつ積んでいくことで【自分もやればできた】という自信がつきます。
これは、学習意欲や粘り強く問題に取り組む、やり直しをする際の原動力になります。
親はテストの点数といった成果だけでなく、子どもの努力の過程を褒めることで、少しずつ難しくなる勉強に取り組めるようサポートをするようにしましょう。
小学校3年生からは、単なる暗記では乗り越えられない単元が増えてきます。
たとえば、国語では比喩や要約、算数では分数や小数も少しずつ学びますし、桁数の増えた計算、文章題の応用といったパッと見てすぐに答えが出てこない勉強では頭の中で試行錯誤する抽象的な概念の理解が求められます。
ここで躓いた子は、後の単元に連鎖的に苦手意識を持ちやすく、結果的に学力が下がっていく傾向があります。
また、勉強が難しくなるからこそ基礎力の強化にも力を入れていく必要があります。
とくに小学校の勉強での二つの柱である算数や国語の読み書きなどは、理解が追いつかなくなると後の学年でも影響が残ります。
テストの点数の低下などに気づいたら早めに復習し、分からないままにしないことが重要です。
日頃の家庭学習の中でも【この単元を振り返る】と復習の時間を設けてみてください。
家庭学習のアップデートを考える
さて、当たり前のことになりますが学力上位を保てるかどうかのカギの一つは【家庭での学習習慣がどのようなものなのか】になります。
小学校中学年になると、宿題だけでは不十分になるケースも増えます。
低学年までは繰り返しや暗記中心の学習でも成果が出やすいですが、中学年以降は読解力や論理的思考が問われる場面が増えます。
それに伴い、家庭学習では単なる漢字練習や計算ドリルだけでなく【なぜそうなるのか】【どう考えるのか】といった過程が大切になる問題、学びも取り入れることが必要です。
つまりは、受け身の学習から【自分で考える学習】への転換です。
いつまでも基本問題ばかりやっていると、少し難しい問題と出くわした時に早々に諦めたり、答えを教えてもらいたがったりします。
私もそういうタイプの子に塾で出会いましたが、粘り強く勉強と向き合えない子は成績が失速、低迷していきました。
学力の分岐点を乗り越え、上位をキープするためにはこれまでの家庭学習の内容をアップデートし、臨機応変に対応することが必要となります。
難しい単元の理解にはどうしても時間はかかりますし、しっかり定着するには勉強時間を少し増やさないといけません。
勉強時間を増やすという選択肢は避けられないと思ってください。
子どもの負担にならない程度で学習時間を増やしていきましょう。
また、子どもが家庭学習に真剣に取り組むかどうかは家庭での親の声かけや学習環境に強く影響されます。
たとえば、親が毎日少しでも子どもの学習を見守っていたり、読書や調べ学習を促す家庭では、子どもが【学ぶこと】にポジティブな印象を持ちやすくなります。
そして親子のコミュニケーションも分岐点を乗り越えるポイントになります。
子どもが学校で感じた難しさや不安を家庭で話せる環境があると、精神的にも安定しやすく、学習への抵抗感が減ります。
逆に、親が過度に結果を求めすぎると、子どもはプレッシャーを感じ、学ぶことそのものにネガティブな印象を持ってしまう恐れがあるので気をつけてください。
学力上位層の子どもたちは、ただ勉強時間が長いわけではなく、集中して取り組む習慣や、間違いを振り返る姿勢が身についています。
家庭では、学習後に親子で解き方を話し合ったり、間違えた問題を一緒に再確認することで【全て子ども任せにする】は避けてください。
勉強は難しくなるけれど、9歳や10歳というまだまだ子どもの年齢ですから【あとはよろしく】では子どもは学力の分岐点を一人で乗り越えることは難しくなります。
勉強に対する自信と謙虚さと生活リズム
ところで、小学校3年生、4年生の頃は心の成長に伴い【自分は勉強ができる子】【苦手な子】という自己評価が形づくられる時期でもあります。
自分を他人と比較して【自分はできない】と感じやすくなります。
ここで成功体験を重ねられた子は、学ぶことへの自信を持ちやすく、その後もポジティブに学習に取り組みやすくなります。
逆に、繰り返し【できない】【親に叱られる】という経験をしていくと、【自分は勉強が苦手】と刷り込まれ、意欲を失いやすくなります。
この【勉強に対する自己肯定感】が高いか低いかは後の学力差に大きく影響します。
ただし、【自分は勉強ができるからすごい】と他の子にマウントを取る子は伸びなくなります。
私のこれまでの人生で出会ってきた【勉強面でマウントをする子】【優越感に浸る子】というのは意外と5番手校くらいの学校に受かるレベルの学力で、自分よりも成績が良くない子に対してするという子が多く、進学校を目指す子には少ないという傾向があります。
ですから、
また、子どもの学力は感情や生活習慣にも強く関連しています。
短気な子、結果が出るまで努力が続けられない子は忍耐力がなく、理想と現実のギャップに苦しむようになります。
小学4年生以降になると子どもたちの間でも夜更かしや食生活の乱れ、親子関係のストレスなどから学習意欲が低下する子、成績が悪くなる子も増えてきます。
子ども①②③の同級生も小学校4年生から5年生にかけて【動画視聴で夜遅くまで起きている】【スマートフォンでゲームをしていたら12時近くになっていた】という子がクラス内でも増えてきました。
もちろん、生活リズムが崩れている子は成績がガクンと落ちてしまい、その様子を見ている子どもたちは【夜更かしは怖いな】というのを感じています。
塾でも夜遅くまでゲーム三昧で、中学校では居眠りばかりという子が一時いましたが、集中力が甚だしく欠けていて授業中はずっとソワソワしていました。
勉強をしていても常に寝不足、心が安定していないと集中力や意欲の低下につながりやすく、結果として学力にも影響を及ぼします。
小学校中学年は、精神的にも少しずつ自立心が芽生えてくる時期です。
ここで感情を安定させ、生活リズムを整えることを親が意識することで安定した学習習慣にもつながっていきます。
そして、忘れてはいけないのが学力グループ上位層をキープするには、勉強をやればそれで済むというものではないということです。
学力グループ上位にいるということはしっかり勉強をしているということを意味しますが、勉強する原動力になるのは子ども自身のやる気だけでなく、子どもの興味関心の幅を広げ、切磋琢磨できるライバルとの出会いなどもとても重要になってきます。
学力を育てる過程で、子どもの人格や心の豊かさ、忍耐力も一緒に育てていくような関わりが、最終的には最も強い学力の土台になります。