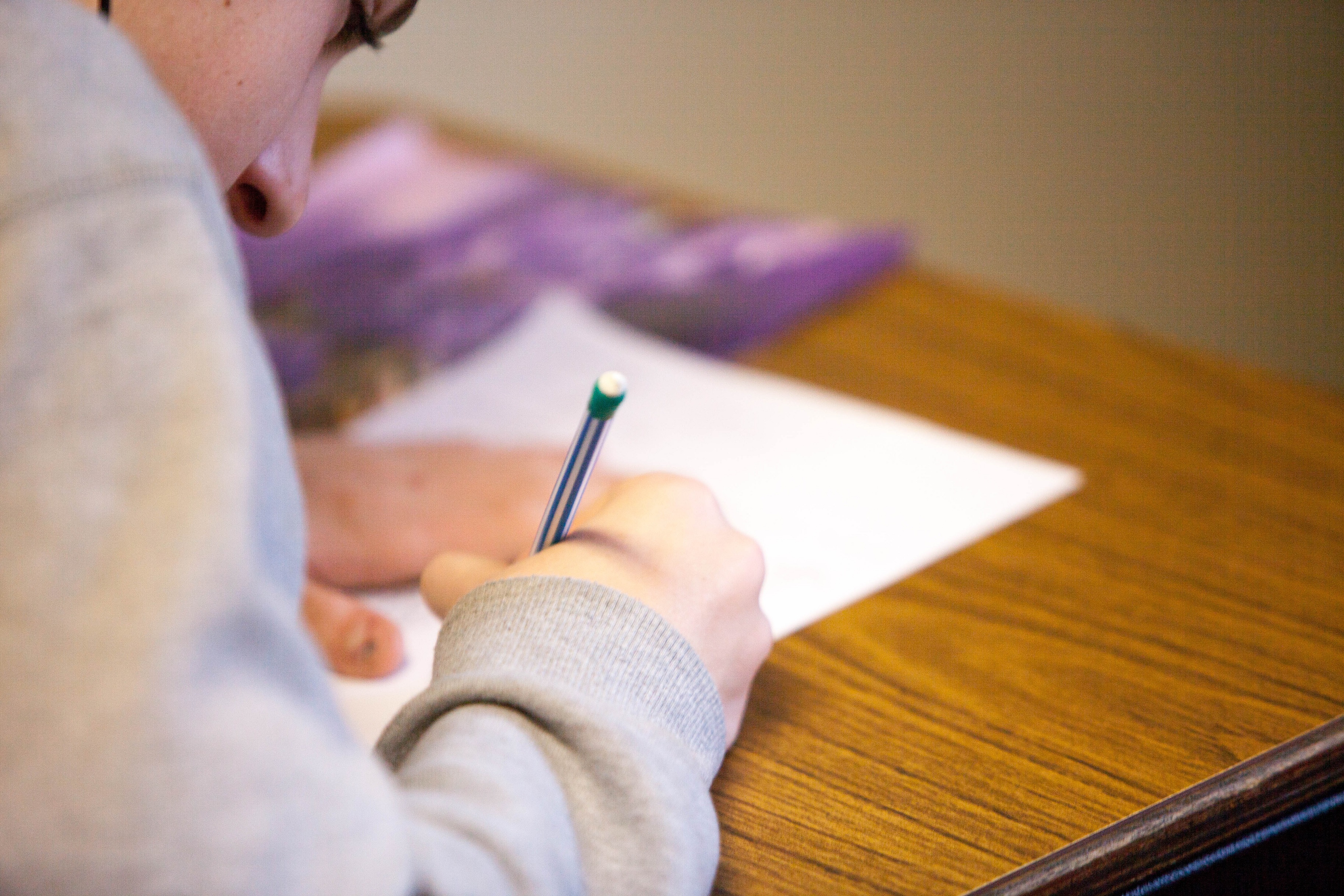今回は【トップ高校合格に近づくために小学生時代から取り組みたいこと】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
住んでいる地域のトップ高校に入るためには、小学生の頃から受験に向けた確かな学力を支える【思考力】【読解力】【学習習慣】の土台を育てることが非常に重要です。
ある日突然目が覚めて、受験まで残り数ヶ月で猛烈に勉強をしたらトップ高校に合格した、ということはありません。
そして、【普段は全然勉強していないけれど勉強をやればサクッと合格する子】もいないと思ってください。
私の小中学生時代、塾で出会った子ども達、我が家の子ども①の周囲を見渡しても【地道に勉強を続けていないとトップ高校に入ることはできない】と断言できますし、楽な方法を探そうとしても無駄です。
小学校4年生、5年生の頃になるとクラス内の学力上位層の中でも【トップ高校が固い子】【2番手校や3番手校に進学しそうな子】に分類されていきます。
一見すると同じくらいの学力があるように見えても、トップ高校に進学する子は小学生の時点で他の子よりも圧倒的な基礎学力と応用力を兼ね備えていることが多いですし、私の同級生の中でもトップ高校で上位層になった子達は【小学校6年間ずっと完全なる優等生】でした。
塾で出会った【トップ高校に入って最難関大学や難関大学に進学した子】は小学生の頃から【この子は並みの賢い子ではないな】と感じていました。
こんな話をしてしまうと、【元が違うから】という結論に達してしまいそうですが、そんなことはありません。
やはり忘れてはいけないのは学力の差は結局【毎日コツコツ勉強してきた差】になります。
自分で決めた学習を毎日、継続してやり抜く経験を重ねていくことがトップ高校受験を突破する重要なカギを握ります。
ただ、この【継続して勉強を頑張る】という極めてシンプルなことができない子が圧倒的に多いです。
いわゆる三日坊主状態です。
そして基本問題以上のことをやろうという気持ちの差もトップ高校にたどり着けるかどうかを左右します。
勉強をやったりやらなかったりということをしないことや、難易度の高い問題も解く意欲がある、という前提で【トップ高校に合格できそう】になると思ってください
今回はそれ以外にトップ高校合格を目指すのであれば、小学校時代から取り組みたいことをご紹介していきます。
挑戦する心と失敗を恐れない気持ちを育てる
まず、挑戦する心と失敗を恐れない気持ちを育てることが大切です。
トップ校を狙うには【ミスしても分析しやり直しができる子】になる必要があります。
私が塾で教えている時に、学力上位層とミドル層より下の子との決定的な違いと感じたのが、【間違いをやり直すかどうか】でした。
トップ高校に合格した子は例外なく【間違えた問題をすぐに解き直す】【先生に質問する】ということができていました。
一方、ミドル層より下の子は【間違い直しを避けたがる】という特徴がありました。
失敗したらそのままにしたり、そもそも応用問題に挑戦する気力がなく、いつも確実に解けそうな問題を解きたがっていました。
殻を打ち破り、学力グループを上げていくには【挑戦できるか】【失敗してもくじけないか】という強い気持ち、ある意味、【ど根性】という昭和的な気持ちが必要です。
こういう気持ちは親が結果や完璧さを求めすぎず、子どもの些細な挑戦も褒める、励ますということを繰り返すことで育てることができます。
もの凄く時間がかかるかもしれませんが、根気強く声がけしていくと高学年になる頃には挑戦することを恐れない子に成長します。
そして、間違いは自分の課題を教えてくれる貴重な機会です。
悪いことばかりではないと家庭で折に触れて話すようにしてください。
失敗を恐れて安全な方に逃げていく子もいます。
本人の性格とも言えますが、小学生のうちに【間違いは学力向上のチャンス】【失敗を恐れない】という価値観を持たせることはとても意味のあることです。
そして、テストで間違えた問題の答えを【赤ペンで書く】だけで終わらせないで、【なぜ間違えたのか】と自分の考え方と正しい考え方の違いを見つめ直すようにしてください。
親もテストの点数ばかりを追い求めるのではなく、【子どもが本当に理解しているのか】に注目しましょう。
何となく、分かった風で解けてしまうこともあります。
子どもが【よく分からない】と自覚している分には苦手克服を進んでやるようになりますが、【なんとなく解けた】だと積極的に復習する気持ちにはなりませんし、結果として学力を高めることができない原因にもなります。
好奇心旺盛な子になるよう意識する
さて、トップ高校合格を手繰り寄せるためにも、子どもの好奇心旺盛な部分を摘み取らないように気をつけてください。
ある程度、基礎学力が身についていても【さらに伸びるかどうか】は好奇心旺盛さにかかってくるといっても過言ではありません。
どんな子も小さい頃は【なぜ?】【どうして?】と思い、疑問を口にしています。
ただ、親がそれに反応するのが面倒で【うるさいから】とか【そんなこと考えなくていいの】と一蹴すると、色々と考えたことを口にしなくなります。
【こんなことを言ったら親に叱られる】という気持ちが優勢になると、子どもは好奇心旺盛さを失うことになります。
何かを知りたい、気になることがたくさんあるというのは勉強する原動力になります。
その原動力がスッポリなくなってしまえば、親に勉強しなさいと言われても【何のために勉強するの?】となるのは当然です。
ですから、子どもの知りたがり屋なところを【面倒だな】と受けとめず、【学びにつながるチャンス】と思って親も全力で対応するようにしましょう。
子どもの好奇心を育てるには、日常の中に【考えるきっかけ】【疑問に思い調べる機会】をたくさん作ることが大切です。
親は無理に教え込まず、子どもの興味を引き出し、自分で気づく楽しさ、調べて理解することを体験させてください。
例えば、【どうして雲の上に乗れないの】とか【どうして野球選手やサッカー選手の年棒は高いの】という素朴な疑問に対しても、【そんなこと考える暇があったら勉強しなさい!】ではなく、【いい質問だね】と親も一緒に考える、図鑑で調べる、図書館に行って調べるなど親子の会話が弾むだけでなく【こうやって調べるのか】【そういう事実が隠されているのか】という思いがけない発見と出会い、新たな知識を得るきっかけにもなります。
一緒に調べる際は、一方的に親が説明するのではなく【これについてはどう思う?】【思っていたのと違かった?】と問い返すことで考える力が伸びます。
塾の講習会参加や中学受験組が解く教材を取り入れる
ところで、トップ高校を目指す時はライバルが【基礎学力あるの当たり前で応用力あります】という学力層になります。
ですから、塾の講習会参加や中学受験組が解く教材を取り入れることで、学力のさらなるレベルアップ底上げにつながります。
我が家の子ども①②も最初は中学受験を考えずに塾に通わせていました。
その塾に通っている子達のメンバーで実際に中学受験をしたのは我が家の子ども達と他数人程度でした。
地方ですから中学受験をしない子の方が圧倒的に多い中で塾に通わせるというのは【高校受験や大学受験を見据えている】という家庭の子が多く、実際に国立小学校の子がかなりいました。
受験しないけれど、小学校以上の勉強を塾に通うことで習うという教育方針の家庭が地方には意外といたりします。
通っている塾では、中学受験組が使用する教材と同じものを使い、単なる基礎学力を鍛えるのではなく、応用力や思考力、記述力、語彙力を重視した問題に取り組みました。
これに取り組むことで、教科書レベルでは得られない【考える力】を小学生の時点でかなり鍛えることができます。
ハイレベルな教材に触れることで、自学自習の時間の質が大きく変わります。
サクサク解けないので、ただ問題を解くだけでなく【なぜこうなるのか】【他の解き方はあるのか】など、深い学びにつながる【考える習慣】が定着します。
また、小学校のカラーテストとは次元の違う塾のテストを受けることで【応用問題がけっこうあるテスト】や【入試本番の緊張感】を体験できます。
子どもの性格にもよりますが、ライバルと切磋琢磨することで未来の目標を見据えた家庭学習をする気持ちが強まります。
レギュラーで通わなくても、季節講習会に参加させてみるなど小学校以外の子との勉強する機会を設けてみるのもおすすめです。