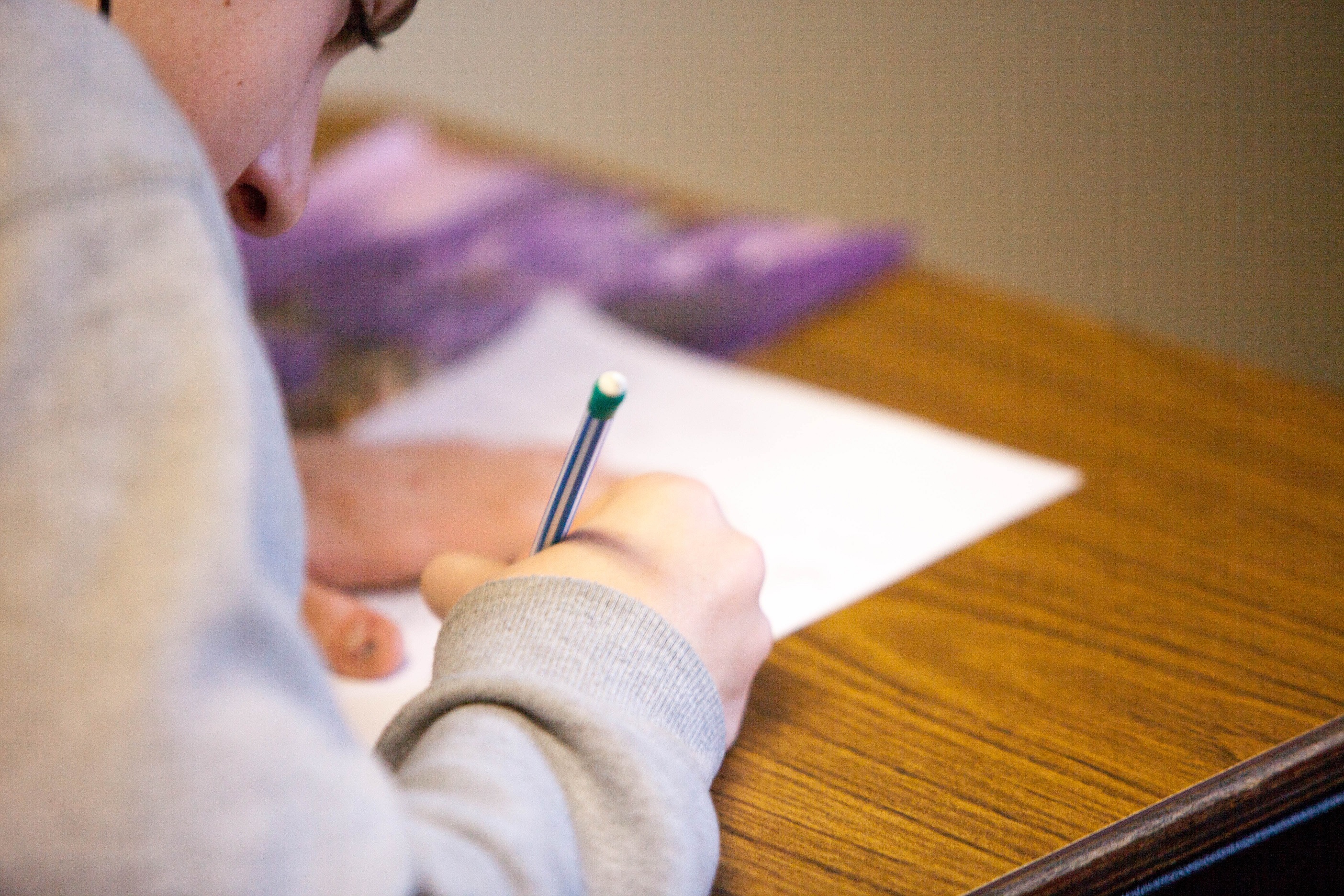今回は【公立中で埋もれない子にするために親が知っておきたい色々なこと】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
大都市圏などを除けば、全国的に【とりあえず中学は地元の公立で】と考えることは珍しくありません。
学区の中学に進むということは、同じ小学校6年間を過ごした同級生も多くいる中で多感な時期を過ごすという安心感もあります。
ただし、公立中に進学したからといって、すべての子が順調に成績を伸ばせるとは限りません。
公立中では【学力が伸びずに埋もれてしまう子】と【中学でもしっかり存在感を保ち、成績も維持する子】の差が大きくなりがちです。
とくに内申点は高校入試に直結する以上、中学生活での埋もれはそのまま進路の可能性を狭めるリスクと隣り合わせになります。
では、どんな子が埋もれやすく、どうすればそのリスクを回避できるのでしょうか?
そして、親として何に気をつけ、どんな支援が必要なのでしょうか?
そこで今回は、【公立中で埋もれてしまう子の特徴】【今からできる改善策】【家庭が注意すべきポイント】の3つの視点から、公立中でもしっかりと力を発揮できる子になるためのヒントを具体的にお伝えします。
これから中学を迎えるお子さんを持つ親の方にとって、進学前にぜひ知っておきたい内容です。
公立中で【埋もれてしまう子】の3つの特徴
まず、公立中学校は小学生の頃に比べて格段に学力・家庭環境・学習意識の幅が非常に広くなります。
私立中学や中学受験を経て選抜された集団とは異なり、地元の子どもたちがそのまま進学するため、多様な背景を持つ生徒たちが同じ教室で学ぶことになります。
そのような環境では、【勉強ができる子】【存在感がある子】が自然と目立ちやすくなる一方で、努力していても目立たず、評価されにくい子が埋もれてしまうことも少なくありません。
とくに公立中では、定期テストの点数だけでなく、授業中の態度や提出物、生活態度などを含めた【内申点】が進学に大きく影響するため、見えにくい部分が成績に直結します。
では、なぜ子どもが埋もれてしまうのでしょうか?
そこにはいくつかの共通した傾向があります。
ここでは、公立中で埋もれてしまいやすい子どもの特徴を3つに分けて解説します。
これを知ることで、親として日頃からどこに目を向けるべきかが見えてくるはずです。
特徴①自分から発信しないと、先生の印象に残らない
公立中学校では、成績を評価するうえで内申点が非常に重視されます。
この内申点はテストの点数だけでなく、【授業態度】【発言】【提出物】【生活態度】などの総合的な評価によって決まります。
そのため、黙って真面目に座っているだけでは評価が高くならないこともあるのです。
たとえば、授業中に質問をされたときに反応しない、あるいは自分から手を挙げることがない。
そうした受け身の姿勢は、先生の記憶にも残りにくく、評価にもつながりにくい傾向があります。
どれだけ真剣に話を聞いていても、それが見える形で表現されていなければ、【関心・意欲・態度】の項目でA評価を取るのは難しくなります。
とくに学年の生徒数が多い学校では、先生が一人ひとりの細かい様子を常に把握するのは困難です。
そのため、【発言する】【提出物を工夫する】【質問に積極的に答える】など、自己アピールにつながる行動が評価につながりやすくなります。
【真面目=評価が高い】とは限らないのが公立中の現実。
自分をしっかり発信できるかどうかが、学力以外の部分での差を生むことを知っておく必要があります。
特徴②平均点で安心してしまい学力が伸びない
公立中学校では学力層が広いため、定期テストの平均点が60点台、場合によっては50点台ということも珍しくありません。
そんな中で【平均点を取れているから大丈夫】と安心してしまうと、上位層との差はどんどん広がっていきます。
中学2年で数学の平均点が58点のテストがあったとします。
60点を取って【クラスの平均より上だ】と思っていても、実際には学年上位層の多くは90点以上を取っています。
この差は高校入試の際に致命的な差となって表れてきます。
また、子ども自身が【うまくいっている】と思い込んで努力をやめてしまうケースもあります。
競争意識が育ちにくい環境にいると、知らず知らずのうちに学習意欲が低下し、【できる子との差】はさらに広がってしまうのです。
親としては、テストの点数だけを見て安心するのではなく、【学年順位】や【偏差値】など、相対的な位置を意識させることが大切です。
常に上を目指す姿勢を育てるためにも、【目標は平均+20点】という基準で家庭学習を支えていくことがカギになります。
特徴③学力以外の要素で評価を落としている
公立中では、【テストでいい点を取ること=内申が良くなる】わけではありません。
実際には、授業態度、提出物の質と期限、協調性、生活態度などもすべて評価対象に含まれており、場合によっては学力よりもそちらが重視されることすらあります。
たとえば、テストで80点を取っていても、提出物が遅れていたり、授業中にぼんやりしていたりすれば、成績は思うように伸びません。
一方で、テストが60点でも、常にノートを丁寧に取り、毎回の宿題を期限内に出し、発言も積極的にできていれば、内申点は高く評価されるケースがあります。
このような総合評価の中では、【コツコツと日々を丁寧に過ごす力】が重視されます。
そしてそれは、普段の家庭生活の中でも育てられる力です。
提出期限を守る、清潔感のあるノートを作る、人の話を聞く姿勢を保つ。
こうした基本的な力こそが、公立中では評価につながります。
親が【テストさえ良ければいい】と考えてしまうと、見落とされがちなこの要素。
子どもの日常的な生活習慣や学習態度にも、しっかりと目を向ける必要があります。
公立中でも【埋もれない子】にする3つの改善策
さて、【うちの子は真面目だし、成績もそこそこだからきっと大丈夫】と思っていても、気づいたときには学年の中で埋もれ、志望校の選択肢が狭まってしまうというケースは決して珍しくありません。
公立中でしっかり評価を得て、将来の選択肢を広げるには、ただ成績を取るだけでは不十分です。
【積極的な姿勢】【目標設定】【生活面での自己管理】など、内申点に反映される多角的な要素を意識して取り組む必要があります。
とくに重要なのは、普段の授業や提出物で見える努力をすること。
そして、自分の学力の位置を相対的に把握し、周囲との比較から目標を立てることです。
さらに、生活態度や人間関係も評価の対象になる以上、家庭内での支援も欠かせません。
ここでは、公立中で埋もれず、存在感を持ち続けながら内申点を安定させるために、今からできる具体的な改善策を3つに分けて紹介します。
日常の小さな積み重ねこそが、大きな評価の差につながることを、ぜひ押さえておいてください。
改善策①発言・提出物・授業姿勢に【見える努力】を
成績に直結する【内申点】は、教師からの印象評価に大きく左右されます。
その中でもすぐに取り組めるのが、授業中の発言や課題の提出など、日々の中で【先生の目に入る努力】を積み重ねることです。
たとえば、授業中に1回でも自分から手を挙げる、提出物にひとことコメントを添える、ノートをきれいにまとめる。
これだけでも、教師の印象は確実に変わります。これらは成績の【関心・意欲・態度】欄に大きく影響します。
親としては、【ちゃんとやりなさい】と言うよりも、【今日の授業で発言できた?】【提出物、どんな工夫したの?】など、関心をもって声をかけることが子どもの意欲を引き出します。
努力を評価される努力に変えるには、自分からアピールする意識を育てることが重要です。
真面目に取り組んでいるのに内申が伸びない、という子の多くは【努力が見えにくい】のが原因です。
少しの工夫で、先生の目にしっかり届く努力に変えていくことが、埋もれない第一歩になります。
改善策②テストの目標は【平均+20点】
公立中学のテストは、平均点が思ったよりも低いことが多く、60点前後でも【まぁまぁ良かったね】と思ってしまうケースがあります。
しかし、進学校や上位高校を目指すなら、その感覚は非常に危険です。
入試で戦うのは地域全体の中学生。つまり、学校内で平均点を取っていても、外の世界では下位になる可能性もあるのです。
そこで重要なのが、常に【学校の平均+20点】を意識することです。
このラインをキープできれば、定期テストでも安定して学年上位に入りやすく、内申も自信を持って出願できます。
日々の家庭学習でも、ワークを1回で終わらせず、最低2回、ミスをチェックして反復するよう習慣づけましょう。
また、学校の定期テストだけでなく、模試や外部テストにも積極的にチャレンジして、自分の立ち位置を広い視野で把握することも大切です。
【クラスで上位】ではなく【地域で上位】を目指す視点が、埋もれないための確かな戦略になります。
改善策③学力以外の【生活力】も評価対象と知る
公立中では、テストの点数以上に【生活全体でどんな生徒か】が重視されます。
具体的には、提出物をきちんと出せるか、授業に集中しているか、友人と良好な関係を築いているか、清潔感のある身だしなみか、といった日常的な生活態度です。
提出物がきちんと期限内に出せない、字が乱雑で読みづらい、話を聞く姿勢に集中力がない。
こうしたちょっとしたことが積み重なり、内申にマイナス評価として反映されます。
一方、特別に目立たなくても、生活面で【安定感】がある生徒は教師からの信頼も高くなります。
家庭では、生活リズムの安定、時間の管理、身の回りを整える習慣づけが大切です。
【時間を守る】【人の話を聞く】【ルールを守る】といった基本的な力が、実は通知表の中身を左右しています。
学力は塾や家庭学習で伸ばせますが、生活力は家庭の関わり方が大きく影響します。
子どもが学校で見られている部分に親が意識を向けることが、公立中での評価アップに直結します。
親が気をつけたい3つの落とし穴
ところで、【子どもは学校で頑張っているし、問題ないはず】と思っていたのに、いざ通知表や模試の結果が出てみると、思っていた以上に評価が低かった、というケースでは、実は親の思い込みや過信が原因になっていることもあります。
中学生になると、子どもがどんな学校生活を送っているのか、親が把握しにくくなります。
本人も【普通だよ】【ちゃんとやってる】と言いがちですが、実際には内申点を落とすような見えにくい課題があることもあります。
とくに公立中学校では、先生一人が多くの生徒を担当するため、細かいサポートは期待できません。
だからこそ、家庭での声かけやフォローが重要になります。
ここでは、子どもが公立中で埋もれないようにするために、親が陥りがちな3つの落とし穴と、その対策について解説します。
落とし穴①【うちの子は真面目だから大丈夫】と過信する
親がよく言う言葉のひとつが【うちの子は真面目だから大丈夫】というものです。
しかし、真面目=内申が高い、とは限りません。
授業で発言しない、提出物が淡々としている、周囲との交流が少ない、という目立たない真面目さは、公立中では評価されづらい傾向があります。
学校の先生も多くの生徒を見ているため、【ちゃんとしているけど印象に残らない子】は、どうしても内申が伸び悩みます。
これは、テストの点が取れていても同様です。
実際に【テストは良かったのに、通知表が思ったより良くなかった】というケースは少なくありません。
大切なのは、真面目さを【見える形】にすることです。
発言をする、ノートを工夫する、提出物に一言添える。
そうした小さな積み重ねが、評価される真面目さにつながります。
親としては、【ちゃんとやってる?】ではなく、【どうやって工夫してる?】【先生にどんな話した?】といった具体的な声かけをすることが大切です。
落とし穴②学校任せ・塾任せで見落とす【家庭の役割】
中学生になると、親の多くが【もう子どもは自立しているから、勉強は本人と学校(あるいは塾)に任せよう】と考えがちです。
しかし、学校や塾に完全に任せきりにしてしまうと、実際の学習状況や困っていることに気づけず、知らないうちに成績や内申が低下していたということも起こりえます。
公立中学校の先生は非常に忙しく、一人ひとりの学習や生活状況を細かく見る余裕がないことも多くあります。
塾に通っていても、塾では補習やテスト対策が中心で、生活面のフォローまでは手が回りません。
つまり、【学習状況を日々把握できるのは、家庭だけ】なのです。
定期テストの点数だけでなく、提出物の状況、ノートの中身、学習時間、集中度など、家庭だからこそ見られる情報があります。
週に1度は勉強の様子を一緒に考えてみたり、親子で【次のテストに向けた作戦会議】をしたりすることが、継続的な学力維持・内申アップにつながります。
子どもが中学生になっても、親の見守りとさりげない介入は必要不可欠。
放任でも過干渉でもなく、【気にかけてもらっている】という適度な関与が、子どもに安心感とやる気を与えます。
落とし穴③学校内だけを基準にしてしまう
多くの親が陥りやすいのが、子どもの成績や順位を【学校の中だけ】で判断してしまうことです。
私も塾で仕事をしている時に、模試の結果よりも学校の順位で受験校を決断する親子と出会ったことがあります。
【学年で上位だから大丈夫】【通知表は良い方だし問題ない】と感じてしまうのは自然なことですが、それが地域の高校入試という広い競争の中では、必ずしも通用するとは限りません。
ある学校では定期テストの平均点が非常に低く、60点を超えれば学年の上位30%に入ることもあります。
けれど、偏差値60以上の進学校を目指す場合、それだけでは到底届きません。
学校内で良くても、地域・県全体で見れば【普通以下】ということも十分にあり得るのです。
だからこそ、【学校外】の模試や外部テストを受けて、自分の位置を正確に知ることが重要です。
また、志望校の偏差値や過去問の難易度を知ることで、目指すべき学力水準がより現実的に見えてきます。
親が相対的な視点を持ち、子どもと一緒に【今どこにいて、どこを目指すか】を確認しながら計画を立てることが、公立中で埋もれずに成長するカギとなります。
子どもが公立中で埋もれないために今できること
公立中学校は、多様な学力層・家庭環境の子どもたちが集まる場所です。
だからこそ、本人が努力していても【見えにくい努力】が埋もれてしまったり、周囲との比較で実力が評価されにくくなったりすることがあります。
しかし、逆に言えば、内申点や通知表でしっかり評価される生徒になるためには、ちょっとした工夫や日々の意識づけが大きな差を生み出すのです。
・自分から発言し、提出物を丁寧に出す【見える努力】
・平均点で満足せず、常に+20点を目指す意識
・授業や学習面だけでなく生活態度や自己管理にも気を配る
そして、親としては、【真面目だから大丈夫】と思い込まず、学校や塾に任せきりにせず、【学校外の視点】からも子どもの実力を客観的に見ていく姿勢が大切です。
中学生活は高校進学だけでなく、将来の学習習慣や自己肯定感を形成する大事な時期です。
だからこそ、埋もれずに、自信を持って評価される子になるための土台を、親子で一緒に築いていきましょう。