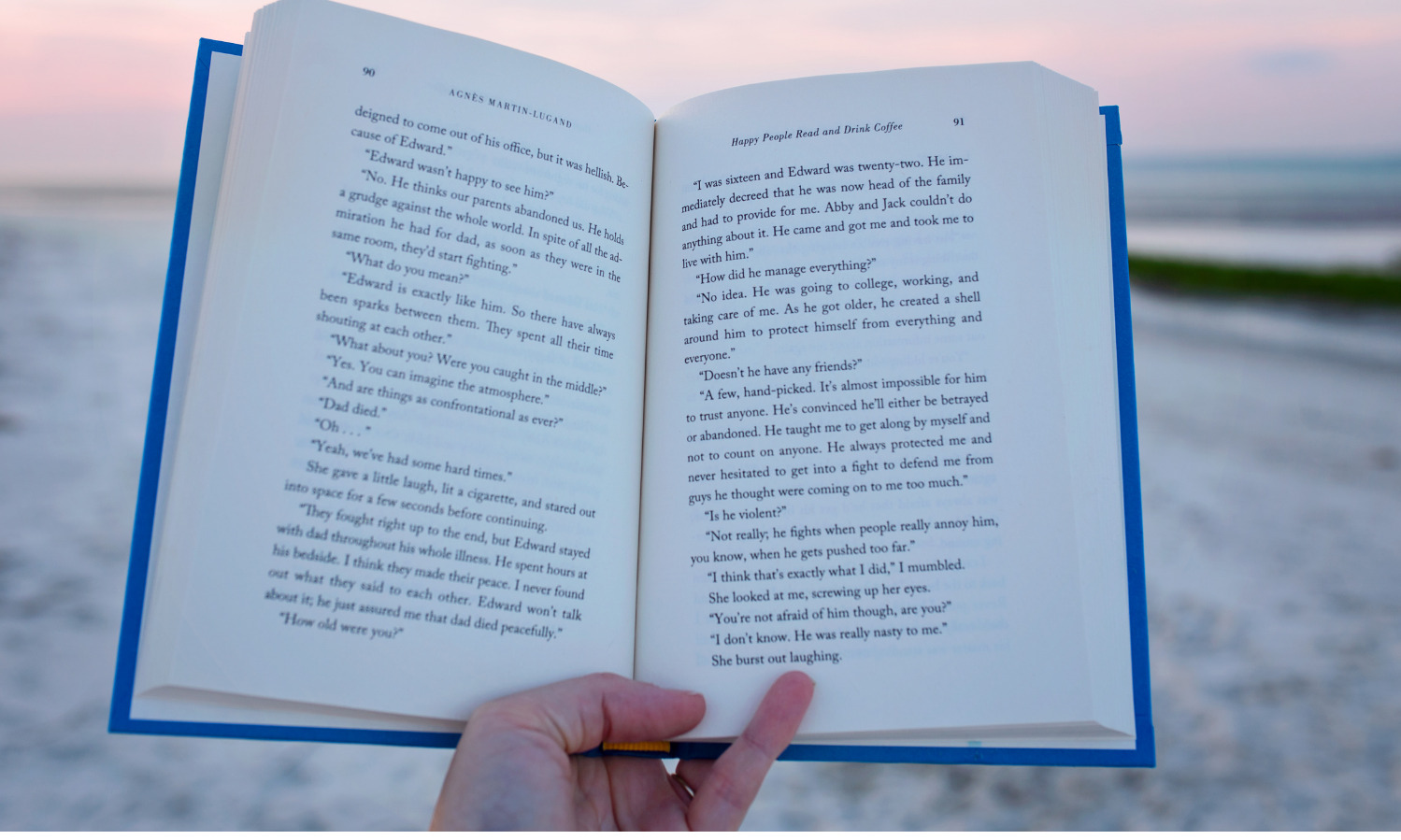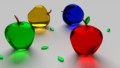今回は【小4の壁は最大のチャンス 子どもの『やる気』を再点火させる】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学4年生というのは、子育ての中でも子どもの勉強での悩みが増えていくタイミングでもあります。
実際、小学校4年生で学力グループが形成されていき、クラス内で【あの子は勉強が得意】【勉強が苦手な子】というのが共通認識になってきます。
学習内容が一気に抽象的になり、教科書を読んでもすんなり理解できなくなる。
テストの点数が悪くなる。
親子ともに【なんだか急に勉強が難しくなった】と感じる時期ではないでしょうか。
今までスムーズにこなしていたはずの宿題やテストでつまずきが目立ち、【あれ?うちの子、こんなにやる気がなかったっけ?】と不安を感じる親も増えてきます。
これが、いわゆる【小4の壁】です。
実はこの【壁】、子どものやる気を見直し、再び前向きに学びと向き合わせる絶好のタイミングという側面でもあります。
学びのステージが切り替わる時期だからこそ、これまでのやり方を見直すチャンスでもあり、今後の学習習慣や自己肯定感に大きな影響を与える分岐点でもあります。
そこで今回は、まず【小4の壁】でやる気が落ちる原因を明らかにし、次にそのような子どもたちの共通する特徴を整理します。
そして、親ができる具体的な3つの対策を紹介します。
子どもが壁の前で立ち止まっているのなら、今こそやる気を再び火をつけるチャンスです。
ぜひこの機会に、【やる気再点火】のヒントを見つけてください。
なぜやる気が落ちる?小4の壁の3つの原因
まず、小学4年生というのは悪い面ばかりではないということも理解しましょう。
子どもは学校生活にもすっかり慣れ、学習や人間関係も安定してくる時期です。
ところが、この頃から【急に勉強しなくなった】【習い事に行きたがらない】といった変化を感じる親が増えてきます。
これがいわゆる【小4の壁】と呼ばれる現象です。
やる気の低下は、子どもの性格や一時的な気分の問題と思われがちですが、実は子どもの成長過程においてごく自然に起こるものです。
この時期は心と頭の働きに大きな変化が生じ、今まで当たり前にこなしていたことにも戸惑いを覚えるようになります。
また、学習内容が難しくなるだけでなく、【自分ってなんだろう】【どうせやってもダメかも】といった自己認識や自己否定の感情が芽生え始めるのもこの頃です。
これは決してマイナスなことではなく、子どもが本当の意味で【自分自身】と向き合い始めるサインでもあります。
ここでは、小4の壁によって子どものやる気が落ちる背景にある3つの主な原因について解説していきます。これを知っておくだけでも、子どもへの接し方が変わってくるはずです。
原因①学習内容の変化と抽象化
小学4年生になると、学習内容が一段階レベルアップします。
算数では分数や小数の計算、理科や社会では実験・観察・資料の分析といった、【考える力】を求められる内容が一気に増えます。
これまでは【覚えること】が中心だったため、言われたことをそのまま受け入れてこなせていた子どもたちも、ここで初めて理解が必要とされる壁にぶつかるのです。
【なんとなくわかる】では通用しなくなり、【わからない=できない】と感じてしまうと、苦手意識が一気に広がります。
こうした小さなつまずきが、【勉強ってつまらない】【やっても意味がない】というネガティブな感情につながってしまうのです。
特に気を付けたいのが、これまでスムーズに学んでこられた子です。
小学4年になり、人生で初めての【分からなさ】に強く戸惑い、自信を失いやすい傾向があります。
学習内容の質的な変化は、小4の壁を引き起こし、子どもの心にも影響を与える大きな要因のひとつです。
原因②自我の芽生えと比較意識の拡大
この時期になると、子どもは周囲と自分を比較する力を急速に身につけます。
【あの子はテストが早く終わった】【自分だけできなかった】など、他人との違いを敏感に感じ取るようになるのです。
それまでは【できた!】【楽しい!】という純粋な感情で取り組んでいたことにも、少しずつ【自分は劣っているかも】という否定的な思いが混じるようになります。
これが自己肯定感の低下に直結し、やる気の減退を引き起こします。
特に真面目で努力家な子どもほど、【できて当たり前】と自分にプレッシャーをかけすぎてしまい、少しの失敗でも【自分はダメだ】と思い込んでしまいがちです。
このように、小4は自我が強くなり始める時期であり、周囲との比較を通じて自己評価を下げてしまうことが多くなります。
やる気を失った背景には、こうした内面の変化があることを理解する必要があります。
原因③周囲の期待と【できて当たり前】の圧力
小学4年生になると、子どもに対して無意識のうちに【もう高学年なんだから】【それくらいできて当然】といった期待をかけてしまいがちです。
親や先生のこうした言葉や態度は、良かれと思ってのことでも、子どもにとってはプレッシャーとなることがあります。
これまで【よくできる子】として評価されていた場合、その期待に応えなければという思いが重荷になり、【失敗したくない】【怒られたくない】という気持ちから、チャレンジを避けるようになります。
また、家庭でも【勉強したの?】【成績はどうだった?】といった成果を重視する会話が増えると、子どもは【結果を出さないと認められない】と感じるようになり、やる気を失ってしまうこともあります。
プレッシャーは、やる気の原動力にもなり得ますが、行き過ぎると逆効果です。
子どもの目線に立ち、【頑張ろう】と思える環境をつくることが、やる気の再点火には欠かせません。
やる気が落ちた子どもに見られる3つの特徴
さて、子どもの【やる気がない】と感じたとき、それは単にサボっているのではなく、心の中で何かが起きているサインかもしれません。
小学4年生は、学習や対人関係が一気に複雑化する時期。
にもかかわらず、子ども自身はその変化をうまく言葉で説明できず、行動や態度で示すしかないことがほとんどです。
【急に宿題を嫌がるようになった】【感情の波が激しい】【前は好きだった習い事をやめたがる】
こうした変化を見たとき、親としてはつい【怠けてるのでは?】【わがままなだけかも】と感じるかもしれません。
しかし、それをただの問題行動として捉えるのではなく、背後にある心理的な変化を理解することがとても大切です。
子どもは成長する過程で、壁にぶつかることで学び、乗り越える力を育てていきます。
今は一見やる気をなくしているように見えても、その裏では【どうしたらいいのか】【これでいいのか】と内面で格闘しているのです。
ここでは、小4の壁によって見られやすい、子どものやる気低下のサインとなる3つの特徴を紹介します。
子どもの変化に敏感に気づき、適切なサポートをするための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
特徴①【無関心・無気力】な態度が目立つ
以前は楽しみにしていた学校や習い事に対して、急に興味を示さなくなる。
テレビを見てもぼーっとしていたり、何を聞いても【別に】【わかんない】と反応が鈍かったり。
これらは、子どもが心の中で何かに引っかかっているサインかもしれません。
無気力な態度は、決して【怠け】ではありません。
むしろ、感情や思考が整理できず、動けなくなっている状態とも言えます。
本人も【やらなきゃいけない】とは思っているものの、気持ちがついてこない状態です。
このときに頭ごなしに叱ったり、【やる気がないならやめなさい】と突き放したりすると、子どもはますます心を閉ざしてしまいます。
まずは、【最近、元気ないけど何かあった?】と声をかけるだけでも、子どもにとっては安心材料になります。
親が静かに見守りながら、話せる環境をつくってあげることで、子どもは少しずつ自分の思いを表に出せるようになります。
特徴②感情の起伏が激しくなる
些細なことで怒ったり、泣いたり、不機嫌になったりと、感情が不安定になるのも小4の壁の特徴の一つです。
親のちょっとした言葉に過剰に反応することもあり、【どうしてこんなことで怒るの?】と戸惑う場面が増えてきます。
これは、子ども自身が自分の中の感情をうまく処理できず、混乱している証拠です。
【やりたいけどできない】【がんばりたいけど自信がない】といった葛藤が、怒りや涙という形で表に出ているのです。
また、学校や習い事など外の世界で緊張している反動として、家庭で感情を爆発させることもあります。
親にとっては大変ですが、逆に言えば【家では安心できる】という証でもあります。
このようなときには、まず子どもの感情を否定せずに受け止めることが大切です。
【そんなことで怒らないの!】ではなく、【今、イライラしてるんだね】と共感してあげるだけでも、子どもの心は少しずつ落ち着きを取り戻します。
特徴③自己否定的な言動が増える
【どうせ自分なんて】【やってもムダ】【ぼくには無理だよ】といった、自己否定的な言葉が増えてきたら、それは子どもが心のどこかで自信を失っているサインです。
これはやる気の低下だけでなく、自尊感情の揺らぎとも深く関係しています。
小4の子どもは、周囲と比べる力がつき始めると同時に、【自分はできていない】と感じやすくなります。特に、勉強やスポーツでうまくいかなかったとき、自分を責めるような言葉が出てくるようになります。
このような言動に対して、【そんなことないよ!】と励ますだけでは、子どもの心には届かないこともあります。
重要なのは、結果ではなく努力した過程をしっかり認めることです。
【前よりも時間をかけてがんばっていたね】【難しいのに最後までやったのはすごいよ】といった声かけをすることで、【できる・できない】だけで判断されていないという安心感を持つことができます。
自分に価値があると思えることが、子どものやる気を支える大きな土台となります。
やる気を再点火!親ができる3つの対策
ところで、【やる気が出ないのは本人の問題】と考えてしまいがちですが、子どもが再び前向きな気持ちを取り戻すためには、周囲の大人の関わり方が非常に大きなカギを握っています。
とくに小4という時期は、子ども自身も自分の変化に戸惑っており、【頑張りたいけど頑張れない】【言葉にできないけど不安】といったモヤモヤを抱えやすくなります。
こんなときに大人が【もっと頑張りなさい】【やる気がないならやめれば?】などと突き放すと、子どもは心を閉ざしてしまいます。
一方で、ほんの些細な声かけや関わり方ひとつで、再びやる気に火がつくことも少なくありません。
重要なのは、【できるようにさせる】ことではなく、【やってみよう】と思える気持ちを引き出すことです。
そのためには、プレッシャーを与えるのではなく、子どもの内側から【やってみたい】を育てる関わりが必要です。
ここでは、やる気を失った子どもに対して、親が今すぐ実践できる3つの具体的な対策をご紹介します。
どれも特別なスキルや道具がいらない、家庭の中で自然に取り入れられる方法です。
対策①プロセスを認め、努力を言葉にする
多くの親はつい【テストで何点取れたか】【結果としてできたかどうか】に目が向きがちです。
しかし、子どものやる気を育てるうえで大切なのは、【結果】ではなく【プロセス】に注目することです。
たとえば、【100点取ってすごいね】よりも、【間違えた問題を見直したのが良かったね】【あきらめずに最後までやったのが立派だね】といった声かけが、子どもの内面に響きます。
人は【自分の行動が認められた】と感じたときに、次もまたやろうという意欲が生まれます。
結果はコントロールできませんが、努力のプロセスは子ども自身の行動に基づいているため、そこを認めてもらえると【自分はがんばれる】という自己効力感が育ちます。
プロセスを褒める習慣をつけることで、子どもは【できた】【できなかった】に一喜一憂せず、自分の努力に自信を持てるようになります。
対策②小さな選択を子どもに委ねる
やる気の原動力は【自分で決めた】という実感から生まれます。
言われたからやる、やらされているという感覚が続くと、子どもはどんどん受け身になり、やる気を失ってしまいます。
そこで大切なのが、日常の中で小さな選択肢を子どもに与えることです。
【今から宿題する?それともご飯のあとにする?】といった具合に、どちらかを自分で選べるようにするだけでも、【自分で決めたことだからやろう】という気持ちが芽生えます。
重要なのは、【やる・やらない】の二択にせず、【いつやる?】【どれからやる?】といった前向きな選択肢を提示することです。
これによって、親がコントロールしなくても、子ども自身が行動を選び取る習慣がついていきます。
子どもに小さな決定権を与えることは、自立の第一歩。
やる気の回復だけでなく、自信と責任感を育てることにもつながります。
対策③親自身が挑戦する姿を見せる
子どもに【がんばれ】と言うだけでは、なかなか本当の意味でやる気は引き出せません。
そんなときに最も効果的なのは、親自身が【がんばっている姿】を見せることです。
たとえば、親が仕事で新しいことに挑戦していたり、家事の中で苦手なことを工夫して取り組んでいたりする様子は、子どもにとって大きな刺激になります。
【大人でもうまくいかないことがある】【それでも努力している】という姿から、子どもは挑戦する意味を学びます。
また、親が失敗したときに【こんなことがあってね、でも次はこうしてみるよ】と前向きに話すことで、子どもも【失敗しても大丈夫】と安心できるようになります。
親の姿は、子どもにとって一番身近なお手本です。
だからこそ、言葉よりも行動で伝えることが何よりも効果的です。
やる気を再点火させるには、まず親自身のチャレンジ精神が火種になるのです。
再点火のカギは【見守り】と【仕掛け】
小4の壁は決して【やる気がなくなる時期】ではありません。
それはむしろ、子どもが自分と向き合い始めた証拠であり、成長への一歩を踏み出すチャンスです。
大人がすべきことは、無理に引っ張るのではなく、子どもの内側に眠る【やってみたい】という気持ちに火をつける仕掛けを用意すること。
そして、その芽が育つまで焦らずに見守ることです。
【気づいてくれてうれしい】【認めてもらえた】【自分で決めた】という体験の積み重ねが、やがて子ども自身のやる気につながります。
小4の壁は、ただの壁ではありません。
その先にある飛躍のタイミングを、親子で乗り越えていけるよう、今こそ心の距離を近づけていきましょう。