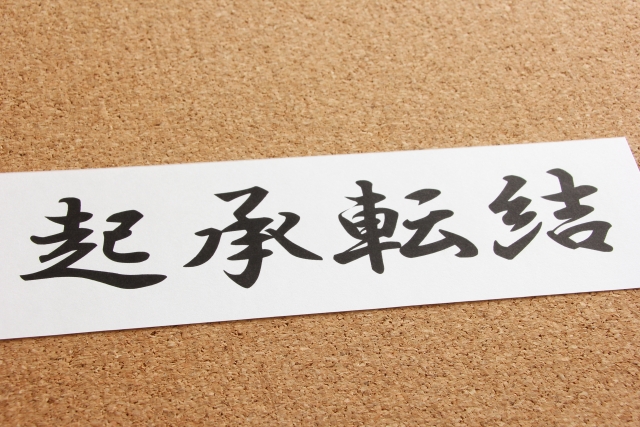今回は【うちの子、もう手遅れ?と悩む前に知っておきたい算数数学の立て直し方】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
【うちの子、算数・数学が本当に苦手で…今さらやり直しても無駄なのでは?】
そんな不安の声を、親の方からよく耳にします。
小学校の高学年から算数の苦手意識が強くなり、中学に入った途端、テストの点数が急に下がる。
これまで普通にできていたのに、いつの間にか【数学は嫌い】【全然わからない】と言うようになってしまう。
そういう子は決して少数派ではありません。
しかし、結論から言えば、算数や数学の苦手は才能のなさではなく、つまずきを放置して進んでしまったことが主な原因です。
算数・数学は、積み上げ型の教科です。
一度理解できない単元が出てきて、それをきちんと取り戻さないまま次の内容に進むと、どんどん難しく感じるようになります。
そして、それが【もう無理】と思い込んでしまう原因になるのです。
けれど安心してください。
たとえ過去にさかのぼっての学び直しが必要だとしても、正しい方法で一歩ずつ復習すれば、今からでも十分に挽回できます。
そこで今回は、なぜ数学が【立て直しにくい】と言われるのかを3つの視点から明らかにし、子どもがどのタイミングでつまずきやすいかを整理します。
その上で、家庭でもすぐに実践できる3つの改善策をご紹介します。
【うちの子、もしかしたらできるかも】と思えるようになる。
そんなきっかけになることを願って、順を追ってお伝えしていきます。
数学が【挽回しづらい】と言われる3つの理由
まず、算数や数学が一度わからなくなると、【どこから手をつけていいのかわからない】【もう無理かも】と感じる子どもが多くなります。
そして、親の側も【国語や英語ならなんとかなるけど、数学は難しい】と思いがちです。
なぜ数学は他教科に比べて挽回が難しいと思われるのでしょうか?
その理由は、数学という教科が積み重ね型の構造になっているからです。
たとえば歴史の年号や理科の用語なら、単元ごとに独立して学ぶことも可能です。
しかし数学の場合、過去の知識を理解していないと、現在学んでいる内容がまったく理解できなくなってしまうのです。
また、【苦手になった原因が過去にある】ことに子ども自身も気づいていないケースが多く、表面的な対策だけではうまくいきません。
むしろ、【何をどう直せばよいのか】がわからないことで、余計に自信を失ってしまうのです。
ここでは、数学が苦手になったときに挽回が難しく感じられる主な理由を3つに整理してご紹介します。
原因が見えれば、対策も立てやすくなります。ぜひお子さんの状況と照らし合わせながら読んでみてください。
理由①子どもが【復習をやりたがらない】
数学の苦手を克服するには、どこでつまずいたかを見極めて、そこまでさかのぼって復習することが大切です。
しかし、実際には子どもが【復習を嫌がる】という壁に直面する親は多いのではないでしょうか。
なぜ子どもは復習を嫌がるのでしょうか?
その理由のひとつは、過去の単元に対して【できなかった記憶】が残っているからです。
一度わからなかった問題に再挑戦することは、大人にとっても気が重いことです。
ましてや、子どもにとっては【またできなかったらどうしよう】【やっぱり自分はダメなんだ】と、不安や劣等感を再確認するような気持ちになってしまいます。
算数や数学はもの凄くできる子はできるため、苦手な子からすると劣等感を抱きやすい教科でもあります。
また、復習を始めるには【何から手をつければいいか】を考える力も必要です。
しかし苦手な教科ほど、勉強の仕方がわからないまま時間だけが過ぎてしまい、【どうせ無理】とあきらめる傾向が強くなります。
親が【まずここから復習してみようか】と具体的に示してあげること、そして【できる】を実感できる小さな課題から始めることが、心理的なハードルを下げるカギになります。
本人の気持ちを否定せず、不安や抵抗を理解しながら寄り添う姿勢がとても大切です。
理由②つまずいた単元が思ったよりも前だった
中学生になって数学がわからなくなったとき、【きっと最近の単元が難しすぎるせいだ】と考えがちです。
しかし、実は多くのケースで、つまずきの原因はもっと前の学年、場合によっては小学校にまでさかのぼることがあります。
たとえば、中2の一次関数でつまずいていた子が、原因をたどると【小5の割合】が理解できていなかったということは珍しくありません。
割合や分数、比などは一見シンプルに思えるかもしれませんが、後の学習に深く関係している基礎項目です。
ここをしっかり理解していないと、中学の方程式や関数、図形などが急に難しく感じるのです。
しかし、親や子ども本人は【中学で急にわからなくなった】と感じるため、つまずいた本当の原因にはなかなか気づけません。
そのため、いくら今の単元を復習しても根本的な解決にならず、【やってもできない】と感じてしまいます。
数学が挽回しにくい理由のひとつは、問題の根が深く、見えにくいことにあります。
一見遠回りに見えても、思い切って小学校の内容まで戻る勇気が、再スタートには必要です。
親が【過去に戻るのは恥ずかしいことではない】と伝え、環境を整えてあげることが大切です。
理由③【数学はセンスの問題】と思い込んでしまう
【うちの子は数学のセンスがないんです】【理系じゃないから仕方ないですよね】
算数や数学を苦手とする子を持つ方からこういった声を聞くことがあります。
また、子ども自身も【自分は数学ができないタイプ】と思い込んでしまうことがあります。
ですが、これは数学の苦手を深めてしまう大きな誤解です。
確かに、数字への直感やひらめきが得意な子もいますが、学校で学ぶ算数や数学は、才能よりも積み重ねと慣れがものを言う教科です。
基本的なルールや計算力、問題文の読み解き方など、誰でも後から身につけられる力が大部分を占めています。
それにもかかわらず【自分には向いていない】と思い込んでしまうと、努力する意欲そのものがなくなってしまいます。
とくに中学以降は、難易度が上がるにつれ【数学アレルギー】になってしまう子も珍しくありません。
そこでポイントとなるのは、【苦手なのは向いていないからではなく、わかる経験が少なかっただけ】と子どもに伝えることです。
そして、基本的な問題から確実に【できる】を積み上げていくことです。
親がその認識を持ち、才能ではなく努力の積み重ねであると、根気よく伝えていくことが、立て直しの出発点になります。
子どもが算数・数学につまずく3つのタイミング
さて、【気づいたら、もう全然わからなくなっていた】
多くの子どもがそう口にするように、算数・数学の苦手意識はある日突然生まれるのではなく、徐々に積み重なっていくものです。
最初は【ちょっと苦手かな】程度だったのが、ある時期を境に【全くついていけない】と感じるようになる。
そしてテストの点数が下がり、自信を失っていくという悪循環に入ってしまいます。
このような負のスパイラルを防ぐには、【つまずきやすいタイミング】を親があらかじめ把握しておくことがとても重要です。
実は、多くの子が苦手意識を持ち始める時期には一定の傾向があります。
ここでは、特につまずきが起こりやすい3つの学年・学習段階を取り上げ、なぜその時期が要注意なのかを詳しく見ていきます。
今まさにその時期にいるお子さんはもちろん、これから迎えるご家庭にも役立つ内容です。
【苦手になった原因はどこだったのか?】【どの単元から崩れてしまったのか?】という視点で、お子さんのこれまでの学びを振り返るヒントとして、ぜひお読みください。
タイミング①最初の壁は【小学3年生】にやってくる
多くの子どもにとって、算数の最初の本格的な壁となるのが小学3年生の内容です。
この時期から、単なる計算練習から一歩進んで、文章題や図形、単位の変換といった【考える力】が問われる問題が増えてきます。
たとえば、長さ・重さ・時間の単位換算、三角形や角度の概念、かけ算やわり算を使った文章題など、目に見えない数のイメージ化が必要になります。
ここで【よくわからない】【難しい】と感じる子が急増するのです。
また、同じタイミングで授業のスピードも少しずつ早くなり、理解が追いつかないまま次の単元に進んでしまうこともあります。
その結果、つまずいたことに気づかないまま【なんとなく】苦手意識を抱え、以後の学習に影響してしまいます。
親としては、3年生の時点で【言われたことはできるけど、応用になると戸惑う】という様子が見られたら注意が必要です。
【考える力】を育てるサポートを意識し、繰り返し練習だけでなく、問題の意味や背景を一緒に考える時間を取ることで、初期の苦手意識をやわらげることができます。
タイミング②小学校高学年で抽象化の壁にぶつかる
小学校4〜6年生になると、算数はさらに難易度が上がります。
とくに割合・速さ・図形など、具体から抽象へと内容が移行する時期は、多くの子が【わからない】と感じ始める重要なタイミングです。
たとえば【割合】は、実生活ではよく使われる概念ですが、子どもにとっては【何を比べているのか】【何に対しての何なのか】といった関係性を理解するのが難しい単元です。
速さの問題も、距離・時間・速さの関係を式で表す必要があり、単位の理解や計算の正確さも求められます。
また、この時期に出てくる図形問題も要注意です。
角度や面積、体積の計算だけでなく、図形の特徴や性質を使って論理的に考える力が必要になるため、単なる暗記では太刀打ちできなくなります。
これらの単元は中学数学の土台になるため、ここで理解が不十分なまま進んでしまうと、中学に入ったときに一気に苦手という問題に直面するリスクがあります。
親としては、【なんとなくできている】ではなく、理解が定着しているかを確認する声かけが大切です。
子どもが【わかった】と言っても、具体的に説明させてみると理解があいまいなこともあります。学びの質を高める関わりが、この時期には特に求められます。
タイミング③中学に入って【教科書が読めない】と感じ始める
中学生になると、算数から【数学】へと教科の性質が大きく変わります。
多くの子がつまずくのが、【教科書を読んでも意味がわからない】と感じるタイミングです。
一次方程式、関数、図形の証明など、数学は考え方を問われる学問へと変化します。
たとえば、解き方がひとつではない問題、途中の論理的な過程を説明する問題などが登場し、読み解く力・論理的思考・抽象的な理解が一気に求められるようになります。
この変化に戸惑い、【自分にはもう無理】と感じてしまう子が少なくありません。
さらに、授業のスピードも早くなり、理解が追いつかないと感じる子どもはどんどん自信をなくしてしまいます。
中学から塾に通い始めるケースも多いですが、【どこから苦手なのかわからないまま】問題集を進めているだけでは効果が出にくいです。
親としては、【教科書が読めない=理解できないのは当たり前】と受け止め、噛み砕いて説明する場を家庭で作ることが重要です。
中学数学に入ったタイミングで、わからないまま流してしまうと、学年が上がるごとに挽回がさらに難しくなります。
このタイミングでのつまずきを防ぐには、【読んでわかる】から【考えて理解する】への切り替えをサポートすることがカギになります。
家庭でできる!数学を立て直す3つの具体策
ところで、ここまで、算数・数学が挽回しづらく感じる理由、そして子どもがつまずきやすいタイミングについてお話してきました。
でも、【じゃあ、どう立て直せばいいの?】というのが、親の一番の関心事ではないでしょうか。
算数や数学のやり直しには、【一気に成果が出る魔法の方法】はありません。
しかし、正しい手順を踏めば、確実に苦手を克服していくことは可能です。
そのカギは、【どこからやり直すか】と【どのように進めるか】という2つのポイントにあります。
大切なのは、【子どもが過去のつまずきに向き合えるような環境づくり】です。
恥ずかしい、今さらやり直すのは嫌だという気持ちを抱えたままでは、やる気も集中力も続きません。
ですから、家庭では【できないのは当たり前。ここから一緒にやろう】という空気感を作ってあげることが何よりのサポートになります。
ここでは、家庭でできる立て直しの具体策を3つに分けてご紹介します。
どれも特別な教材や塾がなくても実践できる方法ですので、ぜひお子さんの様子に合わせて取り入れてみてください。
改善策①過去に戻る勇気を持つ
数学のやり直しで最も大事なのは、子どもがつまずいた【原点】に立ち返ることです。
ところが多くの親や子ども自身が、【今の学年の内容をとにかく理解しなければ】と焦ってしまい、過去の基礎に戻ることを避けがちです。
しかし、今つまずいているのが中1の方程式だとしても、原因が小5の割合や小3のわり算にあることも珍しくありません。
そんなとき、いくら現在の単元を繰り返しても、土台が崩れていては積み上がらず、本人も【やってもできない】と感じてしまいます。
ここで必要なのは、【学年にこだわらず、理解できていない単元から始める】勇気です。
最初は子どもも【小学生向けの問題なんて今さら…】と抵抗を感じるかもしれません。
けれど、実際に解いて【わかる】【できた】という感覚を持てると、自信が芽生え、次のステップへの意欲にもつながります。
親としては、【恥ずかしいことではない】【むしろ大事な見直しだよ】と声をかけ、学び直しは前向きな選択だという雰囲気を作ることが大切です。
今のつまずきは、過去の理解不足が原因。そこに戻ることを肯定する姿勢が、立て直しのスタート地点になります。
改善策②四則計算の基礎を確認し、毎日コツコツ解く習慣を
苦手克服の第一歩として、ぜひ取り組んでほしいのが、四則計算の基礎をしっかり固めることです。
どんなに複雑な文章題や図形問題も、最終的には基本の計算力に支えられています。
逆に言えば、計算ミスが多いと、問題の意図は理解していても正解できません。
とくに注意が必要なのが、【分数・小数の計算】【筆算の正確さ】【わり算の理解】といった、小学校の後半で学ぶ計算の応用部分です。
ここがあやふやなままだと、中学の方程式や関数でも苦戦することになります。
改善のポイントは、難しい問題に挑戦するよりも、【確実にできる計算を毎日解く】習慣をつくることです。
1日5分、10問だけでもかまいません。
計算ドリルや市販の問題集、無料プリントなどを使って、日々の中に【少しだけでもやる】時間を組み込んでみましょう。
この積み重ねによって、計算に対する自信とスピードがつき、自然と応用問題にも対応できるようになります。
親は、結果だけでなく【毎日取り組んでいること】を評価してあげると、子どもは安心して継続できます。
まずは基礎を見直すこと。
コツコツ型の勉強こそが、数学の苦手を根本から解決する近道なのです。
改善策③基本問題から始め、少しずつレベルを上げる
算数や数学の立て直しを始めるとき、ついやってしまいがちなのが【いきなり応用問題に取り組ませる】ことです。
テストの点を上げたいという焦りから、【今出ているレベルの問題を解けるようにしなきゃ】と思ってしまうのは自然なことですが、それでは子どもはますます自信を失ってしまいます。
大切なのは、基本的な問題から始め、理解に合わせて段階的にレベルを上げていくことです。
具体的には、教科書やワークの【基本問題】や【例題】から始め、慣れてきたら【標準問題】→【応用問題】へと、スモールステップで進めていきます。
このとき、1ページ終わるごとに【よく頑張ったね】【できたじゃん!】という声かけをしてあげると、子どもは小さな達成感を積み重ねられます。
この成功体験こそが、【やればできる】という意識につながり、学びのサイクルが良い方向に回り始めるのです。
また、【自力で解けたかどうか】だけでなく、【どこまで理解できているか】に注目することも大切です。
たとえ正解できなかったとしても、【解き方は合ってたね】【式は立てられたね】と、過程を認める声かけが効果的です。
急がば回れ。
やさしい問題から確実に解けるようになることが、長期的な数学力の土台になります。
焦らず、でも着実に。【少しずつできる】が何よりの前進です。
【わからない】を放置しない勇気が未来を変える
算数や数学の苦手意識は、放っておいて自然に解決するものではありません。
むしろ、早くに気づいて適切に向き合えば、必ず立て直しが可能な教科です。
けれど現実には、【どこからどう始めたらいいのか分からない】【もう手遅れかも…】と感じて、不安や焦りを抱える親の方も少なくありません。
今回は、まず算数や数学が立て直しにくいとされる3つの理由を整理し、さらに、よく見られる3つのつまずきのタイミングをお伝えしました。
そして最後に、具体的な立て直し策として、
・思い切って学年をさかのぼる勇気
・毎日の四則計算で土台を固める習慣
・簡単な問題から徐々にレベルを上げるステップ学習
の3つを紹介しました。
どれも特別な才能や教材を必要とするものではなく、家庭で今日から始められる小さな工夫です。
その中でも、親の関わり方が、子どものやる気や自己肯定感に大きな影響を与えることは言うまでもありません。
【わからないままにしない】【できないのはダメじゃない】と、お子さんに安心してもらえる関係性を築きながら、今から一歩ずつ取り戻していく。
その積み重ねが、やがて大きな成長へとつながります。
算数・数学は、一度つまずいても、正しい方法で振り返れば、何歳からでも挽回できる教科です。
遅すぎることはありません。
今こそ、【できるかもしれない】という気持ちを信じて、再スタートを切ってみましょう。