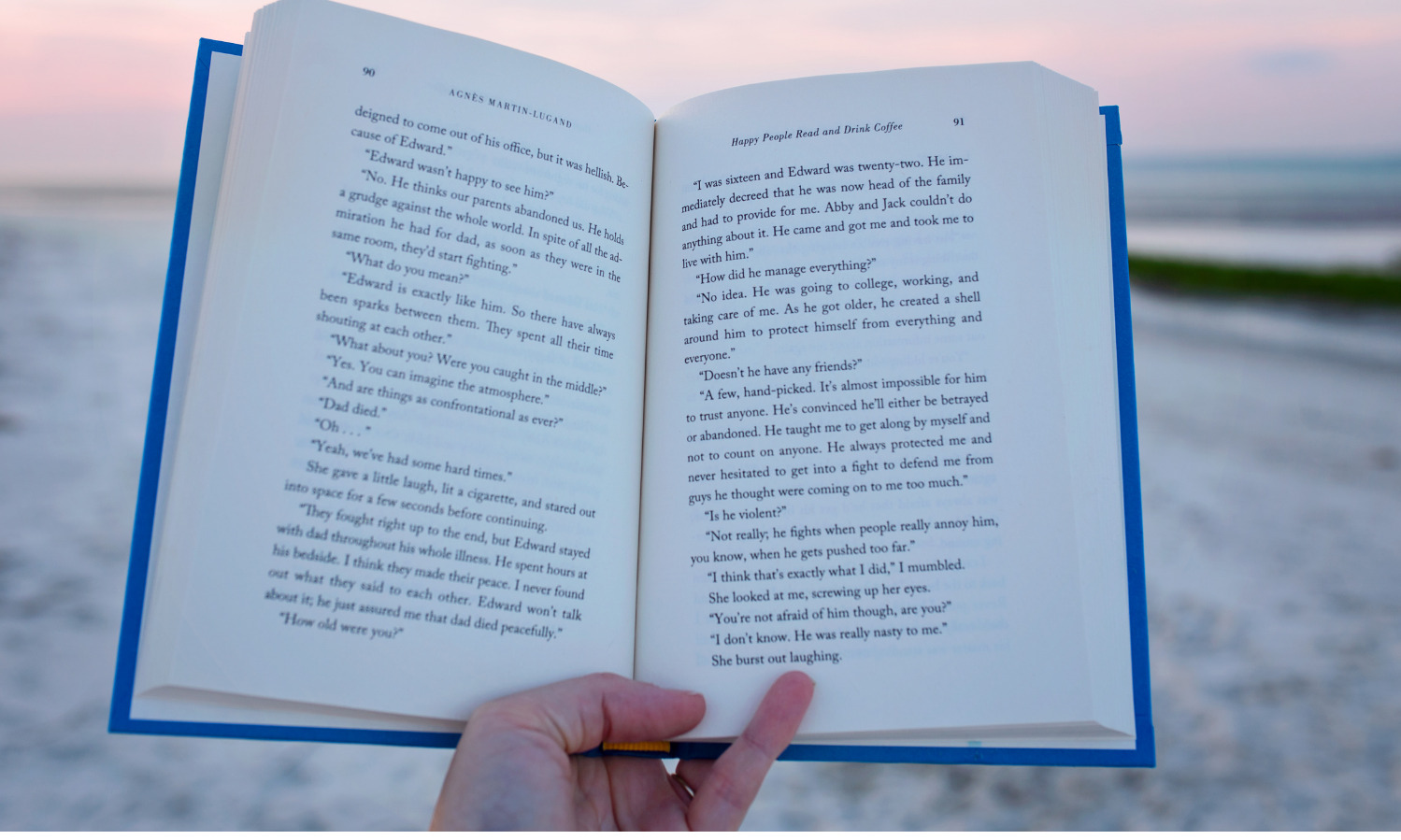今回は【小学6年生からトップ高校を目指す方法】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校6年生からトップ高校を目指す場合、時間はありますが、トップ高校を受験する子というのは各中学校のトップ層にいるだけでなく、そもそも小学生時代から【学校の優等生】という立ち位置で生きてきている子ばかりになります。
小学校6年生の時点でそういう立ち位置にはいない子は、小学生のラストイヤーで基礎学力を盤石なものにし、中学に進学してからは高校受験までの中学3年間でどのくらいの学力にまで到達するかという現実を受け止めつつ戦略的に勉強をしていくことが合格に近づくためのカギになります。
つまり、小6は高校受験というマラソンに向けてしっかり走りきるための重要な準備期間になります。
小学校6年生であやふやだった【勉強の仕方】や【受験勉強を乗り越える土台】をしっかり作っておけば、中学に入ってから一気に加速できます。
そして、トップ高校を目指すなら【中学受験をしたけれど残念ながら不合格となりトップ高校受験に切り替える同級生達】を意識することも必要です。
地方では公立中高一貫校を受験し、涙をのんだ子どもたちは学区の中学に進学してトップ高校受験へと切り替えます。
そうなると、トップ高校や2番手校は【中学受験しない小学生と中学受験をするために勉強してきた小学生】の争いになるわけです。
中学受験をする子の基礎学力や応用力は見過ごすことができないくらい高いです。
ですから、【受験しないからノンビリと過ごす】ではなく、小学校6年生の一年間はプレ中学生期間と思い、しっかり勉強することで中高一貫校を目指して勉強している子に少しでも近づくよう肝に銘じるようにしましょう。
それでは、小6からトップ高校を目指す方法をご紹介していきます。
中学以降につながる学習習慣を定着させる
まず、中学進学に向けて毎日の家庭学習習慣をこの時期に確実に作るよう、親子で学習プランを立てるようにしましょう。
小学6年生になると学校の宿題、家庭学習に取り組む時間も成長に伴い低学年の頃よりは長くなります。
学校の学びも難しくなるので、簡単に解けない問題を解く時もあります。
ただ、【毎日2時間勉強する】と時間で決めて、子どもに任せるというのは避けてください。
時間で括ってしまうと子どもの方も【とりあえず2時間はやる】と時間にとらわれて満足してしまいます。
塾で仕事をしている時も、学業不振の親ほど【とにかく長時間勉強させたがる】という傾向が強く、子どもはものすごく嫌がっていましたし、家で勉強する気力が湧いてこないと愚痴をこぼしていました。
どうしても長時間勉強した方が成績が上がると期待してしまいますが、【量より質】【時間より勉強する内容】を最初は重視することが大切です。
例えば、嫌々ながら、ダラダラの2時間勉強よりも毎日トータル60分以上の集中した学習時間の方が定着する知識も増えますし、子どもの方もメリハリをつけて毎日を過ごせるので学習習慣が定着するのも早くなることが期待できます。
学習の進め方は、親がアレコレ指図すると反抗する年頃になっているので【復習→理解→問題を解く】のサイクルを自分で回せるようになるのが理想的です。
ただ、まだ力をつけるための家庭学習のやり方を自分で考えるのが難しいという子もいるので、【中学進学を念頭にした小学校6年生でやるべきこと】を親子で考え、卒業までにどのくらいの力をつけるかというのをまず書き出して、逆算をして確実にその目標を達成できる学習計画を考えてみてください。
学校のカラーテストで満点を取ることだけでなく、塾のテストを受けてみて【基礎学力と応用力がどのくらいあるのか】を確認してみることもおすすめです。
どうしても、塾のテストは学校の勉強とは別物なのでカラーテストのような高得点を取れない子もたくさんいますが、現在の立ち位置を知ることも大切です。
また、中学受験組の子は塾のテストを受けているので彼ら彼女たちのレベルに近づけているのかを確認することもできます。
家庭学習をするのが当たり前になってきたら、自分で学習計画を立てれるようになりますし、【基本の学習はこうだけれどこういう勉強もしてみよう】と子どもがフレキシブルに対応して勉強できるようになります。
中学進学後は部活と勉強の両立が大きな課題となるので、そういう面でも小学校6年生の間に自学自習ができるようになっていると心強いです。
夏休みからは国語と算数との応用力をしっかり鍛える
さて、小学校の勉強では国語と算数の二つの教科が柱です。
柱の教科である国語と算数の基礎学力を鍛えつつ、勉強時間を確保できる夏休みからは応用力も身につけることを意識しましょう。
国語は読解力と語彙力の底上げを意識するのが肝要です。
小学校での国語は漢字対策をすればカラーテストでもそれなりに良い成績を維持することができますが、中学生になると漢字の読み書きだけでなく、読解力と記述問題への対応力がないと成績上位層には入れません。
私も塾で子どもたちを教えている時に感じましたが、トップ高校を受験する子は【記述力】【要約力】【長文の速読処理】が優れているという共通点がありました。
どうしても国語の成績が上向きになるまで時間がかかります。
しかも、苦手克服に本腰を入れる子よりは【どうにかして国語の勉強を避けたい】と考える子の方が多く、後手後手になると受験学年である中学校3年生になって慌てるということになってしまいます。
そうならないためにも、小6では読書をベースに語彙力・読解力・要約の練習をしましょう。
国語の記述問題はテストでも配点が高いので、部分点でも勝ち取る姿勢が合否を分けます。
要約問題に特化した問題集を家庭学習に取り入れたり、本を読んだ後に【なぜ面白かったか】と親に説明する機会を設けてみるのもおすすめです。
一方、算数の方は高学年で習う割合や速さ、比、図形などの重要単元の理解が曖昧なままだと中学数学の文章題や入試で必ずでる関数の分野に大きな影響が出ます。
高校受験もトップ高校では数学の出来不出来が合否を分けることもあるので、小学生の間に小学校内容を完璧に理解しておくようにしましょう。
そして、図形の面積や体積の求め方や速さ、などの公式だけでなく、【なぜそうなるか】を言葉で説明できるようになっているとなお良いです。
我が家の子ども①②の中学校での数学の勉強を見ていても、学習指導要領の改訂の影響で記述問題や説明させる問題が1年生の定期テストで出たり、入試問題の傾向も親世代の頃とは変わってきています。
【素数とは何か説明しなさい】といった問題に対して【どうやって説明すればいいの?】となると、中学数学に戸惑っていると苦手意識が強まってしまいます。
ですから、小学生の頃に【割合はこういうことだ】というのを他の子に説明できるレベルになるのが理想的です。
また、小学校の算数に苦労していない時は中1の数学の内容を少し先取りしておくとスタートダッシュをきめられるので、個人的にはおすすめです。
理科と社会と英語は中学内容の先取りを意識する
ところで、理科と社会そして英語も小学校6年生のうちから中学内容の先取りを意識すると、中学進学後に大きなアドバンテージになります。
3つの教科は、まず最初に【知識量】【用語】を暗記をしているかどうかという大前提があって、良い成績が狙えるという大きく、先手を打つ価値が高い教科です。
中学での理科と社会は小学校内容をレベルアップしたものとはいえ、【暗記量】は格段に増えます。
私も中学の理科で被子植物と裸子植物という用語を初めて知りましたが、言葉が専門的になり、それを覚えないとテストでどうにもならないという勉強になるので、【理科と社会は中学に入ってから本気になればいい】ではちょっと厳しいと感じています。
理科と社会は興味関心の有無で頭に入る知識量も変わってくるので、小学生の間に学習漫画を上手く活用して先取り内容を知っておくとプラスになります。
小学校3年生から6年生までに習った内容を総復習し、余裕があれば6年生で【中学の理理科社会の導入レベル】に触れておくと中学での授業で【知っている!】が増えて苦手意識が減ります。
そして、英語は【英語の発音に慣れて語彙を覚える準備期間】にしましょう。
小学校5年生と6年生で英語の授業を受けていますが、小学英語は【英語に親しむ】が強く、板書を書き写すことや英単語テストといったことも行われません。
ですから、子どもの方も英単語を暗記するために必死にならなくてもいいわけです。
ただ、他の教科と同じようにカラーテストは実施されていますし、テストの問題には【オレンジ】【赤】など昔の中学1年生の一番最初の定期テストレベルの英単語の書き取りも出ています。
家庭で基本的な英単語の暗記に取り組むといったことをしていないと、カラーテストで満点を取るのは難しいです。
本格的な英語学習、つまりは英文法をガッツリ勉強し始める前に中学英語の下地を作っていき、小学校6年生の間に親世代の頃の中学1年生で学んだレベルの英語の先取り学習をしていると英語への苦手意識も和らぎます。
我が家の子ども①は小学校6年生の冬から中学英語の勉強をさせようとしたのですが、私のアドバイスを無視してほぼ何もやらずに過ごしていたところ、新中学1年生の春休みの講習会でクラス替えの英語のテストがボロボロで、一旦下のクラスになりました。
そこから這い上がるために相当な気合を入れて英単語の暗記、英文法の勉強をして元のクラスに戻りましたが、小学校の英語と中学校の英語のレベルはかなり違うということを肝に銘じてください。
小学校6年生の1年間は勉強に対する姿勢”を作り直す最後のチャンスです。
【なぜ勉強するのか】【どの高校に行きたいか】など、目標意識を育てる対話をしておくと、中学に入ってからの加速が違います。