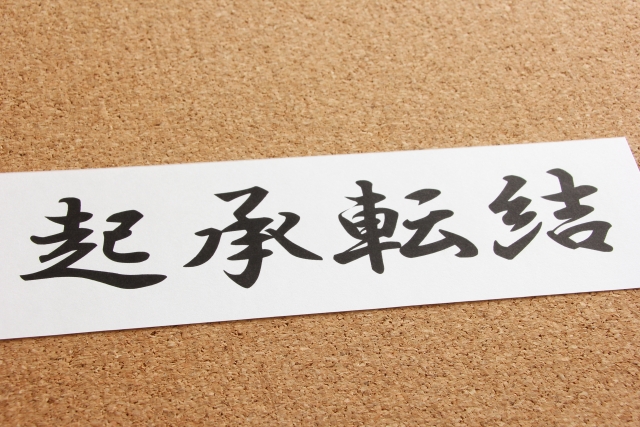今回は【進学校に入っても伸びる子の特徴】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子育てにおける大イベントの受験はいくつかあります。
全国的には人生初めての受験は高校受験という子が圧倒的多数です。
地方では塾に通うと言えば中学生が一番多く、それだけ高校受験に対する親子の思いというのも強いです。
最近は私立高校の授業料無償化もあり、地方のように公立優位の地域でも最初から私立の進学コースを目指すという子もいます。
公立私立問わず、巷では進学校と言われる学校に入るにはちゃんと勉強をして筆記試験をパスしなければいけないわけですが、高校に入ってからも大学受験に向けて学力を鍛えられる人と、高校に入ったまでの人に分かれていきます。
入学直後は同じくらいの学力、学力差があったとしてもほんの少しという程度だったのが、高校3年生の受験期には偏差値15、20近いくらいの差が生じています。
つまり、上は東大、京都大、旧帝大の医学部医学科、東京科学大や一橋大学、私立なら早慶を筆記試験でパスできるレベルから、地方の全国的な知名度のない私立大学に進学する子と高校受験の時からは想像できないようなくらい同級生同士でも学力差が生まれていきます。
これが小学校のように長丁場の6年間ならまだ分かりますが、たった3年間で埋められないような差ができてしまうのも高校に入ってからの伸び方が個人個人違うからです。
私は高校に入ってからまるで伸びないタイプの人間でしたし、その反省を踏まえて塾でも志望校である進学校に合格して浮かれている生徒に現実を話したり、子育てでも子ども①にも高校入学後に同級生たちの間で起きる厳しい現実を折に触れて予言めいた話をしてきました。
子ども①は塾の先生からも私と同じ話を聞かされました。
例えば、【高校に入ってからが本当の勝負】【浮かれている子はどんどん置いてけぼりとなり学力差が広がる】【高校1年の夏休み明けにはどうにもならないくらいの差となっている】ということです。
そして、実際に子ども①の高校では話の通りのようなことが周囲で起きており、本人もかなり驚いています。
入学した時点で最上位層だった子で学力を落としていく子はかなりのレアケースですが、全くいないわけではありません。
進学校でも努力次第では多少なりとも成り上がることも可能な世界だと思っていいでしょう。
それでは、どのような子が高校に入ってからも学力、成績を伸ばすことができるのでしょうか。
高校受験が最大の目標ではなかった
まず、高校受験が最大の目標ではない、という特徴があります。
地方あるある話だけでなく、大都市圏でも超有名高校、難関校に合格したことで満足し、燃え尽きてしまって入学後に勉強する意欲が低下する子がいます。
受験で合格することが親にとっても子どもにとっても【人生最大の目標】と言わんばかりの情熱を持って臨んでいると、無事に合格した後に目的がなくなってやる気が出ない、または合格したことで安心して勉強を横に置いてしまうようになります。
どの受験でも【合格】に向かって勉強を頑張っていくわけですが、【合格すればそれでいい】という考えでいると入学後に本格的に勉強がスタートする時に心の切り替えが上手くいかなくなります。
そもそも、進学校ではほぼ間違いなく100%の生徒が大学進学を考えているわけですから、小学校や中学校時代のように新年度の最初の頃は色々と係決めなどに時間を費やすということもなく、サクサク授業が進んでいきます。
しかも、かなりハイレベルな授業です。
予習、復習もせずに全てを理解できるのはごく限られた神童さんのみの話ですし、神童さんほど予習を勝手に進めているので普通に努力をして合格した子が中学生時代の感覚のままで、予習もなく進学校の勉強を乗り越えるのは無理があります。
高校に入ってから成績を伸ばす子は【無事に合格したから次は高校の勉強を頑張る】と切り替えています。
進学校の授業スピード、レベルは義務教育時代の中学校の授業とは比べ物にならないくらいの違いがあります。
難関大学を目指す子もいるので、小学校や中学校の頃のように【学力的に真ん中より下の子が理解できるような授業を心がける】ではありません。
ですから、高校に入って学業不振となると授業内容も理解できず、定期テストや民間企業の模試を受けてボロボロになるという、これまで優等生人生を歩んできた子にとっては経験したことがない出来事に直面するようになります。
高校に入って伸びる子は、高校のレベルを理解して【学校の中で上位35%から30%以内にいるのを目指す】【旧帝大の推薦入試や早慶の指定校推薦を狙っているから評定でオール5になるよう頑張る】と具体的な数値を意識して勉強を頑張ります。
高校合格というゴールも大切ですが、あまりにも大きくしてしまうとその先の大学受験のゴールが全く見えてこなくなるので、最大の目標にしないよう気をつけてください。
高校受験組のハンデを理解している
さて、大学受験を考える上で高校受験組が忘れてはいけないのは【世の中には中高一貫校と言う学校がある】ということです。
中高一貫校の子は高校受験がないので先取り学習を進めており、中学生で高校内容を勉強するというのが常識になっています。
もちろん、全員がそのスピード感ある勉強についていけるわけではありませんが、大学受験で対峙するライバル達が【先を走っている】というのは事実です。
けれど、インターネットが普及しているとはいえ、地方では都会の教育事情が伝わらないということがありますし、教育に関心が高い親であっても【都会は都会の話だし】ということで自分たちとは違う世界のことだと捉えて高校受験までたどり着くことができます。
そうした状況が一変するのが大学受験です。
大学受験は全国の高校3年生、または既卒生の戦いになります。
もはや都会だから、地方だから、という考えは通用しません。
地方の進学校で成績が伸びる子は高校受験組のハンデを理解し、【中高一貫校の子に負けないよう自分も予習を進めていく】という気持ちが強いです。
子ども①の周囲にいる神童さん達も、高校受験が余裕で受かることから高校数学を先取りしていたり、高校1年の夏休み頃には数学ⅢCまで全て自分で予習し終わっていました。
神童さん達は進学校の中でも別格扱いですから、同じようなスピードで予習することは無理があるものの、勉強を頑張っている子ども①の同級生たちも時間を見て予習を独自で進めているようです。
こうした高校受験組のハンデを考えて勝手に自学自習している子と、そういうことはせずにリアルタイムの授業を受けているだけという子もいたりと、学校内でも勉強の向き合い方に差が出ていると子ども①は口にしていました。
大学入試を逆算して1年生から受験を意識している
とにかく地方の高校受験組は大学受験で大きなハンデを背負っているので、高校1年生の頃から大学入試を逆算して受験を意識して勉強することが大学受験戦略になっています。
子ども①の周囲の神童さん達は高校1年生の秋くらいから部活を頑張りながらも受験モードに突入しているようです。
その様子を見た子ども①は【成績がいいのに今から本気モード全開は勘弁してほしい】と嘆いていました。
進学校になると毎年どのくらいの人数がどの辺りの大学に合格しているのかという目安のような数値が安定しています。
そうした実績を踏まえて【校内順位でこの位なら○○大学の○○学部には入れそう】というのを考えることができます。
ただ、高校1年生は厳しい受験を乗り越えたばかりですから【大学受験のことは忘れて学校生活を楽しみたい】と考えている子は圧倒的多数です。
こうした環境の中で大学入試のことを考えながら勉強していると成績は伸びやすくなります。
もちろん、進学校に入ってから伸びる子も終始勉強ばかり考えているわけではありませんが、【勉強を忘れて楽しみたい】とまでにはならず、大学入試のことも逆算して【この時期はこういう勉強をしていこう】【英語の長文読解が苦手だから今から頑張って入試に備えよう】と計画を立てて勉強しています。
ちなみに、子ども①の周囲にいる超賢い子達は部活も頑張りつつ高校1年生の頃から【大学入試を筆記でも推薦でも対応できるよう色々取り組む】ということをしています。
ノープランで高校1年生を過ごしてしまうと差がどんどん広がっていくので、合格したとしても浮かれすぎず現実を忘れずに勉強と向き合っていくことが大切です。