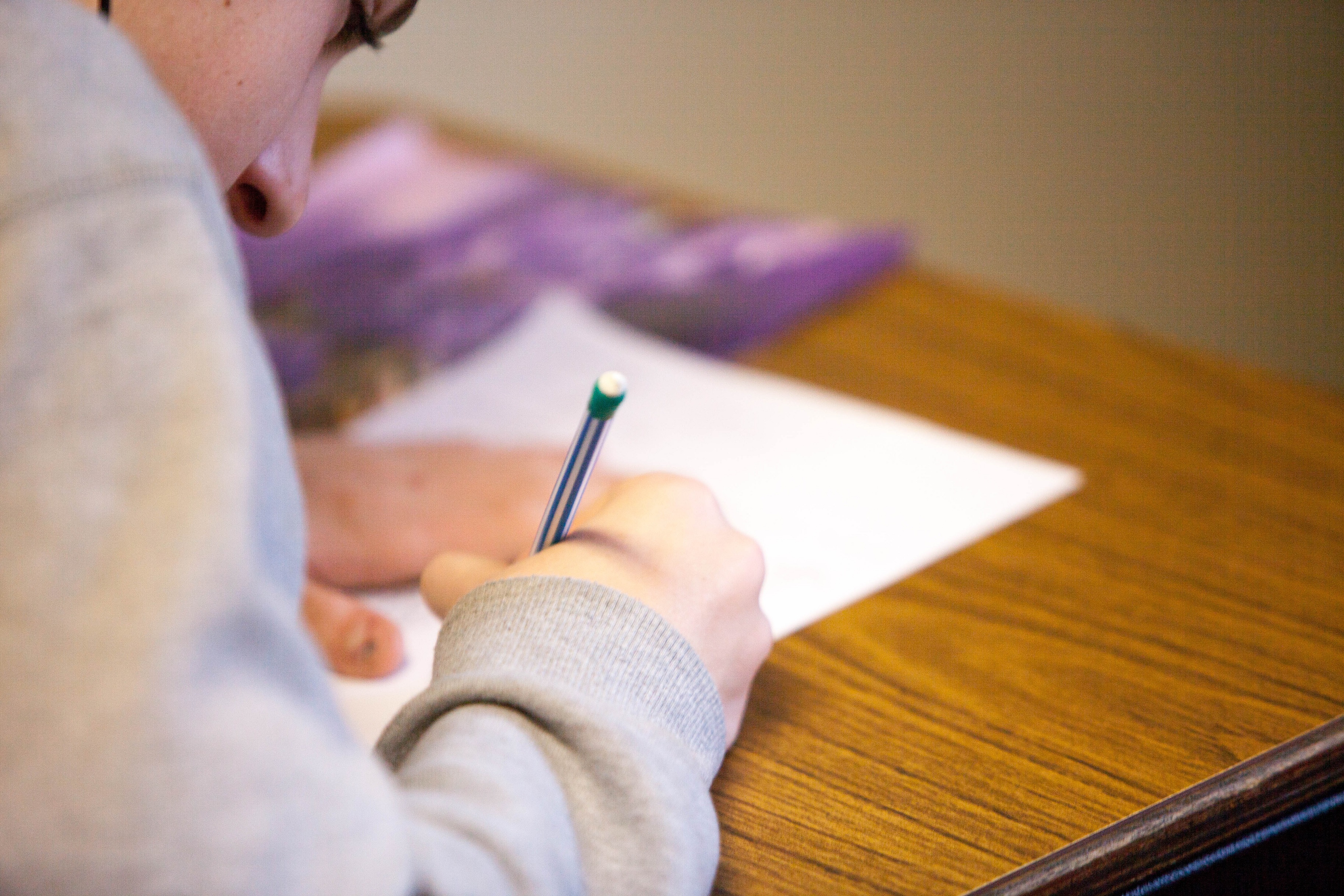学区は大切!と感じる保護者、地方でも増加傾向です。
これも、ネットの発達により親世代では一部の人しか知らなかったことが一般市民にも共有できるようになってきたからなのでしょう。
yahoo知恵袋で【学区 評判】【小学校 評判】と検索すると全国津々浦々の自治体のものにヒットします。
こちらのブログでも、過去に何回か取り上げたことがあります。

今回は年長~小学生の保護者向けに引っ越し先の学区選びのポイントについて書いていこうと思います。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
転勤族におすすめの基本エリア2つとNGエリア

転勤族の方は、子供が中学入学直前まで全国津々浦々に引っ越すことが多いと思います。
私の周囲でも、「子供の中学入学までは転勤についていく」という奥様が多いです。
中学入学後は、高校受験などが控えているのでそう簡単に引っ越し出来なくなります。
子供の高校卒業までは母子はその地にいる、またはどちらかの実家近くに越すという選択をする方も多いです。
さて、ここでは小学生までのお子さんを持つ転勤族におすすめのエリアを説明していこうと思います。
転勤族の方のほとんどが、地方都市に住むケースがほとんどだと思うので、地方都市に詳しい私が地方都市でおすすめのエリアの特徴を紹介していきます。
OK1.大企業・大学・国家公務員の社宅がある地域

大企業は都市銀行・地銀大手・証券会社・鉄道などの社宅、国家公務員の官舎がある地域は安定の学区です。
将来的に大都市圏の本社や本庁に戻るので、子供の教育に熱心な家庭がほとんどです。
出入りも激しいので、ドロドロっとした雰囲気もゼロ・笑。
ママ友の付き合いもサラッとできるメリットもあります。
旦那さんの肩書を気にするママさんもいるかもしれませんが、そういうタイプはスルーしましょう。
こういう地域には、ニーズがあるのでスポーツやピアノ、英会話や勉強系などの習い事教室も多いので送り迎えにも便利と言えます。
google mapで【宿舎 ○○大学】【官舎 or 社宅】とキーワードを入力して検索できます。
それをリサーチした上で、学区情報と照らし合わせてみるとかなり精度の高い情報を得られるはずです。
OK2.昔ながらの文教地区

私の生まれ故郷でも、昔ながらの文教地区があります。
そして、現在の住まいでもあり、そこの学区は教育熱激アツとして有名です。
落ち着いた環境で、習い事教室も多くあり小さいお子さんを持つ親としては住んでみたい街でもあります。
しか~し、不動産会社は文教地区の物件を高めに設定していることがほとんどなので会社から支給される家賃補助の金額と睨めっこする可能性が高いです・・・。
その条件をクリアすれば、おすすめのエリアと言えます。
文教地区と言うこともあり、他の子の成績を気にするママさんも存在すると思いますが、上手くかわしていきましょう・苦笑。
NG1.郊外の裕福層が住む宅地開発された住宅地

郊外の宅地開発された住宅地の中でも、建売ではない街は裕福層が住むので教育熱は高いです。
そういった地域にも、戸建ての賃貸(転勤などで貸し出すなど)がありますが、転勤族向けではありません・・・。
理由は3つあります。
- すでにママのネットワークが出来上がっていて入りにくい
- 戸建てが多く入れ替えがほとんどない→人間関係の構築に躓くと辛い
- 子供の成績や旦那の出世が自分の全てと考えるママがいる、はず
出入りの少ない街であるがゆえに、トラブルに巻き込まれる可能性が高まるので、私でしたら100%避けます・笑。
やはり王道は、【転勤族が多く教育熱が高い家庭が住んでいる街】ですね。
それでは次からは、具体的に学区の情報を得る方法を紹介していきます。
引っ越し先の学区の情報を探る4つの方法

年中~小学生の子供を持つ親が、転勤などによる引っ越し先選びで気にするのが学区です。
社宅があるなら、そこに入るしかありません。
完全に私の個人的感想ですが、地方都市にあるそれなりの企業や公務員系の社宅は安定学区に立地しているイメージがあります。
私が通った小学校も、その地域では安定の学区でした。
近所には某都市銀行の社宅があり、そこに住んでいる同級生と仲良くなりたまに遊びに行った記憶があります。
「3年おきに引っ越しをする」とその子から聞いたときは、驚きましたね~。当時の私はそんな世界があるのを知らなかったので・笑。
さて、ここでは具体的に安定学区を調べる4つの方法を紹介していきたいと思います。
1.ネットで検索する

今や王道の方法なのが、ネット検索です。
yahoo知恵袋で検索すると似たような質問がわんさかヒットします。
「○○市 小学校 文教地区」「○○市 小学校 おすすめ」とキーワードをなどで検索することです。
そうすると評判の小学校や学区がバァ~、と出てきます。
県庁所在地から人口NO.3位の街であればかなりの情報をゲットできるはずです。
2.不動産屋さんとタクシー運転手に聞く

地元の人の声を知りたい!、という時は不動産屋さんとタクシー運転手に聞くのがベストです。
不動産屋さんは、賃貸などを扱うのでその土地に精通しています。
環境の良い学区に関して熟知しているからです。
賃貸情報を見ていて【○○小学区】と目立つように押している物件は、人気学区がほとんどなので確認することをオススメします。
また、タクシー運転手も生きた情報を常に蓄積しており、転勤先の学区に関して聞いてみると特ダネを教えてくれるかもしれません。
立ち寄るコンビニで見かける学生の姿も目にするので、どういった雰囲気の生徒が多いのか不動産屋以上に詳しいといえます。
住んでいる層も把握しているので、物件探しの際はタクシーを使うこともいいアイデアです。
リアルな情報を知りたい時は不動産屋さんとタクシー運転手に聞いてみましょう。
3.会社の同僚・先輩・上司に相談する

会社の同僚・先輩・上司の中で、転勤先に住んだ経験のある人がいたら迷わず相談してみましょう。
信頼できる人の情報は、何よりも心強いものです。
「○○はネットで評判と書いてあるけど、実際は学力差が大きいよ」など住んだことのある人しか分からない情報を得られるかもしれません。
会社の人なら誰でもいい、という訳ではなく【教育熱が高めの人】に聞くことがポイントです。
子供の教育に無関心だと、そういった情報を把握していないと思うので優先順位は低いと言えます。
4.裏技・地域NO1、2の塾に問い合わせる

これは裏技ですが、転勤先で規模の大きい塾に問い合わせてみるのもおすすめです。
いきなり「学力高い学区」とストレートに聞くのも気が引ける場合は、遠回しに「転勤族が多い学区はどの辺りになりますか?」と聞いてみましょう。
塾の先生は教えることが好きなので、質問にしっかり答えるはずです。
もちろん、全員に当てはまるとは限りませんが・・・苦笑。
また、学区内の学習系の習い事教室の数もチェックしてく
ださい。
英会話教室、公文、学研、塾が多い地域は通っている生徒が多いので、そういった教育産業も進出していると考えて間違いはありません。
教育熱が高いので、教室数が多いのです。
まとめ
子供が乳幼児だったら、単に小児科が近い、スーパーが近くにあるという基準で住まい探しをします。
成長し、年中以上になるとどうしても学区を頭に入れながらの住居探しとなってしまうので、大変さが増していきます。
今ではネットという便利なツールがあるので、最大限に活かして転居先を探していきましょう!