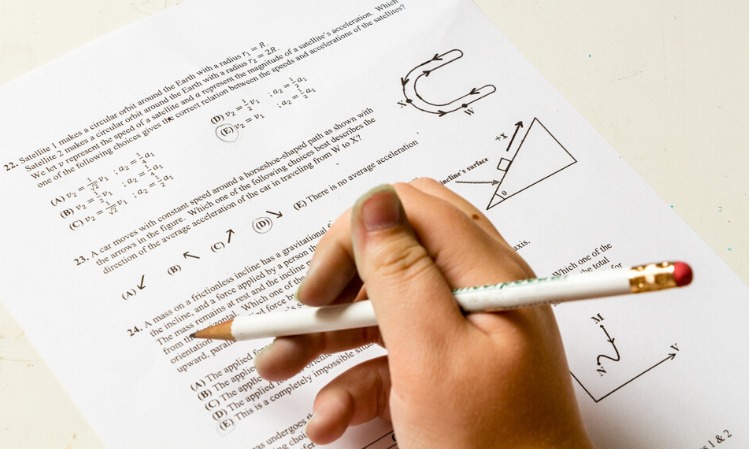今回は【中学で苦労しないために 小4の壁でつまずかないための学習計画】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子どもが小学校4年生になり、【授業の内容が急に難しくなった】【算数でつまずき始めた】と感じる方も増えてきます。
我が家でも、子ども①②③が全員【がい数】の単元のテストがいつもより悪いという思い出があります、3人でどのくらい取ったかという逆マウントをして話が盛り上がることもあるくらい、違った意味で思い出になっています。
小学校4年生、つまり10歳の時期は、通称【小4の壁】または【10歳の壁】と呼ばれ、子どもたちの学力に大きな差がつき始める時期です。
この壁をうまく乗り越えられるかどうかで、その後の学習成果、特に中学での成績が大きく左右されると言われています。
私も、グータラ小学生なので小学生時代の勉強での思い出というのはほぼないに等しいのですが、それでも、自分のことは棚に上げて【クラスのみんなの点数がなんだかばらけてきたな】と感じるようになったのが小学4年生だったというのは記憶しています。
それまで、家庭学習もしっかりやっていて高得点だと見せてくれた幼馴染の子が時折テストの点数を隠したり、すぐにランドセルにしまいこむことがあったのを覚えています。
ただ、なぜ、この時期が重要なのかと疑問に思う方もいることでしょう。
今も昔も、小学校4年生というのは学力の分岐点です。
小学校の低学年までは、足し算や引き算、ひらがなの書き取りなど、反復練習で身につく学習が中心でした。
しかし、4年生になると、分数や小数、図形、理科や社会といった抽象的な概念が増え、【暗記】から【思考】へと学習の質が変化します。
この変化に対応できるかどうかで、子どもたちの学習意欲や成績は大きく分かれていきます。
そこで今回は、なぜこの【小4の壁】が中学での苦労に繋がるのかを解説し、壁にぶつかった時の対策、そして中学進学で飛躍するための効果的な学習計画についてお伝えします。
なぜ中学での苦労は『小4の壁』が原因なのか
まず、【うちは中学受験をしないから、今ちょっとくらい成績が下がっても問題ないだろう】と思っている方は全国津々浦々にいると思います。
たしかに、受験を意識しないご家庭では、成績の一時的な停滞をそれほど気に留めない場合もあるでしょう。
しかし実際には、中学で勉強につまずいている生徒の多くが、小学4年生の時期に学習の壁にぶつかっているという傾向があります。
つまり、【小4の壁】を乗り越えられなかったことが、後の学力低下の引き金になっていることが少なくないのです。
この【壁】が中学での苦労に繋がる理由は、主に2つあります。
1つ目は、基礎学力の抜けがそのまま積み残されてしまうことです。
小学校の学習内容は、1年ごとに区切られているように見えて、実はすべてがつながっています。
たとえば、小4で学ぶ【小数】【分数】【角度】【面積】などの内容は、それ以前に学んだ計算や図形の理解があってこそ成り立ちます。
九九があやふやなまま割り算に進むと、分数の理解に大きな壁が立ちはだかります。
さらに5年生になると、【割合】【速さ】【単位量あたりの大きさ】など、複雑な単元が次々に登場し、理解が追いつかなくなります。
こうして生まれたわからないままの単元は、やがて中学で学ぶ数学の【文字式】【一次方程式】【関数】などの理解にも影響します。
同様に、理科での物理計算や化学的な単位変換など、抽象的で論理的な思考が求められる場面でも、小学校の知識が欠けていると深刻な足かせになります。
つまり、小4でできた【小さな穴】が、時間の経過とともに【大きな落とし穴】となって中学で現れるのです。
そして2つ目の理由は、子どもの【勉強に対する意識】が変わってしまうことです。
小4ごろは、ちょうど子どもの自我が強くなり始め、【できた・わかった】という達成感がやる気につながりやすい時期です。
ところが、ここで初めて【つまずき】や【できない経験】に直面すると、子どもの心には、【勉強=苦手なこと】【自分は頭が悪いのかもしれない】というネガティブな思い込みが芽生えます。
この思い込みが厄介なのは、勉強そのものに対する興味や意欲を奪ってしまう点です。
一度【勉強が嫌い】と感じてしまうと、自分から机に向かうことが少なくなり、親がどれだけ声をかけても反発されたり、無視されたりするようになります。
そしてそのまま中学へ進学すると、部活動や友人関係といった新しい生活リズムに忙しくなり、学習への優先順位はさらに下がります。
気づけば授業についていけず、定期テストでも点が取れなくなり、自己肯定感の低下へとつながってしまうのです。
では、この状況を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか?
まず大切なのは、【つまずきに気づいたときの対応】です。
テストの点数が下がったとき、親としては不安になり、【もっと勉強しなさい】【どうしてこんなミスをしたの?】と感情的に叱ってしまいがちです。
しかし、それでは子どものモチベーションは下がるばかりで、根本的な解決にはなりません。
むしろ、【どこで困っているのか】【なぜ理解できなかったのか】を一緒に探し、必要であれば学習方法そのものを見直すサポートが重要です。
【小4の壁】は、子どもが【考える力】を育てるための、ひとつの成長の段階です。
この時期のつまずきは、本人の努力不足ではなく、学び方の転換点にうまく対応できていないだけかもしれません。
焦らず、責めず、一緒に乗り越える姿勢が、子どもに安心感を与え、次への前向きなステップへとつながります。
小4の壁、10歳の壁でつまずいた時の3つの対応策
さて、子どもが【小4の壁】にぶつかった時、親としてどのように対応すればよいのでしょうか?
焦って難しい問題集を買ったり、長時間勉強させたりするのは逆効果です。
大切なのは、子どもがつまずいた原因を冷静に分析し、適切なサポートをすることです。
ここでは、つまずきを乗り越えるための効果的な対応策を3つご紹介します。
①基礎に立ち返る【リセット学習】
成績が下がると、【とにかく先に進まないと】と焦ってしまいがちです。
しかし、まずは一度立ち止まり、子どもがどこでつまずいているのかを把握することが何よりも重要です。
小4の内容が理解できないのは、小3や小2の学習内容に【抜け】がある場合がほとんどです。
算数: 小4で学ぶ分数や小数が理解できないなら、九九や割り算、繰り上がりのある足し算といった、基礎の基礎に戻って復習させましょう。
子どもの苦手な単元を特定し、その部分を集中的に復習する【リセット学習】を行うことで、自信を取り戻すことができます。
国語: 文章読解で苦戦しているなら、漢字や語彙、主語・述語といった文法の基礎を固めるドリルに取り組んでみましょう。
地道な作業ですが、この基礎固めがその後の読解力向上に直結します。
この【リセット学習】は、子どもの【わからない】という不安を取り除き、【自分にもできる】という成功体験を積み重ねる上で非常に重要です。
焦らず、子どものペースに合わせて進めましょう。
②勉強を【ゲーム】に変える工夫
この時期の子どもにとって、学習は【やらされるもの】と感じることが多いです。
そのため、モチベーションを維持するのが難しくなります。
そこで、勉強をゲームに変える工夫をしてみましょう。
ゲーム感覚を強めるには、目標達成を可視化するのがオススメです。
毎日10分間の計算練習で、正解した問題数に応じてシールを貼ったり、ポイントを貯めたりする【見える化】は効果的です。
目標を達成するたびに、子どもは達成感を感じ、次の学習への意欲が湧いてきます。
また、競争要素を取り入れるのも良いアイデアです。
漢字練習では、タイマーを使って【1分間で何個書けるか】を挑戦させるなど、ゲーム感覚で楽しんで学習に取り組めるように促します。
家族で競争するのも良いでしょう。
競争しながらの勉強にはご褒美が必要になることもあります。
ただし、【頑張った後】がポイントです。
勉強が終わった後に、好きなゲームやテレビを見る時間を用意するなど、ご褒美を設定することも有効です。
ただし、このご褒美は【勉強を頑張ったから】という文脈で与えることが重要です。
これらの工夫は、子どもが学習を【苦痛なもの】ではなく、【楽しいもの】と認識するきっかけになります。
③【過程】を褒める声かけ
結果(テストの点数)ばかりに注目すると、子どもは失敗を恐れるようになります。
大切なのは、【頑張った過程】を褒めることです。
テストで点数が悪くても、【最後まで諦めずに問題に取り組んだね】【この前できなかった問題ができるようになったね】といった声かけをしましょう。
努力を具体的に褒めることも忘れないでください。
【すごいね!】だけでなく、【この問題、粘り強く考えていたね】【今日の漢字練習はいつもより丁寧だね】など、具体的な努力に焦点を当てて褒めることで、子どもは自分の成長を実感しやすくなります。
間違いをポジティブに捉える: 間違えた問題に対しては、【いい間違いだね!どうしてこう考えたの?】と問いかけることで、子どもは間違いから学ぶことの重要性を理解します。
間違いは【失敗】ではなく、【成長のチャンス】であると伝えましょう。
これらの対応策は、すぐに効果が出ないかもしれません。
しかし、子どもの学習に対する【姿勢】を根本から変える上で、非常に重要なアプローチです。
中学進学で飛躍するために親子で力を入れたい3つのポイント
ところで、【小4の壁】を乗り越え、中学進学でさらに飛躍するためには、小学生のうちに何をすべきなのでしょうか。
ここでは、中学の学習にスムーズに移行し、スタートダッシュを切るために、親子で力を入れたい3つのポイントを具体的にご紹介します。
①英語の学習を始める
中学から始まる英語は、学習のスタートラインが全員同じです。
しかし、英語が苦手な子どもは小学校英語でも苦戦しますし、中学に入って英語が好きになることもないです。
しかも、それなりに出来ている子でも中学に入ってから挫折する子もいます。
そうならないために、小学生のうちから英語に触れる機会を作りましょう。
英語を【楽しいもの】と感じ、抵抗なく中学の授業に入れるようにすることが重要です。
無理に英会話教室に通うのではなく、YouTubeの子供向け英語チャンネルを見たり、ゲーム感覚で学べる英語学習アプリを利用したりするだけでも効果があります。
英語の歌を歌ったり、簡単な英語の絵本を読んだりすることで、自然と英語に親しめます。
そして中学英語では、リスニングが重要になってきます。
小学生のうちから、簡単な英語の音声を聞く習慣をつけましょう。
繰り返し聞くことで、英語の音に慣れ、スムーズに聞き取れるようになります。
中学に入ると本格的に始まる英文法や読解問題、英作文では単語を覚えることが不可欠です。
語彙はすべての英語学習の基礎となります。毎日5個ずつでもいいので、イラスト付きの単語帳やカードを使って、ゲーム感覚で単語を覚える練習を始めましょう。
②文章題・読解問題の教材を取り入れる
小4以降の学習で、多くの生徒が苦手とするのが【文章題】や【読解問題】です。
これは、算数や国語だけでなく、理科や社会の応用問題にも共通する課題です。
文章を正確に読み解き、筆者の意図や背景を理解する力は、すべての教科の基礎となります。
そうした読解力をつけていくには、読書の習慣化をして、読書の習慣をつけましょう。
子どもが興味のある本であれば、ジャンルは問いません。
漫画や雑誌でも構いません。
活字に触れる時間を増やすことで、自然と語彙力や読解力が身につきます。
そして、読んだ本や記事について、子どもに【この話で一番大切なことは何?】と尋ねてみましょう。
自分の言葉で内容をまとめる練習をすることで、文章の構造を理解し、要点を掴む力が養われます。
多くの子が苦手とする算数の文章題でつまずいたときは、問題文を声に出して読んだり、【何がわかっていて、何を求められているかな?】と問いかけたりすることで、問題の構造を理解させましょう。
③【学習計画】を親子で立てる習慣を
中学に入ると、学習内容が多岐にわたり、部活や行事で忙しくなります。
そのため、自ら計画を立てて学習する能力が求められます。
まず、【小さな目標】から始めるよう心がけてください。
週末に【今週は算数のこの単元を復習しよう】【国語の漢字を20個覚えたい】といったように、具体的な目標と計画を立てる練習をします。
無事、目標を達成したら、カレンダーにシールを貼ったり、親子でハイタッチしたりして、達成感を共有しましょう。
何かと忙しくなる中学生は勉強の中身も大切になります。
【30分勉強する】ではなく、【算数の宿題を終わらせる】【漢字を10個書く】といったように、やるべきことを具体的に決めるのがおすすめです。
終わりの見えない勉強は、子どもにとって苦痛になりがちです。
定期テストなどの勉強の計画性のニーズが急激に高まる中学進学に向けて、今から親子で学習計画を立てる練習をしていきましょう。
ただ、学習計画を考える際、子ども一人に任せるのではなく、親子で一緒に計画を立ててください。
子どもの意見を尊重し、【いつ、何を、どれくらいやるか】を話し合って決めることで、子どもは勉強に主体的に取り組めるようになります。
これらのポイントは、中学に入ってからの学習をスムーズにし、子どもが自信を持って取り組むための土台となります。
焦らず、子どものペースに合わせて取り組んでいきましょう。
学力は【才能】ではなく【習慣】で決まる
【小4の壁】は、すべての子どもが直面する可能性のある課題です。
しかし、この壁を乗り越えられるかどうかは、決して才能や生まれつきのものではありません。
大切なのは、この時期に【なぜつまずいたのか】を親が理解し、適切な対策を講じることです。
今回紹介した【基礎に立ち返る学習】【過程を褒める声かけ】【中学を見据えた学習計画】は、どれもいますぐ実践できることです。
これらの積み重ねが、子どもの学習能力を飛躍的に向上させ、中学での飛躍の大きな原動力となります。
子どもの成長を信じ、焦らず、時には一緒に楽しみながら、この大切な時期を乗り越えていきましょう。