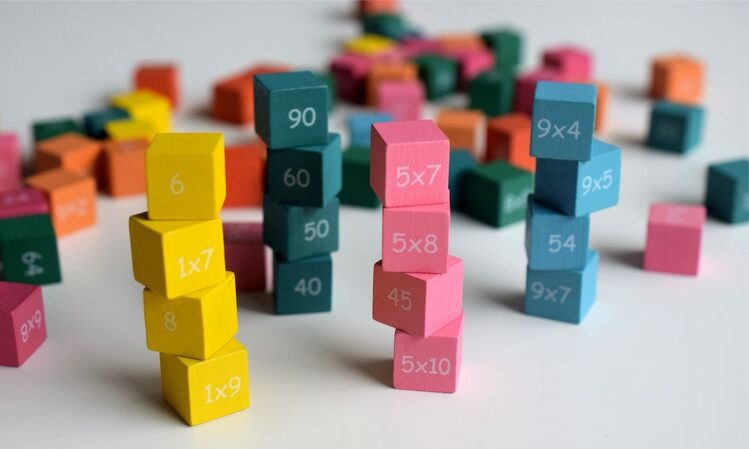今回は【家庭で実践! 子どもの学力差を乗り越えるコツ】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子育てをしていると、10歳頃、つまりは小学校4年生くらいから【学校のクラスでテストの点数差が出ているようだ】というのを感じるようになります。
再テストが行われたり、できる子とテストの結果が芳しくない子がハッキリしてきます。
それを10歳の壁、小4の壁と言われていますが、親としては遅かれ早かれやってくる子どもたちの間で出来上がってくる学力差を何とか乗り越えたいという気持ちを持つと思います。
塾や家庭教師、通信教材の力を借りる家庭もありますが、家庭で乗り越えることも可能です。
家庭で子どもの学力差を乗り越えるには親子の連係プレーが大切なため、【大変だったけれど乗り越えた】という経験は、上手くいけば学業だけでなく子どもの精神面でもプラスになり、将来の自信や社会性にも大きな影響を与えます。
その一方で、学力差を放置すると、子どもは自己肯定感を失い、勉強への意欲が低下してしまう可能性があります。
とくに、小学生時代は基礎学力を身につける大切な時期であり、学力差が広がると、今後の学習にも影響が及びます。
家庭で適切なサポートをすることで、子どもは自分のペースで学び、自信を持ちながら成長できます。
また、家庭は子どもにとって最も安心できる場所であり、親が積極的に学力差を乗り越えるというなかなか大変な状況に適切に関わり、サポートをすることで学習への前向きな態度を育むことができます。
学力の向上は、単にテストの点数を上げるだけでなく、自己管理能力や問題解決能力、忍耐力など、将来に役立つスキルも養うことにつながります。
家庭での学習サポートは、子どもが自分の可能性を信じ、学び続ける力を育む最初のステップとなります。
そこで今回は、家庭で実践できる子どもの学力差を乗り越えるコツをご紹介していきます。
親に質問しやすい雰囲気を作る
まず、小学生が学力差を乗り越えるために、家庭で【親に質問しやすい雰囲気を作ること】を意識して作っていきましょう。
子どもが家庭で質問しやすい環境にいると、学ぶことに対してポジティブな姿勢を持つようになります。【わからないことがあっても質問していい】という安心感があると、疑問に思ったことをすぐに解決しようとする姿勢が育ちます。
小学生の頃から、わからないことをそのままにせず、積極的に学ぶ習慣が身につきます。
結果として、学力の向上が促され、学びに対するモチベーションも高まります。
その一方で、わからないことをそのままにしておくと、後々理解が深まらず、勉強がどんどん難しく感じるようになります。
これは、私も塾で【質問をしない子】を指導していて強く感じましたが、質問するかしないかで、単元の理解度、勉強に対するモチベーションも違いました。
もはや、成績を上げたいのであれば、【質問する】の選択肢しかないのでは、と思うくらいの違いがありました。
ですから、家庭で質問しやすい環境があれば、すぐにその場で疑問を解決できるため、誤解が積み重なる前に早期に解決できます。
例えば、算数や国語の問題でつまずいた場合、親に質問することで、問題の本質や解き方の考え方をクリアにし、次のステップに進む際に不安を感じることなく学習を進められます。
この早期解決は、学力差を縮めるために非常に効果的です。
質問しやすい雰囲気があれば、子どもは授業内容の疑問をその都度解消できるため、学習内容の理解が深まります。
【わからない】と思ったことをその場で聞くことで、授業が終わる前に自分の中で疑問を解決でき、学習内容をしっかりと自分のものにできます。
これが繰り返されることで、学力が着実に向上します。
そして、私も子育てをしていて感じますが、学力差を乗り越えるためには、自己肯定感を高めることが不可欠です。
質問しやすい雰囲気が作られている家庭では、子どもは自分の疑問や不安を自由に話せるため、自分の理解度に自信を持つことができます。
もし間違った答えを出しても、【間違えても大丈夫、次にどうすればいいか一緒に考えよう】というポジティブな対応をしてもらえると、失敗を恐れずに挑戦できるようになります。
自己肯定感が高まることで、学習だけでなく、その他の活動にも前向きな姿勢が生まれ、総合的に成長します。
親に質問しやすい雰囲気ができると、学習面だけでなく、親子のコミュニケーションが深まります。
日々の学習の中で親が関わることで、子どもは自分が大切にされていると感じ、信頼関係が築かれます。
この信頼関係は学習だけでなく、子どもの成長全般に良い影響を与えることになります。
また、親子のコミュニケーションが頻繁に行われることで、子どもは他の問題にも質問しやすくなり、家庭内での相談がスムーズできるようになります。
質問をしやすい環境は、学習面だけでなく、子どもの自己肯定感や親子の関係にも良い影響を与え、成長を促進する強力なサポートとなります。
応用力を鍛える教材を取り入れる
さて、家庭学習で【応用力を鍛える教材】を取り入れることも小学生が学力差を乗り越えるためには非常に効果的です。
応用力を鍛える教材は、単純な計算や暗記だけで解ける問題ではなく、条件の整理や複数の手順を必要とする問題が中心です。
こうした問題に日常的に取り組むことで、子どもは【どう考えたらいいか】を意識しながら学習するようになります。
考える習慣がつくと、難しい問題に出会ってもあきらめずに向き合う力が身につきます。
基礎問題だけでは、表面的な知識の習得にとどまることがありますが、応用問題では、知識をどう使うかという【活用力】が求められます。
応用教材に取り組むことで、習った知識をどう組み合わせればよいのかを体験的に学べるため、知識の定着が深まります。
これが本当の「理解」であり、学力の土台をしっかりと築くことにつながります。
学力差は、「基礎ができていない」だけでなく、【応用的な思考ができない】ことでも生まれます。
応用教材は、思考過程を意識する構成になっているものが多く、問題文をどう読むか、どの情報を使うか、といった、考え方のトレーニングにもなります。
これにより、根本的な理解力や読解力を高めることができ、学力差を埋めるための力強い支えとなります。
応用問題は難しい分、解けたときの達成感も大きく、子どもにとって【自分でもできた!】という自信になります。
この成功体験が積み重なると、学習に対する前向きな気持ちが育ち、【もっとやってみよう】【次はこうしてみよう】といった自主性にもつながります。
学力差があっても応用問題を少しずつ解けるようになることで、自分の成長を実感しやすくなります。
合否を決める応用問題が解ける力が身についているということは、入試においても大きな強みになります。
中学受験や高校受験、さらには大学入試においても、単純な知識だけでは太刀打ちできません。
文章を読んで情報を整理し、論理的に解答を導く力、つまり応用力が重視されます。
小学生のうちからその力を意識して育てておくことで、進級進学して難化する学びにスムーズに対応できる力を身につけることができます。
計画的な学習時間の確保
ところで、家庭で計画的な学習時間を確保して勉強に励まないと、遅かれ早かれくる学力差を乗り越えるのは難しくなります。
計画的な学習時間の確保は学習内容の理解を深めるだけでなく、習慣化・時間管理能力の向上にも影響し、長期的に安定した学力向上を支えるベースとなります。
学力差を縮めるためは、いかに【継続的な学習】ができるかどうかがカギを握っています。
毎日決まった時間に学ぶ習慣があることで、勉強が特別なことではなく、日常生活の一部となります。
たとえ短い時間でも、毎日繰り返すことで知識が自然と定着し、忘れにくくなります。
反対に、勉強が不定期だと、理解が浅くなりがちで、学力差がさらに広がる原因になってしまいます。
計画的に学習時間を確保することで、【復習】【予習】【問題を解く】など、目的に応じた学習ができます。
特に復習は、知識を定着させる上で非常に重要です。
授業で習った内容を家庭で再確認することで、理解が深まり、苦手な部分に気づきやすくなります。
こうして学びを重ねることで、表面的な理解ではなくさらに学力がパワーアップし、【応用力】が身についていきます。
計画的に少しずつ学ぶことで【できた!】という体験が積み重なり、自信へとつながります。
学力差がある子どもは、【どうせできない】と感じがちになるので、そういう気持ちにならないよう回避することができます。
自信を持てば、次の学習にも前向きになれ、自然と苦手意識も減っていきます。
塾で教えていても、そして子ども①②③を見ていても、子どもが勉強をするかしないかは気持ちの持ちよう次第だと強く感じています。
学力を伸ばすには、子どもの心理面も考慮して学習計画、どうやって学習を継続させていき力をつけていくかといったことも考えていかないといけません。
そして、計画的に決められた時間に集中して勉強する習慣が身につくと、短時間でも効率的に学べるようになります。
ダラダラ勉強するのではなく、【この30分は本気でやる】とメリハリをつけた学習ができれば、理解も深まり、学習効率もアップします。
中学生となり、部活動が始まると、このメリハリがないと勉強との両立が上手くいかないので、小学生の頃から【勉強に集中する時間】【メリハリをつけて勉強する】を身につけることは大きなメリットになります。
計画的な学習時間の確保は、小学生が学力差を乗り越えるうえで欠かせないポイントです。
学習の習慣化、知識の定着、時間管理能力の向上、そして何より「できた」という自信の積み重ねが、子どもの学びを支える力になります。
無理のない範囲で、毎日の生活の中に学習の時間を組み込み、継続できる環境を整え、サポートを心がけてください。