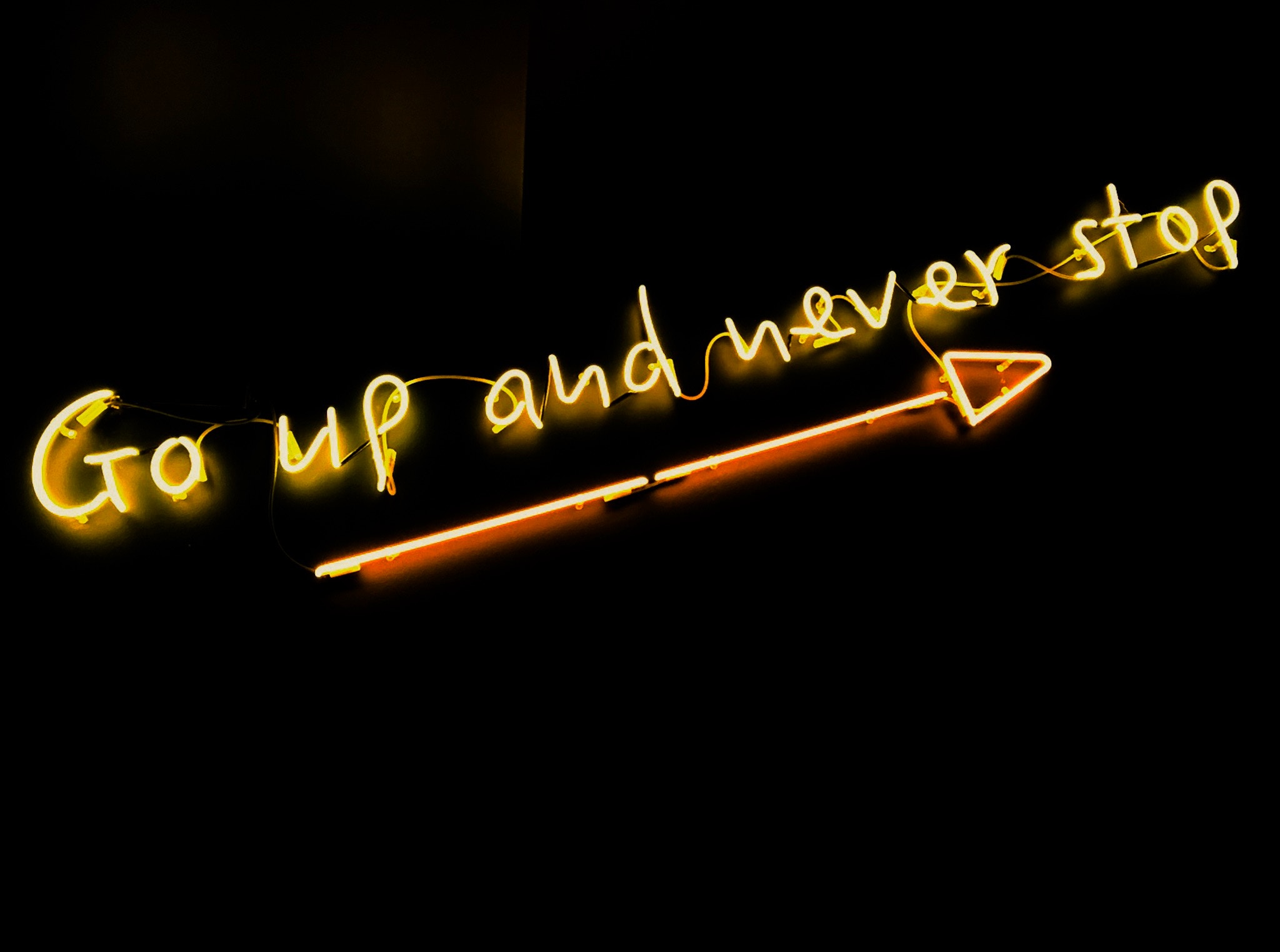今回は【優等生でも伸びる子と伸びなくなる子の分岐点】と題し、お話していきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子育てをしている中で勉強の悩みというのはどんどん大きなものになっていきます。
学力差がで始めるというのは案外早いタイミングですが、その中でも小学校や中学校で成績上位を維持している我が子を見ると、親としては安心感があります。
しかし同時に、【このまま順調にいけるのだろうか?】という不安を感じている方も少なくありません。
実際に【小4の壁】【中1の壁】と呼ばれるタイミングでは、それまで優秀だった子が突然失速するケースが多く見られます。
私も同級生や塾で出会った子どもたちの中に、伸びが鈍化してしまった子が一定数いたのを覚えています。
真面目に勉強はしているけれど、差が出てしまうのは不思議なことです。
けれど、伸びるかどうかという差を生むのは、才能や地頭ではありません。
むしろ、【優等生】という評価に安心してしまう心理と、学びの姿勢を点数基準から思考基準へと切り替えられるかどうかが分岐点になります。
そこで今回は、優等生であっても伸びる子と伸びなくなる子がいる不思議さを取り上げていきます。
最初に【伸びなくなる優等生】の特徴を分析し、次いで【伸び続ける優等生】の共通習慣を紹介します。
そして最後に親が意識すべき成長の分岐点での関わり方を具体的に整理します。
【優等生を維持する】から【真に伸びる子へ】。
その変化を促すのは、親の視点と関わり方のちょっとした転換です。
なぜ失速?【伸びなくなる優等生】の3つの特徴
まず、小学校や中学校で上位を保っている子どもを見ると、【この子は安心】と思いたくなるのが親心です。
しかし、学年が上がるにつれて、思わぬ形で失速してしまう優等生の壁は多くの家庭で見られます。
それは単純に学力が足りないからではありません。
むしろ【優等生】という成功体験が、子ども自身の中に変化を受け入れにくくする心理を生み出してしまうのです。
小学校までは、授業をしっかり聞き、丁寧にノートを書き、テストで間違いなく正解を出せる子が高く評価されます。
けれども中学以降は、答えにたどり着くまでの【考え方】【根拠の説明】が重視されるようになります。
つまり、学びの質が問われるようになるのです。
この切り替えがうまくいかないと、【努力しているのに伸びない】【突然成績が落ちた】という現象が起きます。
ここでは、その原因となる3つの特徴、①正解志向の強さ、②努力の固定化、③承認依存について見ていきましょう。
特徴①正解志向が強すぎて思考が止まる
【間違えたくない】【完璧でいたい】。
優等生タイプの子ほど、この思いが強くなります。
親が気がつかなくても、自分で自分を苦しい立場に追い込んでしまっている優等生はけっこういます。
テストで高得点を取ることが自分のアイデンティティになっているため、間違うことや分からないことを恐れてしまいます。
悪い点数を取ると親から叱られるという気持ちが日増しに大きくなり、【間違えるのが怖い】【分からない問題は解きたくない】という考えが強まります。
小学校では再現型の問題が中心で、正確さがそのまま成果につながります。
しかし中学以降は、思考の筋道や自分の考えを表現する力が問われ、【分からない】ときにどう立ち向かうかが成長のカギになります。
ところが、正解志向が強すぎると、【間違うくらいならやらない】【分からない問題には手を出さない】といった挑戦回避の傾向が出てしまいます。
この段階で思考の幅が狭まり、応用力が育ちにくくなるのです。
そして、定期テストでの校内順位が小学生時代の立ち位置とはマッチしないものになってしまうのです。
こうした状況は避けたいところです。
親としてできるサポートは、【正解】ではなく【思考のプロセス】を褒めること。
たとえば、【その考え方、面白いね】【どうしてそう思ったの?】と聞くことで、子どもは考えること自体に価値を見出し始めます。
優等生が失速するか、伸び続けるか、という分かれ目は、間違いとの付き合い方にあります。
特徴②努力の方向が固定化してしまう
優等生に共通する長所のひとつは、努力を惜しまないことです。
しかし、その努力が【正しい方向】に向いていなければ、どれだけ時間をかけても成果が上がらなくなります。
多くの子が陥るのは、【これまでのやり方に固執する】ことです。
たとえば、【ノートをきれいに書けば安心】【宿題を完璧に仕上げれば満点が取れる】といった、形式的な努力にとどまってしまうのです。
学年が上がると、求められる力は【整理】から【思考】へと変化します。
つまり、学びの本質が【覚える】から【使う】へと移るのです。
にもかかわらず、過去の成功体験に縛られると、新しい勉強法やアプローチを拒み、成績が伸び悩むようになります。
私も、塾で成績が伸び悩んでいる子に【こういう勉強法を取り入れてみよう】と提案しても、それを受け入れてくれない子に出会ったことがあります。
なかなか時間がかかりますが、従来の学びを少し変えていくよう。親が【やり方を変えてみよう】と促すサポートというのはかなり重要なポイントになります。
結果ではなく、方法の柔軟性を褒めることで、子どもは【変えること=前進】と感じられるようになります。
努力量から努力の質へ。
この転換が、優等生が次のステージに進むカギです。
特徴③承認依存が強く自発性が育たない
優等生の中には先生や親の評価に敏感な子がいます。
【先生に褒められたい】【親にすごいと言われたい】という気持ちが、勉強のモチベーションの大部分を占めているケースが多くあります。
この承認欲求は、初期の努力を支える大切なエネルギーになります。
しかし、それが唯一の原動力になると、成績が下がった途端にモチベーションが急落します。
外からの評価に依存しているため、自分の内側から学び続ける力が育ちにくいのです。
特に中学以降は、課題の難易度が上がり、結果がすぐに出ないことも多くなります。
こうなると、【難しい単元に立ち向かう気力】がない子は成績が頭打ちになるのも時間の問題です。
思うような点数が取れないたびに【もうダメかも】と感じてしまう子は、精神的な消耗が激しく、本来の力を十分に発揮できなくなってしまうのです。
親が意識すべきは、【結果に対する評価】よりも【挑戦そのもの】を認めること。
たとえば、【そこまで考えたのはすごい】【時間をかけて工夫したね】といった言葉が、
子どもの内的動機づけを刺激します。
優等生が本当に伸びるためには、【褒められるための勉強】から【自分のための学び】へと、モチベーションの軸を移す必要があるのです。
なぜ伸びる?【伸び続ける優等生】の3つの習慣
さて、【優等生だったのに伸び悩む子】と【さらに伸びる子】の違いは、勉強時間の長さでも、もともとの頭の良さでもありません。
決定的な違いは、学びの姿勢が変化に対応できるかどうかです。
学年が上がるほど、教科内容は複雑になり、答えが一つではない問題が増えます。
単なる暗記では通用せず、【なぜそうなるのか】【どう使うのか】を考える力が求められます。
このときに、伸び続ける子は、勉強を作業としてではなく、思考の訓練として捉えています。
つまり、伸びる優等生は【間違い】【説明】【探究】をうまく使いこなす子です。
具体的には、①失敗を分析し、次につなげる【振り返りの習慣】、②自分の考えを言葉で整理する【説明の習慣】、③知的好奇心を自分で広げていく【自走の習慣】です。
この3つを持つ子は、壁を越えて学ぶ楽しさを維持できます。
それぞれの特徴と、家庭でのサポート法を見ていきましょう。
習慣①【間違いノート】で失敗を素材化する力
伸びる優等生の第一の特徴は、間違いを恐れず、活用する姿勢を持っていることです。
彼らはテストの失点や失敗を【自分の欠点】ではなく、【次の成長材料】として扱います。
たとえば、テスト後に【間違いノート】をつくり、どんな問題でどんな思考ミスをしたのかを整理しておく。
これを定期的に見返すことで、自分の思考パターンを客観的に理解できるようになります。
この【自己分析】の力こそが、学びを持続的に成長へ導く土台です。
逆に、間違いを避け続ける子は、伸びしろを失っていきます。
完璧ではなく未完成を受け入れる姿勢が、次のステップを生み出すのです。
親のサポートとしては、テストの点数よりも【分析の深さ】を褒めること。
【今回はどんな発見があった?】【次はどう直せそう?】と問いかけるだけで、
子どもは考える学びを意識できます。
間違いを恥じるか、素材にするか。
この違いが、伸び続ける優等生と止まってしまう優等生を分ける分岐点です。
習慣②【説明する力】で理解を再構築する
伸びる子ほど、【説明する】習慣を持っています。
自分の理解を他人に言葉で伝えようとすることで、頭の中の知識が整理され、論理的な構造として定着します。
家庭で【今日の授業で一番おもしろかったことを教えて】と聞くだけでも十分です。
その一問一答の中で、子どもは自分の言葉で知識を再構築していきます。
単なる暗記や模倣ではなく、【どうしてそうなるのか】を説明する過程にこそ、本当の理解が宿ります。
さらに、説明する力はすべての教科に応用できます。
国語では読解の根拠を、算数・数学では解法の筋道を、理科では現象の因果関係を。
この【言葉にする力】が鍛えられれば、どんな教科も論理的に理解できるようになります。
親ができるのは、【すぐ答えを教えない】こと。
代わりに【どう思う?】【なぜそうなると思う?】と投げかけ、子ども自身の説明を引き出すことが大切です。
説明する学びは、理解を再構築する学び。
その積み重ねが、壁を越える思考力を育てていきます。
習慣③【自分で課題をつくる】自走型の学び方
本当に伸びる優等生は、【与えられた課題】だけで満足しません。
【もっと深く知りたい】【自分で調べてみよう】と、学びを自分のテーマに変えていく力を持っています。
これは単なる好奇心ではなく、自走力と呼ばれる能力です。
授業や宿題がきっかけとなり、【これって本当はどうなんだろう】と自分で問いを立てる。
この問いを生む力が、思考の深度を一段引き上げるのです。
具体的には、調べ学習・自主研究・読書メモなどを通じて、【自分で決めて学ぶ】経験を増やすのが効果的です。
自分で立てたテーマに取り組むことで、学びは【義務】から【探究】へと変わります。
親の役割は、方向づけではなく支援です。
【それを調べてみようか】【どうやって探す?】と伴走することで、子どもの中に自分の学びを自分で動かす力が芽生えます。
受け身の優等生から、自走する子へ。
この変化を起こせた子は、どんな壁にも柔軟に対応できるようになります。
運命の【分岐点】と親がすべき3つの戦略
ところで、子どもの成績の伸びは、実は親の関わり方で大きく変わります。
特に【優等生タイプ】の子どもは、努力家で素直である一方、繊細で変化に弱いという面も持ち合わせています。
このタイプの子は、学びの壁に直面したときに、【もう自分には無理なのかもしれない】と自己否定に陥りやすい。
そんなときに、親がかける言葉や行動が、その後の進路や学習意欲を左右する分岐点になるのです。
親がやるべきことは、子どもを管理することではありません。
【見守る】と【導く】の間で、最適な距離感を保つことです。
つまり、子どもが自分で成長を選べる環境を設計することが、親の戦略になります。
ここでは、優等生が失速しないために、家庭でできる3つの具体的な戦略、①【目標設定】を子どもと共有する、②【努力のプロセス】を見える化する、③【親の期待】を再設計する、を紹介します。
戦略①【目標設定】を共有し主体性を引き出す
伸びる子の親は、【目標】を一方的に与えません。
一緒に考え、納得して決めることで、子ども自身がその目標を【自分ごと】として捉えられるように導いています。
多くの優等生は、親や先生の期待に応えようとするあまり、自分のための学びを見失ってしまいがちです。
だからこそ、親が【何のために頑張るのか】を一緒に言語化することが大切です。
たとえば、【この学校に行きたい】よりも【こんな環境で学びたい】【この分野をもっと深めたい】と、
興味や価値観を基準に目標を立てると、モチベーションは長続きします。
親の役割は、目標を設定するリーダーではなく、ナビゲーター。
【あなたはどう思う?】【どんな未来を選びたい?】と問いかけることで、
子どもの主体性が引き出されます。
与えられた目標ではなく、一緒に作った目標こそ、
優等生を伸ばす最強のエンジンになるのです。
戦略②【努力のプロセス】を見える化し、継続力を育てる
多くの子が勉強を続けられなくなる理由は、【頑張っているのに成果が見えない】からです。
だからこそ、努力のプロセスを見える化する工夫が必要です。
具体的には、1日の学習内容や振り返りを記録する【学びジャーナル】や、テストの分析シートなどが有効です。
【やった・できた】を客観的に可視化することで、子ども自身が成長している実感を得られるようになります。
さらに、親が【昨日より一歩進んだね】【この工夫はよかった】と、プロセスそのものに言及して褒めることが大切です。
これにより、子どもは結果依存型ではなく、成長実感型の学び方に変わります。
また、計画と振り返りをセットにする習慣を作れば、中学・高校・大学と進む中でも、自律的な学習サイクルを維持できます。
努力の価値を点数ではなくプロセスに見出せる子ほど、壁を乗り越えて、長く伸び続けるのです。
戦略③【親の期待】を再設計し精神的な安全基地をつくる
最後の分岐点は、親の【期待のかけ方】です。
優等生の多くは、無意識に親の期待を背負っています。
【頑張らなきゃ】【失望されたくない】と感じることで、モチベーションが恐れに変わってしまうことがあります。
ここで大切なのは、【結果を出すこと】より【挑戦を続けること】を評価軸にすることです。
親が【点数より過程を見ている】【失敗しても信じている】という姿勢を示すと、子どもは安心して次の挑戦に踏み出せます。
また、親自身が【完璧な結果を求めない姿勢】を見せることも効果的です。
【間違っても大丈夫】【挑戦できたことが価値】と言葉にするだけで、家庭が安全基地になります。
子どもが安心してリスクを取れる環境は、学びの成長を何倍にも加速させます。
優等生を守るだけの関わりではなく、信じて任せる関わりへ。
それが、分岐点を【飛躍のきっかけ】に変える親の最大の戦略なのです。
【優等生の壁】は親子で越えられる成長のチャンス
【優等生の壁】と聞くと、どこか避けたいもののように感じるかもしれません。
しかし実際には、それは成長の限界ではなく、【次の学び方】に進化するための通過点にすぎません。
最初にお伝えしたように、伸びなくなる優等生は、【間違いを恐れる】【努力を変えられない】【評価に依存する】といった成功体験の固定化にとらわれがちです。
それは一見まじめで良い姿勢に見えますが、変化の時代では成長の足かせになります。
一方、次に紹介した【伸び続ける優等生】は、間違いを学びに変え、説明を通じて理解を深め、自分で課題をつくりながら学びを楽しむという、自走力を持つ子どもたちでした。
彼らに共通するのは、【学びを自分のものにしている】ことです。
そして最後に示したように、その分岐点を左右するのは親の関わり方になります。
子どもと目標を共有し、努力のプロセスを可視化し、結果ではなく挑戦を信じる親の姿勢こそが、優等生を次のステージへ導く最大の力になります。
優等生の壁は、【できる子】だからこそ訪れる課題です。
しかし、それを乗り越えた先には、自ら学び、挑戦し続ける大人への成長が待っています。
親が焦らず、信じて、共に考えること。
それこそが、優等生を真の学び手に変える最強のサポートなのです。