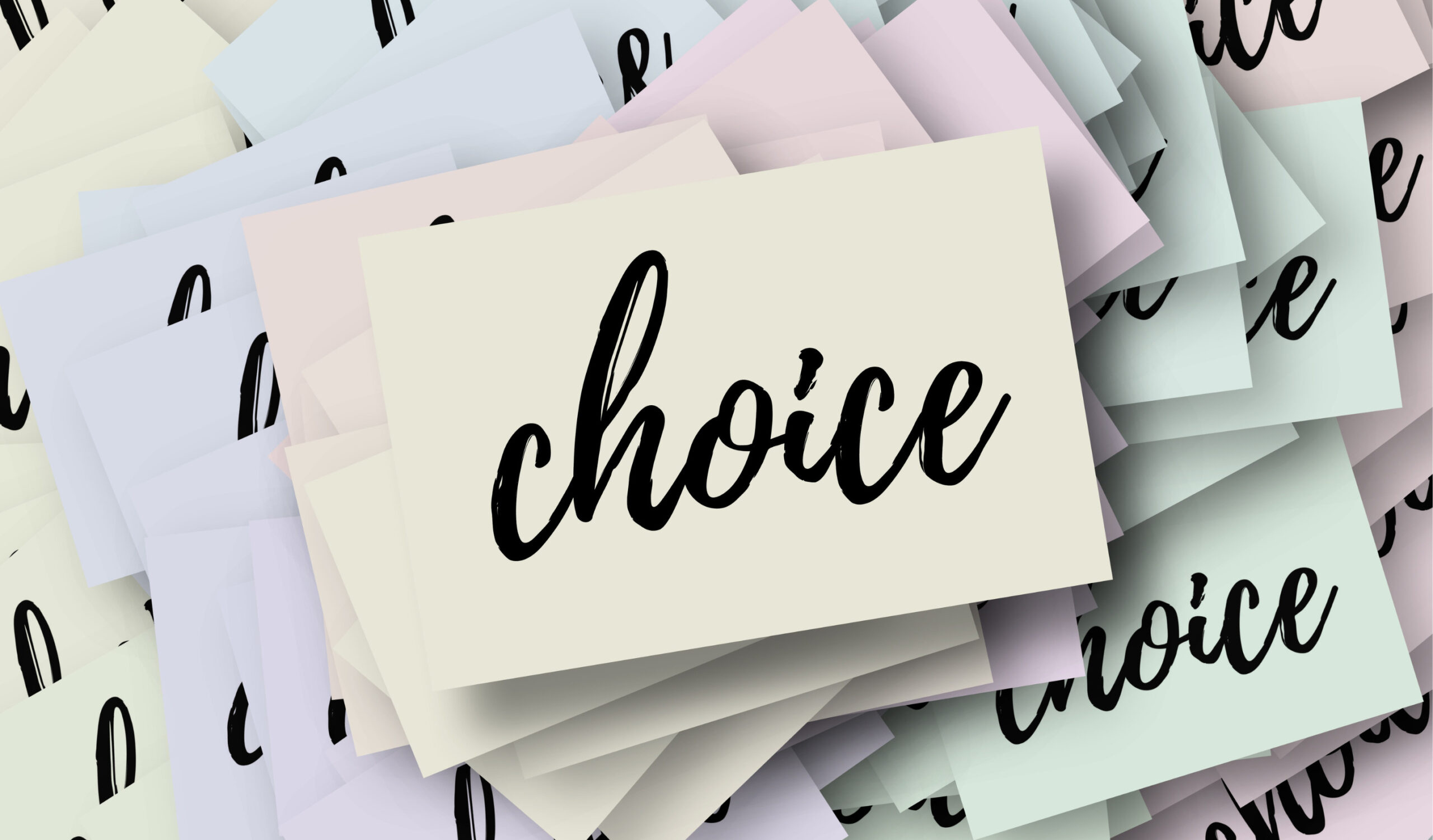今回は【学力の差がつく子・つかない子の決定的な違い3選】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子どもの学力差は、中学や高校でつくと思われがちですが、実際には小学校の中学年、特に10歳前後からはっきり表れはじめます。
私も塾で仕事をしている時に感じましたし、実際に3人の子どもたちを育てている中で色々と見聞して【10歳から学力差が目立ってくる】という話は本当だな、と痛感しています。
しかも、10歳の壁、小4の壁は単にテストの点数だけで語るレベルではなく、思考力・理解力・学習姿勢など、目に見えにくい部分でも【学ぶ力の差】が広がっていきます。
そしてこの差は、特別な才能の有無よりも、家庭での過ごし方や学習への向き合い方によって生まれることが多いです。
つまり、誰でも学力がつく子になる可能性を秘めているということになります。
逆に、正しいサポートがないと、努力してもなかなか伸びない、親が教育熱心でも思うような結果が出ない、という状況に陥ることもあります。
そこで今回では、【学力差をつける子は何が違うのか】【差がつかない子の特徴とその回避法】【中学でも上位を維持するための教科別対策】という3つのテーマに分けて、具体的なポイントを解説していきます。
小学生のうちに気づき、対策することで、学力は大きく伸びていきます。
今日からできる一歩を一緒に探っていきましょう。
学力差をつける子は何が違うのか
まず、子どもが4年生くらいになると、様々なことからクラスの中で学力差が生まれてきているというのを感じる機会が増えてきます。
テストの点数だけでなく、挙手の回数、話す内容、言動などあらゆる面で【あの子は賢い子】と見られる子もいれば、勉強が苦手な子、勉強していない子、というのも同じように認識されるようになります。
同じ教科書、同じ授業を受けているのに、【理解が早い子】と【なかなかついていけない子】の差はどんどん広がっていきます。
この学力差は、子ども本来の学力スキルの違いだけでなく、学校や家庭での学びに対する取り組み方や家庭学習の有無などから生まれている場合がほとんどです。
とくに小学校中学年以降は、授業内容が抽象的になり、自分の力で理解・整理する力が求められます。
このとき、学力の高い子は【勉強のコツ】を無意識に身につけており、それが結果として差となって表れます。
実は、学力差をつけていく子にはいくつかの共通した特徴があります。
大きな努力をしているように見えなくても、【学び方】や【取り組み方】が的確であるため、少しの努力でも効果的に力を伸ばしているのです。
ここでは、学力が高い子どもに共通する3つの特徴を紹介します。
それぞれ、小学生のうちから身につけることができる要素ばかりです。
自分のお子さんに足りている部分・足りない部分を見直しながら、日々の学びに活かしてみてください。
特徴① わからないことを放置しない
学力を伸ばす子の第一の特徴は、【わからないままにしない】姿勢を持っていることです。
授業中にわからなかったことをそのままにせず、自分で教科書を読み直す、先生や親に質問する、ノートを見返すなど、何らかの行動をとります。
この【疑問を解決する力】は、自然に身につくものではなく、幼い頃からの習慣が土台になっています。
わからないことに出会ったとき、【どうせできない】とあきらめるのではなく、【なんとかして理解したい】という気持ちが、理解力や思考力の差につながっていきます。
特に小学生の段階では、【わからないのは悪いことではない】と伝えることが大切です。
親が【よく気づいたね】【いい質問だね】と声をかけることで、子どもは安心して質問できるようになります。
学びの成長は、間違いや疑問の中にあります。
放置せず、1つずつ解決していく姿勢が、確かな学力へとつながっていくのです。
特徴② 間違いから学べる
学力が高い子の多くは、間違いを【失敗】ではなく【学びのチャンス】と捉えています。
テストで×がついても落ち込まず、【なぜ間違えたのか】【どうすれば次は解けるか】を冷静に考えることができます。
このような子は、ただ丸つけをして終わりにせず、ノートに間違えた理由や正しい解き方を書いたり、苦手な問題を繰り返し解いたりと、次に活かす工夫をしています。
こうした取り組みが、着実な成長へとつながっているのです。
一方、間違いを恥ずかしいと感じたり、指摘されることに過敏になる子は、間違いから目を背けがちです。
親としては、まず【間違えても大丈夫】という安心感を与え、【次に活かせるね】と前向きな声かけを意識することが重要です。
間違えること自体は問題ではありません。
そこからどう学ぶかが、成績の伸びを大きく左右します。
家庭での声かけ一つで、子どもの受け止め方は変わっていきます。
特徴③ 学びに前向きで、自分から動ける
学力差がつく子どもの3つ目の特徴は、【学びに前向きで、自分から動ける】という点です。
【もっと知りたい】【やってみたい】という好奇心が強く、自ら学ぼうとする気持ちを育てていきます。
このような子は、宿題だけでなく、自主的に調べたり、問題集に挑戦したりと、自分から学習に取り組むことができます。
その根底にあるのは、【学ぶこと=楽しい】【わかると嬉しい】というポジティブな感情です。
では、こうした前向きさはどう育てるのでしょうか。
答えは、親の関わり方にあります。
【よく頑張ったね】【工夫して解いたね】など、結果よりも努力や過程を認める声かけが、子どもの内発的動機づけを育てます。
また、子どもの興味を大切にし、【どうして?】【なんでそう思う?】と問いかけることで、思考を深めるきっかけにもなります。
前向きな学びは、長期的に見て最も強い武器になります。
やらされる勉強から、自分で進む学びへ。その姿勢が、学力の差を確実に広げていくのです。
学力差がつかない子の特徴と回避する3つのコツ
さて、【頑張っているのに、なかなか成績が上がらない】【真面目なのに、学力が伸びてこない】という様子の子どもを見て、どうすればいいのか悩んだ経験はありませんか。
学力差が開いてしまう背景には、努力不足ではなく、努力の方向性がずれていることが多くあります。
たとえば、ただプリントをこなすだけで内容を理解していなかったり、わからない問題を飛ばして終わらせたり、間違いを見直す習慣がなかったり。
こうした行動は、子どもが意識せずにやっていることが多く、親が気づいてサポートすることが非常に重要です。
また、【勉強=つらいこと】【やらされるもの】というイメージが強いと、自発的な学びにはつながりません。
これでは、いくら時間をかけても学力は定着せず、成績に反映されにくいのです。
でも大丈夫です。
少しの工夫と声かけで、子どもの学び方は確実に変わります。
ここでは、学力差がつかない子にありがちな特徴と、それを回避するための具体的な3つのコツをご紹介します。
どれもすぐに家庭で実践できる内容なので、ぜひ今日から取り入れてみてください。
コツ①振り返りを習慣に
間違い直しをせず、ただ【正解か不正解か】で終わってしまう。
これは学力が伸びない子にありがちな行動です。
丸つけをして終了では、どこでつまずいたのかを自分で理解できず、同じミスを繰り返しやすくなります。
学力を伸ばすには、【なぜ間違えたのか】を考える振り返りの習慣が欠かせません。
たとえば、専用のノートを用意して、間違えた問題とその理由、正しい解法を書き残す【間違い直しノート】を活用するのも有効です。
そうすることで、子どもは自分の思考のクセや理解のあいまいさに気づくことができます。
振り返りを定着させるためには、親の声かけが大きな役割を果たします。
【ここはどこで迷ったの?】【次はどうしたらいいと思う?】と優しく問いかけるだけで、子どもは自然と考えるようになります。
正解することよりも、学ぶ過程に目を向ける。
この意識が、理解力と応用力を育て、学力アップへとつながるのです。
コツ②【毎日10分】で学習リズムを整える
【時間があるときにまとめてやる】よりも、【毎日少しでも続ける】ことのほうが、学力の定着には効果的です。
勉強が苦手な子ほど、勉強を特別なものと捉えやすく、机に向かうハードルが高くなっています。
まずは短時間でも、毎日続ける習慣を作ることが大切です。
特に効果的なのは、【1日10分だけ】の学習タイムを決めて習慣化すること。
時間帯を固定すると、子どもの中にリズムが生まれます。たとえば【夕食前の10分】【学校から帰ったらすぐ】など、生活の流れに自然と組み込むのがポイントです。
また、親が【今日の10分、がんばってたね】と声をかけてあげることで、努力が認められる喜びが自信となり、学習意欲が育ちます。
時間よりも継続を大事にし、【毎日やるのが当たり前】という雰囲気を家庭に根付かせましょう。
勉強を生活の一部にすること。
それが、学力をつける第一歩です。
コツ③【すぐ教える】より【考える時間】を与える
子どもが問題に詰まったとき、すぐに教えてあげたくなるのが親心です。
しかし、すぐに答えを与えてしまうと、子どもは【わからなければ誰かが助けてくれる】と思い、自分で考える力が育ちにくくなります。
学力の土台をつくるためには、【考える時間】をあえて与えることが重要です。
たとえば、【どこまでわかった?】【どうしてその答えにしたの?】と問いかけ、自分の頭で整理するきっかけを作りましょう。
こうしたやり取りを重ねることで、子どもは少しずつ【考えることが大事なんだ】と実感できるようになります。
そして、自分で考えて答えにたどり着いた経験は、自信につながり、さらに学びへの前向きさを育てます。
もちろん、ずっと黙って見守る必要はありません。
考えたうえで行き詰まっている場合は、ヒントを与えたり、考え方の順序を示したりして、解決のサポートをしましょう。
【教える】より【気づかせる】ことを意識する。
それが、思考力と学力の差を生み出す大きなカギになります。
学力上位層になるための主要3教科と対策
ところで、小学校のうちはできる子だったのに、中学校に入ってから急に成績が伸び悩む。
そんな子が身近にいる、子どもの同級生にいる、ということがあるかもしれません。
中学の学習内容は一気に難易度が上がり、小学校での【なんとなくわかったつもり】が通用しなくなるタイミングです。
このギャップを乗り越えられるかどうかが、上位層に入れるか否かの大きな分かれ道になります。
中学生になると、定期テスト・内申点・高校受験というように、学びがより具体的な評価につながっていきます。
中でも特に差が出やすいのが【数学】【英語】【国語】の3教科です。
これらの教科は、基礎が不十分なまま進んでしまうと、苦手意識が定着しやすく、後からの巻き返しが難しくなってしまいます。
しかし、逆に言えば、小学生のうちにこの3教科の【土台】をしっかり固めておくことで、中学以降の学習にスムーズに対応できるようになります。
ここでは、学力上位層を維持・獲得するために特に重要な3教科について、それぞれ小学生のうちからできる具体的な対策をご紹介します。
今から備えることで、中学のスタートダッシュが大きく変わります。
教科①数学(算数) 計算力と論理的思考をセットで育てる
中学の数学では、小学校よりも複雑な式や関数、図形など、抽象的な内容が一気に増えます。
ここで大きな壁になるのが、【ただの計算力だけでは太刀打ちできない】という点です。
算数の延長ではなく、論理的に考える力が求められるようになるのです。
そのため、小学生のうちにやっておきたいのは、【計算を正確にこなす力】と【なぜそうなるのかを説明できる力】の両方を育てること。
たとえば、文章題をただ解くだけでなく、答えに至るまでのプロセスを言葉で説明する練習を取り入れてみましょう。
これにより、表面的な理解から一歩進んだ思考力が身についていきます。
また、図形問題や表・グラフの読み取りなども、論理的思考の練習に最適です。
【なんでそうなるの?】【他の方法はある?】と親子で会話する中で、自然と考える力が育ちます。
計算力の訓練も大切ですが、それだけに偏らず、考える算数を意識することが、中学数学での得点力を大きく左右します。
教科②英語 音に慣れることから始めるのがカギ
いよいよ中学校で本格的に始まる英語の勉強は、得意・不得意が最もはっきり分かれやすい教科の一つです。
多くの子が戸惑うのは、【音と文字の関係】に慣れていないこと。
小学生時代に国語でのアルファベットの練習や英語の授業でアルファベットを扱うことをしてきてあるていど読めても、単語を聞き取れなかったり、正しい発音ができなかったりするのは、小学生時代に英語の音に触れてこなかったことが原因です。
英語を得意にするためには、【音で覚える】【耳で慣れる】ことが何より重要です。
英語の歌やアニメ、絵本の読み聞かせなど、生活の中で自然に英語に触れる機会を増やすことで、英語に対する抵抗感が減り、発音やリズムも無理なく身につきます。
小学生のうちに英語を完璧に覚える必要はありません。
大切なのは、【英語って楽しい】【なんとなくわかるかも】と思える自信の種を育てておくことです。
それが中学に入ってからの学びをスムーズにします。
また、単語の意味だけでなく、感覚的に【使い方】も学ぶことが大切です。
たとえば【I like 〜】というフレーズを何度も使ってみるなど、使うことで記憶に残していきましょう。
教科③国語 読解力はすべての教科のベースになる
国語は単なる【日本語の教科】ではありません。
実は、すべての教科に共通して必要な【読解力】【語彙力】【論理的思考力】を育てる、最も基礎となる教科です。
問題の意味を正確に理解できなければ、どんな教科も得点に結びつきません。
とくに中学での国語は、文章量が増え、設問も複雑になります。
小学生時代は満点や高得点を連発していた子でも、振るわなくなることも珍しくありません。
【何が問われているのか】【どこに答えが書いてあるのか】を読み解く力がなければ、知識があっても点が取れなくなってしまうのです。
このため、小学生のうちから深く読む力を養うことが重要です。
おすすめは、音読や要約練習、読んだ内容について親子で話し合うことです。
たとえば、【登場人物はどう思っていた?】【一番大事なことは何?】といった問いかけが、理解を深めるきっかけになります。
また、語彙力を増やすには読書が効果的です。
漫画や物語だけでなく、図鑑や新聞記事なども幅広く読む習慣をつけると、表現力や論理的な文章構成力が自然と育ちます。
読解力の差は、すべての教科の成績に影響します。
国語を制する者が、学力全体を制するのです。
学力差はちょっとした意識で大きく変わる
学力の差は、生まれつきの能力やセンスだけで決まるものではありません。
日々の学習への向き合い方、間違いへの対処、そして家庭での声かけや習慣づけによって、どんな子でも着実に力を伸ばすことができます。
とくに小学生のうちは、【わからないことにどう向き合うか】【考えることを面倒に感じないか】【毎日少しずつでも取り組む習慣があるか】といった学ぶ姿勢が、学力の伸びを大きく左右します。
これは、ちょっとした意識や関わり方で変えていけるものです。
また、将来の学力の土台となるのは、算数(数学)・英語・国語といった主要教科への準備です。
小学生のうちから少しずつ対策をしておくことで、中学・高校でも自信をもって学びを進めることができるようになります。
大切なのは、点数や順位ではなく、【自分で学ぶ力】を育てることです。
焦らず、比べず、一歩ずつ積み重ねていくことで、子どもは必ず伸びていきます。
今日からできる工夫を少しずつ始めて、将来の学力の自信につなげていきましょう。