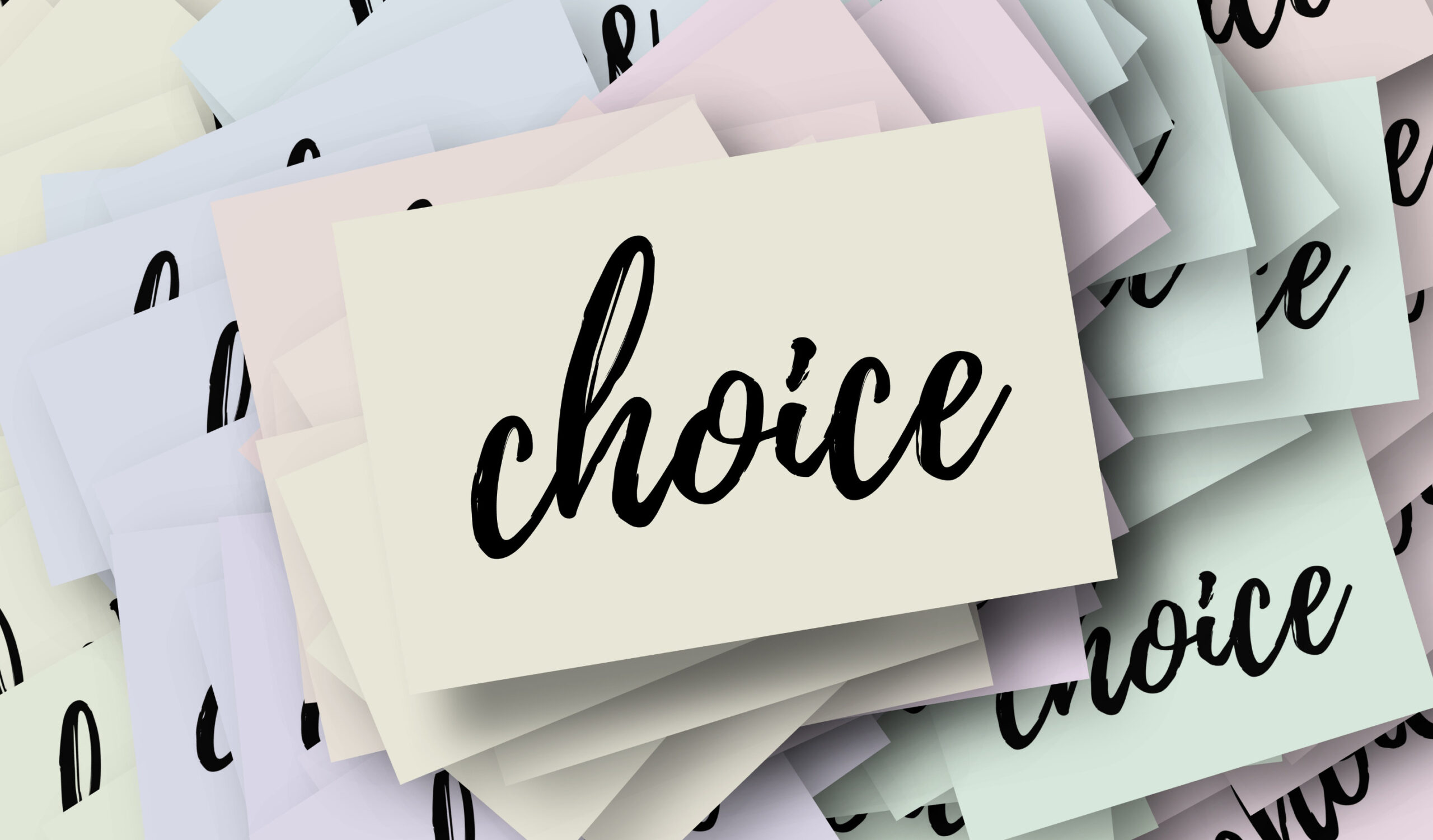今回は【高学年から伸びる子はここが違う! 親が今すぐできる学習サポート術】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校高学年になると、子どもたちの勉強に対する姿勢に大きな違いが見え始めます。
これは、学校でのクラス内でもノンビリと過ごしている子でも気がつくような変化です。
我が家のノンビリと過ごす代表格の子ども①でも、小学校5年生から明確にクラス内での学力差、それぞれの学力グループに誰が属しているのかが分かるようになってきました。
2025年度に小学5年生となった子ども③にも確認したところ、ハッキリとした学力の違いが共通認識になっているようです。
子どもの勉強は一応、小学1年生からスタートをし、学校では同じような学びを受けてくるわけですが、高学年になるまでに自主的に机に向かう子もいれば、宿題をこなすだけで精一杯という子とザックリ分かれていきます。
この差の背景には、【自我の芽生え】と【自学自習ができるかどうか】という2つの要素が大きく関係しています。
高学年は、子どもが【自分はどうしたいのか】【なぜ勉強するのか】と考え始めるタイミングです。
つまり、親に言われてやる受け身の勉強から、自分の意思で取り組む主体的な学びへと意識を切り替えられるかどうかが、成績の伸びを大きく左右するのです。
また、子どもが安心して勉強に集中するためには、家庭内の雰囲気も極めて重要です。
親の口調が常に厳しかったり、夫婦間の空気がピリついていたりすると、子どもは無意識のうちに緊張し、学びに向かう気持ちを失ってしまいます。
学力を育てるための土台として、【この家にいれば安心】【自分は大切にされている】と子どもが感じられることが、なによりのサポートになります。
そこで今回は、
・高学年で成績が伸びる子の特徴
・中学でも上位を狙える親の関わり方
・各教科ごとの具体的な学習アドバイス
の3つの視点から、親が今日から実践できる学習サポート術をお伝えします。
高学年で勉強への意識が変わる子の3つの特徴
まず、小学校の3〜4年生までは、親や先生に言われたことをこなす【受け身の学習】が中心です。
宿題を出されたらやる、授業で教わったことをそのまま覚える。
それでもある程度は通用します。
しかし、5年生以降になると学習内容が格段に難しくなり、ただ指示に従うだけでは太刀打ちできなくなってきます。
ここからが、子どもによって勉強に対する姿勢が大きく分かれ始める時期です。
成績がぐんと伸びる子は、【なぜこの問題はこう解くのか?】【どこが理解できていないのか?】と自分で考えながら学ぶようになります。
一方で、成績が伸び悩む子は、【とりあえずやればいい】と形式的な学習にとどまり、知識の定着が不十分なまま進んでしまう傾向があります。
この違いは、才能や地頭だけで決まるわけではありません。
むしろ、高学年という年齢ならではの【自我の芽生え】や【自分で学ぼうとする意識】が育っているかどうかがポイントです。
そしてその意識が芽吹くかどうかは、日常のちょっとした習慣や環境によっても大きく左右されます。
この章では、実際に多くの子どもたちを見てきた中で浮かび上がってきた、【高学年から勉強への意識がガラッと変わる子の3つの共通点】について詳しく解説していきます。
お子さんがこれから学びに向かうきっかけをつかむためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
特徴①【勉強は自分のためという意識が芽生えている】
高学年から成績が伸びる子に共通しているのが、【勉強は自分の人生のためにやるもの】と捉えていることです。
まだ将来の夢が明確でなくても、【こんな大人になりたい】【この分野って面白いかも】といった小さな興味が、学びへの前向きな姿勢につながっていきます。
このような意識を育てるには、親の声かけも大切です。
【〇〇しなさい】ではなく、【どう思う?】【どんなことに興味ある?】といった問いかけを通して、子ども自身が考えるきっかけを作るようにしましょう。
【自分で決めて勉強する】という感覚が持てると、学習そのものの質が大きく変わります。
たとえ同じ内容を勉強していても、受け身ではなく主体的に取り組む子は、理解度も深まりやすく、習得のスピードも早くなります。
この【勉強は誰のため?】という問いに、子どもが自分なりの答えを持てるようになると、自学自習の力が自然と伸びていくのです。
特徴②【わからない】を放置せず、自分で調べる・試す習慣がある
自分で学ぶ力を育てるうえで最も重要なのが、【わからない】をそのままにしない姿勢です。
成績が伸びる子は、つまずいたときにまず自分で解決しようとします。
教科書を読み直したり、ノートを確認したり、辞書やインターネットで調べたりと、自力で理解する努力を惜しみません。
その一方で、成績が伸びにくい子は【わかんない】とすぐに手を止めてしまいがちです。
こうした習慣が続くと、わからないことがどんどん積み重なり、やがて勉強そのものが苦手意識へと変わってしまいます。
親としてできるサポートは、【わからないことがあるのは当たり前】【まず自分で調べてごらん】と伝え、考える時間を待つ姿勢を持つことです。
すぐに答えを教えるのではなく、子どもが自分の力で解決するプロセスに付き合ってあげることで、学ぶ力は確実に育っていきます。
理解できた喜びを重ねることで、勉強が【面白い】と感じられるようになります。
特徴③【できた!】という成功体験を積み重ねている
高学年から成績がぐんと伸びる子には、【できた】【わかった】【やりきれた】といった小さな成功体験が数多く積み重なっています。
それは決して100点のテストだけではなく、【昨日よりミスが減った】【自分から勉強を始められた】といった、日々の中での前進そのものです。
こうした成功体験は、自信と学習意欲の源になります。
【また挑戦してみよう】【もう少し頑張ってみたい】と感じることで、学ぶ姿勢が自然と前向きになっていきます。
親の役割は、この小さな変化を見逃さずに認め、励ますことです。
結果にとらわれず、【よく集中してたね】【昨日より考えてたね】とプロセスを褒める声かけが、子どものやる気を引き出します。
小さな達成感の積み重ねは、やがて【勉強に自信がある子】を育てていきます。
そしてその自信こそが、長期的に見て最も大きな学力の源となるのです。
中学でも上位を狙うために親が意識したい3つの気配り
さて、小学校高学年から中学生になるにつれ、子どもの勉強に対する姿勢や学力の伸びは、本人の努力だけでなく、親の関わり方にも大きく左右されます。
中学生になると、学習内容が難化し、部活動や人間関係の悩みも増えるため、学力の差が徐々に広がっていく時期です。
そんな中で成績上位を維持する子どもたちは、特別な才能を持っているというよりも、【安心して学べる家庭環境】が整っているという共通点があります。
子どもが自分に自信を持ち、勉強に前向きに取り組めるためには、親の何気ない声かけや態度、家庭内の雰囲気がとても大きな影響を与えているのです。
中学以降、勉強の内容は親が直接教えるのが難しくなる場面も多くなります。
だからこそ、学習支援の中心は【勉強を教えること】ではなく、【子どもが学べる環境を整えること】へと変わっていくのです。
ここでは、勉強のテクニック以前に大切にしたい、親が意識しておきたい3つの気配りについてご紹介します。
子どもが精神的にも安定し、意欲的に学び続けるための土台作りを一緒に考えていきましょう。
気配り①【結果】ではなく【努力の過程】に目を向ける
中学生になると、定期テストの点数や通知表の成績が気になり始めるのは自然なことです。
しかし、親が【何点だったの?】【どうしてこんな結果なの?】と結果ばかりを重視すると、子どもは【認めてもらえない】と感じ、やる気をなくしてしまうこともあります。
大切なのは、【どんな努力をしてきたか】に目を向けることです。
【毎日コツコツ続けていたね】【苦手なところに取り組んでいたね】と、過程をしっかり見て言葉にしてあげるだけで、子どもの自己肯定感は大きく育ちます。
結果はすぐに出ないこともありますが、努力する姿勢が評価されれば、【また頑張ってみよう】と前向きな気持ちが生まれます。
勉強への意欲を育てるには、努力を認める視点こそが土台となるのです。
気配り②家庭の安心感が学習意欲の土台になる
子どもが落ち着いて勉強に取り組むには、家庭が【安心できる場所】であることが不可欠です。
思春期に入る中学生は、親の表情や雰囲気にとても敏感です。
もし家庭内がギスギスしていたり、親が不安定な様子を見せたりしていると、子どもは無意識のうちに気を張ってしまい、集中力を欠く原因になります。
家の中でホッとできる環境があると、子どもは気持ちが安定し、【よし、やってみよう】と前向きになれます。
学習計画や教材選びに気を配る前に、まずは家庭の雰囲気を整えることが先決です。
【何があっても味方だよ】という安心感を伝え続けることで、子どもは本来の力を発揮しやすくなります。家内安全は、何よりも大切な学習サポートの土台です。
気配り③【親自身が学ぶ姿】を子どもに見せる
中学生になると、親の言葉よりも行動のほうが、子どもには強く伝わるようになります。
とくに【学び続ける大人の姿】は、子どもにとって大きな刺激となります。
もし親が毎日スマホを見ているだけで勉強しろと言っても、説得力はありません。
一方で、読書や新聞を読む、資格の勉強をするなど、学びに向かう姿を自然に見せることで、子どもは【勉強は大人になっても大事なんだ】と感じ取ります。
【お母さんも最近〇〇を勉強してるよ】【一緒にこれ調べてみようか】といった声かけも、親子の信頼関係を深め、学習への好奇心を引き出す効果があります。
高学年から順調に伸びるための教科別アドバイス
ところで、小学校高学年になると、教科ごとの学習内容が一気に難しくなり、単に【毎日机に向かっている】だけでは成績が伸びにくくなってきます。
そこで大切になるのが、各教科の特性に合わせた取り組み方を意識することです。
国語には読解力、算数には論理的思考力、理科や社会では理解と暗記のバランス、英語では音声感覚や語彙の定着など、それぞれ必要とされる力が違います。
また、子どもによって得意・不得意も分かれるため、画一的な勉強法では対応しきれない場面も出てきます。
そのため、親が教科ごとの特徴を理解し、それに合った声かけやサポートをすることで、子どもの苦手意識を防ぎ、自然と成績アップにつなげることが可能になります。
たとえば【この教科はこう学ぶといいよ】といった具体的なアドバイスがあるだけで、子どもも迷わず勉強に取り組めるのです。
ここでは、国語・算数・理科・社会・英語の5教科について、家庭でできる実践的なアドバイスをお伝えします。
国語:読解力は【会話】と【読書】が育てる
国語力の土台は、教科書や問題文の内容を【正しく読み取る力】です。
これは単なる暗記では身につかず、日常的な言葉のやりとりの中で育っていきます。
家庭での会話がとても大切で、【どう思う?】【なんでそう考えたの?】といった問いかけを通じて、子どもに自分の考えを言葉で表現する練習をさせましょう。
また、読書習慣も読解力の育成には欠かせません。
物語や説明文に触れることで、語彙力や文章構造への理解が深まります。
親子で同じ本を読んで感想を話し合うのもおすすめです。
読解力が高まると、他教科の文章問題でもスムーズに読み取れるようになり、総合的な学力アップにつながります。
算数:公式の暗記ではなく【納得する】ことが大事
高学年になると算数は一気に抽象的になります。
小数や分数、割合、図形、速さなど、理解が追いつかないと一気に苦手科目になってしまいます。
ここで大事なのは、公式をただ覚えるのではなく、【なぜそうなるのか】を理解して納得すること。
たとえば、分数の計算でつまずいたら、図を描いて一緒に考えたり、具体物を使って説明したりすると、感覚的に理解できることがあります。
また、間違えた問題を放置せず、【どこで間違えたのか】【どう考えたらよかったのか】を一緒に振り返る時間を作ることで、応用力も鍛えられます。
算数は積み重ねが命。
わからないまま進まないよう、こまめに確認しましょう。
理科:【不思議】と思う気持ちを引き出す工夫を
理科を好きになる子は、知識を詰め込まれたからではなく、【なぜ?】【どうして?】と感じる機会が多かった子です。
高学年では力や電気、天体など抽象的な単元も出てきますが、まずは身の回りの現象に興味を持たせることが理科の入口です。
家で簡単な実験をしてみたり、図鑑や科学系の動画を一緒に見ることで、学びがぐっと身近になります。【この前のニュース、理科で習ったことと関係あるよね】と声をかければ、教科の枠を超えて知識を関連づけられるようになります。
好奇心を育てることが、理科の成績を伸ばす一番の近道です。
社会:バラバラの知識をつなげて【意味ある理解】に
社会科は暗記教科と思われがちですが、高学年からは【なぜこの出来事が起きたのか】【どのようにつながっていくのか】といった背景理解が得点に大きく関わってきます。
地理や歴史を点で覚えるのではなく、流れや因果関係で理解させるのが重要です。
また、ニュースや旅行、地域の話題など、身近な情報と社会科の内容を結びつける工夫も効果的。
【この街、昔はどんな産業だったんだろう?】など、日常生活での会話が学びに直結します。
資料の読み取り問題も多くなるため、地図やグラフを読む練習も忘れずに取り入れましょう。
英語:【意味がわかる体験】で苦手意識を防ぐ
小学校で英語が必修になった今、子どもにとっても親にとっても避けては通れない教科になっています。
しかし、【わからない】【聞き取れない】と感じると、苦手意識が先行してしまう子も多いのが実情です。
こういう気持ちを抱いてしまうと、中学からの挽回は不可能に近くなるので、勝負は小学生時代にあると言っても過言ではありません。
大切なのは、英語に毎日少しずつ触れる【習慣】を作ることです。
英語の歌やアニメ、絵本など、子どもが楽しめる形で【聞いたことある】【意味がなんとなくわかる】という経験を積むことで、安心感と親しみが育ちます。
音読や簡単な英単語カードを使ったクイズも効果的です。
英文法をガッツリで始めるより、まずは【好き】【わかる】感覚を育てることが、英語への入り口になります。
成績が伸びる子に共通するのは【学ぶ力】と【安心感】
小学校高学年からグッと成績を伸ばす子に共通しているのは、【自分で考えて学ぶ力】と【家庭という安心できる土台】があることです。
勉強そのものよりも、どんな環境で、どんな心の状態で学ぶかが、実は成績に大きく影響しています。
親がすべきことは、無理に詰め込ませたり、毎日細かく管理することではありません。
それよりも、【勉強って面白いかも】と思えるような声かけや、【間違えても大丈夫】と思えるような空気をつくることが大切です。
安心して学べるからこそ、子どもは主体的に学び始め、自信をつけ、やがて自分の力で前に進めるようになります。
声かけを少し変える。
生活リズムを見直す。
親子の会話を少し増やす。
そんな小さな変化が、未来の学力の差を生み出します。
【うちの子、これからどうなるだろう】と不安に思ったら、まずは家庭の雰囲気や日々の接し方を見直してみましょう。