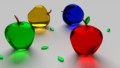今回は【トップ高校に進む子 小学生のうちにこの教科をモノにしている】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
地方でも、トップ高校に進む子というのは小学生の頃から優等生の中でもキラリと輝く何かを感じるような子が多いです。
【中学に入ってもずっと成績が安定している子って、小学生のころから違ってた気がする】という子なので、もし、トップ高校を目指すのであれば中学から本気を出すのではなく、小学生から目出すというのがお約束のようなものになっています。
小学校は6年間と長く、その間に子どもたちの間の学力差は進んでいき、小学校を卒業し、中学に進学して、そこでも最上位層でいる子、トップ高校に合格する子というのは【小学生のうちにこの教科は苦手になっていない】という特徴があります。
その特徴とは、【国語】と【算数】という、いわば学力の2本柱の基礎をしっかり築いているということです。
多くの親は【算数が得意だから理系に向いていそう】【国語は苦手でも理科が好きだから大丈夫】といった見方をしてしまいがちですが、実はこの2教科こそが、すべての教科に波及する【学力のエンジン】になっているのです。
中学受験では算数が合否を分けるという見方は強いですし、高校受験でも偏差値の高い学校であればあるほど数学の点数が合否を分けるという都市伝説のような話が広まっていますが、一つだけ強くてもトータルバランスが悪すぎると、勝てる受験も勝てなくなります。
ですから、国語と算数という二本柱をいかに強固なものに出来るかというのが子どもの進路進学を決めてしまう重要なポイントになります。
改めて確認しますが、国語は読む力、考える力、伝える力の基盤であり、算数は論理的に物事を筋道立てて考える力の土台です。
どちらも、中学以降の学習内容だけでなく、社会に出てからの思考力や問題解決力にも直結しています。
とくに国語力は、理科や社会の資料読み取り、数学の文章題、英語の読解など、教科を超えて必要とされる能力です。
一方、算数は中学以降の数学の礎となるため、積み上げ式の理解が求められる教科です。
では、小学生のうちに国語と算数をモノにするとは具体的にどういうことをすべきなのか、 どうすれば苦手意識を持たせずに家庭でこの2教科の土台を築けるのでしょうか。
今回は、トップ校に進む子たちの共通点をもとに、親ができる関わり方や家庭での習慣作りのポイントをご紹介していきます。
国語力が【すべての教科の理解力】につながる理由
まず、国語はどう考えても全ての教科の土台となる教科なので、トップ高校を目指す場合は絶対に苦手にしたまま放置しておくというのは避けないといけません。
【国語は好き嫌いが分かれる教科】と言われることがありますが、実際には好みの問題以上に、子どもが何をどれだけ【読み取れているか】が問われる、極めて子どものリアルかつ総合的な学力が見えてしまう教科です。
国語力が高い子は、単に国語のテストで点を取れるというだけでなく、他の教科、とくに理科、社会や英語などにも強く、学力全体の安定感があります。
ではなぜ、国語が【すべての教科の基礎】と言われるのでしょうか。
それは、国語という教科が【読解力】【語彙力】【論理的思考力】から成り立っており、すべての学びに不可欠な能力を含んでいるからです。
たとえば、算数や数学の文章題は、問題の意味が正確に読み取れなければ、どんなに計算力があっても正解にはたどりつけません。
理科では、実験の手順や結果の説明文、社会では統計資料の読み取りや歴史的背景の因果関係など、情報を正しく読み解く力が求められます。
また、中学以降に登場する【記述問題】や【探究学習】【小論文】では、自分の意見を明確にし、根拠を示しながら他者に伝える力が必要です。
これらはまさに、国語で培われる表現力・要約力・論理構成力そのものです。
トップ高校や進学校の入試問題を見ても、読解問題の分量が多く、記述問題の比率が高い傾向があるのはこのためです。
それでは、小学生のうちにその土台となる国語力をどう育てていけばよいのでしょうか。
まず大切なことは、家庭の会話の中で【言葉と思考】を結びつける習慣をつけることです。
たとえば、本を読んだあとに【どうだった?】【どの場面が心に残った?】と問いかけたり、日常の出来事について【どう思う?】【なぜそう思うの?】と考えを言語化させたりすることで、子どもは自分の頭で整理して話す練習を自然と行うようになります。
また、読書についても読みっぱなしにしない工夫が効果的です。
本を読んだ後の感想を共有したり、【この登場人物の気持ちは?】【別の展開だったらどうなる?】など、内容を深く掘り下げる質問を投げかけると、単なる娯楽としてではなく、考える読書へと質が変わっていきます。
さらに、忘れてはならないのが語彙力です。
語彙が不足していると、そもそも文章を正しく読み取ることが難しくなります。
読解が苦手な子の中には、【言葉の意味をなんとなくで読んでいる】ケースが多く見られます。
家庭では、読んだ本や文章の中に出てきた新しい言葉を一緒に調べたり、似た意味の言葉と使い分けを話し合ったりすると、語彙が定着しやすくなります。
たとえば、【理由】と【原因】の違いを親子で話すだけでも、子どもにとっては大きな学びです。
こうした積み重ねによって、記述問題でも【何をどう書けばよいか】が自然と分かるようになります。
このように、国語力は【勉強の一分野】ではなく、すべての教科に通じる思考の道具箱のようなものになります。
早いうちからこの力を育てておくことで、子どもは中学、高校でも、与えられた知識をただ覚えるのではなく、理解し、つなげ、活用する学び方ができるようになります。
トップ高校に進学する子は、例外なくこの力を小学生のうちに身につけているのです。
算数のカギは積み上げの重要性と応用力
さて、国語と並び、もうひとつの重要な柱が【算数】です。
トップ高校に進学するような子どもたちは、小学生の段階で算数に対して確かな理解と自信を持っていることが多くあります。
計算が速い、図形が得意、というレベルを超え、筋道立てて考える力や、数的センスを磨いているのが特徴です。
算数の最大の特徴は、【積み上げ型の教科】であるという点です。
とくに小学3年生から5年生までの内容は、中学以降の数学とダイレクトに接続しています。
分数・小数・割合・速さ・図形の面積と体積など、この時期にしっかり理解しておかなければ、中学数学の土台がぐらついてしまいます。
トップ層の子は、計算力だけに頼るのではなく、【なぜこの式になるのか】【なぜこのやり方で答えが出るのか】を理解しようとします。
つまり、【解き方】より【考え方】を重視しているのです。
公式をただ覚えて当てはめるのではなく、その背景にある仕組みや意味に興味を持つ姿勢が、応用力と数学的思考を育てています。
一方で、算数が苦手な子は、よくわからないまま暗記的に学んでいる場合が多く、応用問題や文章題になると一気に歯が立たなくなります。
そして、いったん苦手意識を持ってしまうと、【できない→嫌い→避ける→さらにできなくなる】という負のスパイラルに陥ってしまいがちです。
このような状態を防ぐには、家庭での関わり方がとても大切です。
まず、個人的におすすめしたいのが、【式の意味】や【考え方の言語化】を日常的に促すことです。
たとえば、【なんでこの式になったの?】【どうやって考えたの?】と問いかけてみてください。
子どもが嫌々ながらも自分の考えを言葉で説明する過程で、理解が深まり、あいまいな部分も浮き彫りになります。
また、文章題や応用問題にも怖がらずに挑戦する姿勢を育てることも重要です。
最初から正解を求めず、【こう考えてみたけど違った。でもどこでズレたのかな?】というように、間違いから逆算から学ぶプロセスを大切にしましょう。
家庭でよくあるNG対応が、【どうしてこんなミスをしたの?】【前に教えたでしょ】と責めてしまうことです。
そうではなく、【ここで引き算にしてたね。どうしてそう思った?】と、間違いの背景にある思考を一緒にたどってみてください。
そうすることで、子どもは【できなかったこと】に向き合う力を身につけていきます。
さらに、図や表、線分図などを使って視覚的に考える習慣も効果的です。
とくに、割合や速さ、比などはイメージがしづらいため、図で整理することで飛躍的に理解が進みます。
トップ層の子どもたちは、自然とこのような図解スキルを身につけています。
小学生のうちに【算数は楽しい】【工夫すれば解ける】と感じられる経験を重ねることで、数学に対するポジティブな土台ができます。
この【自分は算数が得意かも】という自己認識が、その後の理系教科への興味や、文理選択、さらには大学入試での進路選択にまで影響を及ぼします。
トップ高校に進む子の多くは、こうした思考のプロセスを通して、問題に対して柔軟に、かつ深く考える習慣を小学生のうちから育てています。
算数は単なる教科ではなく、論理的思考力と忍耐力を鍛える知的トレーニングの場なのです。
国語×算数が学力の伸びしろを決める
ところで、これまで述べてきたように、国語力と算数力は、それぞれが重要な学力の柱でありながら、実は相互に深く関係しています。
つまり、この2教科は別々のものではなく、子どもの学びの質を高める両輪のような関係なのです。
国語では【読む・考える・伝える】力を養い、算数では【筋道を立てて考える】【具体と抽象を行き来する】力が育ちます。
この2つの力が融合すると、他教科の学習にも良い影響を与えます。
たとえば理科での観察記録や、社会での資料読解、英語での長文理解など、どれも読む力と論理的に考える力が求められます。
実際、トップ高校に進学する子どもたちは、小学生の段階ですでにこうした学びの姿勢を身につけています。
単にたくさん勉強しているのではなく、【なぜそうなるのか】といった考え方の質が異なります。
こういうタイプの子どもたちは、学習量が少なくても深く理解できるため、効率よく成果を出すことができます。
そして一度得た知識を知識のままにせず、新しい課題や状況に応じて応用する力が備わっています。
これはまさに、国語と算数という土台が強固であることの証です。
こうした力を家庭で育てていく上で、まず意識したいのは、【テストの点数】よりも【考え方や過程】に注目することです。
正解、不正解に一喜一憂するのではなく、【どうやってその答えにたどりついたのか?】を親子で一緒に振り返ることが大切です。
仮に間違っていたとしても、【よくそこに気づいたね】【この考え方はおもしろい】と、プロセスを肯定する言葉が、子どもの思考力をさらに伸ばします。
次に、【わかるって気持ちいい!】という成功体験を小さなステップで積ませることです。
問題が解けたとき、【なぜできたと思う?】【前よりもどこがよくなった?】と問いかけてあげることで、子どもは自分の成長に気づき、自信を持ちます。
この喜びが、やがて自ら学ぶ【自走型の学習】につながっていきます。
さらに重要なのは、【間違えてもいいから、まず考える】という向き合い方を大切にすることです。
家庭でよくある【なんでこんなミスをするの?】【ちゃんと見直したの?】という言葉は、思考を止める要因になりかねません。
代わりに、【どこで迷った?】【何と何を間違えたと思う?】と問いかければ、子ども自身が自分の思考を振り返る習慣を身につけていきます。
そして、家庭でのサポートがしっかりしていれば【塾に入らないとダメだ】【ドリルに頼らないとできない】と考える必要はありません。
日常の中で学びの視点を持つことこそが、もっとも効果的なサポートになります。
身近な例で言うと、買い物中に【割引率の計算】をしてみたり、テレビのニュースを一緒に見ながら【この言葉の意味って?】【どういう理由でこうなったのかな?】と話すだけでも、国語と算数の力を鍛える実践の場になります。
こうした習慣が積み重なることで、子どもは単なる受け身の勉強ではなく、【自分で考え、表現する学び】に変わっていきます。
そしてこの変化こそが、トップ高校合格につながる真の【学力の伸びしろ】を生むのです。
小学生のうちに身につけておきたいのは、ただのテストの点数ではなく、将来も伸び続けるための土台である思考力の種です。
国語と算数という2つの教科は、学力の核となる存在です。
国語は、すべての教科に通じる【読む力】【考える力】、算数は【論理的に筋道を立てて解く力】を育てます。
トップ高校に進学する子どもたちは、小学生の時点でこれらの力の芽を着実に育てています。
だからこそ、親としては今、【この子は考えることができているか?】【なぜ?どうして?を自分の言葉で語れるか?】という視点を持つことが大切です。
学力の本質は、正解を出すことよりも、わからないことに自分で向き合える力をどれだけ育てられるかにかかってきます。
その力を支えるのが、家庭での関わり方です。
5年後、10年後の進路は、今の小さな習慣の積み重ねで決まってくると肝に銘じてください。