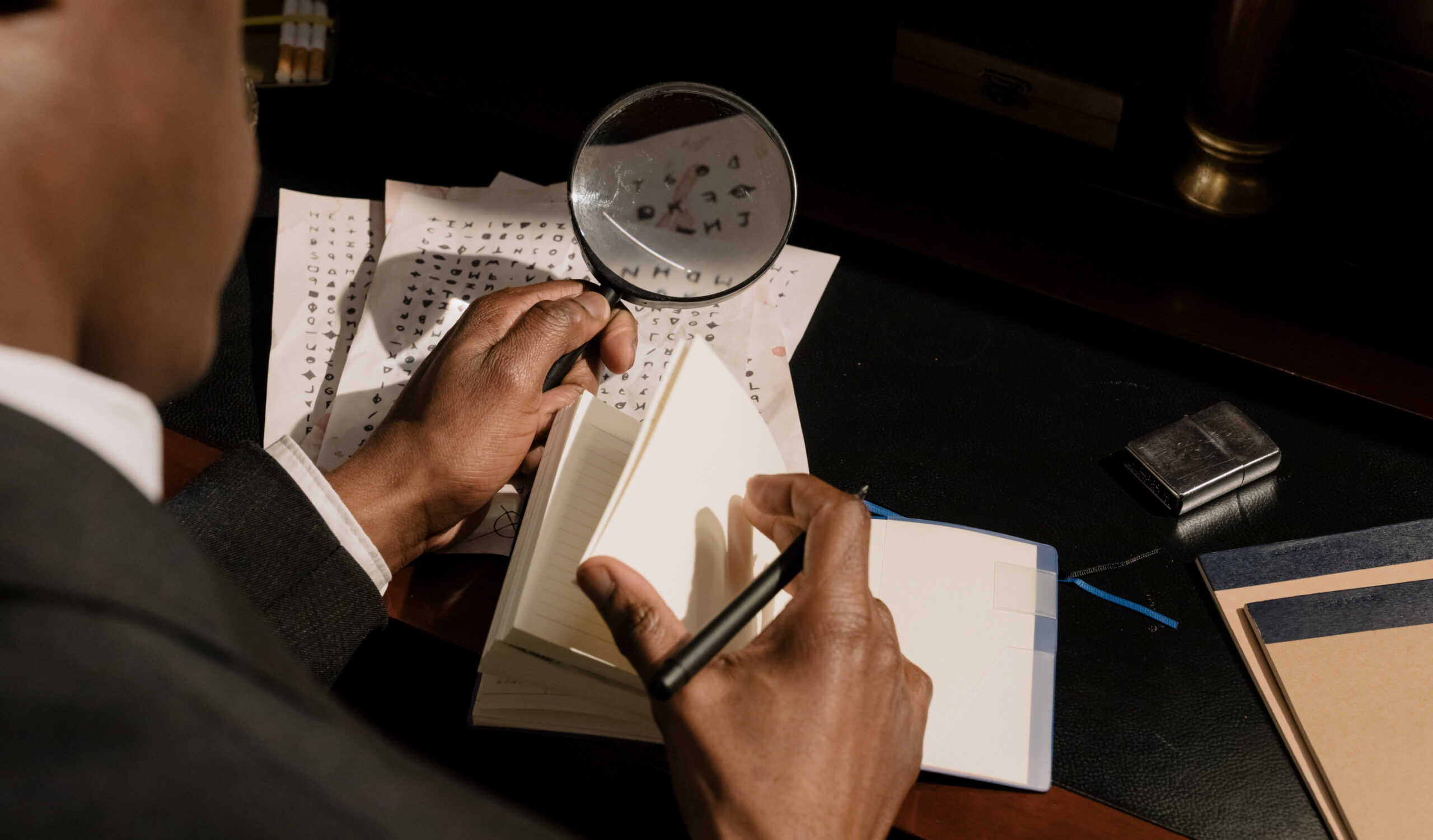今回は【小学生の分かれ道 小4の壁を越えられない子を避けたい】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
「小4の壁」という言葉を一度は聞いたことがあると思います。
小4の壁、10歳の壁と呼ばれる問題は、小学3年生までは順調に見えた子が、4年生に入った途端に学習面や精神面でつまずきを見せる現象を指します。
小学校生活も折り返しを過ぎ、子どもたちはただ【習う】だけでなく、考える、応用する、といったより高度な学習が求められ始めるのがこの時期になります。
算数では抽象的な概念や資料の読み取りが登場し、理科・社会では単なる暗記だけではなく理解力も問われます。
学校のテストでも、どの教科でも70点台の点数を取る子の顔ぶれが固定化していき、反対に満点や高得点しか取らない子の顔ぶれも同じように決まってきます。
さらに、心の面でも変化が表れます。
何でも親に話をしていた子が急に口数が減るということも起きます。
親の方は学校や友達関係で嫌なことがあったのではと心配になりますが、特段何もないということも珍しくありません。
【別に】【必要以上に話しかけてこないで】と冷たい態度を取るようになり、親の方も不安からイライラへと子どもに対する気持ちの変化が出てくることもあります。
しかも、心が成長していることが悪い方になってしまうこともあります。
自我が芽生え、親や先生に対して反抗的になる子も増え、【わからない】と素直に言えずに抱え込むケースが目立ちます。
また、友達との関係や他人の目を気にするようになることで、勉強の優先順位が下がることも少なくありません。
そこで今回は、こうした子どもの成長には避けては通れないような【小4の壁】を正しく理解することで、子どもに実際にどんな兆候が見られやすいのか、そして親ができる支援にはどんなものがあるのかを、具体的にご紹介していきます。
学習面の「壁」
まず、小4の壁の最も顕著な現象の一つが、算数での難化です。
これまでは九九や単位換算など具体的な内容が中心だったのが、【図形】【資料読み取り】など抽象的で複雑な内容に切り替わり、5年生以降になると【割合】【速さ】とさらにレベルアップした内容を学んでいきますます。
計算も小数や分数を学ぶため、パッと見て解ける問題も減ります。
数だけでなく、情報をどう処理するかが問われるようになります。
ここで躓くと、自信が揺らぐだけでなく、学習意欲そのものが停滞することにつながります。
算数の基礎が積めないと、中学に進んでからの数学を苦手意識を持って臨むことになります。
また、理科や社会の知識の未定着も深刻な壁です。
小4からは【電気や植物】【身近な歴史や地理】など、用語や背景知識を覚えることが求められる単元が増加します。
しかし、教科書を読むだけでは理解にとどまり、定着しづらいという問題が起きてしまいます。
たとえば【なぜ地層ができるのか】を言葉で説明する訓練がないと、ただ【砂が積もったから】と表面的に受け止めるだけ。
思考をともなう学びがなければ、将来の記述問題や応用力も育ちません。
さらに、【わからないと言えない空気】も見逃せないポイントです。
小4になると他者の目を気にし始め、【恥ずかしい】【言うのが面倒】という理由で、子どもが自分の理解の曖昧さを口に出さなくなります。
親や先生から【分かったかな?】と聞かれ、つい【分かっている】と答えていても、実際には【わからないままになっている】になっていて、けれど子どもは正直に言えない、ということも起きます。
これが繰り返されると、【分からない単元が増える】になり、子どもは素直に言えない、誤魔化してばかりの自分に嫌気がさして自己肯定感が下がり、【どうせ自分にはできない】という思考パターンが定着してしまいます。
このように、小学校4年生で直面する学習面の壁は、算数の難化、理理科社会の知識が定着していない、そして【わからない】と言えないことによる精神的な悩み、という三重構造になっています。
これを放置しておくと、学習意欲・自信・基礎知識のすべてが脆弱になり、結果として【学びの土台そのものが崩れる】という状態になってしまいます。
精神面と生活習慣の「壁」
さて、小4の壁と呼ばれる時期において、学習内容の難化に加えて、子どもの心の成長や生活習慣にまつわる変化も見逃せない要素です。
とくにこの年代は、親との関係性、友人との距離感、自分の意思との葛藤などが交錯し、学習への姿勢に大きな影響を及ぼします。
小学校4年生前後になると、子どもは次第に自我を強め、【干渉されたくない】という思いが芽生えます。
親が【勉強したの?】【宿題やった?】と声をかけるだけで、拒否反応を示すようになったと感じた経験がある方はかなりいると思います。
親自身も子どもの頃に言われてカチンときたことを、子どもに言ってしまうということもあるでしょう。
これは、親の声かけが口うるさく感じられるようになる時期だからです。
親が良かれと思って促しても、子どものやる気は逆に失われ、学習の手が止まってしまうケースが多いのです。
こうした反発の裏には、親との関係性が学習のモチベーションに直結しているという事実があります。
適度な距離感と、見守る姿勢がこの時期には重要になってきます。
また子どもの性格によっては小学4年生、10歳くらいになると、周囲との比較をするなど、一層、その程度が激しくなります。
友達の進度や成績、学校外の活動などが気になり、自分と比べて落ち込んだり、焦ったりすることが増えていきます。
さらに、【みんなと同じでいたい】という同調意識が強まることで、自分に合った勉強法やペースを保てなくなる子も出てきます。
たとえば、友達に合わせて宿題を早く終わらせようとしたり、わからないことを【聞いたらバカにされるかも】と口にできなかったりと、勉強への姿勢がブレやすくなります。
こうした環境によって、自信を失ったり、学びから逃避したりする兆候が現れることもあるので気をつけてください。
そして現代の小学生に特に大きな影響を与えているのが、スマホやゲームです。
便利で楽しい反面、【つい触ってしまう】ことが日常の中に定着してしまうと、学習時間や睡眠時間の減少につながってしまいます。
とくに夜にスマホを見たりゲームをしたりする習慣がついてしまうと、睡眠の質が下がり、翌日の集中力低下につながるという悪循環が起こります。
これにより、授業内容が頭に入らず、勉強自体に苦手意識を持ち始めることも少なくありません。
スマートフォンの使用に関しては始めが肝要です。
親子でキッチリとしたルールを決めて、使用状況を小まめに確認するようにしましょう。
壁を越えるヒントとサポート
ところで、小4の壁を乗り越えるためには、学力の立て直しだけでなく、心や生活の土台づくりも欠かせません。
単に勉強を【やらせる】のではなく、つまずいた背景に目を向け、親が寄り添って支えることで、子どもは再び学びへの意欲を取り戻していきます。
まず、必要なのは、学びの土台を再確認し、無理なく戻ることです。
算数で躓いている子には、丁寧に苦手単元を特定し、前の学年の内容、必要性を感じるのであれば二学年前まで戻って復習していくことが効果的です。
理科や社会の知識が頭に残っていない場合は、漫画や図解の入った教材を一緒に読むなど、親子で共有する学習が有効です。
【わかる!】という小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感を回復させ、学びへの意欲を引き出せます。
また、反抗期に差し掛かる子には、頭ごなしの声かけよりも、【最近どう?】【困っていることある?】といった会話の入り口を開く関わりが大切です。
勉強のことに直接触れなくても、日々の雑談や生活の中で信頼関係を築いていくことで、【勉強の話】も受け入れやすくなります。
そして、友達や周囲の目を気にして動けない子には、強制するのではなく、「〇〇してみるのはどう?」と選択肢を与えて誘導する形が効果的です。
子どもの自尊心を保ちつつ、自発的な行動につなげる工夫がカギです。
親の関わり方一つで、子どもの未来は変わっていきます。
小4の壁は、学習面と心の成長が同時に複雑に変化していく重要な時期です。
この時期に算数の躓きや反抗的な態度、睡眠不足といったトラブルの兆しが見えたら、早めに気づいて対策を講じることが欠かせません。
支援のポイントは、過去の基礎を丁寧に【今の学年に戻る力】をつけると同時に、未来に向かって自信を持って進む【前に進む力】を育むことです。
親としては焦らず、子どもの今の気持ちや声に耳を傾けながら、しっかり寄り添って伴走していく姿勢が大切です。
こうした関わりが、小4の壁を乗り越え、健やかな学びと成長の道を拓く大きな力になります。