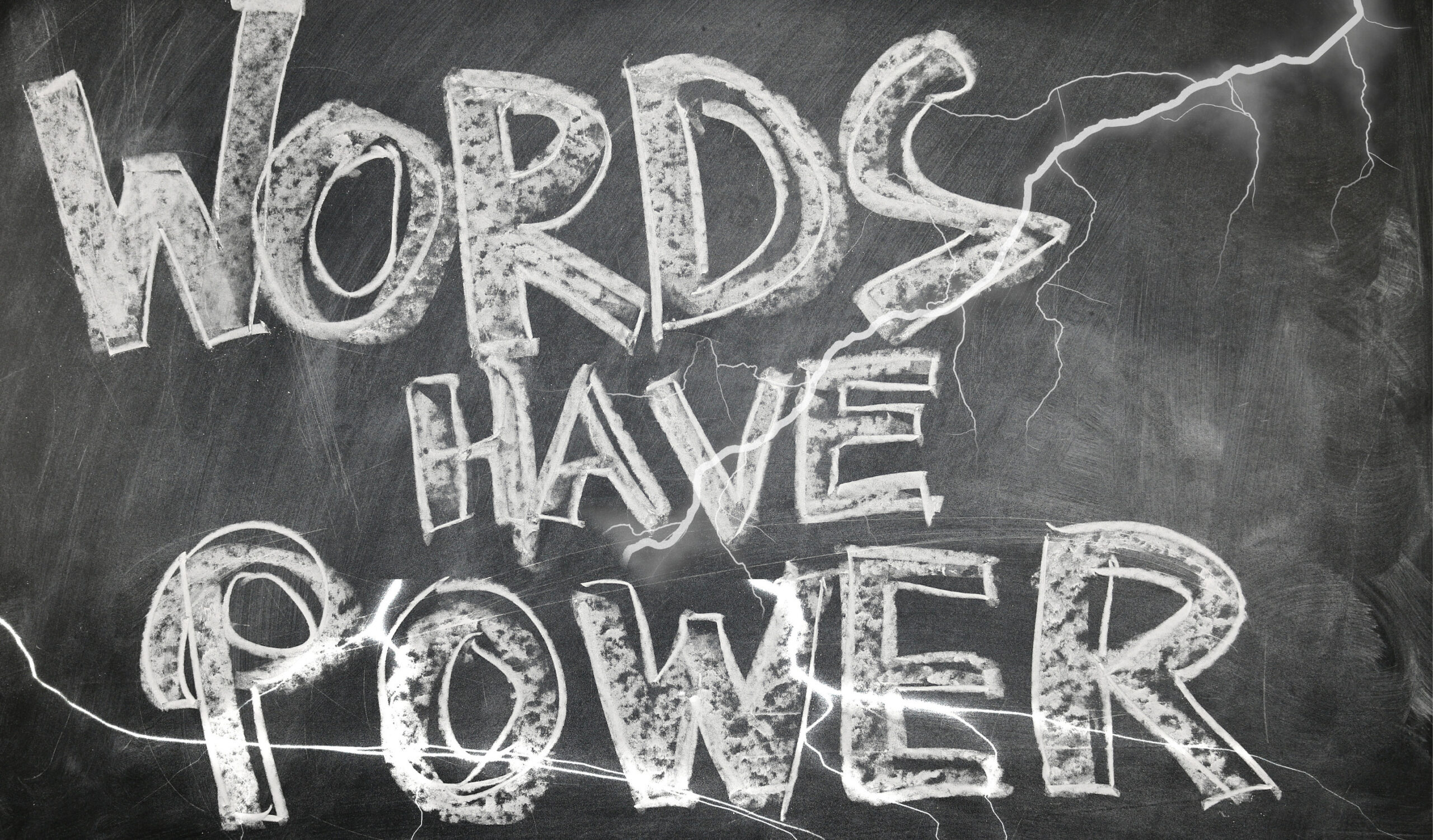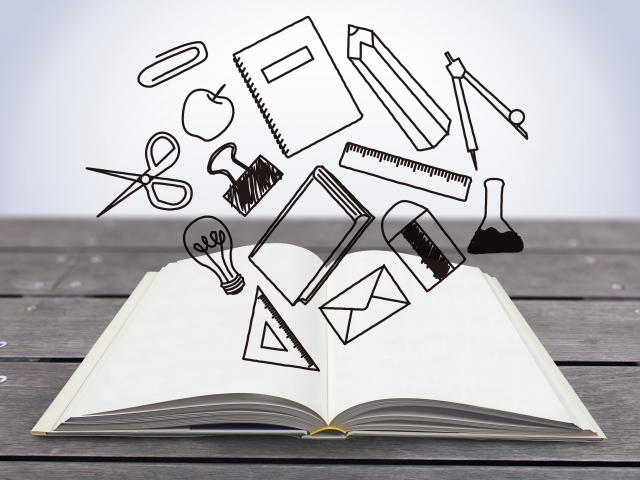今回は【進学校に近づくために小学生時代から取り組むべきこと】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
教育に関心の強い親は【子どもは大学に入る】ということを前提とした子育てをしていきます。
小学校に入る前から家でひらがなやカタカナの練習をしたり、数数えや簡単な足し算引き算を勉強させることや、学研や公文に通わせることもあります。
ただ、小学校6年間の間で先取り学習をしてきてリードしていても、小学校4年生くらいから後発組に追いつかれ、追い抜かれていき、中学生になったら【偏差値60以上の進学校に入るのはちょっと無理】となってしまう子もいます。
私の子ども時代、塾で出会った子ども達、そして子ども①②の周囲でも長いスパンで見ると、【あれだけ熱心に親が教育に情熱を注いでいたけれど子どもは伸びなかった】というケースがけっこうあります。
原因は各家庭によって異なるでしょう。
親の熱心さに子どもがついていけないことや、子どもの気持ちや子どもの生まれ持った学力スキルを完全無視して最初から飛ばし気味で勉強させたことで、心身ともに疲れさせてしまった
他人があーだこーだ言うのは色々と問題がありますが、教育熱の高い親としてはこうした事態になることは避けたいところです。
子どもを勉強嫌いにさせる理由もあれば、勉強をしっかりやる子に育てられる秘訣もあります。
まさに表裏一体のような話ですが、【こういうことをしていくとプラスになる】というものがあります。
そこで今回は世間的に進学校と言われる偏差値60以上の高校、有名大学への進学者も多くなる偏差値65以上の高校への進学を少しでも考えている時は小学生時代からどのようなことに親は気をつけ、そして子どもはどんな子に育てていけば良いのかをご紹介していきます。
自学自習できる子に育てる
まずは、親に言われなくても勉強する子、つまりは【自学自習できる子】に育てることがポイントになります。
中学受験では【自走できる子】というのが理想像として語られていますが、高校受験においても同じで【自分から勉強する子】というのは高い学力をキープする、成績を上げる、合格を引き寄せることができます。
言葉で言うのは簡単なので、親の方も【うちの子もそうなるはず】と期待してしまうところがあります。
しかし、実際は勉強をする子に育てるというのは親の誘導やサポートが不可欠です。
子どもの方は【気がついたら自分で勉強するようになっていた】という感覚かもしれませんが、そういう子の親は何も考えもせずに、教育方針もなく子育てしているわけではありません。
【自分から勉強できるようになれば子どもにとっても将来助けとなる】と思い、小学校入学前後から家庭学習が定着できるよう見えないところで試行錯誤を繰り返しています。
子どもの方が【自然と家で勉強できるようになった】と捉えているのは、親が子どもの性格を踏まえて嫌がらないような方法で少しずつ勉強する子になるよう、上手く誘導してきたからです。
これが、最初からガッツリ長時間勉強させる、ガミガミ言いながら勉強させる親であれば子どもの方も強烈な思い出として記憶していますし、そういう家庭はどこかのタイミングで子どもの教育方針で夫婦の衝突または親子の衝突が起きて進学校に近づくのが難しくなってしまいます。
いざこざが絶えない家庭を尻目に、自学自習できる子は学校の宿題の他にも親が準備した教材に取り組んでいき、問題のレベルも少しずつ上がっていき、学習量は徐々に増えていきます。
小学校高学年になる頃には集中して勉強できる時間がクラスメイトに比べると長かったり、中学進学に見据えて英語や数学の先取り学習をしていたりと余裕をもって勉強に取り組む子もいます。
自学自習できると親の方も不安、または不満をあまり感じていないので、子どもが成長して反抗期や思春期に突入した時に親と勉強について話をする際も【このままだと志望校に合格できないでしょ!】【うるさいな黙っていてよ!】といった喧嘩となる可能性も低く、家内安全でいられます。
受験生と接していると【親子関係の良し悪し】が子どもの成績、受験に向けた気持ちの不安定さを鎮めるということを感じました。
進学校を目指すのであれば、ただ勉強させれば良いというわけではありません。
家庭の中が平穏無事な中で子どもが勉強に励めるには、自分で勉強できるようになるために親が頑張り、サポートをし、そして子どもの性格を踏まえて無理のない範囲で【この時期はこの位の学習時間で様子を見る】と家庭学習の習慣を定着させるようにしてください。
将来について親子で話し合いをする
さて、進学校を目指す子というのは個人個人、目的意識が異なります。
【近所だから】と言う子もいれば、【親が行けとうるさい】【偏差値が高いから】という理由で目指す子もいます。
その一方で、受験では王道である【校風が自分に合っている】【将来の夢を考えるとその高校に行くのが一番の近道になる】【高校でやりたいことがある】という目的をもって勉強を頑張る子もいます。
どちらのタイプの子が受験という厳しい道を乗り越えられるかは言わなくても分かると思います。
また、晴れて合格となり、入学してからの高校の勉強を頑張れるのはどちらなのか、というのもすぐに分かるでしょう。
とくに大学受験をする場合は高校の勉強を横に置いて高校生活をエンジョイしていると、あっという間に学校の勉強についていけなくなります。
義務教育時代とは異なり、進学校の使う教科書や副教材は【難関大学を受ける子がちゃんと大学受験できるように】という前提で揃えられ、そして授業もハイレベル&ハイスピードです。
地方に住んでいると、大学受験が全国のライバルとの戦いだという意識を持ちにくく、高校受験と同じような感覚で乗り越えようとしている子もいますが、こうなると戦えるだけの学力を身につけておらず、ボロボロになってしまいます。
小学生時代から将来について親子で話をするということは、志望校を早めに明確にすることと、高校での勉強を怠けない、そして大学受験に向けて現実的な戦略を考えられる準備にもなります。
私はそうした準備がスッポリ抜けていて、高校入学後は大変苦労しました。
私の反省を活かして、子ども達とは小学生の頃から色々と将来について、進路進学に関して話をし、子どもの考えを踏まえて【こういうルートが良いのでは?】という話をしてきました。
子どもも親に話をすることで具体的に未来を考えるようになり、【自分はこういう道を歩んでいけるか】と自問自答をしつつ高校受験などを自分事として考えるようになります。
塾で出会った子どもたちの中には、自分のことなのにどこか他人事のような感覚でとらえている子達もいました。
そういう子は成績不振という子が圧倒的に多く、学力の高い子のように勉強を頑張る原動力となっている将来の夢がないという子も少なくなかったです。
スマートフォンやゲーム時間のルール作りの徹底
そして、進学校に近づくためには勉強時間を減らす存在でもあるスマートフォンとゲームのルール作りというのは不可欠です。
今の子ども特有の事情でもあり、実際に子ども①②③の周囲でもスマートフォンやゲームに夢中になって勉強時間がどんどん少なくなってしまった子もいます。
我が家の子ども①の周囲にいる神童さんの一人も、中学生になり親からスマートフォンを渡された直後に無料のアプリゲームを入れて夢中になってしまい、怖くなってゲームは全部消したと口にしていたそうです。
ただ、自分から気がついて削除できる子は本当に限られています。
【もう少しだけ】【もうちょっと】という気持ちが出てくると、勉強時間があっという間になくなってしまいます。
親世代の子ども時代はスマートフォンというものは存在しておらず、テレビや漫画、ファミコンやスーパーファミコンがその代わりだったと思います。
ただ、ゲームを除くと【延々と見たり読んだりする】ということはできません。
テレビ番組は30分や1時間と区切りがあります。
漫画も読めば終わりで、読み終わったらその場ですぐに何度も繰り返し読むということはしません。
しかし、スマートフォンは動画視聴、無料ゲーム、LINEでメッセのやり取りができるなど、1台で何時間も時間を潰せるアイテムです。
親が渡す前に家庭のルールを決めて、使用時間の厳守と守れなかったときの罰則、どのような使い方をしているのかを小まめに確認するなどして、学業に悪い影響を与えないように気を配る必要があります。
進学校、トップ高校に合格する子ほどスマートフォンの取り扱いに気を使っている印象があります。
ただ、合格したことで満足してしまうと、たとえ偏差値65以上の高校に入っても授業中にスマートフォンを操作してしまい勉強どころではなくなってしまう子もいるくらい中毒性のあるものですから、【うちの子は本人任せでも大丈夫】とは決して思わずに親も子もしっかり話をしてルールを決めてください。