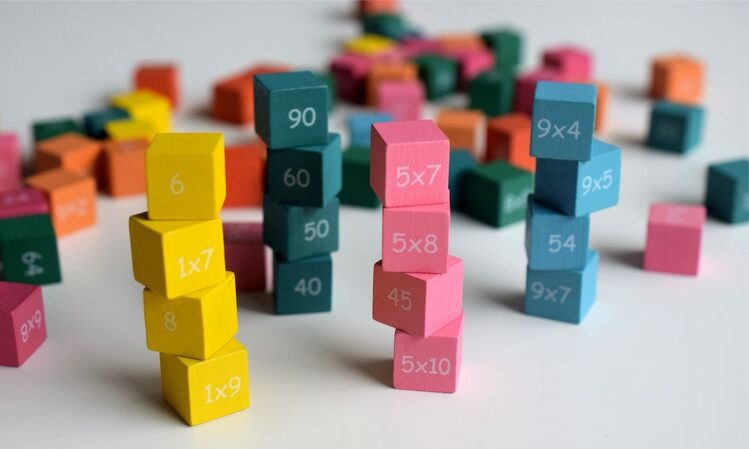今回は【算数のセンスがなくても算数嫌いにさせないコツ】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
算数という教科は【センスがあるかどうか】で説明されることが多く、しかも【センスがないから算数が苦手】で納得してしまう人も多い何とも不思議な教科です。
中学受験を考えている場合は、算数の出来不出来が合否に直結してしまうくらい重要な教科ですし、中学受験をしない小学生にとっても、割と早い段階から苦手意識を持つ子が出てきたりと、親としてはとても気になる教科と言えるでしょう。
しかも、小学校に入学する前から家庭で足し算や引き算の基本的な問題に取り組んでいる子もいたり、そろばん教室、公文、学研に通って算数がそれなりにできるよう仕上げた状態でいる子もクラスにいます。
計算スピードのように優劣を競い合うような勉強を通じて、子どもたちの間で【できる・できない】が入学した直後でハッキリしていたりします。
子ども①②の学年でも小学1年生から補助の先生がサポートして教えてもらっている子もいたので、そのくらい算数の学びというのは6歳、7歳頃から残酷な面もありますが差が分かってしまいます。
そして、学年が上がると算数も難しくなります。
それなりに家庭学習をしてきた子の中でも躓き、少し苦手意識を感じ始めるようになります。
そのタイミング小学校3年生、4年生で、難しい単元が次から次へとやってくる5年生になると算数に対して嫌だな、まぁまぁ得意かな、という気持ちが固定していきます。
私も塾で仕事をしている時に、何かしらの特定の教科に苦手意識を抱いている子の気持ちを変えるということがいかに難しいか、というのを経験してきました。
私は文系科目を教えていましたが、例えば英語が苦手な子、英語アレルギーの子を【そこまで嫌いではなくなる】とするには中学校卒業までになるかならないか、というくらいなかなか大変で時間のかかることでした。
まだ英語はセンスで語られる教科ではないので【勉強すればちゃんとテストで点数が取れる】という受け止め方を生徒達もしていました。
しかし、算数や数学は【自分にはセンスがない】と決めつけてしまうところがあります。
こうなると、算数の勉強を積極的にやることもないので、やはり算数嫌いにさせない、ということが親にとっては大きなミッションになります。
それでは、算数嫌いを避けるにはどういうことをしていけばいいのでしょうか。
算数は難しいなどマイナスな言葉を言わない
まず、親が【算数は難しい】【こんな問題もできないの】【算数はセンスがあるかないかで決まる】といったマイナスな言葉を子どもに言わないことが大切です。
小さな子どもにとって、親の言葉というのは絶対的です。
【お母さん、お父さんに言われたから自分は算数が得意な子ではないんだ】と思い込んでしまうきっかけとなります。
とくに親自身が算数がスラスラ解けた経験があると、我が子の算数の理解に時間がかかり、なかなか思うように正答率が上がらないとイライラが募り、ついキツイ言葉を投げかけてしまいます。
しかし、親が得意だからといって子どもも得意とは限りません。
私も、親が理系系の仕事に就いているけれど子どもは文系科目が得意という生徒と接する機会がありましたが、そういう子は親から【なぜできないのか】と責められてすごく苦しんでいました。
そして、自分の能力と比較してしまうと子どもは【自分は算数ができないんだ】と解釈して、悪い方に考えてしまい、算数が好きになることも得意になることもできません。
親は自分と子どもを同一化しないよう、掛け値なしの子どもの算数の理解力がどのくらいかということを把握してください。
また、算数が苦手だった親も【算数はすごく難しい】【割合とか速さなんて理解できるはずがない】と自分の嫌な思い出を子どもに伝えることは控えましょう。
親が苦手なものは自分も苦手だ、と子どもはどういうわけか思う傾向があります。
ですから、子どもの算数のテストや宿題に取り組む時間を色々と考えてしまう、自分の小学生時代に似ていると思っても、決して【お母さん、お父さんと同じで算数が苦手になる】という類の言葉は口にしないでください。
算数の勉強をさせる以前に、こうしたマイナスな言葉を言わないことが、算数嫌いにさせない第一歩になります。
センスの塊の子は別世界の人と割り切る
ただし、たしかに算数や数学に関して天才的なセンスを持つ子はいます。
子ども①②の周りにもいますし、どんなに頑張ってもあんな風になれないだろう、というのは子どもも親も感じてしまう別格な子がいます。
親が【あの子のようになりなさい】と無理に勉強させるのも酷なことです。
センスがある子というのは、大都市圏の最難関中学や高校に地方に住んでいるけれど合格できるような子、小学校高学年で中学内容を全部終わらせるような子、中学生であれば勝手に高校数学をガンガン進めていくような子です。
そして、理系学部で最難関大学にサクッと入れるような子でもあります。
こうしたことに真っ向勝負させるのは流石に酷です。
【世の中には超別格な子もいる】【レベルがすごいけれど少し参考になるところを探そう】と話をし、【自分はダメな子だ】という感情を抱かせないようにしてください。
我が家の子ども①②の周囲にもレベルが違い過ぎる算数、数学のセンスの塊の子がいます。
最初はその子達と自分を比べては落ち込んでいる様子がありましたが、【まぁまぁ、あの子達は異次元な子で宇宙人だと思おう】と声をかけて、子どものスローな算数や数学の成績向上を全力で褒めることにしました。
小学校高学年、中学生になる頃には【世の中にはああいう子もいる】と受け止めるようになり、今では気にせずに勉強できるようになりました。
勉強は思う以上に感情に左右されるところがあるので、凄い子が身近にいて【自分なんて・・・】と思っている様子であれば、そういう天才の子は別世界の人と割り切れるような言葉をかけていくようにしましょう。
解けた、分かった体験を増やす
さて、算数に限らず、勉強に対して苦手意識を払拭していくには【分かった!】という瞬間があると、学ぶ喜びを感じて、もっと頑張ろうという気持ちが芽生えていきます。
この気持ちを引き出すことができたら、【算数嫌い】から脱出する兆しが見えてきたと言っていいでしょう。
我が家では、子ども②が塾の算数に対して抵抗感が強めで、一歩間違えれば算数嫌いになりそうな状態だったことがありました。
塾算数は学校の算数と異なる点もありますが、算数というジャンルでは【これまで分からない問題が解けた】となると、他の教科以上に喜びが大きく、【自分もやればできるんだ】と思ってくれます。
算数が苦手な子は、解く前から【自分には無理】と拒絶する傾向があります。
まずは、【自分でも解ける】と実感させていくことが大切です。
親の方も【こういう問題が解けるようになりたい】と思わず、子どものリアルな学力よりもやや簡単だと思うような問題に取り組んでいくようにして、少しずつ自信をつけるよう計画を立ててください。
基本問題を繰り返し解いていき、次には少し応用問題も解き、分からない時は解答の説明を読みながら解き方を考えていき、次は解答を見ずに類題を解いていくという勉強を続けていくと、応用問題を解ける力がついていきます。
正直、短期間で結果が出るわけではありません。
我が家の子ども②の場合、成績がほんの少し上向きになるのに4カ月から5カ月はかかりました。
つまり、半年弱です。
しかも、結果が出るまでの時間もどのくらいかかるかは個人差があります。
どうなるか見えない中で続けるというのは苦しいものがありますが、
投げやりになりそうな時は、親も励ます言葉をかけましょう。
【解けるようになった】【以前は基本問題もパーフェクトではなかったけどできるようになった】という改善した点をしっかり伝えるよう心がけてください。