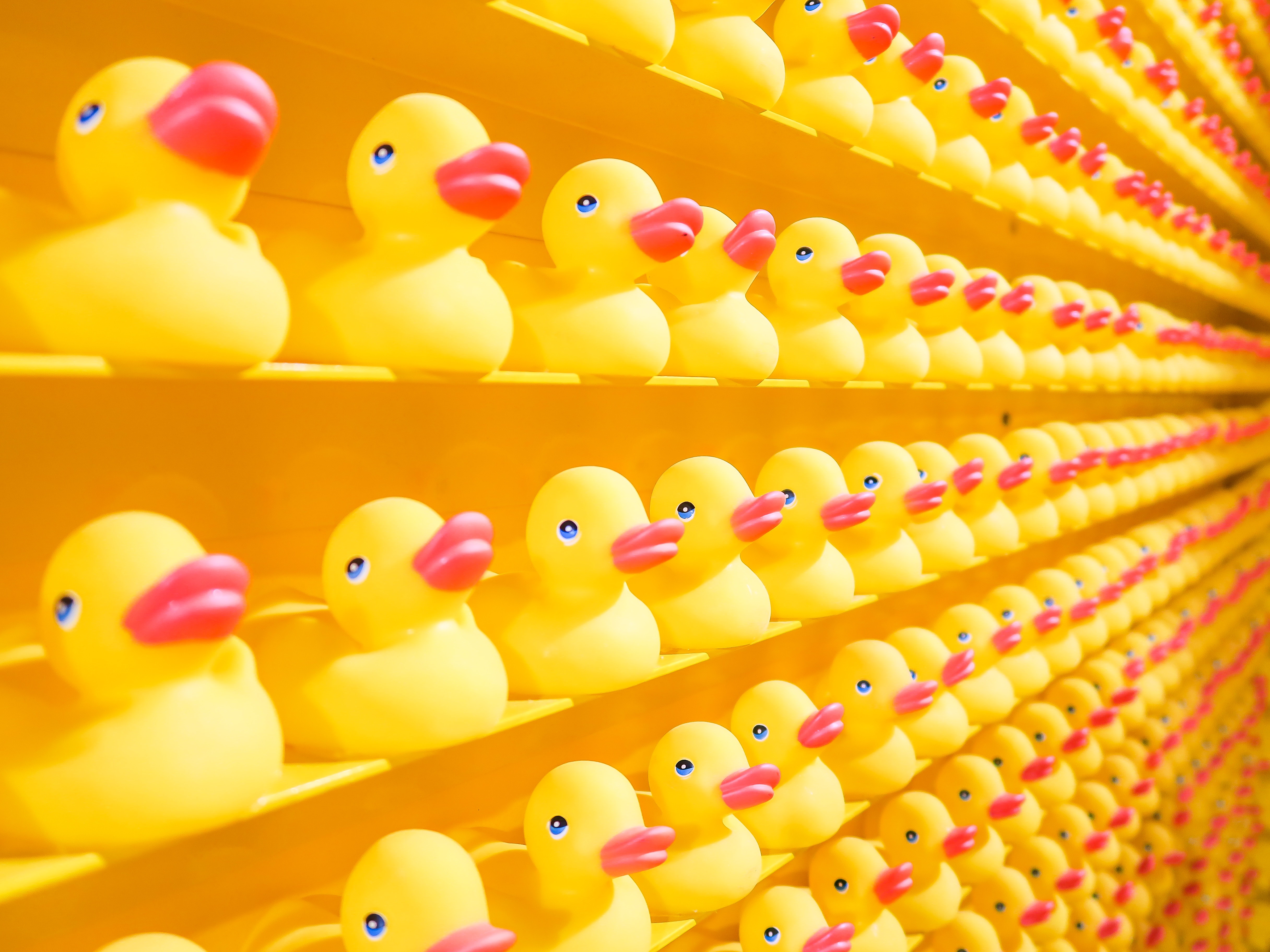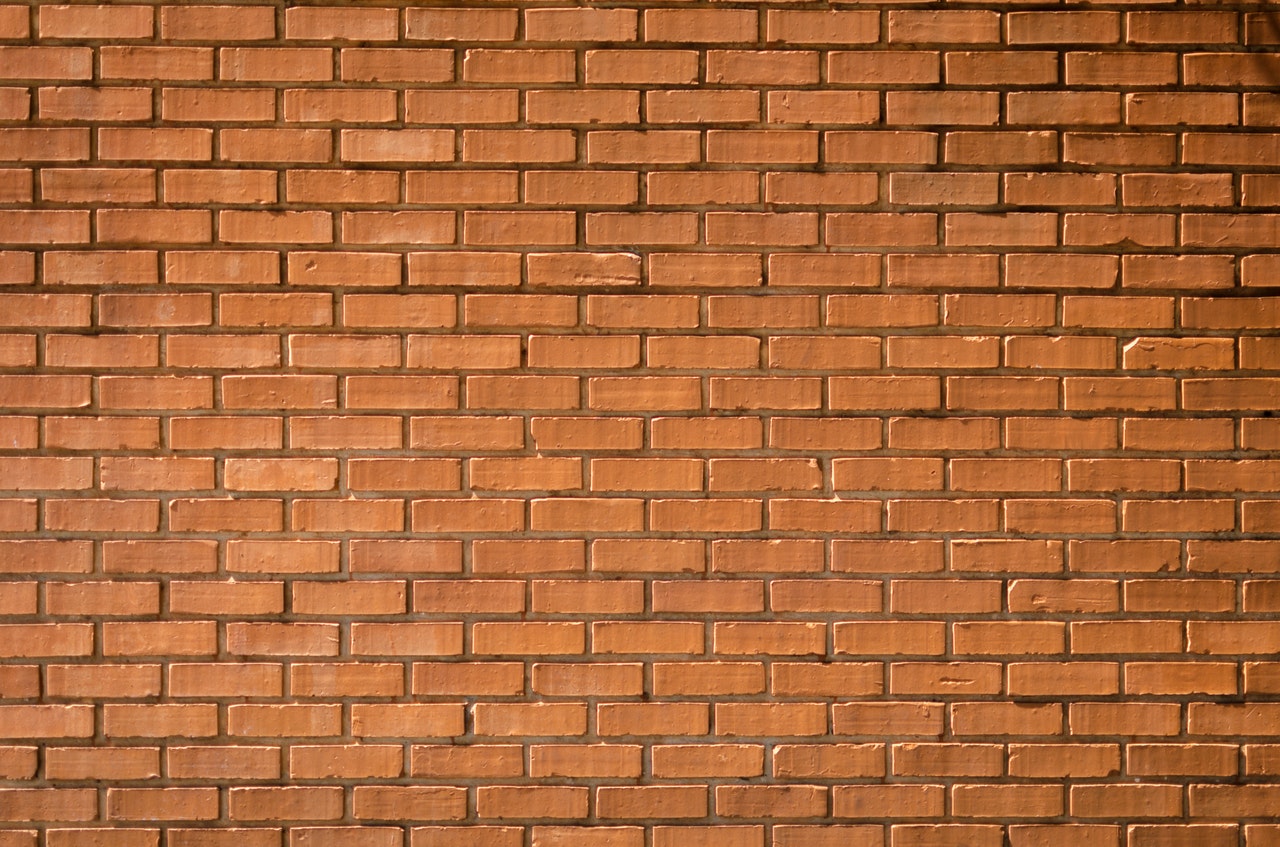これまで、家庭学習の定着の大切さを訴えてきたつもりです。
低学年から実行していくと、その後は勝手に自分から学習計画を立てて勉強してくれる可能性が飛躍的に高まります。
まだ1年生だから、と放置するのはもったいないです!
あとで苦労するのは子供本人。
今回は、今まで書いてきた記事をまとめてみました。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
低学年は家庭学習を身につけるチャンス
私はグータラ小学生だったので、中学1年時に猛烈な努力によってそのツケを払いました。
いや、払いきっていなかったのは高校入学後にトップ層の同級生と出会い痛感したのです。
塾で仕事をしているときも、中学生では心入れ替える子はほぼおらず、小学校高学年で学力の固定化が進んでいることが判明しました。
今、3人の子供を育て、上の2人は小学生になりました。
就学時から、家庭学習を身につけるべく試行錯誤。
その結果、勉強に前向きに取り組む子にとりあえず成長しています。

家で使う教材を吟味する
新学期早々は、新しいクラスなどに慣れるため、勉強どころではないかもしれません。
まだいいか、と思わずに、1日5分程度の家庭学習を実行してみましょう。
アレコレ目新しいドリルや問題集に飛びつきたい親の心理、分かります。でも、コレクターにはならずに1冊終わり切るモノを選ぶようにしてくださいね。
さて、低学年だと勉強の大切さを深く理解していないとは思います。ちゃんとやらないと困るらしい、くらいの感覚かもしれません。
親があ~だこ~だ説明しても、頭に入らない可能性もアリ。
そういう時は、文字(漢字など)をたくさん知っておいた方がお友達との会話が楽しくなるよ、計算が速いとカッコいいね!、と持ち上げる手段が一番です。
我が家の子供①&②はそんな罠にはまりました・笑。

↑は、1年生向けの教材を複数紹介しています。
1年間を通じ、どのタイミングで使用したのかも書いてあるので参考にしてください。
↓は2年生向けの記事です。

2年生というと、九九を思い浮かべる方が多いと思いますが、隠れ躓きポイントの単位換算についても書いています。
また、春先に店頭に並ぶ【教科書ワーク】は秋や冬以降に取り組ませると、学年の復習になり導入をおススメします。
⇒ 【灯台下暗し】やっぱり復習は重要、と気づかされた教科書ワーク
苦手単元克服
公文では、つまづきポイントにクローズアップしたドリルなどを出版しています。
我が家の子供②は、このシリーズの「は・を・へ」を使用して克服に励みました。
小学生の苦手ポイントをよく理解しているな、公文、と思うようなシリーズ。
なかなか、こういった単元のみを扱ったドリルってないんですよね。
あったとしても、応用系だったりします。
保護者に知ってもらいたい情報
本屋さんなどでは、賢い子になる系の本がたくさん売られていますよね。
塾で仕事をしていて感じたのは、こういう家庭環境・考えだと子供は勉強しない子になる、を世に広めた方が役に立つのでは、ということ。
そのために、書いた記事がコチラになります。

子供が成長し、自覚が芽生えて自分から勉強してくれる♪、はハッキリ言って幻想です。
中には、超レアケースでいるかもしれませんが、50ctのダイヤモンドみたいにレアです。
勉強するための小道具
低学年ですと、すんなり勉強するようになる子もいれば、グタグタ系の子もいます。
後者のタイプの子には、ぜひご褒美作戦を試してみてください。
我が家はドーナツ作戦と題して10日間家庭学習したらドーナツ1個ゲット!、を実践。そのうち、勉強が当たり前のようになってきてドーナツ気にならなくなりました・笑。
そして、低学年の親御さんなら気にするであろう【計算スピード】は小道具を使って改善を狙います。

公立小の学習指導のチェック
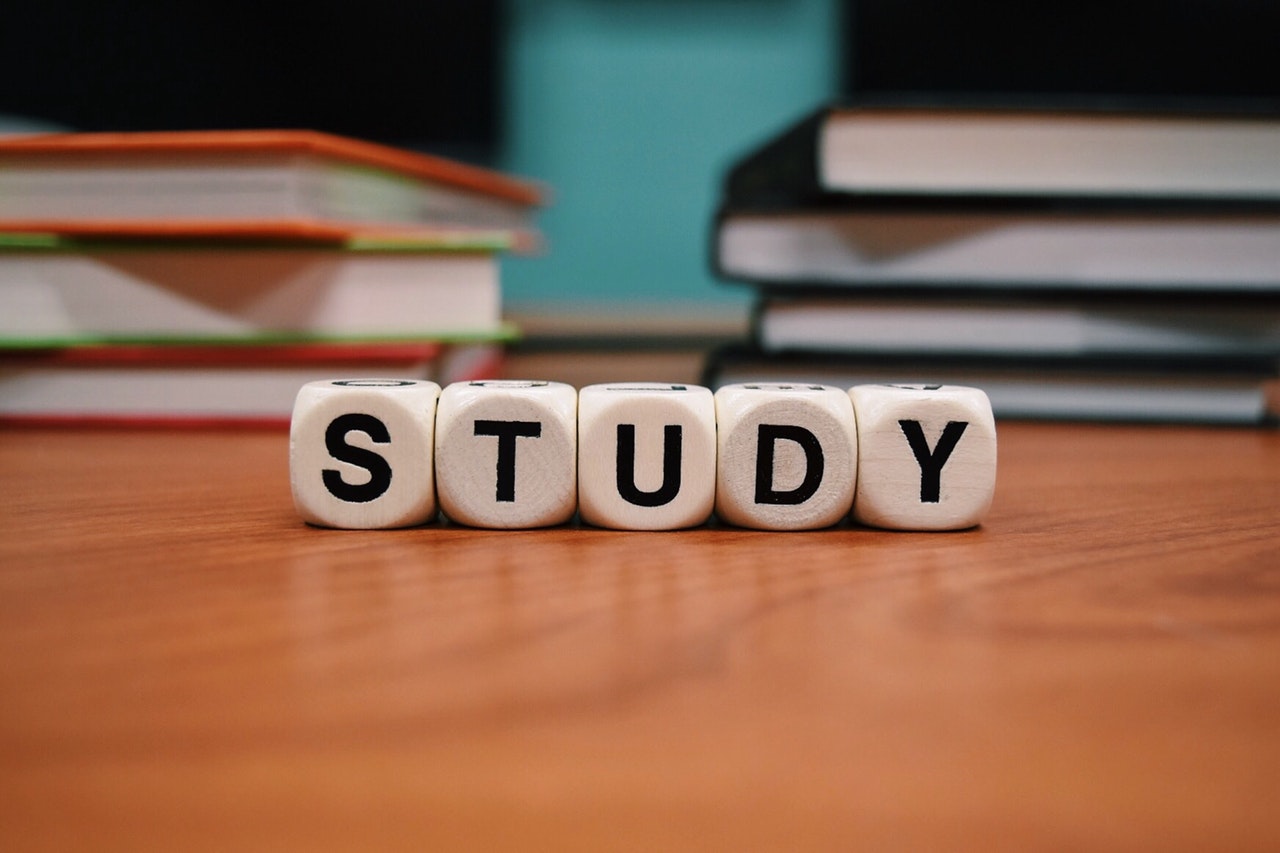
学年主任の先生の考えで学習指導がゆるくなる場合があるのを、子供②の1年時に経験しました。
同じ小学校でも、子供①は新学習指導要領(教育改革)に向けて、先生方も工夫しているのを感じていただけに、衝撃的でしたね。
こういった場合は、家庭か公文や学研、通信教材などでカバーするしかありません。

とくに1年生は学校の先生の言うことが全て正しい、と思うので、親がアレコレ悪口を言わずにそっとサポートすることをおススメします。
他にも公立小に通って感じて書いた記事を2つ紹介します。
まとめ
あっという間に低学年の時代は過ぎ去っていきます。
地方都市でも、小学4,5年になると通塾の話や習い事の整理の話がママ間で話題になってきます。
家庭でするのか、学研&公文を使用するか、通信を頼むか。
方法は何通りもあるので、お子さんと家庭のスタイルに合った勉強法を導入してみてください。
王道のところを比較したのが以下の記事です。
小学1年生がどうやって家庭学習を身につけたかを書いた記事はコチラになります。
完全に我が家スタイルです。ユルイですが、こういった方法もあるのか、と参考にしてみてください。
2017年度、子供①が小3、子供②が小1の時に使用した問題集の紹介している記事はコチラ↓
⇒ 元塾講師ママが選び、使用した問題集【参考程度にして下さい】
低学年から勉強意力を培うためのポイントが書いてあります↓