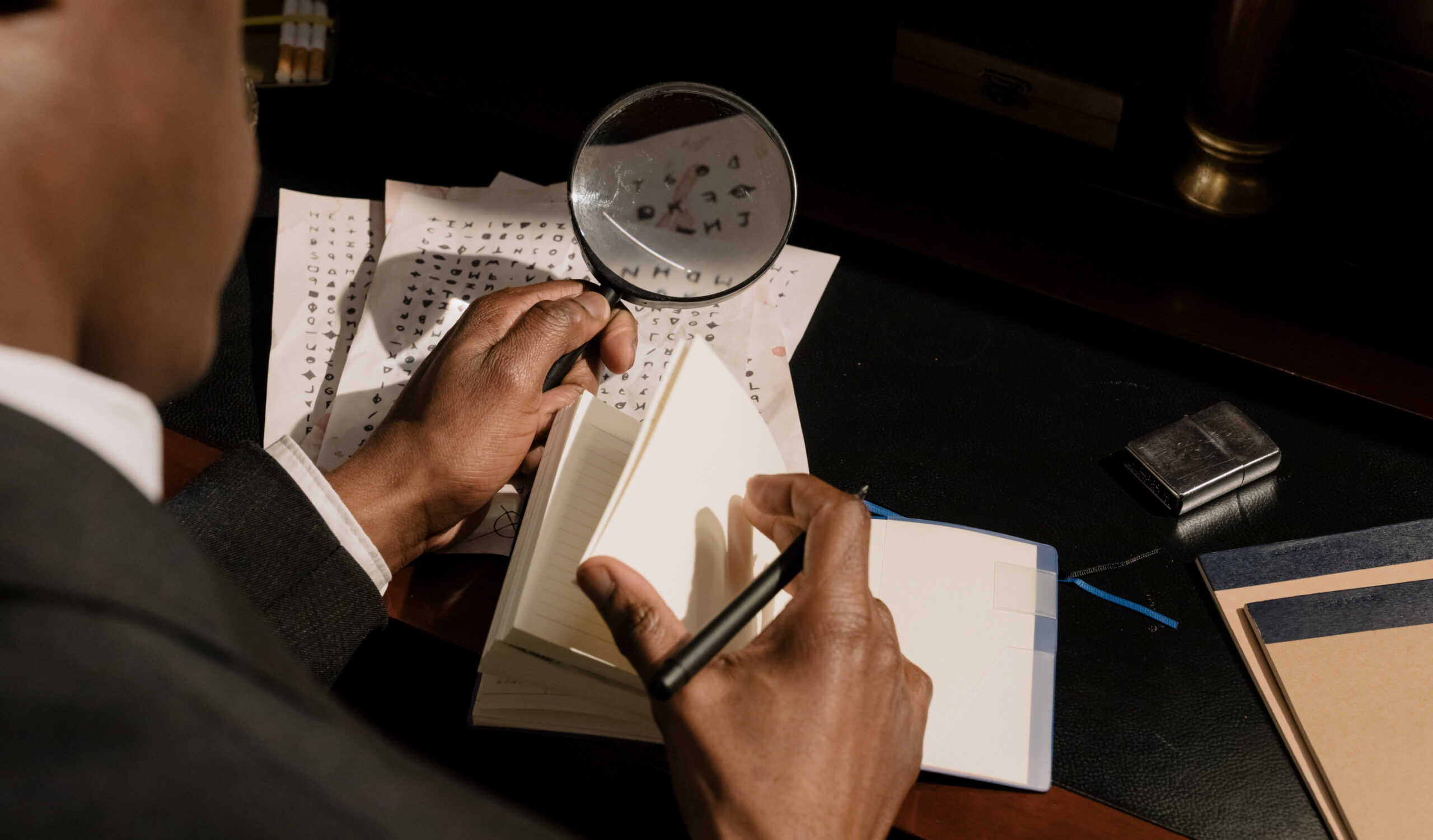今回は【公立中学で勝つ! 公立中で上位キープする子】と題し、お話していきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
公立中学校に進学すると、小学校とは異なる学習環境と評価制度に直面します。
複数の小学校が集まり同級生の人数も増える学校生活、部活動、先輩後輩といった人間関係の問題、定期テスト、提出物の締め切り、そして内申点。
牧歌的な雰囲気から、ちょっとした社会人のような世界に足を踏み入れることになります。
その中で【学力上位層にいる】ためには、ただテストで点数を取るだけでは足りません。
むしろ、毎日の【コツコツ型】の習慣を丁寧に積み重ねている子が上位をキープしています。
なぜ【コツコツ型】が強いのでしょうか。
それは、多くの変化や波のある中学校生活の中で、一時的な追い込みではなく、安定的に学習し続けるベースがあるからです。
定期テストで結果を出すのも大事ですが、むしろ毎日の授業態度、ノートや提出物、復習の仕方、生活リズムといった細かな積み重ねこそが、先生からの評価や実力の基盤となります。
そこで今回は、まず上位層にいる子の3つの特徴を整理します。
次に、今の位置から上位層を目指すための3つの改善策を紹介します。
そして最後に、親子で意識を変えていくための3つの意識改革をお伝えします。
親として何を見守り、どのように支えれば良いかを具体的に考えていきましょう。
上位キープの子が持っている3つの特徴
まず、公立中学校で安定して上位をキープしている子どもには、全員が特別な才能があるわけではありません。
正直、地方においてもそのエリアの最上位層は公立中高一貫校などに進学していることも少なくないため、各小学校のナンバー2、ナンバー3だった子たちが学区の中学でトップ争いをしていたりします。
そういう事情もあり、公立中学の多くの上位層の子たちは、日々の学びや生活において【地味で継続的な努力】を積み重ねているコツコツ型タイプが中心です。
短期間の追い込み型では、学力を一時的に上げることはできても、それを維持するのは困難です。
公立中では、定期テストの点数だけでなく、授業態度、提出物、日々の学習姿勢などが総合的に評価されるため、日々の行動がダイレクトに内申点へとつながっていきます。
ここでは、公立中で上位を維持する子たちが共通して持っている【3つの特徴】に注目します。
いずれも、決して才能や特別な環境によるものではなく、家庭でも意識すれば再現可能なものばかりです。【うちの子はそこまでやっていないかも】と感じたら、ぜひ今日から少しずつ取り入れてみてください。
点数の裏にある見えない努力こそ、学力を下支えする本質なのです。
特徴①授業中の参加と提出物の質が高い
上位をキープしている子どもに共通するのが、【授業に真剣に取り組む姿勢】と【提出物の完成度の高さ】です。ただ椅子に座って話を聞くだけではなく、授業中に先生の話を積極的にメモしたり、黒板に書かれたことを自分なりに整理してノートをまとめたりしています。また、分からない部分があれば放課後に質問するなど、理解を深めるための行動も見られます。
さらに、提出物に対しての意識も非常に高く、ただ出せば良いという考えではありません。
きちんと期日を守るのはもちろん、内容も丁寧で誤字脱字が少なく、調べたことや自分の考えを書き加えるなど、先生が【評価したい】と思う工夫が自然とできています。
このような日常の積み重ねは、テストの点数だけでは測れない学びの質を育て、内申点の加点にも直結します。
学校という評価の場では、【きちんと取り組んでいる子】という印象が積み重なり、信頼という形で学力にも反映されていくのです。
特徴②毎日の復習を習慣化している
上位の子たちは、毎日の学習内容をその日のうちに軽くでも復習する習慣が身についています。
これは、定期テスト前に一気に詰め込むような学習スタイルとは対照的です。
例えば、授業で出た新しい用語や公式をノートで再確認したり、宿題の間違い直しを丁寧にやったりすることが習慣化されています。
復習といっても、長時間かける必要はなく、1日10〜15分程度で十分です。
この【短くても毎日続ける】という積み重ねが、知識の定着に大きな差を生みます。
学んだことを翌日までに一度整理するだけで、記憶への定着率は大幅に上がります。
また、復習することで授業の内容がより深く理解できるため、次の単元や応用問題にもスムーズに対応できるようになります。
多くの子が【授業を聞いてもすぐ忘れてしまう】と感じる一方で、上位層は忘れる前に手を打つ学び方をしているのです。
毎日の学習習慣が、成績の安定と伸びに直結している好例と言えるでしょう。
特徴③生活リズムと時間管理が整っている
成績上位をキープしている子どもは、学習内容だけでなく【学ぶための土台】である生活リズムもしっかり整えています。
たとえば、朝は決まった時間に起き、夜はダラダラせずに早めに就寝。
スマホやゲームの時間も自分でコントロールできており、学習時間とのバランスを保っています。
こうした安定した生活リズムは、集中力や記憶力、さらには学習意欲にも大きく影響します。
また、時間の使い方が上手で、無駄な時間を減らしてすきま時間を学習に活かす工夫も見られます。
休み時間に単語帳を見たり、部活動の前後にワークを1ページだけ進めたりと、短時間でも継続的に学んでいるのです。
このような時間の意識があると、【あとでまとめてやる】ではなく【今やれることをやる】という行動に変わります。
生活と学習がうまく連動していることで、自然と学力の高い状態を維持できるようになります。
このように、地元の公立中学の上位層の子どもは、私立中高一貫校のような神童さんがひしめき合う世界ではなく、日々の習慣や環境作りを地道に続けて学力向上をしている子が大半を占めています。
上位キープを目指すための3つの改善策
さて、【うちの子は頑張っているのに成績が伸びない】【上位に入りたいけど、何を変えればいいのかわからない】と感じているご家庭は少なくありません。
実は、学力上位の子とそうでない子の差は、才能ではなく【やり方】の違いにあることが多いのです。
ほんの少しの工夫や視点の切り替えによって、学習効率は大きく変わります。
この章では、今の学力や成績にかかわらず取り組める【具体的な改善策】を3つご紹介します。
どれも特別なスキルや高価な教材は必要なく、日常の中で取り入れられる実践的な方法です。
重要なのは、継続できるかどうか。無理なく取り入れ、習慣化していくことで、お子さん自身の学びの質を底上げし、確実に上位キープへの道を開いていくことができます。
まずは家庭での小さな変化から始めてみましょう。
積み上げたものは、確実に結果となって表れてきます。
改善策①学習の【小さな習慣】をつくる
いきなり毎日1時間、2時間勉強する!と意気込んでも、長続きしなければ意味がありません。
上位層の子が実践しているのは、【小さな習慣】の積み重ねです。
たとえば、毎晩寝る前にその日の授業で出てきた語句を5つ復習する。
朝食前に10分だけ英単語を見る。
ワーク1ページを【終わらせるのが日課】など、負担の少ないルールを自分で決めて、無理なく続けていくのです。
この続けられる仕組みを家庭でサポートすることが、最も効果的な学力向上の土台になります。
【完璧にやること】よりも【毎日やること】が大事です。
脳は繰り返し触れることで、情報を長期記憶に移す性質があります。
短くても、毎日繰り返すことで知識が定着し、学習に対する自信も育ちます。
また、小さな成功体験を積むことで、勉強への苦手意識が薄れ、【やればできる】という自己効力感も育っていきます。
勉強が特別なことから日常の一部になると、やがてそれは他の子との差になります。
小さな習慣が、大きな差を生むのです。
改善策②【振り返りノート】で思考を整理する
成績を伸ばしたいなら、【できなかったこと】と向き合う力が不可欠です。
そこで効果的なのが、自分の理解を整理するための【振り返りノート】の活用です。
これは、授業や家庭学習のあとに、自分なりに【今日学んだこと】【間違えたこと】【わからなかったこと】を簡単に書き残すノートです。
ポイントは、完璧にまとめる必要はなく、自分の頭の中を【見える化】すること。
この習慣を続けることで、自分の弱点や理解不足が明確になります。
さらに、振り返った内容を週末に見直すことで、知識が定着しやすくなり、応用力や記述力も向上していきます。
ノートに【どう考えたか】【なぜ間違えたのか】といったプロセスを書くことは、思考を深める訓練にもなります。
多くの子はテストの点数だけに一喜一憂しますが、振り返ることで【成績を上げるためのヒント】が見えてくるのです。
また、親がこのノートを一緒に見ることで、学習の過程に寄り添い、的確な声かけやアドバイスもしやすくなります。
結果ではなく、プロセスに注目する学び方こそ、安定して成績を伸ばすカギなのです。
改善策③生活リズムを整えて学習の土台を固める
学習の質は、生活のリズムに大きく左右されます。
上位層の子が安定して力を発揮できるのは、体調管理ができており、心身ともに学びやすい状態を保てているからです。
反対に、夜更かしやスマホの長時間使用が習慣化していると、集中力が落ち、学習効率は確実に下がってしまいます。
そこでまず見直したいのが【睡眠時間】と【学習時間の確保】。毎日同じ時間に寝起きし、余計なダラダラ時間を減らすだけで、1日30分〜1時間の学習時間は簡単に確保できます。
また、スマホやゲームは完全禁止にするより、【使う時間を決めて守る】ルール作りが現実的です。
大切なのは、子どもが自分の生活リズムを意識し、自己管理できる力を育てることです。
さらに、家庭の中で【勉強がしやすい環境】を整えることも重要です。
テレビや音の少ない空間、机の上が片付いている状態など、集中しやすい環境づくりが、毎日の学習を後押しします。
生活の土台が整ってこそ、学習の成果も安定して出るのです。
中学校生活でのトラブルを遠ざけて上位層に近づく秘訣
ところで、中学校生活では、学力だけでなく【学校生活での安定】も、上位をキープするための大きな要素になります。
とくに思春期に差し掛かる中学生は、友人関係、部活動、スマートフォンの使い方など、学習以外の場面でも多くの問題や誘惑に直面します。
これらの【学習以外のトラブル】は、集中力を削ぎ、勉強へのモチベーションを落とし、結果的に成績を下げる要因となるのです。
多くの親は、テストの点数や宿題の有無には敏感でも、子どもの日常生活の中に潜む学力低下のリスクには気づきにくいものです。
とくにスマホの使い方やLINEトラブル、部活動の影響などは、学習に直接関係ないように見えても、実際には大きな影響を及ぼします。
逆に言えば、これらをうまくコントロールできれば、勉強に集中しやすい環境が整い、自然と学力も安定していくのです。
ここでは、中学校生活における3つの代表的な【落とし穴】と、それを避けて上位層に近づくための具体策をお伝えします。
何か特別なことをする必要はありません。
ちょっとした意識の違いや親子での事前の話し合いが、トラブル回避と安定した学力維持のカギになります。
秘訣①LINEトラブルを未然に防ぐ親子のルール作り
LINEは便利な連絡ツールですが、中学生にとっては人間関係のトラブルを引き起こす温床にもなり得ます。
みんなが使うグループLINEでは、【既読スルー】【返信の遅さ】【言葉の誤解】などが原因で、無視や仲間外れといったトラブルが発生しやすいです。
子どもはそれを気にしすぎて、メンタルを消耗し、勉強に集中できなくなるケースも多く見られます。
こうした問題を防ぐためには、スマホを持たせる前に、親子でしっかりとルールを話し合っておくことが必要不可欠です。
たとえば【夜9時以降はスマホを使わない】【不快な内容はすぐに相談する】【人の悪口は書かない】など、明確な基準を共有することがトラブル回避に役立ちます。
さらに、ルールを一度決めたら終わりではなく、定期的に見直すことも重要です。
実際に使い始めてから感じることもあるため、【困ったことはいつでも話していい】と子どもに伝えておくことで、トラブルが大きくなる前に気づくことができます。
親の過干渉ではなく、適度な見守りが子どもの心を守り、安定した学校生活と学習環境を支えていきます。
秘訣②スマホ依存を防ぎ学習習慣を守る
スマホは中学生の生活に欠かせないアイテムになっていますが、使い方を誤ると、たちまち学力低下を招く原因になります。
SNSや動画アプリは時間を奪いやすく、気づけば1時間、2時間と無自覚に過ぎてしまうこともあります。
これにより学習時間が削られるだけでなく、脳の処理能力が下がり、集中力の低下や睡眠不足を引き起こす可能性もあります。
こうした事態を防ぐためには、家庭でのスマホ使用ルールを明確にし、子ども自身が【使い方を選ぶ力】を持てるようにすることが大切です。
たとえば【勉強の時間は通知オフにする】【21時以降はリビングで保管】【SNSは30分まで】など、具体的で実行可能なルールを一緒に作ることで、納得感も得られ、守りやすくなります。
また、子ども自身が【スマホを触らない時間】を意識的に作る工夫も有効です。例えば勉強の前後に少し散歩をしたり、紙の本を読んだりすることで、デジタルから距離を取る時間を確保します。スマホを完全に遠ざけるのではなく、自分を律する力を育てることが、中学生活の中で上位を維持するための基盤になります。
秘訣③学力との両立を見据えた部活選び
中学校生活の大きな柱となる部活動。友人とのつながりや学校生活の充実感を生む一方で、活動時間の長さや人間関係のストレスが、学習に支障をきたす場合もあります。
とくに強豪運動部や週末も遠征がある部活では、勉強時間を確保できず、成績がジリジリと下がってしまう子も少なくありません。
だからこそ、部活選びの段階で【学力との両立】を視野に入れることがとても重要です。
好きなことを続けるのは大切ですが、それが生活リズムや勉強時間を圧迫しすぎないか、事前にしっかりと見極める必要があります。
たとえば【週3程度の活動で十分な文化部】や【活動時間が短めの部活】を選ぶことで、学習とのバランスが取りやすくなります。
また、どの部活に入っても、【時間の使い方】を意識することがポイントです。
すき間時間を活用して宿題をこなす、テスト前は練習後に集中して勉強するなど、自己管理力を鍛えることで、どんな部活でも両立は可能です。
親は【成績が下がったらやめなさい】と言うのではなく、【どうやったら続けながら成績も保てるか?】と、一緒に考えてあげるスタンスが理想です。
部活動も学びの一部として、上手に取り入れましょう。
学力差を超えるのは派手な才能より【日々の積み重ね】
中学校生活は、小学校とは比べものにならないほどスピードも内容も濃くなり、学力差が一気に広がる時期です。
しかし、決して【最初から優秀な子】だけが勝ち残るわけではありません。
今回ご紹介してきたように、上位をキープする子たちに共通するのは、地味だけど確実に続ける力を持っているという点です。
最初に上位層にいる子の特徴として、計画的な学習習慣、自己管理能力、そして生活全体の安定感を紹介しました。
次にそれらを身につけるための具体的な改善策として、小さな習慣作り、振り返りノートの活用、生活リズムの見直しを提案しました。
そして最後に中学生となってから気にすべき学習以外で足を引っ張りやすいスマホやLINEトラブル、部活選びの注意点を通じて、勉強に集中できる環境づくりの重要性をお伝えしました。
【うちの子は優秀じゃないから無理かも】と思う必要はありません。
むしろ、【地道に、少しずつ】を大切にできる子こそ、学力の波に飲まれず、長く上位で戦っていけるのです。
親ができる最も大きなサポートは、【結果】より【努力の過程】に目を向けてあげるようにしてください。
そして、生活面からの安定を支えることです。
中学校生活は3年間と短いです。
ただ、子どもの人生を左右するくらい重要な時期でもあります。
今日から一つ、小さなことを始めてみましょう。
それが明日の学力の差を生む第一歩になります。