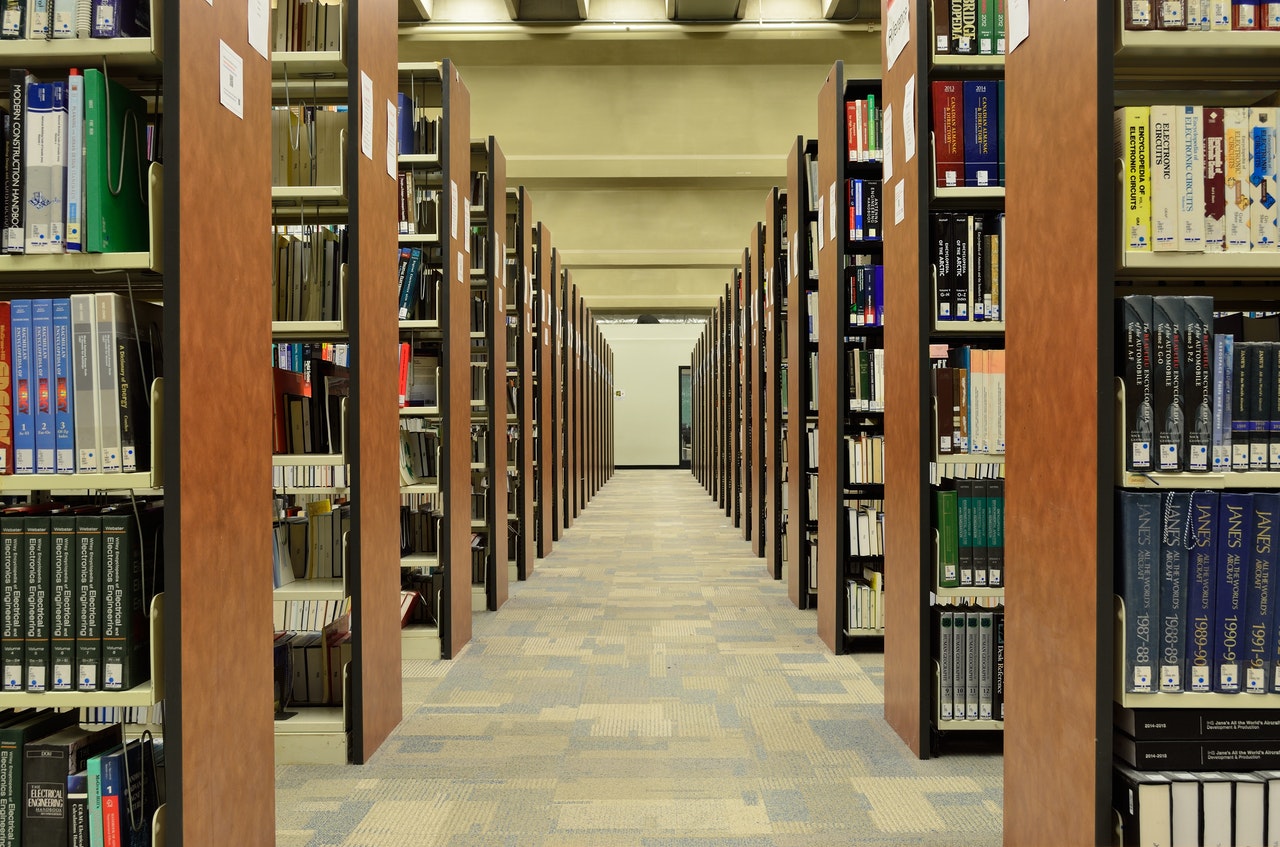今回は【小学6年生で学力上位層に残る子の勉強法】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
公立小とはいえ、小学校6年間でクラス内では学力差がハッキリしてきます。
親としてはなるべく勉強で困らない、できれば学力上位層にいて、そのまま中学に進んで欲しいと願ってしまいます。
それでは、どういう勉強を心がければ小学校ラストイヤーである6年生で学力上位層にいられるのでしょうか。
子どもの学力はとくに3年生、4年生の時に振るいかけられ、学力グループが出来上がっていきます。
難しくなる勉強内容を理解できる子しか上位には残りません。
残るというのはけっこう大変で、親がそれなりに勉強に関して気をつけていても、確実に上位層になるとも限らないのです。
残る残らないは子どもの学力スキルの違いが影響することもあります。
とくに小学生では、吞み込みの早い子、暗記力や理解力がかなりある子は学校の授業だけで全てを理解できるような子もいます。
【勉強は宿題だけだよ】でもカラーテストで満点連発している子もいます。
ただ、こういうタイプの子は子どもを持つ親からすると参考にできるところが少なく、真似したいとは思わないでしょう。
やはり、大半の親は勉強をやったりやらなくても良い点数が取れてしまうタイプの子より、【しっかり勉強して学力上位層になっている子】に近づけることを求めてしまいます。
そこで今回は、小学6年生になってもクラスや学校で学力上位層でいられる子の勉強法をご紹介していきます。
学校の宿題と家庭学習時間が他の子より多い
まず、6年生になると学校の勉強も難しくなるだけでなく、中学進学が目前に控えるためこれまでの小学生とは違う感じで勉強と向き合う必要があります。
学力上位層の子は学校の宿題をし、この他に家庭学習をしていきます。
6年生になると塾に通っている子、通信教材を使用して勉強している子もいますが、放課後の勉強時間はかなり増えてきて、受験しなくても、習い事のない平日は2時間から3時間近くという子も珍しくないです。
ちなみに、中学受験をした子ども①②の小学校6年生時代の勉強時間は、学校の宿題と塾の勉強を含めると平日は3時間くらいはしていたと記憶しています。
子ども②の親友は中学受験をしない子でクラスで上位層の子でしたが、小学6年生の時点で塾に通い、その子は【習い事のない平日は毎日2時間くらいは勉強している】と口にしていました。
入学したばかりの頃はさほど学習量の違い、というのは感じないのですが、2年生、3年生、そして4年生になると【家で勉強していない子としている子】がハッキリしていきます。
高学年になると宿題を10分程度で終わらせ、その他の時間はずっと遊んでいる子もいます。
そうなると、毎日の勉強時間は両者の間で2時間以上の違いが生まれます。
平日5日間で考えるとザクっと10時間から15時間の差があるわけですから、学力差が広がっていくのもある意味当然なことかもしれません。
成績が良いには理由があるわけで、他のクラスメイトよりも努力をしているというのは学力上位層になる必須条件になります。
ただ、6年生になったらいきなり2時間、3時間勉強させるというのは無理があります。
学力上位層になる子は、低学年の頃から少しずつ学習時間を増やしていき、6年生になった時点で【平日何もない時は2時間から3時間は勉強している】という状態になっているわけです。
学習量を増やすのも徐々に、時間をかけていくのが子どもにとっても負担が少ないので、【じわりじわりと増やしていく】ということを計算し、長期的な視点で家庭学習を考えていくように考えましょう。
応用問題にも取り組んでいる
さて、勉強するには問題を解いて知識を増やしていきますが、どういう問題を解くかは家庭の判断、子どもの学力次第になります。
学業不振の子や苦手単元や教科がある子であれば、基本問題を解いて【分かった】を繰り返していき、知識を定着させていきます。
そこそこできる子は基本問題を好み、自分から応用問題を解こうという気持ちがなかなか芽生えてきません。
やはりずっと基本問題を解き続けていては、さらなる学力をつけていくのが難しくなります。
私も塾で【そこそこできる】から【できる子】になりたいと考えている親子と接することがありましたが、応用問題に取り組めるかどうか、が学力上位層に近づけるパスポートのようなものでした。
そして、小学校6年生で学力上位層になっている子は基本問題はパーフェクトにできて、応用問題にも果敢にチャレンジしています。
小学生の時の同級生や、子ども①②の同級生で学力上位層の子は【学校での勉強以上のこと】を勉強していました。
正直、中学受験をしない限り、学校のテスト以上のレベルの問題を解いて何か意味があるのかと考えている親もいますが、中学進学後の公立中のテストも学校によっては応用問題も出ます。
塾に入れば塾のテストを受けて、そこで応用問題に遭遇することもあります。
そして、高校受験に向けて模試を受ければ【高校入試はこんな感じなんだ】と小学校のカラーテストとの違いを実感するようになります。
いずれのテストも【基本問題がパーフェクトにできて応用問題が解ける】にならないと学力上位層にはなれません。
中学進学後の次の進学先である高校は受験をパスしなければいけません。
受験は子どもの学力が審査されることになるので、志望校に受かるだけの学力を身につけていないといけません。
偏差値65の高校を目指すなら、偏差値65以上にならなければ合格する可能性が低くなります。
小学生でありながら、先を見越して家庭学習に取り組んでいます。
分からない単元を放置しない
子どもの学力は小学3年生から4年生の間に拡大していきますが、なぜその学年なのかと言うと、【理科と社会の勉強がスタートする】【勉強していない子がすぐに理解できない単元が増える】【抽象的な内容の勉強に足を踏み入れる】というのが大きく影響していると感じています。
学年が上がることで起きる学びの質の変化は、リアルタイムで勉強している子ども自身はなかなか気がつきません。
ですから、親の観察力が重要になってきます。
親がテストの点数が下がってきた教科、いつもより低い点数の単元や宿題に取り掛かるのを嫌がる、宿題に時間がかかるという、いつもと違う【何か】を察していくことで、【ちょっと復習しないといけない単元】【理解不足の教科】を把握して家庭学習でカバーすることが大切です。
我が家の場合、【この単元はまだちゃんと理解していない】と感じたらインターネット上にある無料教材を印刷して、理解を深めるということをしていきました。
塾で出会った成績の良い子は分からないことをそのままにしない、という共通の特徴があり、そのことを参考にして取り入れています。
我が家の場合は私がグータラ小学生でしたので、小学生時代の勉強法に関しては母親の私の経験が全く活かされない、活かすことができないという問題があったので、塾で教えていた賢い生徒たちを思い出して【こんな感じで勉強していたな】というのを実践しています。
とにかく、小学校6年生で学力上位にいるには【理解不足のところがない状態】であることを心がけていくことが大切です。
小学校6年間の間でポツリポツリと知識の抜けがあると、徐々に学校の授業を理解できなくなったり、テストの点数が下がるだけでなく中学に入ってからの勉強に苦労することになります。
小学6年生でも上位、中学生でも学力上位を目指すのであれば【分からない単元を放置しない】を徹底してください。