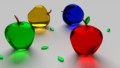今回は【地方トップ校の幻想 本当に全国レベルの実力?】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
【うちの子は地元で一番の高校を目指しているから大学受験も大丈夫なはず安心】と勘違いしてしまう地方の親は少なくありません。
確かに、地方のトップ高校に入ることは大変な努力の成果であり、誇るべき目標です。
しかし、それを【ゴール】としてしまうと、大きな落とし穴にはまる可能性があります。
インターネットが普及し、地方にいても色々な教育情報に簡単にアクセスできるようになりましたが、地方の進学校と、大都市圏の超難関校との間には、学力水準・進学実績において、大きな差があります。
地方ではトップでも、全国レベルで見れば中堅、【名の通らない学校】ということも珍しくありません。
たとえば、地方トップ校から東大・京大・旧帝大・早慶に進学するのは、その学校の中でも限られた上位層の生徒のみです。
つまり、合格しただけでは全国の最難関大学への切符は見えてこないのです。
それにも関わらず、進学実績の数字だけを見て【この高校に入れば大丈夫】と思ってしまう親子が少なくありません。
だからこそ重要なのは、中学生の段階、可能であれば小学生の段階から【全国にはもっと上がある】という視点を持つことです。
その第一歩として、駿台中学生テストなどの全国レベルのテスト、模試を活用し、地元での成績だけでは測れない【本当の実力】を知ることが大切です。
そこで今回は、そうした視点を持つためのヒントをお伝えしていきます。
【地方トップ校】の進学実績は本当にすごいのか?
まず、地方に住んでいると、地元の進学校がまるで全国屈指のエリート校のように見えることがあります。
実際、多くの地方トップ校では、【◯◯大学に○人合格】【旧帝大合計○○名】といった地元の他の学校を圧倒する進学実績を誇り、地域内では別格の存在と見なされます。
パンフレットや学校説明会でその数字を見れば、【ここに入れば安心だ】と思いたくなるのも当然です。
しかし、ここで一つ冷静になって考えてみてください。
その進学実績は、学年全体のうち何%の生徒のものなのか? ということです。
たとえば、学年に300人いる高校で、現役で東大に3人、京大に3人、旧帝大を合わせて20人程度が合格していたとします。
数字だけ見れば【すごい!】と思うかもしれませんが、それは全体の上位数%の生徒の成果です。
裏を返せば、残りの約270〜280人の多くは、旧帝大や難関私大には届いていない、という事実になります。
つまり、【◯◯高校=難関大に入れる高校】というのは、正確には【◯◯高校で上位10%以内に入れれば、難関大が見えてくるかもしれない】ということなのです。
これは見落とされがちですが、【地方の教育事情あるある】で、非常に重要な視点です。
多くの学校は、実績を良く見せようと、いわゆる数字のマジックを使います。
優秀な生徒が最難関私立や難関私立を複数校合格した結果をすべてカウントする。
推薦・AO入試の合格実績を明確に区別しないなど、これらの情報が交じり合うと、【実態】としての進学実績は非常に見えづらくなります。
そして、そうした数字を鵜呑みにしてしまうと、【この高校に入れば、自然と有名大学に届く】といった誤解につながります。
さらに見逃せないのが、合格者の多くが学校以外の教育産業を活用しているという点です。
たとえその高校で上位層に入っていても、塾・予備校・通信教育を併用しているケースは非常に多く、完全に学校の授業やカリキュラムだけで難関大合格に到達するのは、実はかなり厳しいのが現実です。
地方進学校の中で、難関大学への合格実績を出しているのはほんの一部です。
では、上位層以外の生徒はどうなっているのでしょうか。
多くは、地元の国公立大学や、私立大学に進学します。
もちろん、それが悪いというわけではありません。
しかし、最初から【難関大学を目指したい】という明らかな意志がある場合、地方の進学校に進学するだけではまったく力が足りないかもしれないということを、早い段階で認識、自覚する必要があります。
なかには、【高校に入ってから頑張ればなんとかなる】と考える人もいます。
しかし、難関大合格者の多くは中学生の時点で相当の学力基盤を持っており、そこからさらに加速していきます。
現役で国立大学医学部医学科に合格した私の中学、そして高校の同級生もそうでした。
子ども①の周りにいる神童さん達も中学生の時点で【全国レベルの力】を持っていました。
それ以外の子が高校受験で一息ついてしまえば、スタートラインで大きく出遅れてしまうのです。
高校受験は子どもの人生において大きな分岐点の一つですが、【ここからがスタート】という位置づけだと思ってください。
地方進学校の進学実績は【一部の上位生徒】による成果であり、全体像を正しく反映していないことが多いです。
【何人合格】よりも、【学年全体の何%が合格しているのか?】という視点を持ち、高校受験とは別に、難関大学合格者のレベルに到達するにはどうすれば良いのかと考え、上位層以外は地元の大学や私立に進学するケースが多いという現実も受け止めてください。
駿台中学生テストを通じて【全国の位置】を知る
さて、我が子が地元の中学校で成績上位を維持し、定期テストでも常に90点以上と優等生だと、【このまま地元の進学校に進めば、大学も安心】と思ってしまう方は少なくありません。
しかし、地方の学力評価には限界があります。
地元の定期テストや模試では、学校の平均レベルや出題内容が地域の水準に最適化されており、【全国的に見た学力】とは別物です。
そこで、地方に住んでいて、進学校を目指して全国的な知名度を誇る大学を目指している親子がぜひ活用して欲しいのが、駿台中学生テストです。
自宅受験も可能なので、どこに住んでいても全国での自分の立ち位置を把握することができます。
これは中学生を対象とした全国規模の学力試験で、高校受験で最難関校を目指している子や、東大・京大・旧帝大・早慶などの最難関大学を本気で目指している子が受験しています。
たとえ地元の学校でトップクラスの成績を収めていたとしても、駿台模試を受けてみると、ボロボロで、偏差値が50未満、偏差値45程度という事実に直面することも珍しくありません。
逆に言えば、そうした現実を早い段階で知ることができることに価値があります。
そもそも地方では、親も子も【高校合格】が第一の目標になりがちです。
しかし、駿台模試を受ける中学生たちは、高校受験を通過点と捉え、その先の大学入試に照準を合わせています。
子ども①の周りでも受けている子はいましたが、すでに中学段階で、高1・高2レベルの問題演習に取り組んでいる子がゴロゴロいました。
我が家では、井の中の蛙になりがちな子ども①の目を醒ますために受けていたところがありますが、高校生となった子ども①は【あの時に受けてガツンと衝撃受けたことは大きかった】と口にしています。
中学生時点で全国との差を知っているかどうかという差が、高校入学後にじわじわと大きな壁となって立ちはだかります。
地元トップ校に入学して安心してしまい、学習のペースを落とした子と、全国模試で自分の課題を把握し、戦略的に学習を進めてきた子。
大学入試において、どちらが有利かは言うまでもありません。
難関高校を受けるわけでもなく、地元の公立トップ高校を第一志望にしているのに、なぜ駿台テストを受けるべきなのかと言われれば、やはり【全国のライバルと比較できる】の一言に尽きます。
偏差値や順位だけでなく、【どの分野で全国に遅れを取っているか】が一目で分かります。
我が家の子ども①②も受けていて、【理科のこの単元が苦手】【英語のこの文法が甘い】というのが学校の定期テスト、塾のテスト、模試以上に明確になりました。
これにより、学習の優先順位がハッキリします。
そして、学校の授業や定期テストでは取り上げられない難度の問題に触れることで、応用力・記述力・論理的思考力が試されます。
子どもにとっては厳しい現実と向き合うことにもなりますが、荒行のようなもので逆にモチベーションアップにつながることもあります。
全国に自分より優れた生徒がいると分かることは、決してネガティブなことではありません。
【負けていられない】と自ら机に向かう原動力になります。
今は昔と違い、地方に住んでいても、全国レベルの情報や教材は手に入る時代です。
駿台模試のようなツールを活用すれば、【情報格差】や【意識の差】を埋めることができます。
また、早い段階から全国模試を経験しておくことで、高校入学後の模試や共通テスト模試にもスムーズに対応できる基盤が築けます。
模試慣れは、受験期の精神的安定にもつながります。
さらに、テストを通じて【自分の現在地】を客観視することで、漠然とした進学希望から一歩踏み込んだ【戦略的な進路設計】が可能になります。
【何となく旧帝大に行けたらいいな】ではなく、【今の学力から逆算して、どう伸ばしていけば到達できるか】を考える力が育ちます。
親が意識してほしいことは、やはり地元のトップ高校の合格で満足しないことです。
進学校に入るということは、100%大学進学を目指しているわけですから、次の受験は全国が相手になります。
先を見越して、全国レベルの模試を受けることに意味があると子どもに伝え、親は地域では得られない情報や教材に、積極的にアクセスし、学校に頼りすぎず、必要に応じて塾・通信教材・オンライン学習を活用する柔軟さも求められます。
駿台中学生テストは、単なる学力判定ではなく、【全国との距離を可視化する】ための貴重な機会です。
地元の成績が良いからといって安心せず、一度全国レベルで自分の立ち位置を確認してみる。
それこそが、地方から最難関大学を目指すために必要な行動です。
高校受験より先を考えるのに何が必要か
ところで、地方の進学校からでも、東大・京大・旧帝大、早慶といった最難関大学に進学する生徒は確かに存在します。
ただし、その人数は毎年限られています。
トップ校でも最上位層、上位層のみです。
そして、その上位層にいる子に共通しているのが、【高校や教師に頼りきらない学習姿勢】と【全国を見据えた情報収集と行動】です。
つまり、【地元で一番の高校に入ったから、あとは先生に言われた通りにやっていれば大丈夫】といったスタンスでは、到底そのレベルには届きません。
必要なのは、【主体的に学ぶ姿勢】と【戦略的な学習計画】です。
私の同級生や先輩後輩、塾で出会った子ども達や子ども①の高校で実際に地方トップ校から旧帝大や早慶に進学した生徒たちに共通する特徴があります。
彼ら彼女たちは高校受験を【通過点】と冷静に捉えています。
中学の段階から【自分は東大を目指す】【早稲田に入りたい】と明確な目標を持ち、それに見合う学習に取り組んでいます。
駿台テストや全国統一模試などで、自分の立ち位置を確認し、大学入試レベルの問題にも中学から触れ始めているケースもあります。
高校入試が終わった瞬間に燃え尽きてしまう子も少なくありませんが、難関大合格者は違います。
むしろ、高校入学後の方が学習量・学習密度ともに増しています。
とくに地方の進学校は、高校入学後に学年トップ層に食い込めるかどうかが勝負の分かれ目となります。
子ども①の周囲にいる旧帝大以上に合格できそうな子達は【怠けることなく部活と勉強を両立している】【指定校推薦や総合型選抜などでの進学を目指すから定期テスト対策が鬼のように万全】と抜かりなく対策をしています。
そして、難関大学を目指すには、学校の授業だけでは不十分なことが多いのが現実です。
通信教材を自分で選び、自学自習の習慣を確立しています。
また、地方では難関大向けの専門塾が少ないため、オンライン予備校や個別指導の活用がカギになりますし、そういうものを利用しつつ、高校生になっても最低限の教科のみを取って塾に所属して自習室を確保するというケースもあります。
先取り学習もガンガン進め、高校3年の冬までに完全に仕上げるという戦略を立てて1年生から勉強しています。
このように、単に成績が良いだけでなく、【目的に合わせて自分で戦略を立てて行動している】のが大きな違いです。
もちろん、地方の進学校は、教育環境としては決して悪くありません。
熱心な先生方も多く、一定水準以上の授業も行われます。
ただ、難関大志望者向けの特別対応が不十分といった課題も多く、【学校に任せていれば何とかなる】という考えでは不十分です。
ですから、子どもが高校生になっても多少なりとも家庭でのサポートが必要な場面が出てくることもあります。
それでは、親ができるサポートとはいったい何なのでしょうか。
まずは、【子どもが目指す大学・学部について一緒に調べ、情報を共有する】【学校外での学習(通信教育・オンライン講座など)に理解を示し、必要なら費用をサポートする】【地元で得られない情報をネットや書籍から積極的に取り入れ、【全国基準】を一緒に把握する】ということをしていきましょう。
また、失敗しないためにも【地方での成功パターン】を学ぶことが大切です。
たとえば、【中学時代から全国模試を活用し、立ち位置を客観視していた】【高校1年のうちから大学入試に向けて計画を立て、教材選びにもこだわっていた】【部活動と両立しながらも、日々の学習習慣を崩さなかった】など、地道で継続的な努力が共通点として挙げられます。
【地方だから】【情報が少ないから】【塾がないから】と諦める必要はありません。
むしろ、今は全国模試・通信教育・オンライン教材など、場所を問わず全国トップ層と同じ土俵で戦える環境が整いつつあります。
大切なのは、【地元のトップ高校に合格すること】ではなく、そこから先をどう見据えるかです。
学校任せではなく、自分から動き、調べ、実行する。
そんな姿勢が、地方からでも旧帝大・早慶といった最難関大学に合格するカギとなります。
地元のトップ高校に合格することは確かに素晴らしい成果ですが、それが全国トップレベルの学力と直結するとは限りません。
地方から最難関大学を目指すためには、【高校に入ってからが本当のスタート】だという意識が必要です。
【うちの子は成績がいいから大丈夫】ではなく、【全国で見たら今どの位置か】という広い視野を持つことが、子どもが本当に望む未来をつかむためのスタートになります。