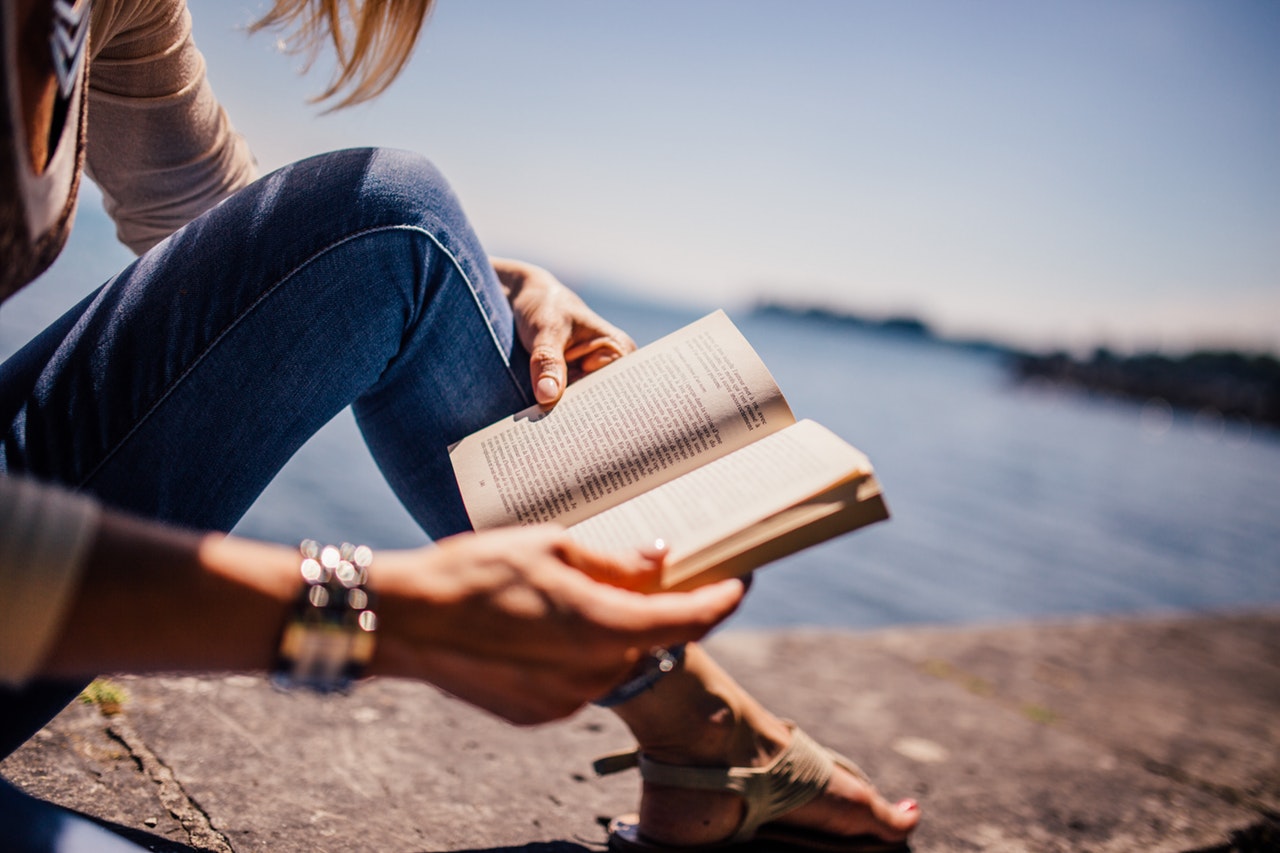今回は【トップ層に食い込む子の親がやっていないこと】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子どもの勉強に関する悩みというのは多岐にわたります。
その一つが【ちゃんと勉強してるのに、なぜか成績が伸び悩む】というものです。
そんなお悩みを持つ方は少なくありません。
子どもは真面目に学校の宿題をこなしている。
中学生になり部活との両立や高校受験に向けて塾にも通い、それなりに頑張っているのに、模試や定期テストでは【偏差値60前後】で止まってしまう。
いわゆる地方でも中堅校止まりの状態になっている子は少なくありません。
もちろん、それ自体が悪いわけではありません。
ただ、実際に偏差値65〜70台のトップ層に届いていく子たちと比べると、【どこかに決定的な差があるのでは?】と感じることもあるのではないでしょうか。
親としてはもうひと伸びして欲しいけれど、どうしても無理で、このまま高校受験に進んでも、【それなりの高校】に落ち着きそうな気配が漂い始めていると、色々とこれまでの家庭学習の進め方を反省したり、勉強時間を増やそうと小言を行っては子どもと衝突することも起きてしまいます。
焦ってあれこれ言えば反発されるし、今の成績を否定するような発言も避けたいけれど、どう関われば、子どもの力をもう一段引き上げられるのだろうかと悩んでいる方は、私も塾で仕事をしている時に出会ってきました。
どうしても、親は子どもの成績が上がらないことを【子どもの頑張りが足りないから】ということにしがちですが、このあと一歩伸びない原因、実は子どもの努力不足や能力の限界ではないことも多いです。
むしろ、見落とされがちなのが、家庭の雰囲気や親の接し方です。
意図せず親が良かれと思ってやっていることが、子どもの思考力や自立心の伸びを妨げているケースも少なくありません。
たとえば、すぐに答えを教えてしまったり、間違いを責めたり、親が先回りして管理しすぎた。
こうした習慣は、一見サポートのようでいて、実は【子どもが自分で考える力】を奪ってしまうのです。
そこで今回は、学力がもう一段階伸びる子の親がやっていないことに注目し、【やめることで子どもの伸びしろが広がる】親の関わり方を紹介します。
親が教えすぎない家庭ほど子は伸びていく
まず、成績があとひと伸びしない、頑張っているけれど偏差値60前後の位置にいる子どもたちには、ある共通点があります。
それは、【真面目で、指示に従える】という点です。
小学校のころからコツコツ努力できるタイプで、宿題も忘れず提出し、先生からの評価も良好。
塾に通えばきちんと成果を出し、親が手をかけてきた分だけの結果は出せています。
けれど、ここで一つの壁が現れます。
それは、【言われればできるけれど、自分からは動かない】という状態です。
つまり、自走力が弱いのです。
この自走力こそ、偏差値60を越えてトップ層に食い込むための、決定的な差になります。
偏差値70台前後に入ってくるような子どもは、誰かに勉強を指示されなくても、自分で考え、工夫して学習を進めています。
今日やるべきことを自分で整理し、必要ならば自分で参考書を選び、テスト後には自然と復習をしています。
もちろん、小学生や中学生のうちからそんなに完璧にできる子は稀ですが、それでも【どうしたらもっと良くなるか】を自分で考え続ける姿勢はあります。
一方で、偏差値60前後で止まってしまう子は、親が管理してくれている環境に慣れており、【指示がないと動かない】【やり方を教えてもらうのが当たり前】になっていることが少なくありません。
塾でも痛感しましたが、トップ高校に余裕で入る子と偏差値60前後の高校に進む子の勉強との向き合い方で決定的に違うのは【受け身か自分で勝手にガンガン勉強できるか】でした。
この差は小学生の間は大きく開くことはありませんが、中学生になるとガツンと出てきます。
やはり、親の関与が多すぎると、子どもが自分の頭で考える力を持つ機会を奪ってしまうので気をつけてください。
トップ層の子どもの親が共通してしていないことの一つが、【手取り足取り教えること】です。
最上位層の子の親は、【勉強しなさい】と命令する代わりに、【今、どこでつまずいてると思う?】【これ、自分で気づいた?】と問いかけます。
そして、子どもが考える時間を大切にします。
問題の正解をすぐに教えるのではなく、たとえ遠回りでも【自分で気づくまで見守る】のです。
ミスをしたときも、【なんでこんな間違いをしたの?】ではなく、【ここって、どう考えたの?】と、振り返りを促す会話をします。
トップ層の子どもたちが育つ家庭では、思考のプロセスが大切にされているのです。
では、どうすれば今から教えすぎない関わり方にシフトできるのでしょうか。
いくつか、すぐに実践できるポイントをご紹介します。
まず、 子どもが小学校高学年になっても勉強のスケジュールを全て親が決めないようにしましょう。
進級するにつれて、子ども自身に【今日、何をするか】を考えさせる機会を増やしていくようにしてください。
たとえ非効率に見えても、時間がかかって面倒だなと思っても、根気よく取り組んでください。
子ども自身が自分で決めることで責任感と自己管理力が育ちますし、客観的に自分の勉強を考えるようになっていきます。
次に、 ミスを責めず、【気づいたこと】を評価する意識を親が持ってください。
【どうしてこうなったの?】【ここって、なんか気づいた?】と問いかけることで、ミスを振り返る力が育ちます。
次に、子どもの勉強で 解き方や考え方を言語化する癖を身につけるよう促すことも学力が伸びやすくなる土台になります。
【この問題、どうやって解いたの?】と聞いてみてください。
子どもは解いていた問題の考え方を言葉にすることで、理解が整理され、【こういう考え方をする】というのを徐々に身につけていきます。
親としては、【わからなさそうにしていると、つい教えたくなる】【先に答えを示した方が早い】と感じることもあるかもしれません。
けれど、それでは考える体力が育ちません。
たとえば、泳ぎ方を教えるときに、親が水の中で手を引いてばかりいたら、子どもは自分の力で泳げるようにはならないのと同じです。
ただ、手を貸さないことは、無関心とは違います。
【自分で乗り越える力を信じて、待つ】ことこそ、子どもの知的な成長には不可欠なのです。
子どもの力を伸ばすことを考えるのであれば、ガンガン親主導で詰め込み教育をするのではなく、考える余白を親が残す取り組みをしていくようにしてください。
【親が教えすぎない】ことは、放任ではなく見守る力です。
トップ層に入っていく子どもたちは、たくさん考え、たくさん間違えながら、自分で前に進む力を少しずつつけています。
そういう子の親がやっていないのは、【口を出すこと】【手を貸すこと】【答えを急がせること】です。
その代わりに、【問いを投げること】【考える時間を与えること】【自立を信じること】をしています。
その関わり方の違いが、数年後の大きな差を生み出します。
今の成績に一喜一憂する親がやりがちな3つの誤算
さて、あとひと伸びが足りない偏差値60という成績帯は、多くの親にとって【安心】と【焦り】が入り混じる地点です。
平均よりは上、でもトップ層というには届かない。
子ども本人も親も納得しているなら良いのですが、そうではなく、惜しい位置にいると感じていると、つい【もう一段、上に行けるはず】【でもどうすればいいのか】と悩みが深まっていきます。
そして複雑な悩みが、無意識のうちに【成績の数字】に向きやすくなっていきます。
模試の偏差値や定期テストの点数に一喜一憂して、【次はもっと点を取ろうね】【このミス、もったいないよね】と声をかけてしまう。
決して悪気はないけれど、そうした声かけの積み重ねが、子どもの勉強が点数に縛られた学びにしてしまうのです。
では、偏差値60前後の家庭でよく見られる【やりがちな誤算】とは何か。
その代表的な3つをご紹介します。
誤算一つ目は【定期テストの点数=学力だと思ってしまう】というものがあります。
【今回のテスト、95点だった!】【また学年10位以内に入った!】
そんな報告に安心し、【やっぱりうちの子は頑張ってる】と思いたくなるのが親心です。
でも、実は定期テストで高得点を取れることと、真の学力、すなわち思考力や応用力が高いことは、必ずしも一致しません。
定期テストはあくまで【範囲内の理解度】を測るものです。
つまり、予習・復習の効率が大きく影響します。
一方でトップ層の子どもたちは、初見の問題への対応力や、知識を組み合わせて考える力が卓越しています。
これは、テスト前だけの詰め込み学習ではなかなか育ちません。
だからこそ、【点数が取れている=大丈夫】という認識は要注意なのです。
むしろ、点数の裏側にある【なぜ間違えたのか】【この問題、どう考えたのか】といった思考のプロセスに注目すべきです。
二つ目の誤算は【短期的に成果が出る勉強法を重視してしまう】、です。
点数が伸び悩んだとき、【どうやって覚えさせよう】【どの問題集をやらせればいい?】と、ついテクニック的な方法に走ってしまうことがあります。
たしかに、暗記カードやパターン演習、YouTube解説動画など、短期的な点数アップに効果のある勉強法はたくさんあります。
しかし、それらは【覚えること】【正解を出すこと】が目的化しやすく、深い理解にはつながりにくいという落とし穴があります。
トップ層の子どもたちは、【なぜそうなるのか】を考える習慣が身についています。
一見遠回りに見えても、【教科書をじっくり読む】【ノートを自分でまとめる】【先生の解説を自分なりに再構成する】といった、地味で深い勉強に時間をかけています。
長期的に見れば、時間をかけて考える力のある子の方が、伸び続けます。
三つ目の誤算が【苦手を潰せば成績が上がると思い込む】です。
【うちは数学が苦手だから、まずはそれを何とかしなきゃ】と、苦手克服に力を入れるご家庭は多いです。
もちろん、基礎を固めることは大切です。
しかし、苦手潰しばかりに集中すると、子どもが学ぶ楽しさを見失いやすいという問題点もあります。
むしろ、トップ層にいる子どもたちは、【得意を伸ばす】ことをまずは重視しているところがあります。
理科が大好きならば、図鑑や動画、実験に夢中になる。
国語が得意なら、読書量が膨大。
英語が好きなら、自分で洋楽や海外ドラマを楽しむ。
このように、強みが深まっていく中で、思考力・探究力・好奇心が育ち、様々な力が身についてきて苦手科目克服へと本腰をしていくという流れをつくったり、気がついたら他の教科も上がってきたということになってくことが珍しくありません。
また、【苦手を克服させる】よりも、【この分野、好きそうだね】と子どもの関心に寄り添い、得意を伸ばすサポートをしています。
成績の良し悪しに一喜一憂するのではなく、【この子がどう学び、どう成長していくか】という視点で、長い目で見ているのです。
あとひと伸び足りない、偏差値60前後という位置は、【このままでも良い】ようにも見えますし、【あと少しで上に行ける】位置でもあります。
だからこそ、親の関わり方が大きな分岐点になります。
トップ層に食い込んでいく家庭は、【点数を上げる勉強】ではなく、【学びの質を上げる関わり】に力を注いでいます。
数字ばかりに目を奪われず、その背景にある子どもの思考・関心・成長のサインに目を向けてみましょう。
【今】ではなく、【これから】に目を向ける。
それが、もう一段上のステージへとつながる確かな一歩になります。
正解主義の家庭からは、飛び抜ける子が育ちにくい
ところで、学校や塾では、【正解】を出すことが評価されます。
テストの点数も、偏差値も、すべては正しい答えを早く出す力によって測られています。
そのため、多くの子どもたちは【答えを知っている=賢い】【間違える=ダメ】と感じるようになります。
親もまた、【これは正しくできたの?】【なんでこんなミスしたの?】と、つい正しさを急ぐ声かけをしてしまいがちです。
けれど、トップ層にいる子どもたちは、正解を出すスピードよりも、【考え続ける力】を大切にしています。
むしろ、【正解がない問い】や【自分なりの視点を求められる課題】に強いのが、彼ら彼女たちの特徴です。
それとは逆に、家庭で正解主義が強くなると、子どもは次のような傾向を見せます。
わかっていることしか手を出さない。
少しでも難しそうだと【無理】【どうせ間違える】と挑戦を避ける。
【間違えたら怒られる】【恥ずかしい】と思ってしまう。
その結果、未知のものに挑む勇気や、思考の柔軟さが失われていきます。
実際、偏差値60前後の子どもたちは、パターン化された問題や定番の解き方には強くても、初見の応用問題や記述式問題でつまずきやすい傾向があります。
これは、答えを出す練習ばかりして、考え方を深める練習をしてこなかったからです。
一方で、トップ層の子どもたちは【なぜ?】【どうして?】という問いを楽しみます。
わからないことに出会っても、【ちょっと考えてみよう】【仮説を立ててみよう】と、粘り強く向き合います。
これは、生まれ持った才能というよりは、家庭の環境、親の関わり方の差が出てしまうスキルです。
トップ層の子どもの家庭では、【どうしてそう思ったの?】【他にどんなやり方があるかな?】【この出来事、どんな影響があると思う?】といった、学問に通じる会話が当たり前のように繰り広げられています。
こうした問いかけが、子どもの思考の幅を広げ、【正解が一つではない世界】に慣れさせていくのです。
そして、正解を褒めるのではなく、考えた過程を認めることが、トップ層の子を育てる家庭の共通点です。
たとえば、子どもが難しい問題に取り組み、間違えたときでも、【この解き方、面白いね】【こういう考え方もあるんだ】と肯定的に受け止める。
また、記述の答案や作文に対しても、【この表現いいね】【こういう視点はなかったな】と伝えることで、【自分の意見を出すこと】に対する自信がついていきます。
こうした日常を過ごすうちに、子どもは【正解するために学ぶ】のではなく、【考えることそのものを楽しむ】ようになります。
家庭で【正解のない学び】を育てるには次のようなことを実践していきましょう。
ニュースやテレビの話題をきっかけに、【あなたはどう思う?】【もし○○だったらどうする?】と聞いてみましょう。
今の子どもたちはYouTubeをメインに見たり、家で新聞を取っていないということも多いので、自分の興味関心の情報ばかりを見たりと偏りがちになりやすく、幅広い分野の知識を得るためにもニュースなどから世界情勢、経済、地域のニュースをピックアップして話をするようしてください。
また、今の学校での学びではディスカッションも多く、社会に出てからも正解がない問題に直面することもあります。
【答えは一つしかない】ではない世界に慣れるためにも、読書、ディスカッション、観察、創作など、自分なりに考えが求められる活動に取り組む時間を設けましょう。
穏便に子どもに勉強させることに力を注ぐのであれば、やはり親自身も【学んでいる】を見せることが大切になってきます。
わからないことがあったら一緒に調べたり、【お母さん、お父さんも知らなかったな】と正直に話すことで、子どもにとって【知らない=恥ずかしいことではない】という価値観が育ちます。
偏差値60前後の子どもは、確かな基礎力と素直さを持っています。
その一方で、やりすぎる親の存在が、知らず知らずのうちに、子どもの自走力や思考力の芽を摘んでしまっていることも。
トップ層に食い込んでいく子の家庭は、【教えすぎない】【焦らない】【正解を急がない】であり、【見守る】【問いかける】姿勢を大切にしています。
その引いた関わりによって、子ども自身の【考える力】が少しずつ芽を出していきます。
今すぐ何かを足すよりも、何をやらないかを見直してみる。
その選択が、子どもの可能性を静かに動かし始める確かな一歩になります。