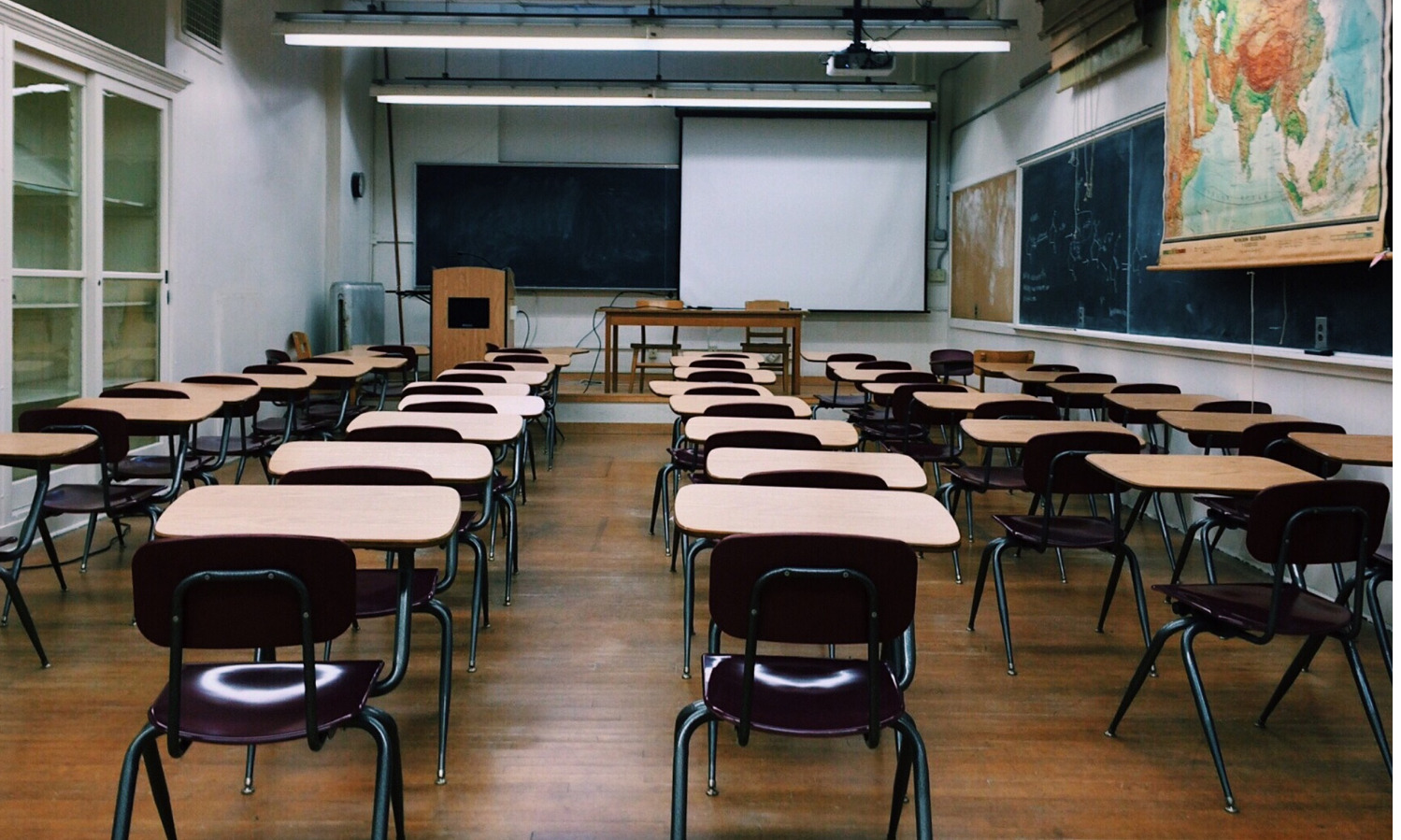今回は【「うちはほったらかし」って本当? 優秀な子に共通する家庭習慣とは】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
「うちは何もしてません。放っておくだけで自分でやるんです。」
これは、成績上位の子どもを持つ方がよく口にする言葉です。
私も塾や子育ての中で学力上位層の子の親ほどこれに似た言動をするというのを見聞きしてきました。
同じように子育てや勉強サポートに奮闘している親にとっては、ちょっと本気で言っているのか測りかねない、衝撃的なひと言かもしれません。
「え?本当に何もしていないのに、そんなにできるの?」と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、結論から言えば、この言葉をそのまま信じるのは危険です。
本当に【完全な放任】で子どもが勝手に育ち、勉強もうまくいっているというケースはごくわずか。
多くの場合、ほったらかしているように見えるだけで、裏ではしっかりとした家庭の土台づくりや見えない関わりが積み重ねられています。
例えば、小さい頃から読書を習慣づけていたり、学習習慣が自然と身につくような生活リズムを整えていたりしています。
あるいは、勉強に直接口を出さなくても、子どもが自分で学べるように環境と声かけで促していたりします。
我が家の子ども①②の周囲にいる神童さん達の親は、子どもが疑問に思ったことをすぐに調べたり、家で出来る科学的な実験を頻繁に検証会をしてみたりと、明らかに【そりゃあ賢い子に育つ】と感心するような行動をしています。
ただ、それが親や子にとっては【特別なこと】ではなく、【日常の当たり前】になっているため、周囲から何か特別なことをさせているのか質問される、探りを入れられても【うちは何もしてない】と答えるのは仕方がないことでもあります。
そして、聞いた側は信じ切ってしまってはいけないという面も持ち合わせています。
そこで今回は、放任主義と主張している家庭での【見えない努力】に焦点を当て、優秀な子どもの家庭に共通する習慣や関わり方の実態を考えていきます。
「放任」ではなく「戦略的に見守っている」
まず、ほったらかしと口にしている賢い子の親は放任主義ではなく【戦略的に見守っている】というスタンスで子育てをしています。
【うちは何もしていません】【放っておくだけで、子どもが自分でやるんです】と語る親は何もしないのではなく、「戦略的に見守っている」タイプです。
表面的には放任に見えても、よく話を聞いてみると、その裏には周到な関わりと準備があることが見えてきます。
賢い子の親に共通しているのは、【子どもを放っておく】のではなく【子どもを信じて見守る】というスタイルです。
子どもの力を信じながらも、放任にはせず、必要な支えを見極めています。
たとえば、小さい頃から【机に向かう習慣】【読書の習慣】などを自然と身につけさせたり、日常生活の中で【学ぶことが当たり前】という空気を家庭内に作っていたりします。
こうした家庭では、学びの環境がすでに整備されている特徴があります。
たとえばリビング学習ができるスペースの工夫、静かな時間帯の確保、テレビやゲームのルール作りなど、子どもが集中できる条件をしっかり整えています。
個人的な話になりますが、私の家は乱雑で、四六時中テレビがつけっぱなしで、勉強する環境は全く整っていませんでしたが、お友達の勉強をしっかりやっている子の家はいつ遊びに行っても学習机の周辺はきれいに整頓されていたり、本棚もきれいで、自分の家との差というものを感じていました。
家庭力の違いを感じましたし、【何もしていない】と言いながらも、たいていは学校の授業内容やテストの日程、宿題の傾向なども親がある程度把握しているケースが多く、【困っている様子があれば声をかける】【ミスが続くようなら一緒に原因を探る】といった柔軟なサポートも忘れていません。
ただし、子どもが自ら気づくような働きかけを心がけており、【やらされ感】ではなく【自分でやる力】を育てる姿勢がハッキリしています。
このように、自由にさせているようで、実は【自由が成立する土台】が作られているのです。
これとは真逆な【本当に放任主義な親】は子どもが今何を勉強しているかや、どの教科が得意なのか苦手なのかを把握しておらず、テストの結果、宿題の確認もしません。
私の親がまさしく絵に描いたような放任主義の親でしたので、私は勉強する習慣が身につかないまま小学校6年間をまさに自由気ままに過ごしました。
このように家庭内でのルールや空気感、学びに対する肯定的な価値観が、子どもにとっての無言のガイドとなり、自発性を引き出しています。
つまり、【何もしていない】という親の言葉の裏には、子どもの学びを信じて任せられるだけの準備と環境づくりがあるのです。
これこそが、【優秀な子が育つ家庭の本質】なのです。
優秀な子に共通する家庭の空気
さて、【なんか知らないけれどうちの子は変わっていて、放っておいても勝手にやるんです】という言葉の裏には、実は家庭に流れる空気そのものが違う、ということがあります。
優秀な子どもたちは、単に能力が高いのではなく、【学ぶのが当たり前】という文化が家庭内に自然と根付いています。
勉強しなさいと口うるさく言わなくても、自ら机に向かう子は多くの場合、【やるのが当たり前】という空気の中で育っています。
たとえば、リビングに参考書や図鑑、親の本が並び、日常の延長線上に知識に触れられる環境であったり、
家族の誰かが読書していたり、ニュースを見て考えを語っていたり、大人が学んでいる姿を子どもが自然と目にしているのです。
このような家庭では、勉強や学びが特別なことではなく、会話の一部になっています。
たとえば、【今日のニュースで〇〇って言ってたけど、どう思う?】と子どもに問いかける、【この言葉、どういう意味だと思う?】と辞書を引かせる。
そんなやりとりの中で、語彙力や考える力が自然に養われていきます。
やはり、普通の家庭と、賢い子の家庭との違いは本棚、テレビや親子の会話の質の違いがあります。
本棚には学習漫画や図鑑、親の趣味の本、辞書などが混在しており、【本棚の中に学びのヒント】が詰まっている。
ふとした時に手に取れる距離に知識があることで、子どもの知的好奇心が刺激されます。
正直、教育熱が高いけれど子どもの学力の伸びがそうではない、実際に伸びなかったという家庭では【本棚に並んでいる本の数】がさほどではない、【親が本を読まない】という傾向があるので、そうした差が親がグイグイ勉強させているわけではないけれど子どもが賢い子と、親が教育に熱心だけど子どもの成績が頭打ち状態、という違いとなるのではと感じることはこれまで何度かありました。
また、テレビ番組や日常会話においても、【言葉のセンス】が自然に育つようなやりとりがなされていることが多いです。
言い換えや比喩、ちょっとした雑学を交えた会話が、子どもの思考力や表現力に影響を与えていきます。
つまり、優秀な子の家庭では、目に見えない【学びの空気】が生活の中に溶け込んでいる、そこかしこに漂っているという点が共通しています。
これは決して特別な教材や高額な教育サービスではなく、日々の家庭環境とコミュニケーションの積み重ねによって作られているものです。
逆に言えば、すぐにでもできることなので、ぜひ実践してみてください。
親がポイントを抑えている
ところで、一見【放任主義】のように見える優秀な子の家庭ですが、実際はただ放っておいているわけではありません。
よく観察してみると、親が直接勉強を教えることは少なくても、要所で重要な関わりをしているケースがほとんどです。
たとえば、宿題やテストの解き方を教えることはせずとも、【どうやって振り返るか】はしっかり伝えています。
【どこで間違えた?】【なぜその答えになった?】といった問いかけを通して、子どもが自分の思考を上手く言葉にして表現する、つまり言語化し、理解を深めるよう導いているのです。
これにより、自力で考え直す力=学力の“根っこ”が育ちます。
また、子どものモチベーションの源を、親子で共有しているという特徴も見られます。
【〇〇になりたい】【こんなことを学びたい】といった目標や夢、興味を、日常会話の中で一緒に確認し、応援する。
単なる【頑張れ】ではなく、子どもの内側から湧く意欲を支える土台ができているのです。
さらに、子どものペースを尊重しながら、勉強から目をそらさせない工夫もポイントです。
たとえば、リビング学習にして、自然に目が届く環境をつくったり、タイマーを使って時間管理をサポートしたりしてみましょう。
我が家では、自分で勉強する習慣がまだ定着しきっていない間はリビング学習を続けていましたし、時間に超ルーズな子ども①はタイマーを導入してから勉強の質が劇的に向上しました。
【今から30分だけやってみようか】と声をかけることで、負担を感じさせずに机に向かわせることができます。
そして【勉強したの?】とやったかどうかの確認をするだけではなく、【今日は何か発見はあった?】と尋ねる姿勢も意外と重要です。
この質問は、子どもの学びの内容に焦点を当てており、子どもにとって【学ぶことが大切にされている】と感じられる関わりになります。
賢い子の親は放任ではなく、信頼しながらも意図的な関わりを持ち、子どもの自立心と学力の土台を育てていきます。
私も経験したことのある【ほったらかし】は、自由が成立する環境が整っていない様子で、逆に子どもを苦しめることになるので混同しないでください。
【うちは放任主義ですから…】という言葉の裏に、家庭の見えない土台があります。
当たり前なので、【何もしていない】と本当に言っていることもあるのですが、それを真に受けて【何もしなくてもそのうち勉強するはず】という考えを持たないように気をつけてください。
子どもが自分で学べる環境を勝手に整えることはありません。
整えるのは、親の大切な仕事です。
そして、勉強を教えるだけが子どもの学力をあげる関わり方ではありません。