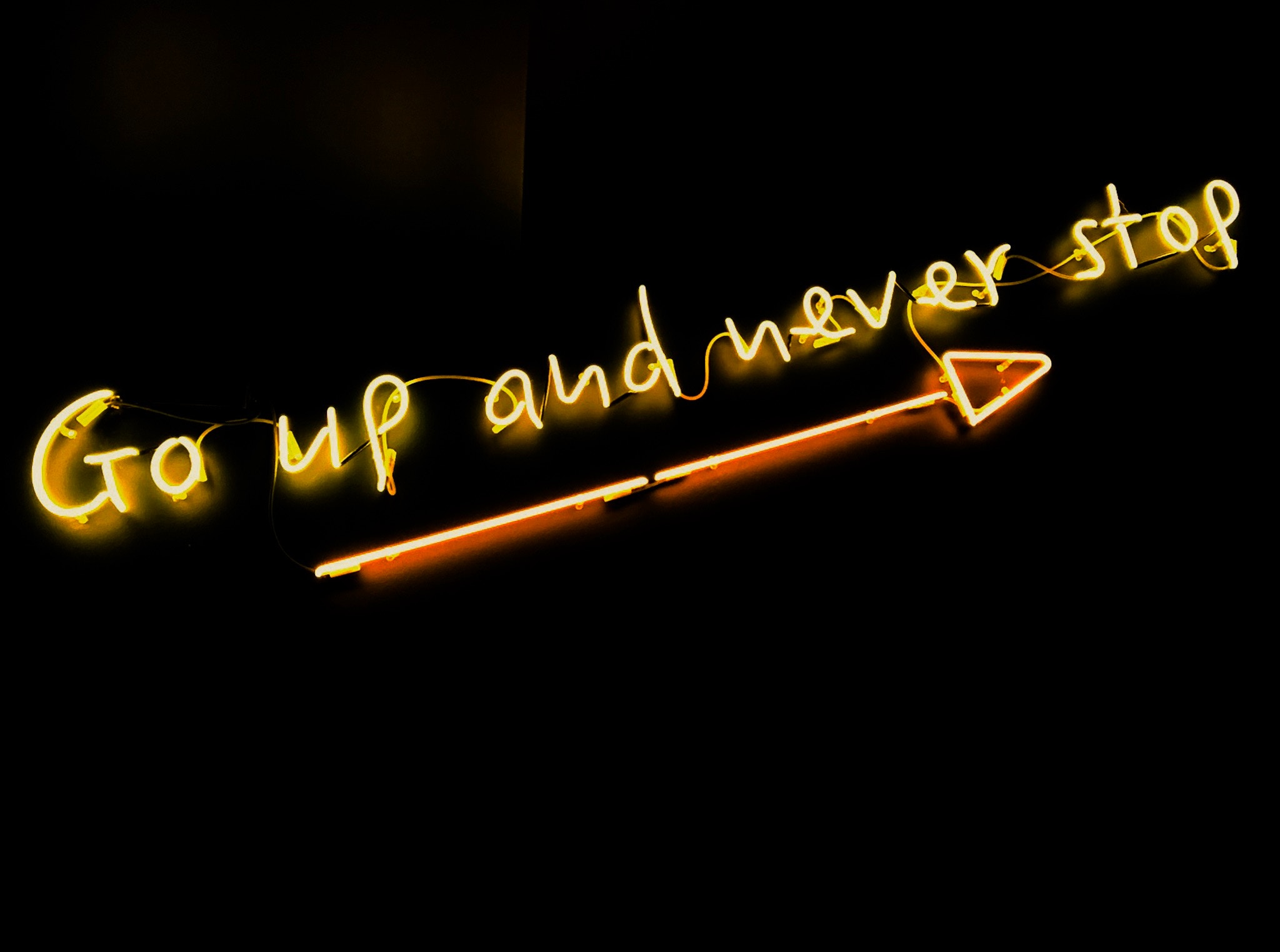今回は【子どもの学力 これをやったら自分から勉強する子に育ちません】と題し、お話していきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子どもの教育に関心がある、中学受験も視野にいれていると、【こういう感じで勉強を進めていきたい】【学校のテストで高得点を取るようにしたい】と色々と就学前、または小学校1年生の頃から考えて対策を講じてくると思います。
親が【我が子はこういうルートで進学して欲しい】という大まかな願い、プランを考えている時は、そのプランを達成できるよう学習習慣を定着させ、子どもの学力を鍛えていくように誘導していきます。
小学1年生から3年生は基礎固めかつ難易度高めの教材を使用して、小学3年の2月の入塾に備えるなどが一番良い例でしょうか。
上手くその方法で成績が上がっていく、学力が伸びていくのであれば良いのですが、やはり上手くいかないこともあります。
どちらかといえば、とんとん拍子で事が進む方が珍しいです。
全て親の思惑通りになる子育てなんてありません。
何かしらの壁にぶち当たり、そのたびに軌道修正していき、子どもにとってより良い家庭学習、塾選びをしていくことになるというのが現実的に起こりそうななかでも理想的な進み方でしょうか。
しかし、中には【この進め方だと逆効果】というケースもあります。
親のやることなすことが全て子どもにとってマイナスになり、【どうして上手くいかないのか】【あれだけ尽くしたのに全く成績が振るわない】という事態になったら、自分の子育てに自信を失うだけでなく、子どもに対して不甲斐なさを感じたりと親子関係に亀裂が入ってしまいます。
こうした事態は親としては極力避けたいです。
どういうことをしたら、子どもが自分から勉強する子に育たないのかを紹介していきます。
1.親が全て学習計画を考えて計画通りに進ませる
教育に関心がある方は情報を色々と仕入れて、【この教材をやると良い】【勉強時間はこの位からスタートする】と家庭教育を始めていきます。
子どもが家庭学習の習慣が身についてくると、子どもの学力や苦手克服などを考慮して教材をチョイスしていくようになります。
中学受験するなら応用的な問題のある教材を取り入れるタイミングも考えたりと、親が家庭学習の全体像を把握して誘導していくわけです。
しかし、いつまでも全て親が取り仕切っていると子どもが【自分の理解度が足りない単元はここだからちょっと時間をかけて勉強したい】と自分の学力を冷静に受け止めて、臨機応変に学習内容を変えていくという力を育てることが難しくなります。
しかも、この力は子ども時代だけでなく、大学生、社会人になってからも求められる力です。
親が全部担当し、誘導して小学校高学年、中学生になっても『今日の勉強はこれね』と、日々の学習すべきことをスケジュール管理していたらどうなるでしょうか。
中学受験をする場合でも、中学に入って定期テスト計画を考える時や高校受験でも【自分の勉強はどう進めれば分からない】という中で勉強することになります。
こうなるといつまで経っても自分から勉強する子にはならいないです。
最初は親が誘導することは絶対に必要ですが、子どもに学習計画を考える機会も与えるようにしてください。
我が家では、小学校4年生から5年生の始めにかけて【自分で学習計画を考えよう】を実践してきました。
どうしてそういうことをしたかというと、塾で仕事をしている時も、学力上位層、成績が上がる生徒は【今やるべきこと】【やらないといけないこと】【いつまでにどのくらいできるようにするか】を考えながら勉強に取り組んでいました。
その一方で、学習習慣のない子や成績が上がらない子は自分で学習計画を立てることが出来ませんでした。
一応立てますが、【休日は一日8時間からい時間勉強する】と普段勉強していないのに無謀な計画。
空言のような実現不可能な予定を立てていて、結局とん挫するということを繰り返していました。
これとはちょっと違いますが、やはりある時点から子どもに計画を考えさせる経験を積ませていかないといけません。
2.子どものリアルな学力を受け止めない
学校、そして塾で働いた方なら一度は『子どもの学力を真正面から受け止められない親』に出会うと思います。
親の求める進路進学と、子どもの実力がかけ離れているにも関わらず『この学校を受けさせます』という親です。
理想が高いことは悪いことではありませんが、本当にそこまで到達できるのかという冷静さも必要です。
全ての子どもが勉強が得意というわけではないです。
運動神経と同じように、元々持っている、基本となる『暗記力』『理解力』は個人差があります。
勉強をしてその差を埋めようとしても、埋められないということもあるというのは多くの人が理解しています。
ちょっとスポーツでたとえると、野球が好きで小学生、中学生とやっていても名門学校からお誘いの声がかかる子は限られています。さらに、プロ野球選手になる子は本当に極々わずかです。
親が前のめりになりすぎて、子どもの才能を冷静に見ることができずに『必ずうちの子はプロ野球選手になれる』といって強豪校でレギュラーを取るような子と同じような練習を強いるのと同じです。
こういうことをされたら、最初は楽しかった野球も辛く嫌なものになっていきます。
勉強の場合は『勉強嫌いに拍車がかかる』になり、学習意欲が低下します。
そして、受験校に関しても親が勝手に決めるので不合格の連発になり益々自信喪失していきます。
親が理想と現実を受け止められないというケースは、多くはないけれどあります。
しかも、珍しいことではないです。
カタカナがまだ怪しいのに漢字をガンガン先取りさせたり、足し算と引き算の繰り上がりや繰り下がりが定着しきっていないのに九九の暗記やかけ算をやらせてしまうなど、子どもの理解不足の単元を全く振り返らずに『他の子よりも早く進める』『何としてでも○○校に入る』と理想を追い求めてしまい、子どもが置き去り状態になります。
正直、子どものリアルな学力と向き合うというのは覚悟が必要です。
とくに親の理想が高ければ高いほどキツイものがあります。
受験学年だけれど、親は偏差値65くらいの学校を親は求めている。
けれど、子どもの偏差値は45から50未満を行ったり来たりしている場合は『どうしたら偏差値15以上上げるか』よりも『どうやって偏差値50までもっていけるか』を考える方が現実的な問題です。
その偏差値から短期間、または一年でトップ校に合格できるレベルにさせるというのは無謀です。
100人、いや1000人いれば一人くらい実行できる子がいるかもしれませんが、その他大勢にとって無謀なチャレンジです。
子どもの学力、成績から目を背けたくなる気持ちは分かりますが、理想ばかり追い求めても決して子ども自ら勉強する子には育ちません。
3.親の言うことが絶対という考えを持って子育てをする
これは理想を追い求めてしまう親に似ているかもしれませんが、『親の言うことが絶対』というのは『この教材を使っていれば大丈夫』とか『この方法で勉強していけば大丈夫』や『この学校に行けば子どものためになる』と全ての面で口出しをし、子どもの考えを無視するタイプの親です。
勉強させるにも子どもが疲れている、体調が悪くても『今日やる予定の学習量をやらせる』と譲らなかったりと、子どもは親の操り人形と勘違いしている、教育虐待をしている親に育てられると、間違いなく子どもの自立心がスクスク育つことはありません。
成績が上がらなければ子どもの意思を確認せずに塾に入れさせる、または塾の掛け持ちをするということもあります。
習い事もキツキツで、子どもの自由時間など完全に無視です。
横暴な君主のような親で、子どもの気持ちはどんどん離れていきます。
子どもに勉強させるのは色々と理由があります。
学校の授業についていけるようテストで良い点数を取ることなどから始まり、最終的な目標が『受験で志望校に合格する』に変化していきます。
受験というのは子どもにとっては人生で初めての挫折を感じることもある、大イベントです。
そして、受験を機に心身ともに成長する子も多く、一概に『しんどいイベント』の一言で片づけることはできません。
子どもながらに悩み、努力をし、周囲との差を知り落ち込んだり奮い立ったりと喜怒哀楽の全てをぶち込んで受験期を乗り越えていきます。
なかなか難しい時期を経験することで、より一層たくましくなるので必ずしも親にとってはデメリットばかりではないです。
しかし、『親の言うことが絶対』という子育てをしていると子どもが成長する機会を全部摘み取ってしまいます。
子どもと親は別の人格を持ち、全く同じとして考えてしまうことに問題があります。
考えさせる子育てをしないと、結局子どもが大いに困り、親子関係もボロボロになるので誰も幸せになりません。
まとめ
子どもが自分から勉強する子になるというのは、全ての親にとっての願いです。
しかし、現実はそんな簡単に事が進むことはありません。
親も誘導しながら学習習慣を定着させていくので、面倒なことの連続です。
ただ、その面倒さを越えるとあとは子どもが自分から学習計画を立てて勉強していくようになるので、最初がすごく重要になってきます。
とはいえ、親が教育熱心で家庭学習もしっかりやっているのに自分からテストや受験に向けて色々と計画を立てて勉強できない子もいます。
よかれと思ってやったことが全部裏目にならいよう、子どもの学力を受け止めつつ子どもの成長、自立心を考えて家庭学習を進めていきましょう。