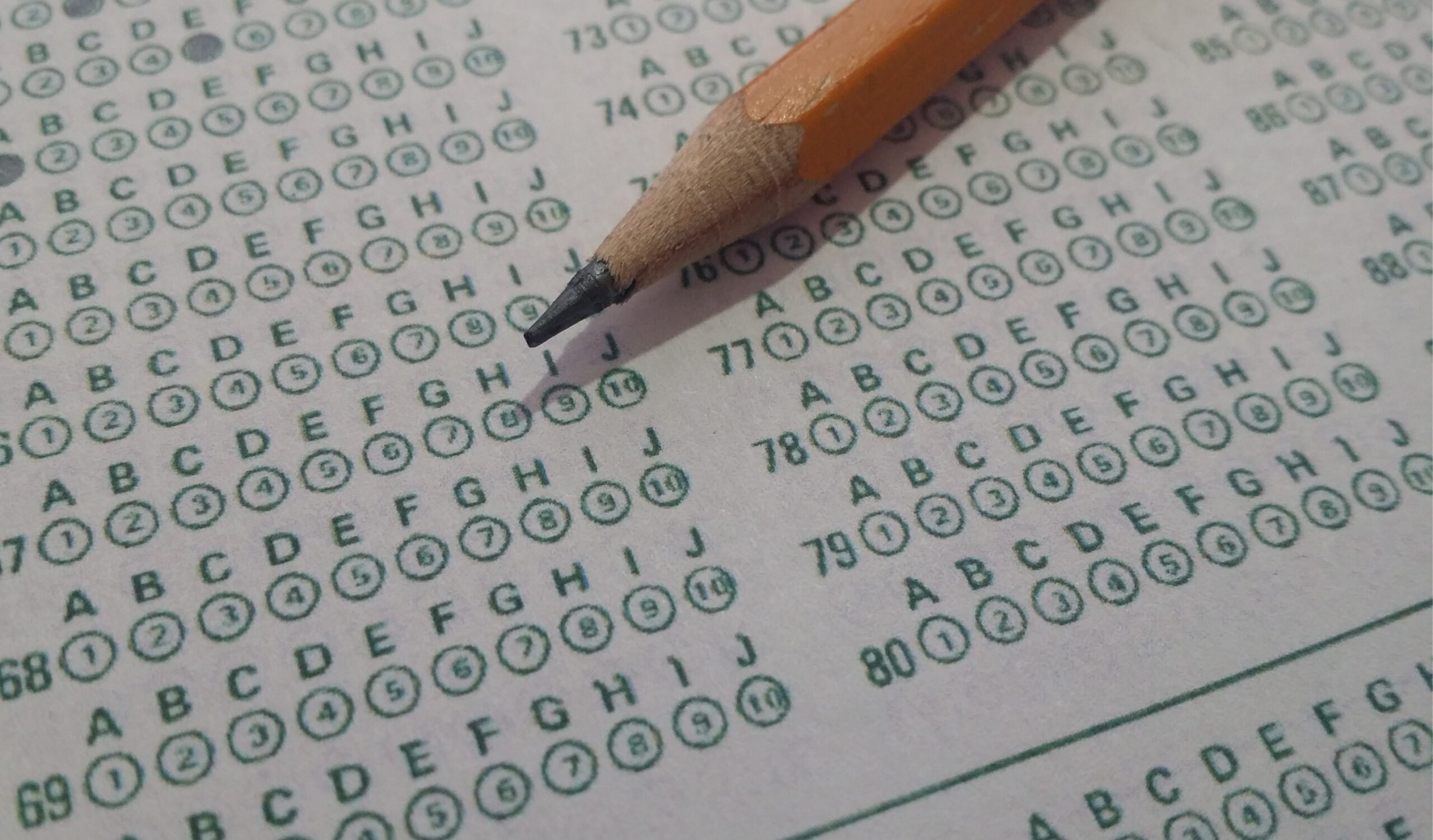今回は【賢い子の親の【ほったらかしにしている】を真に受けてはいけない】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
子育てをしていると、他の子よりも明らかに賢い子に出会うことがあります。
その時、少しでも参考にしたいと思い、【どんな風に子育てをしているのか】【家庭学習はけっこうさせているのか】と気になり、質問することもあります。
ただ、そういう質問をしても、賢い子の親ほど【何もやっていない】【ほったらかしにしている】と口にすることがほとんどです。
ご存じの通り、日本では子どもの学力について自慢と受け取られないように気をつける文化があります。
謙遜するのが美徳と言われ、たとえ学校のテストで満点を連発していても、図工が得意でも、運動神経がずば抜けていても【うちの子は天才なんです】と口にする親に出会う確率は極めて低いです。
そのため、周囲から【すごいですね】【どのように育てていますか?】と聞かれても、【いえいえ、うちはほったらかしですよ】と控えめに答える親が圧倒的に多いです。
しかし、実際には、教育方針がしっかりあったり、家庭学習をする上でのルールを決めていることがほとんどです。
つまり、本当に【何もしていない】ということはないと思っていいでしょう。
賢い子の親が【何もやっていない】【ほったらかしにしている】と口にするのを真に受けてはいけないのは、実際には多くの“見えない努力”が積み重ねられていることが多いからです。
例えば、家庭内に学習しやすい環境を整えたり、生活リズムを安定させたり、本や会話を通じて知的好奇心を育てているケースがほとんどです。
親が意図的に教育していないように見えても、子どもの成長に必要な土台を無意識に築いている場合が多く、【なんだ、本当に何もしていないのか】と信じてしまい、子どもを放任すれば、学力差が広がる恐れがあります。
他人の言葉ではなく、子どものリアルな学力や性格、家庭内の環境をよく考えて【賢い子に近づく道筋】を考えることが大切です。
そこで今回は、賢い子の親は【ほったらかしにしている】の言葉に隠されている教育方針をご紹介していきます。
本人の自主性を重視している
まず、賢い子の親ほど本人の自主性を重視しており、【あーだこーだ】とガミガミ指示するということはしていません。
塾で出会った最上位層の親は、世間一般が思い描くようなガチガチの教育ママという方はいませんでした。
一見すると放任主義に受け止められることもありますが、親が真の学力や生きる力は【自ら考え、行動する力】によって育まれることを深く理解しているからです。
ただ教え込むのではなく、子どもが自分の意思で学びに向かうよう導くことが、長期的に見て最も効果的な教育だと捉えています。
親が一方的に【勉強しなさい】と言い続けても、子どもが心から納得していなければ、勉強は長続きしません。
とくに小学生の段階で親主導の勉強に頼ってしまうと、自分で考えて取り組む力が育たず、学力が一時的に伸びても、後に伸び悩む傾向があります。
一方、自主性を尊重された子どもは、【学ぶことは自分のため】と理解し、【やりたいからやる】という気持ちが原動力となり、学び続けるようになります。
自主性を尊重する教育では、子どもが自分で考えて選び、試行錯誤する経験が積み重なります。
普段の生活でも、宿題をするタイミングや勉強の方法を自分で考えることで、【どうすれば効率よくできるか】を自然と身につけていきます。
こうした経験をしていくことで思考力や判断力が強固となり、応用問題や日常生活の課題にも柔軟に対応できる力を育てていきます。
また、放任主義にみえても、子どもの自主性を重んじる家庭では失敗を否定せず、【どうすれば次はうまくいくか】を重視し、親子で一緒に考えます。
賢い子の親は、失敗こそが学びのチャンスだと理解しており、【挑戦することが大切】というスタンスで子どもと接しています。
成功ばかりを求める親の下では、子どもは伸び伸びと自分らしく勉強する、成長することはできません。
そして、常に親が先回りして正解を与えてしまうと、子どもは自分で判断する機会を失い、失敗を恐れ、避けるようになります。
【失敗をしても平気】と思っている子は、失敗を糧に成長を促す経験により、子どもは失敗を恐れず挑戦するマインドを成長しても持ち続けます。
現代社会では単に知識を持っているだけでなく、自分で考え、行動し、他者と協力しながら課題を解決する力が求められる時代です。
公教育や入試でも【知識を問う問題】から【資料を踏まえて考える問題】が増えています。
親が全てを指示して育った子どもは、将来、進学や社会に出たときに【自分で動けない】【指示待ち】になりがちです。
一方で、自主性を持った子どもは、どんな環境でも自ら考え、目標に向かって努力できるため、変化の激しい時代にも対応できる生きる力が育ちます。
賢い子の親は【学力=知識の量】だけでなく、【自ら考え、学び、行動する力】こそが本当の意味での賢さであり、将来につながる力だと理解しているからこそ、子どもの自主性を重視しています。
自然に学ぶ環境が整っている
さて、賢い子の親は家庭内で子どもが自然に学べるよう、環境を整えています。
意識的または無意識でも日々の生活や会話、空間づくりを通じて【学びを特別なことにしない工夫】をしています。
親としては子どもに勉強を押しつけるのではなく、【自発的に知りたくなり】【自分から考えたくなる】ということを大切に、そういう気持ちを育てる環境を提供しようと考え、行動に移しています。
賢い子の家庭では【勉強は机に向かうもの】という固定観念に縛られず、日常生活そのものが学びの場となっています。
たとえば、料理中に分量を一緒に計算したり、買い物中に価格やお金のやりとりを通じて算数の感覚、量当たりの値段や割合を学んだり、日常の会話で歴史や社会の話題が出たりします。
こうした習慣は、子どもにとって学びが自然なものとして定着するため、特別な準備や努力をしなくても、知的好奇心が刺激されやすい環境になります。
そして、賢い子の親は、子どもの【なぜ?】【どうして?】という疑問を大切にし、本を渡して【勝手に調べなさい】ということはせず、一緒に調べたり考えたりする傾向があります。
また、家に図鑑や本、地図、パズルなど、知的好奇心をくすぐるアイテムが自然に置かれていることも多く、子どもは遊びの延長で学べるようになっています。
とにかく、子どもの好奇心の芽を見逃さず、潰さず、学びにつなげる力があり、結果として子どもの学力を底上げしています。
勉強に関しても、親から【勉強しなさい】と言われる前に自ら学ぶことが多く、親子の衝突も起きにくいです。
賢い子の親は【特別な教育をしているわけではない】と口にしていても、その家庭には学びが自然に根づく環境が整っています。
それは、親の姿勢、家庭の雰囲気、生活習慣、価値観が一体となって、子どもの学ぶ力を育てているからです。
賢い子の親は、子どもが子どもらしく楽しく学んで欲しいという気持ちを持って子育てをしているので、【ほったらかしにしている】と謙遜だけれど、ある意味本当に気がついたら自分で勝手に勉強している子に育っていることもあります。
ただ、こうした教育方針、環境の下にいたらすぐに子どもが自発的に勉強するようになるわけではなく、それこそ子どもが乳幼児期の頃からそういう環境をしっかり作っていこうという意識を持っているので、【ほったらかしにしている】という言葉を真に受けないようにしてください。
親子で見えない努力をしている
ところで、賢い子の親は、子どもが自分で考えて動く力を信じています。
宿題や学習についても、手取り足取り教えるのではなく、【自分でやり方を工夫させる】【時間管理をさせる】など、あえて手を出さない場面を大切にしています。
しかし、これは放任とは異なり、【見守る】【待つ】ことを意味しています。
この【見守る努力】は一見すると何もしていないように見えますが、実際は親の方に忍耐力が求められるキツイ、サポートでもあります。
この【待てるかどうか】が子どもの自習性、学習意欲や達成感を持てるかどうかのカギを握っていると個人的には感じています。
結果を求めてしまう親は、どうしても誘導する、先回りをしてしまうところがあります。
塾でも、短期間でサクッと成績が改善することを強く望む親に出会ったことはありましたし、おそらくそういうことを考えている、期待している親の方が多いと思います。
しかし、本当に賢い子の親というのは、【親が陰ながら見守る】を徹底し、必要最小限の口出しにとどめているところがあります。
コスパやタイムパフォーマンス重視とはちょっと違う感覚を持っていると思ってください。
そして、子ども本人は知らなくても、親は学校や塾の情報を収集したり、教材を選んだりと、陰でたくさんの準備をしています。
また、子どもの性格や得意、不得意に応じて、声かけや接し方を調整するなど、表には見えない細やかな配慮をしていることが多いです。
これらの努力はあえて口に出されることはなく、【自然にうまくいっているように見える】形で現れるため、周囲からは【何もしていない】と誤解されがちです。
ただ、【何もしていない】【ほったらかしにしている】と語る親の多くは、実は“見えない努力”を日々重ねています。
それは、子どもの力を引き出すために必要な【信じて任せる】【環境を整える】【適切に関わる】という、表に出にくい関わり方の積み重ねです。
そうした見えない努力こそが、子どもに無理なく学力や思考力を育て、結果として【賢い子】を育てる力になっています。