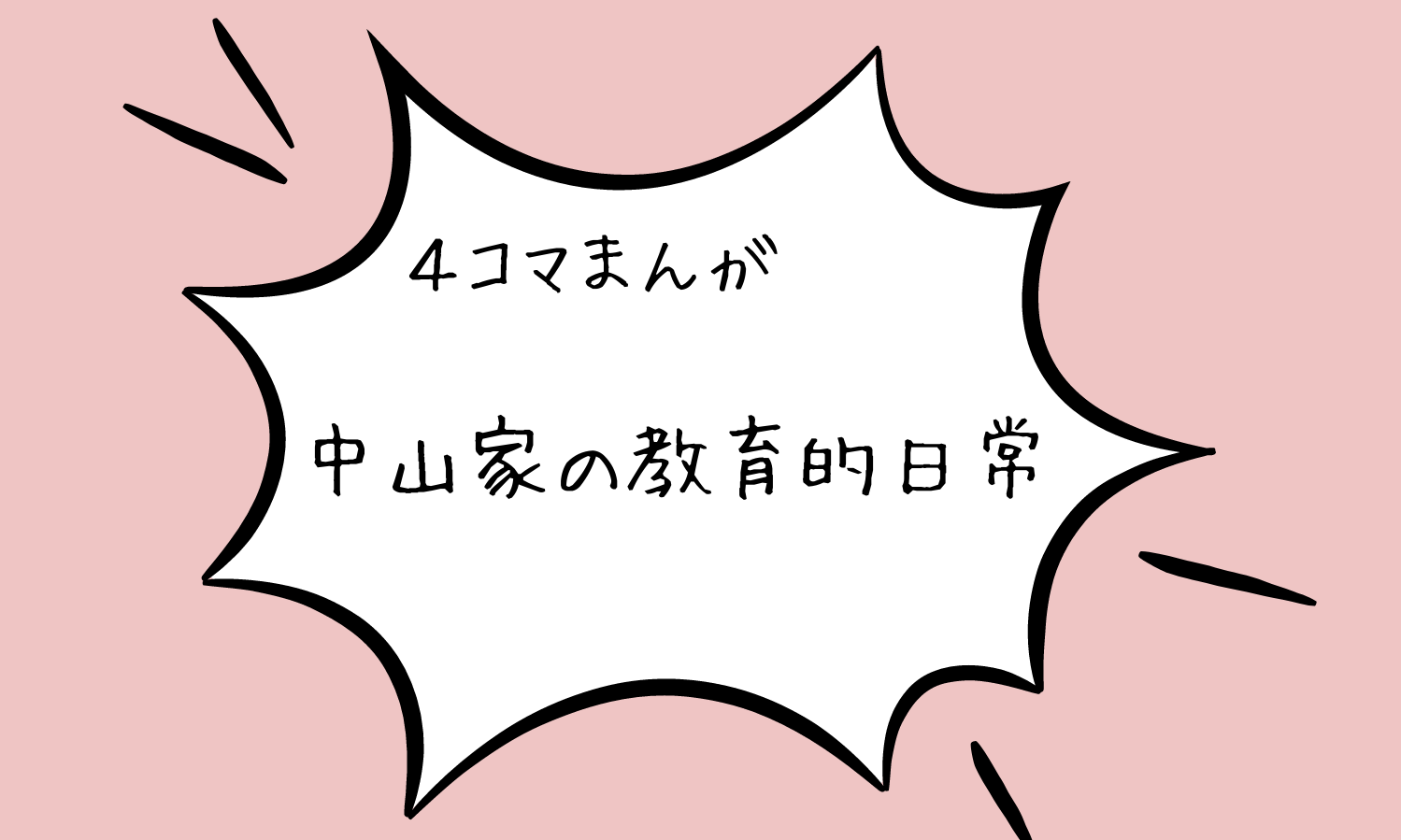今回は【高学年での学力差は小学3年生までの差 苦手をぶっ飛ばす方法】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校高学年になると、子どもたちの学力差が一気に表面化してきます。
今まではなんとなく同じように授業を受け、同じように宿題をこなしていたのに、ある日を境に【うちの子、なんだか点数が下がってきている?】と感じるようになる。
これは、決して珍しいことではありません。
我が家の子ども①②③が小学4年生、5年生頃に【算数のテストの差がヤバイ】などの話を耳にすることが増えました。
ただ、その前触れともいえることは小学3年生の時に実は起きていたのです。
それは、漢字テストで再テストを受ける子、桁数の増えた四則計算でミスが多くて何度もやり直しをする子が1年生や2年生の頃よりも増えているという話。
小学4年生や5年生で明らかに出る差は、いきなり現れたように見えて、実は小学校3年生までの積み重ねの違いが原因です。
たとえば、文章を読むのが苦手なまま放置していた子は、問題文の意味を理解するのに時間がかかり、算数でも国語でもつまずきやすくなります。
計算のやり方は覚えていても、【なぜそうなるのか】【どの式を使えばいいか】がわからない子も、応用問題に太刀打ちできません。
学校の授業は基本的にクラス全体の平均に合わせて進むため、わからなくても流されてしまうこともあります。
テストの点数に現れて初めて、親も【思っていたより差がついていた】と気づくのです。
しかし、ここで大切なのは【今からでも巻き返せる】という視点です。
高学年で見えてきた学力差は、あくまでもこれまでの積み重ねの結果であって、これからの伸びしろを決めるものではありません。
今、どこに穴があるのかを把握し、日々の学習に親子で向き合うことで、十分に追いつき、追い越すことが可能です。
そこで今回は、高学年での学力差は小学3年生までの差である理由や、苦手を潰していく方法をご紹介していきます。
高学年の成績差は小3までの土台で決まる
まず、小学校高学年での成績差、学力差というのは時間を巻き戻して小学校3年生までの土台力の違いからきています。
【小学校高学年になって、急に勉強が難しくなった】
【これまで普通にこなせていたのに、最近テストで点が取れない】
そんな声が、4年生の秋頃から一気に増えてきますし、クラスの中で目に見えて差がつきはじめ、焦りや不安を感じている家庭も多いことでしょう。
ですがこの学力差は突然生まれたわけではありません。
その根っこは、小学3年生までの基礎学習の【理解の深さ】にあります。
小学3年生までの学び方、学んだ内容の使いこなしが、高学年での学力の伸びしろに直結しています。
ご存じの通り、1年生、2年生までは、学習内容が比較的シンプルです。
【暗記】【計算】【言われた通りに解く】といった表面的な理解でも、ある程度の点数が取れてしまいます。
実際、九九や漢字テストなど、短期記憶や繰り返し練習が得点に直結しやすいのがこの時期です。
しかし、小学校での3年間が終わり、4年生からはガラリと変わります。
算数では、割合・速さ・面積・体積・図形の角度など、【考えながら式を立てる】力が必要になります。
国語でも、説明文や意見文が増え、【読み取り→要約→記述】のように、文章全体を理解し、自分の言葉で表現する力が問われます。
つまり、知識のインプット型から、思考・活用・表現するアウトプット型へと求められる力が変化するのです。この切り替えにうまく対応できた子は、高学年でもグングン伸びていきます。
一方で、【表面的な理解】にとどまっていた子は、ここで壁にぶつかりやすくなります。
では、どんな単元・学び方が高学年の伸びに関わってくるのでしょうか?
教科別にポイントを整理してみましょう。
算数では、小学1年生の繰り上がり・繰り下がりのある筆算、算数でも文章題の読み取りと、どの計算を使うかの判断力を鍛えるスタートラインです。
そして、四則計算と同じくらい重要なのが単位です。
小学1年生からコツコツと学んでいく単位は、意外と苦手にしている子は多く、しかも【その時やっただけ】で、定着しないことも珍しくありません。
時間、長さ、重さ、かさの感覚と単位換算をしっかり理解、そして定着させることが肝要です。
算数の中でも苦手とする子が多い図形は、中学では入試問題で必ず出る証明問題を筆頭に、超有用単元です。
小学校低学年で絶対に苦手意識を持たせないと決めて、基本的な図形の性質、辺や角に対して理解させるよう市販の教材や無料教材を駆使していきましょう。
一方、国語はひらがなの読み書きはできていても、発音、つなぎの【を】と【お】、【ず】と【づ】などで混乱している子もいます。
ちなみに、国語が得意な我が家の子ども②も小学校低学年の頃はこの辺りの知識がボロボロで、かなりしっかりと家庭学習でカバーした思い出があります。
低学年の宿題の鉄板である音読も、正直言うと子ども目線では面倒なものですが、【言葉の意味を理解しているのか】を確認しながら音読をすると語彙力が鍛えられていきます。
そして、塾に通っていると、みっちり勉強するけれど、学校ではサラッと学ぶ程度の【主語・述語・修飾語など文の構造の理解】は小学生の時に基本的なものを理解していると、中学に進学してからだいぶ楽です。
漢字・語彙・ことわざなど言葉の知識の蓄積も、家庭で学校プラスアルファしていると、子どもの身を助けることになります。
文章の要点をつかむ練習を市販の教材を使用して【何が大切なのかを見抜く力】を身につけていくと、国語力が伸びやすくなります。
これらはすべて、当たり前のようで奥が深い学びです。
単に正解を出すだけでなく、【なぜそうなるのか】を考えたり、【こういう場面ではどう応用するのか】を想像したりすることが、小学3年生までにできていると、その後の学力の伸び方が違ってきます。
当たり前のことですが、基礎があやふやなまま高学年を迎えると、問題文を読んでも何を聞かれているのかがピンとこない、計算はできても、【どうしてこの式なのか】がわからない、答えは書けても、自分の言葉で説明できない、間違えても何が原因かわからず、改善につながらない、ということが次から次へと起きます。
そして、いちばんの問題は、【ちゃんとやってるのに、結果が出ない】という経験から、子どもが自信を失ってしまうことです。
【自分は勉強が苦手なんだ】と思い込み、さらに考えることを避けるようになる悪循環に陥りかねません。
これは決して、【小3までに完璧にしないとダメ】ということではありません。
大切なのは、今の段階で【どこに戻るべきか】を親子で見直し、必要な基礎にもう一度丁寧に取り組むことです。
土台の穴を見つけて、ひとつずつ埋めていけば、高学年からでも十分に伸びていけます。
家庭で始める立て直し戦略
さて、高学年になってから学力に不安を感じ始めたら、最初にすべきことは【今どこでつまずいているのか?】を見つけることです。
学校では平均的な授業進度に合わせて進みますが、子ども一人ひとりがつまずいている箇所は異なります。
表面上では【理解できているように見える】問題も、実は根本的な考え方が身についていないということがよくあります。
こうした理解の穴は、学校の授業だけで埋めるのは難しく、家庭でのフォローが非常に重要になります。
親子で一緒に【何が苦手なのか】【なぜ間違えたのか】を言語化・可視化し、具体的に学び直すプロセスを作ることが、学力の再構築には不可欠です。
そこで、家庭学習を見直すポイントをご紹介していきます。
1.短時間×毎日のルーティン化をする
まず最初に短時間×毎日のルーティン化していきましょう。
家庭学習は長時間やることより毎日やることが大切です。
1日30分でも構いません。
【今日は計算問題3問と漢字2つ】など、無理のない分量で日々の学習を習慣づけてください。
継続することで、学ぶ姿勢が自然と身につきます。
2.ノートの使い方を見直す
なかなか、小学生だと最初は難しいかもしれませんが、ノートの使い方を考えてみることも大切です。
正解を書くことが目的ではなく、【どうやって考えたか】【どこで迷ったか】など、プロセスを残すノートを心がけましょう。
思考の痕跡を残すことで、自分の弱点やクセに気づけるようになります。
3.【間違い直しノート】を作る
間違えた問題をそのままにせず、どうして間違ったかを自分の言葉で振り返り、正しい解き方を整理する練習をします。
親が先回りして答えを教えるのではなく、ヒントを出しながら【自分で気づく】ことが大切です。
4.親子で週1学習会議を開く
1週間の学習の振り返りと、次週の目標を一緒に話し合う時間を持ちましょう。
【できたこと】【わからなかったこと】を共有するだけでも、子どもは安心し、モチベーションを保ちやすくなります。
親としては、子どもの勉強への取り組み方や考えを知ることができ、将来の進路進学での【そんな話聞いていない】といった衝突を防ぐことにもつながります。
5.タブレットやアプリを上手に使う
計算や漢字など反復が必要な学習には、学習アプリも効果的です。
ただし、思考力が求められる読解や応用問題については、親と対話しながら進めるアナログ学習の方が効果的です。
あくまで補助として活用しましょう。
そして、高学年になると、【なんでこんな問題もわからないの?】と親が戸惑うことも増えてきます。
しかし、子どもには子どもなりの理由があります。
代表的なつまずき例と、家庭でできる対応策をまとめました。
1.すぐに【わからない】と言ってあきらめる
【これやってみて】と問題を出したとき、子どもがすぐに【わからない】【無理】と言って手を止めてしまうことはありませんか?
このような反応の背景には、【自信をなくしている】【考えることに慣れていない】といった原因があります。
とくに、低学年までは比較的簡単に正解できた子ほど、ちょっと難しい問題にぶつかったときに【わからない=できない】と短絡的に判断してしまいがちです。
こういうとき、親がすぐに答えを教えるのではなく、小さなヒントを出して、考え続けるきっかけを与えることが大切です。
【最初の一歩だけ一緒にやってみよう】【どこまでならできそう?】と声をかけ、最後までやり切る体験を積み重ねることで、粘り強さや思考力が育ちます。
2.問題文をよく読まず、読み飛ばして解こうとする
【文章題をちゃんと読まずに、適当に答えてしまう】という子もよく見られます。
この場合、原因は大きく2つあります。
ひとつは読解力の不足、もうひとつは【読むのが面倒くさい】という意識です。
長い文章や複雑な条件が出てくると、内容をきちんと理解する前に、勘や思い込みで答えを書いてしまうケースが多く見られます。
これを防ぐためには、問題文を音読させる習慣が効果的です。
音読することで、内容の流れが頭に入りやすくなりますし、集中力も高まります。
また、文章の中で大事な部分(たとえば【何を求めているか】や【条件】)に線を引かせる練習をすることで、読み飛ばしや勘違いを防げるようになります。
3.ケアレスミスがやたらと多い
【わかっているはずなのに、ちょっとしたミスで点を落としてしまう】
これは、高学年になると非常に多くなる悩みです。
計算の符号を間違える、単位をつけ忘れる、問題の聞かれ方を見落とすなど、内容そのものというより注意力や確認不足が原因のケースです。
このような場合は、【もっと気をつけて!】と叱るのではなく、ミスの傾向を一緒に分析することが大切です。
【このミス、前もやってたね】【こういうときに間違いやすいみたいだよ】と、あくまで冷静に客観的に伝えましょう。
そして【次はどんな工夫をすれば防げそう?】と問いかけ、本人に考えさせることで、再発防止につながります。
これらのつまずきは、どれも一時的なものです。
しかし、放っておくと【勉強が苦手】【どうせやってもムダ】というマイナスの思い込みにつながってしまいます。
子どもの様子をよく観察し、【どこで困っているのか】【どうすれば自信を持てるか】を意識したサポートが、長期的な学力の伸びにつながっていきます。
英語は苦手意識ゼロで始められる最高の教科
ところで、小学5年生になると英語を教科として勉強しますが、この英語という教科が学力差のきっかけとなることもあります。
小学校で勉強しているという前提で始まる中学英語は、親世代の頃とは比べ物にならないくらい難しくなっています。
【英語はまだ何も対策をしていない】【中学に入ってから丈夫か?】
そんな不安を抱える親は多いですが、英語は、小学生のうちに得意科目に変えやすい教科のひとつです。
他の教科で差がつき始める高学年こそ、英語が巻き返すチャンスになる可能性があります。
なぜなら、英語は他の主要教科と違い、小学校4年生、5年生から本格的に触れる子がほとんどで、スタートラインがほぼ同じだからです。
算数や国語のように、【積み重ね】が点数に直結する教科と違って、多少なりとも英語教育をしてきている子は先を走ってはいるものの、まだ小学校高学年での差が少ないのが英語の特徴です。
だからこそ、小学生の間に丁寧に基礎を学んでいけば、英語だけは一気に得意教科へと変わっていきやすいです。
では、具体的にどのように家庭で英語に取り組めばいいのでしょうか。
難しく考える必要はありません。
まず大切なのは、【聞く・まねる】ことです。
つまり、英語の音を楽しむことから始めるのがポイントです。
1. 毎日5分、英語を【聞く】だけでOK
昔からの英語学習の鉄板であるNHKの【基礎英語】や、YouTubeにある英語の童話・歌などを活用し、毎日5分間、英語の音声をなんとなくでも耳に入れるだけで十分です。
日本語とまったく違う音に慣れていくことが、後々のリスニング力につながっていきます。
2. 英語の音に慣れてから、文字へ
最初からアルファベットの書き取りや文法を教え込もうとすると、子どもは【英語=難しい】と感じてしまいがちです。
まずは【聞く・話す】の経験を重ね、英語の音とリズムを身体で覚えることを重視しましょう。
フォニックスの動画などを使えば、自然と正しい発音も身につきます。
3. 親子で一緒に楽しむことが最大の効果
英語学習で一番の成功ポイントは、親が一緒に楽しむことです。
たとえば、英語の絵本を一緒に読んでみたり、聞こえた単語をまねして発音してみたり、英語の単語カードや、英語のしりとりなどで遊びながら触れることで、子どもは自然と英語を【楽しい】と感じるようになります。
4. 中学英語の予習的に、少し先取りもOK
小学生のうちに、少しだけ【中学英語】に触れておくのも効果的です。
たとえば、【I am ~】【You are ~】【This is ~】などの簡単なbe動詞や、【Do you like ~?】のような疑問文の形を親子で会話の中に取り入れてみましょう。
意味が完璧にわからなくても、フレーズとして慣れておくことが、中学での理解をぐんとラクにしてくれます。
最後にサラッとまとめをしていきます。
子どもの学力差を感じてきたとき、親としては不安や焦りを感じるのが当然です。
でも、そこで【どうしよう…】と心配するだけでなく、まずやるべきは【何がつまずきの原因なのか?】を一緒に探ることです。
それが、学習の立て直しの第一歩になります。
具体的には、次のようなことから始められます。
〇小学3年生までの学習内容を振り返る【基礎の見直し】
〇子どもの理解度を把握しやすくする【学習の見える化】
〇苦手な単元は無理に進まず【戻って学び直す姿勢】
〇英語は苦手になる前に親しむことを意識し、家庭習慣として取り入れる
大切なのは、【テストの点数を上げる】ことよりも【学ぶ楽しさや達成感を積み重ねること】です。
親が応援者として寄り添うことで、子どもは【自分はできる】と思えるようになり、自信が少しずつ育っていきます。
高学年からの巻き返しは決して遅くありません。むしろ、【今、気づけたこと】こそが最大のチャンスです。
親子で前向きに【学び直し】に取り組み、家庭が安心して挑戦できる場所になれば、子どもは確実に変わっていきます。
明日の成績ではなく、5年後、10年後の子どもの姿を見据えて、焦らず、でもあきらめず、一緒に前を向いていきましょう。