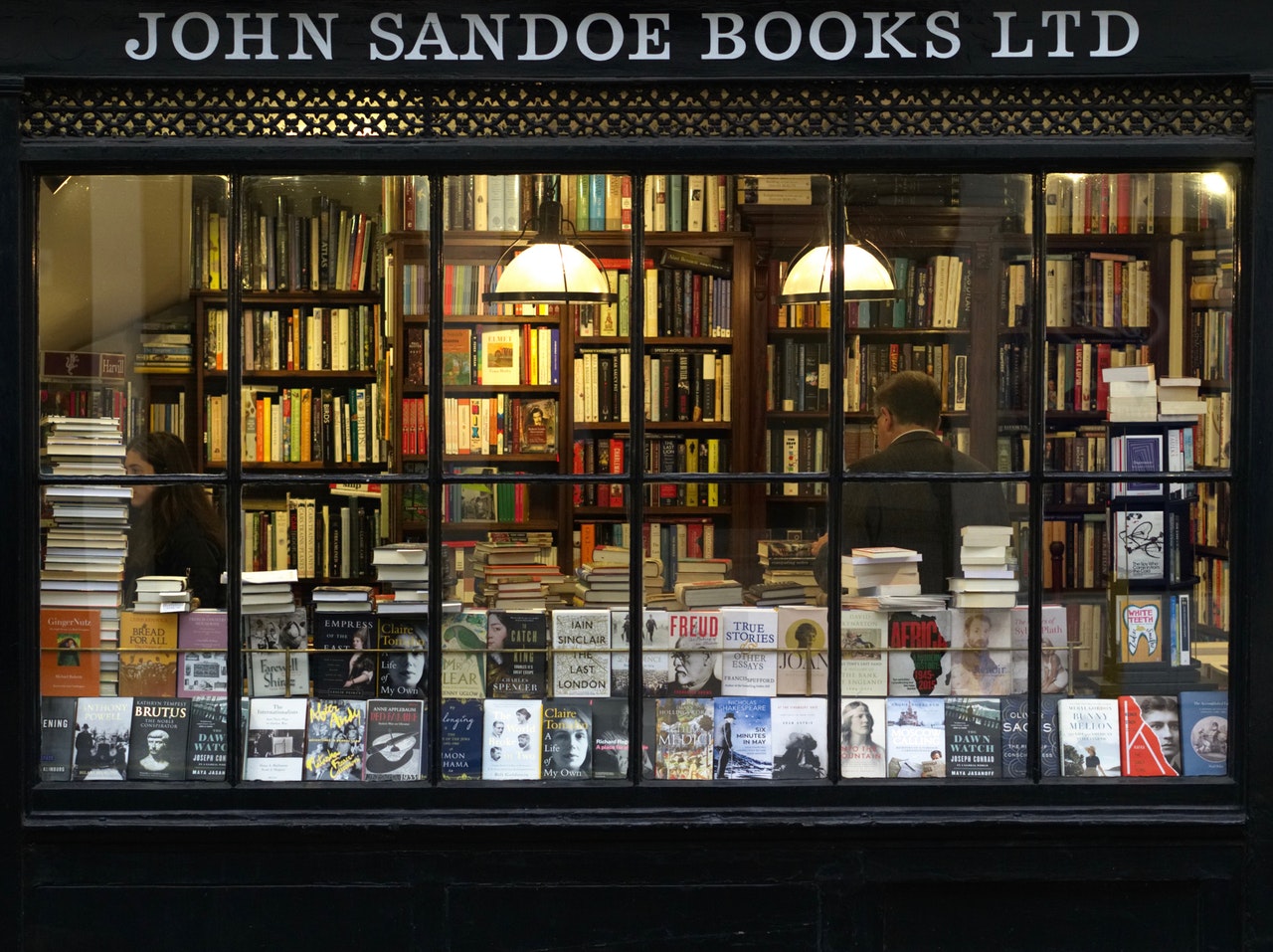今回は【小4の壁で停滞した時の対処法】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小4の壁、10歳の壁というのは目には見えないものですが、子どもが成長する時に主に勉強面で感じる【テストの点数が下がっている】【苦手とする単元が増えてきた】という躓いてしまうことが多くなる現象です。
躓いた単元をそのまま放置してしまうと学力差が広がり、成績が低下していくという親としては大変気になる問題です。
なんとかスムーズに乗り越えて欲しいと願っていても、全員が無事に乗り越えられるわけではありません。
たとえ真面目に家庭学習をしてきた子でも、【よく分からない】と感じる学びが出てきます。
小学4年生の学びは抽象的な概念が求められるようになり、多くの子は戸惑いを覚えます。
算数で言えば四捨五入のがい数、図形などパッと見て答えが浮かんでくるものではない単元、つまり思考力が問われるジャンルを勉強していくので、【よく分からない】の連続になりがちです。
こうした学びの内容が変化していく中で、成績が低迷する子もいます。
とくに中学受験を予定している、または学区の中学に進学してその中で成績上位層となりトップ高校への進学を目指しているという家庭にとっては【小4の壁で停滞してしまった】は避けたいところです。
子ども①②③のどの時も、低学年の頃は成績が良く、とくに計算スピードで無双状態だった子が少しずつクラスの中で目立たなくなってくる、他の成績が良い子と同じような扱いになっていく、中には【まぁまぁできる子になった】ということが起きていました。
【うちの子は勉強ができる方】と安心していたのに、どうもそうではなくなるというのは家庭の一大事です。
ただ、親の方はいったい何が起きているのか掴み切れないところもあります。
気がついたら悪くなっているというのは珍しいことではなく、原因が分からない恐ろしさを親は感じてしまいます。
慌てて塾に入る、通信教材を取り寄せるということをしたいかもしれませんが、急がば回れという言葉があるように、一旦は落ち着いて【この停滞期をどのようにして脱出すべきか】と考えてください。
今回は、小4の壁という難所で子どもの学力をどのようにレベルアップさせていけばよいかをご紹介していきます。
小学校3年間の総点検をする
まず、小4の壁で停滞した状態を打破するには、小学校3年間で学んできたことで【どこかに理解不足の単元がある】と総点検してみてください。
漢字の読み書き、算数の計算や単位換算や図形、理科と社会や生活科で【よく分かっていなかった】というところが隠れているはずです。
国語で言えば漢字がうろ覚えの字があったり、文章を読むのが遅い、何が書いてあるのかよく分からない。
算数では時計の読み方や時刻、長さの単位やカサの単位がよく分からず、何となく問題を解いていたという子も意外と多いです。
また、桁数が増えた計算でミスを連発する子もいるので、正確に計算できる力をつけるよう毎日計算ドリルに取り組むことをしていく必要があります。
理科と社会は3年生から勉強をスタートするので、割とまだ基本的な内容が多かったりしますが、東西南北といった方位、社会では3年生の最初の頃に地図記号を勉強するので、【子どもは地図を読めるか】と確認してください。
今の子どもたちは家に地図がないという中で成長しているので、日常的に地図を読む機会はほぼありません。
子どもにとっての地図はスマートフォンやカーナビの地図であり、【地図の上は北を意味する】というのは学校の授業でしか勉強しない知識かもしれません。
小学校生活の最初の3年間はまだ勉強も簡単だと思いがちですが、社会の地図のように中学でも使用する知識を勉強していたりと軽視することができません。
そして、分からないことを放置していると小学4年生以降の勉強が苦労の連続となります。
小学4年生になり、宿題もやって家庭学習もしているのに成績が停滞している時は【リアルタイムで学んでいること以外にも不調となっている原因があるはず】と思い、総点検をしていきましょう。
総点検をする際は季節休みに販売される総まとめドリルを活用することや、インターネット上の無料教材を印刷するなどして、普段の勉強の他に時間を割いて3年間をおさらいするようにしてください。
算数の文章問題を解かせる
さて、小学校4年生で一番何の教科で差が出るかと言えば、それは算数です。
子ども①②③全員が口を揃えて【一番出来不出来が分かるのが算数】と言っています。
私も小学生時代に勉強が苦手な子が小学3年生の割り算で【よく分からない】と口にしていたのを覚えています。
4年生になると抽象的な概念を使う学びが増えていくことから、子どもの思考力次第で理解度も変わるという学問的な要素が強まります。
そうした中で、読解力も大切になってくるので【先生の言っていることが分からない】【教科書を読んでも分からない】と感じる子も増えてきます。
我が子の思考力や読解力がどの程度のものなのか把握するために、算数の文章問題を解かせることをしていきましょう。
今の小学校では低学年の頃から算数でも文章問題を解きます。
我が家の子ども③が低学年や3年生の時に【この問題文にあてはまる式はどれですか】という、文章を読ませてから、この状況に相応しい式を選択するという文章題満載の算数の宿題が出されたことがあります。
子ども③に【文章を読むのも嫌な子はいない?】と聞いたところ、【読むのがめんどくさいと言って適当に選んでいる子もいる】と言っていました。
文章題は読むのに抵抗感を抱くかどうか、というものがあります。
何の抵抗感もない子は普通に問題を読んで答えを選んでいきますが、問題に文章があるだけで嫌になる子もいます。
計算だけで何とかなる算数は小学4年生で終わりとなり、中学数学も【計算できればそれでOK】ではなくなります。
算数の文章問題を苦手にしているのは小4の壁の停滞だけの問題ではなく、【その先の学び】にも影響してくるので早めに対処しましょう。
文章題に特化したドリルはどの学年にもあるので、書店に出向いてレベルをチェックして家庭学習に取り入れてみてください。
子どもの話をよく聞く
ところで、小学4年生というのは勉強面で悩みを抱える子も増える一方で、心の成長も著しく親に歯向かう、つまりは反抗期に突入する子もいます。
我が家でも子ども①が小学4年生の時に反抗期となりました。
ただ、つい最近本人と話をしたら【自分はそんなに反抗期はなかったな】【本当にうちは家内安全だよ】と口にしていたので、自分にとって都合の悪いことは全部記憶からなくなってしまっているようで、私はちょっと呆れてしまいました。
そんな子ども①の小4の頃は学校のテストは問題はないものの、塾の友達のレベルの高さに驚き、【どうしたらあんな風になれるのか】【でも自分は勉強頑張りたくない】【サクッと努力して皆に近づきたい】と色々と悩んでいました。
反抗期なので、自由に思ったことを口にできなくなっていたのと、不安を素直に言えない自分や頑張れない自分に腹が立って私に八つ当たりをするという状態になっていました。
心が落ち着いていないと成績が停滞している時にいくら勉強させようとしても、親の努力が裏目に出ることや空回りしてしまうことがあります。
成績が上向きにならないと親は心配してしまいますが、まずは子どもの話に耳を傾けて不安を取り除くことをしていってください。
ダイレクトに学力向上につながるわけではありません。
しかし、心の重荷がなくなれば清々しい気持ちで勉強に取り組むことができます。
小4の壁は色々と問題が噴出する時期です。
勉強面をどうにかする、学習量を増やそうと動き出すことも大切ですが、それと同じくらい子どもの気持ちに気がつく、子どもの会話もちゃんとするようにしましょう。
そうすることで、停滞期を脱する期間が短くなるかもしれません。