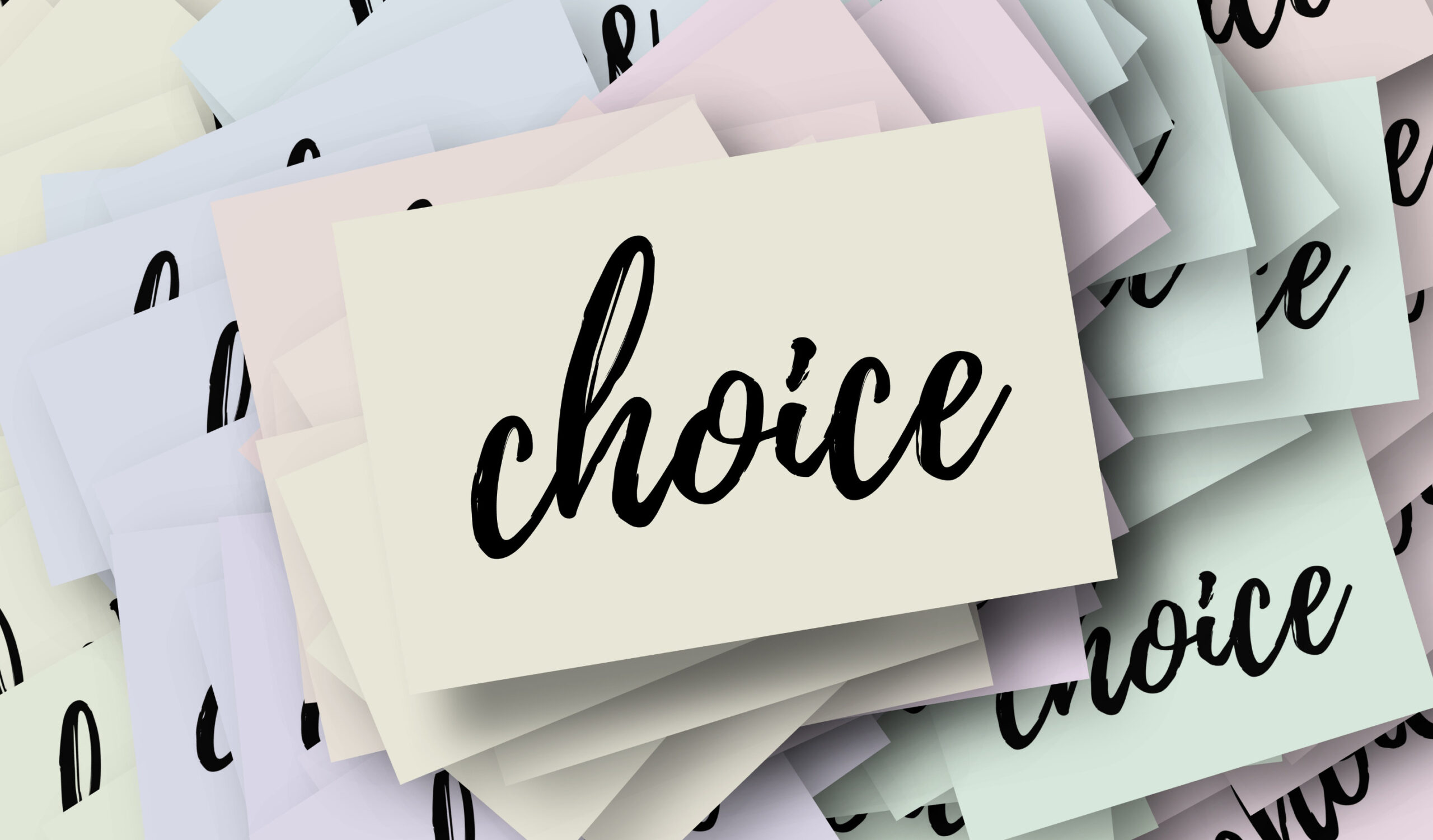今回は【中学数学を乗り越える!【伸びる子】が実践する3つの学習習慣】と題し、お話していきます。
YouTube版
エール出版社より本が出版されました。
小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。
kindle出版しました。unlimitedでも読めます。
完全に無料で読めるコミックエッセイです。
↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。
キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。
内容は一緒です!
透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】
新作です。
kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!
ありがとうございます。
小学校から中学校に進むと、多くの子が最初に戸惑う教科が【数学】です。
これまでの算数では具体的な数の操作が中心でしたが、中学数学では抽象的な関係を扱うようになります。
文字式・方程式・比例反比例・関数など、公式を暗記するだけでは太刀打ちできず、考え方そのものを理解し、応用できる力が求められます。
小学校の算数が得意であっても、中学での数学で成績が伸び悩むという子は意外といます。
数学では定期テストで記述問題が出されることもあります。
【素数とはどういうことか説明しなさい】といった問題が中学1年生の最初の定期テストで出されることも珍しくありません。
数学は高校受験でも合否を握る重要教科です。
中学に入って早々につまずくか、それとも得意科目として伸ばせるかの分かれ道は、子どもの人生を帰るくらいの意味を持ちます。
ただ、その分かれ道を決めるのは単に勉強する時間だけではなく、実は学習習慣の質にあります。
中学数学で成功する子は、ただ勉強時間が多いわけでも、天才的なセンスがあるわけでもありません。
【理解の深め方】【ミスへの向き合い方】【考え続ける姿勢】という3つの習慣が根づいているのです。
そこで今回は、最初に【正しい学習習慣の鉄則】、次いで【つまずき別の対処法】、最後に【親子の心構え】を紹介します。
数学に苦手意識を持つ子でも、習慣を整えれば必ず【できる】が増え、自信と興味がつながります。
そ
の第一歩を一緒に見ていきましょう。
つまずきを未然に防ぐ【正しい学習習慣】3つの鉄則
まず、中学数学でつまずく子どもたちの多くは、【理解力が足りない】わけではありません。
問題の本質は、学び方の習慣にあります。
小学校までは、与えられた問題を正しく計算できれば点数が取れましたが、中学では【なぜそうなるのか】【どんな関係があるのか】を自分で考える力が求められます。
ここで、ただの暗記型学習を続けてしまうと、次第に内容が複雑になる中で理解が追いつかなくなってしまうのです。
逆に、最初の段階で【考える習慣】【振り返る習慣】【継続する習慣】が整っている子は、どんな単元に進んでも自分で整理しながら学びを積み重ねられます。
数学の得意・不得意の差は、この日々の学び方の質によって生まれているのです。
【正しい学習習慣】は、才能や時間の長さよりもずっと大きな力を持っています。
授業で理解した内容を自分の言葉で整理し、間違いを恐れず原因を探り、短時間でも毎日考える。
この3つを意識するだけで、理解は一気に深まります。
ここでは、そんな思考力を育てるために欠かせない3つの学習鉄則、【理解を言葉で説明する】【間違いを主役にする】【短時間でも毎日続ける】を紹介します。
①【理解を言葉で説明できる】まで落とし込む
中学数学で本当に理解を定着させるためには、【わかった気】ではなく【自分の言葉で説明できる】レベルまで落とし込むことが欠かせません。
問題が解けるだけで満足してしまうと、少し形を変えた応用問題で必ずつまずきます。
なぜなら、手順だけを覚えても、根本の考え方を理解していなければ応用がきかないからです。
たとえば【2x+3x=5x】という式を、【同じ文字がついているから足せる】と自分の言葉で説明できる子は、仕組みを理解しています。
逆に、【そういう決まりだから】と覚えているだけの子は、他の場面で応用できません。
数学の力は説明力と比例します。
つまり、【どうしてそうなるの?】と自分に問い返せる力が、考える力の原点なのです。
家庭でできるサポートとしては、答えの正誤よりも【どう考えたのか】を尋ねることが大切です。
【ここはどうしてこうなったの?】【他のやり方もあるかな?】と質問するだけで、子どもは思考を整理し、理解を深めることができます。
また、ノートの端に理由メモを書くのもおすすめです。
【符号を変えたのは移項したから】【分母をそろえたのは比較しやすくするため】など、短く言葉にすることで、思考が可視化されます。
数学は【言葉で考える教科】です。
公式を覚えるだけでなく、自分の言葉で説明できるようになることで、学びは再現可能な理解に変わります。
この力が、どんな単元にも対応できる本当の基礎力をつくるのです。
②【間違えた問題】を主役にする
多くの子どもたちは、勉強のとき【できた問題】を中心に復習します。
しかし、実際に学力を伸ばす鍵を握っているのは、間違えた問題のほうです。
なぜなら、ミスには【理解できていない部分】や【思考のクセ】といった、今後の成長に必要なヒントが詰まっているからです。
つまり、間違いは【弱点】ではなく【伸びしろ】そのもの。
そこに真剣に向き合う姿勢こそが、数学を得意にする子の共通点です。
まず意識してほしいのは、【間違いノート】を作ることです。
間違えた問題をそのまま放置せず、ノートに写して【どこで・なぜ・どう間違えたか】を書き込みましょう。
たとえば、【符号の確認を忘れた】【問題文をよく読まなかった】など、原因を具体的に言語化することで、次に同じミスを防ぐ力がつきます。
これは単なる反省ではなく、自分の思考パターンを見える化する作業です。
また、家庭での声かけも大切です。
【また間違えたの?】ではなく、【どんなところで迷ったのかな?】【次はどう直せそう?】と、分析を促す質問をしてみましょう。
失敗を否定ではなく発見として扱うことで、子どもは安心して挑戦できるようになります。
間違いを恐れる子は、考える前に諦めがちになります。
しかし、ミスを受け入れ、そこから学べる子は、着実に理解を深めていきます。
【できた】よりも【どこでつまずいたか】を大切にすること。
それが、数学を真に得意にするための第一歩なのです。
③【短時間でも毎日】考える習慣を持つ
数学が得意な子ほど、勉強時間の長さよりも【続けるリズム】を大切にしています。
1日3時間ダラダラとまとめて勉強するより、10分でも毎日机に向かう子のほうが、理解は定着しやすいのです。
なぜなら、数学の力は【思考の筋肉】と同じで、使わないとすぐに鈍ってしまうからです。
間隔を空けずに繰り返すことで、考える感覚が保たれ、記憶も長く残ります。
とくに中学生になると、学ぶ内容が一気に増え、1回の授業で扱う情報量も多くなります。
そこで大切なのが、少しずつでも考え続けること。
朝の10分、寝る前の5分でも構いません。
【昨日の問題をもう一度解く】【1問だけじっくり考える】
たったそれだけでも、思考が日常の中に根づいていきます。
また、続けるコツは時間ではなく行動を決めることです。
【夕食後に1問】【お風呂の前にノートを開く】など、生活の中に学ぶタイミングを組み込むと、無理なく習慣化できます。
学習が【特別なこと】ではなく【いつものこと】になったとき、思考力は自然に育ちます。
親も【今日はどんな問題を考えたの?】と一言添えるだけで十分です。
量より継続、速さよりリズム。
数学の基礎力を支えているのは、実はこうした日々の小さな積み重ねなのです。
短時間でも毎日考えることが、学びを持続可能にする最強の習慣です。
成績が伸び悩んだ時の【つまずき別】対処法3選
さて、中学数学の勉強を続けていると、誰もが一度は【頑張っているのに成績が上がらない】と感じる時期に直面します。
これを【限界】と捉えてしまうか、【修正のチャンス】として前向きに受け止められるかで、その後の伸び方が大きく変わります。
実は、成績が伸び悩む原因の多くは【努力不足】ではなく、勉強の方向が少しズレているだけです。
間違った方法で時間をかけても、成果は比例しません。
大切なのは、【どの段階で理解が止まっているか】を正しく見極め、ピンポイントで修正することです。
ここでは、とくに多い3つのつまずきタイプ、①計算ミスが多い、②文章・関数問題が苦手、③応用問題になると手が止まる、に分け、それぞれの特徴と具体的な対処法を紹介します。
つまずきは、弱点ではなく成長のサインと前向きに受け止めてください。
どこで苦戦しているかを知れば、そこが【伸びるポイント】に変わります。
焦らず原因を見極め、正しい方法で軌道を整えていきましょう。
①【計算ミスが多いタイプ】精度を上げる【見える化】練習
数学の成績が伸び悩む原因として最も多いのが、計算ミスや理解不足による小さなつまずきです。
一度のミスは大きな問題に見えませんが、そのまま放置すると積み重なり、応用問題や文章題で急に手が止まってしまいます。
ここで大切なのは、ミスを【失敗】として否定するのではなく、成長のチャンスとして扱うことです。
まず家庭でできる具体的な方法として、【間違えた問題を分類して整理する】ことが有効です。
たとえば計算ミスなのか、手順の理解不足なのか、問題文の読み取りミスなのかを分けるだけで、次に何を重点的に復習すべきかが明確になります。
さらに、同じ種類の問題をいくつか繰り返し解くことで、弱点を補強するだけでなく、解き方のパターンを身につけることができます。
また、子どもにただ解かせるのではなく、【なぜそうなるのか】を声に出させる習慣も重要です。
説明する過程で理解が浅い部分が浮き彫りになり、自分の言葉で整理することで理解が定着します。
保護者は答えをすぐに教えるのではなく、【どう考えたの?】と問いかけ、子どもの思考を引き出すサポートを心がけましょう。
小さなミスを放置せず、一つずつ丁寧に振り返る。
この積み重ねが、数学でのつまずきを未然に防ぎ、学力の底上げにつながります。
計算や基本理解の確認は、成績向上の第一歩です。
②【文章問題・関数が苦手なタイプ】図で見える構造をつくる
文章題や応用問題でつまずく子は少なくありません。
計算はできても、文章を読み解き、自分で方針を立てる段階で思考が止まってしまうケースが多いです。
ここで大切なのは、問題の理解から手順までを【分解して考える】習慣をつけること。
一度に全体を解こうとせず、問題文を小さなステップに分け、【何を求められているか】【どの情報を使うか】を整理させるだけで、見通しがぐっと明確になります。
家庭でできる具体策の一つは、問題文を声に出して読ませることです。
読み上げながら、子ども自身に【ここで何を計算する?】と問いかけると、抽象的な文章を具体的に落とし込む力が育ちます。
さらに、図や表を使って視覚化することも有効です。
数字や関係性を目で確認できるだけで、理解のスピードは格段に上がります。
また、最初から完璧を求めず、失敗を学びの材料として扱うことがポイントです。
一度で解けなくても、どの部分で迷ったのか、どの考え方を忘れていたのかを整理することで、次に同じタイプの問題に出会ったときの対応力がつきます。
親は【できなかった】ではなく【ここまで考えられたね】と、思考プロセスを認める声かけを心がけましょう。
文章題や応用問題は、思考力を育てる格好のチャンスです。
解法のパターンを覚えるだけでなく、【考え方を整理する習慣】をつけることで、数学の応用力は確実に伸びます。
③【応用問題に手が出ないタイプ】考える時間を恐れない
数学のつまずきは、多くの場合【苦手分野】を放置してしまうことから始まります。
一度理解が不十分な単元を後回しにすると、その先の学習にどんどん影響が出て、気づけば全体の理解が追いつかなくなるのです。
だからこそ、苦手を早めに把握し、短時間でも計画的に取り組むことが重要です。
家庭での具体的な工夫としては、まず【苦手リスト】を作ることから始めましょう。
単元ごとに、計算・文章題・図形など、どの分野でつまずきやすいかを可視化するだけで、優先的に学習すべきポイントが明確になります。
次に、1回で完璧にしようとせず、短時間でも毎日少しずつ復習するのがコツです。
たとえば1日5分、苦手な問題を解き、間違いの理由をノートに書く。これを数日続けるだけでも、理解が着実に定着していきます。
また、親子で学習の振り返りをすることも有効です。
【今日はどの問題がわからなかった?】【どう考えたら次は解けそう?】と声をかけ、思考プロセスを整理する習慣を作ると、子どもは自分の弱点を自覚し、改善策を自分で考えられるようになります。
重要なのは【間違えたことを責めず、次の学びにつなげる】姿勢です。
苦手分野の克服は、短期間で完璧にするよりも、日々の積み重ねで自信をつけることがカギです。
家庭での工夫を取り入れるだけで、子どもは数学の苦手意識を少しずつ乗り越え、応用問題にも前向きに取り組める力を身につけられます。
数学を得意科目にするための【親子の心構え】
ところで、【うちの子、数学が苦手で…】という相談は非常に多いですが、その裏には共通する思い込みがあります。
それは、【数学はセンスや頭の良さで決まる】という誤解です。
しかし実際は、数学の得意・不得意を左右するのは親子の学びへの姿勢です。
どれだけ公式を覚えても、どれだけ問題を解いても、【考えることが楽しい】と感じられなければ、学びは長続きしません。
逆に、結果よりも過程を大切にし、考える時間そのものを肯定できる環境があれば、数学は誰でも得意科目に変えられます。
ここでは、子どもの数学力を内面から伸ばすための3つの心構え、①スピードより粘り強さを重視する、②ミスを学びの機会に変える、③応用問題を楽しむ姿勢を育てる、を紹介します。
この3つは、単なる【勉強法】ではなく、人生全般に通じる考える力の育て方です。
数学が得意になるということは、同時に【困難に向き合う力】が育つということです。
①【スピード】より【考える粘り強さ】を重視
中学数学で成績が伸びる子に共通しているのは、問題を解くスピードよりも【考える粘り強さ】を大切にしている点です。
多くの親は、早く答えを出すこと=理解の証だと思いがちですが、実際には途中で諦めず、自分の頭で考え抜く力こそが、長期的な学力につながります。
なぜなら、数学は公式や解法パターンを覚えるだけでは対応できない問題が多く、思考のプロセスをしっかり理解することが求められるからです。
家庭で意識したいのは、解答までの時間よりも【どれだけ自分の考えを整理できたか】に注目することです。
たとえば、わからない問題に出会ったとき、すぐ答えを見るのではなく、【どの情報を使えるか】【どんな方法でアプローチできるか】を声に出して考えさせます。
このプロセスを繰り返すことで、子どもは自然に自分の思考のクセや弱点に気づき、次の問題にも応用できる力を身につけます。
また、親が手を出しすぎないことも重要です。
【ここはこうやるんだよ】とすぐ答えを教えるのではなく、ヒントを出して自分で試行錯誤させる。
その積み重ねが、数学の粘り強さと問題解決力を育むカギになります。
スピードよりも考える力を優先することで、子どもは一見難しい問題にも諦めず取り組む姿勢が身につき、学習効率と理解の定着が同時に高まります。
数学を得意科目にするための土台は、まさにこの【粘り強く考える習慣】にあります。
②【ミス】を【学習の機会】として歓迎する
数学で力を伸ばす子の共通点は、間違いを恐れず、むしろ【学びのチャンス】として捉えている点です。
間違えることは恥ずかしいことではなく、理解の足りない部分や思考のクセを知る絶好の機会です。
この姿勢を家庭で育むことが、子どもの数学力を大きく左右します。
具体的には、子どもが解答を間違えたとき、すぐに訂正するのではなく【どうしてこうなったのか】を一緒に整理します。
【どこで迷ったのか】【どの手順を間違えたのか】を言葉にさせることで、理解の穴を明確にし、次に同じミスを繰り返さない力が身につきます。
親は【失敗したね】ではなく、【ここまで考えられたのはすごいね】と、努力のプロセスを認める声かけを意識しましょう。
さらに、間違いを記録しておくミスノートも有効です。
問題と答え、間違えた理由、正しい考え方を簡単に書き込むだけで、自分の弱点が可視化され、復習の効率も格段に上がります。
繰り返し振り返ることで、間違いは恐れるものではなく、成長のバロメーターとして機能します。
数学は正解を出すだけの教科ではなく、【考え方を育てる教科】です。
ミスを歓迎し、分析し、次に活かす習慣をつけることで、子どもは自分で問題解決する力を身につけ、難しい問題にも前向きに取り組めるようになります。
間違いを学習の機会と捉える受け止められるかどうかが、数学を得意科目にするための重要なステップになります。
③【応用問題を楽しむ】気持ちを育てる
数学を得意にする子どもは、応用問題に出会ったときに【難しい】と感じるのではなく、挑戦する楽しさを感じています。
応用問題は、公式を覚えるだけでは解けないことが多く、自分で考え、試行錯誤する力を育む絶好の機会です。
その経験が、数学に対する自信と前向きな姿勢を作ります。
家庭でのサポートとしては、まず子どもが応用問題に取り組む際、【できなくても大丈夫】と伝えることが重要です。
間違いや失敗を恐れず挑戦できる環境は、思考の幅を広げ、柔軟な解法の発想につながります。
また、問題を解いたあとには、解法を比べたり別のアプローチを考えたりする時間を設けると、思考の深まりが加速します。
さらに、応用問題はゲーム感覚で取り組ませるのも効果的です。
たとえば【この問題、他のやり方で解けるかな?】と問いかけ、違う方法で解く楽しさを経験させると、自然に論理的思考が身につきます。
親が一緒に考えたり、ヒントを出したりして、答えだけでなく思考のプロセスを楽しむ習慣を作ることも大切です。
応用問題に対する前向きな姿勢は、数学だけでなく他教科の学びにも応用できます。
挑戦する楽しさを体感し、自分で考える時間を増やすことが、子どもの数学力を飛躍的に高めるカギとなります。
家庭での工夫で、応用問題を【苦手】ではなく【面白い挑戦】に変える。
これが、数学を得意科目にするための最終ステップです。
【できる子】より【考え続けられる子】を育てよう
中学数学で伸びる子に共通しているのは、【ミスを恐れず考え続ける姿勢】があることです。
今回紹介した【正しい学習習慣】、【つまずき別対処法】、そして【親子の心構え】はいずれも、数学を点数のための教科から思考力を育てる教科に変えるための視点です。
数学の力は、一夜で身につくものではありません。
しかし、日々の学び方を少し変えるだけで、確実に未来が変わります。
【わかった気】で終わらせず言葉で説明する、間違いを主役にして振り返る、短時間でも毎日考えるという3つの習慣は、すぐにでも家庭で始められる最強の学び方です。
また、成績が伸び悩んだときは、【努力が足りない】と責めるのではなく、どこで考えが止まったのかを一緒に探すことが何より大切です。
計算・文章・応用、それぞれのタイプに合った修正法を見極めれば、停滞期は必ず突破できます。
そして忘れてはならないのが、親のまなざしです。
【速さより粘り強さを】【ミスは学びの機会】【応用は楽しむもの】という3つの心構えが家庭に根づけば、子どもは安心して考えに集中できるようになります。
結果だけを評価するのではなく、【どう考えたか】を認めてあげることで、数学への自信と興味が生まれます。
中学数学は、ただの教科ではありません。
論理的に考え、あきらめず挑戦し、自分の力で道を切り開くためのトレーニングです。
焦らず、比べず、今日の一問を大切にしましょう。
【できない】から逃げずに【考え抜く】その姿勢こそ、未来の学びを支える最大の武器になります。
結果は、考え続けた先に、必ずついてきます。