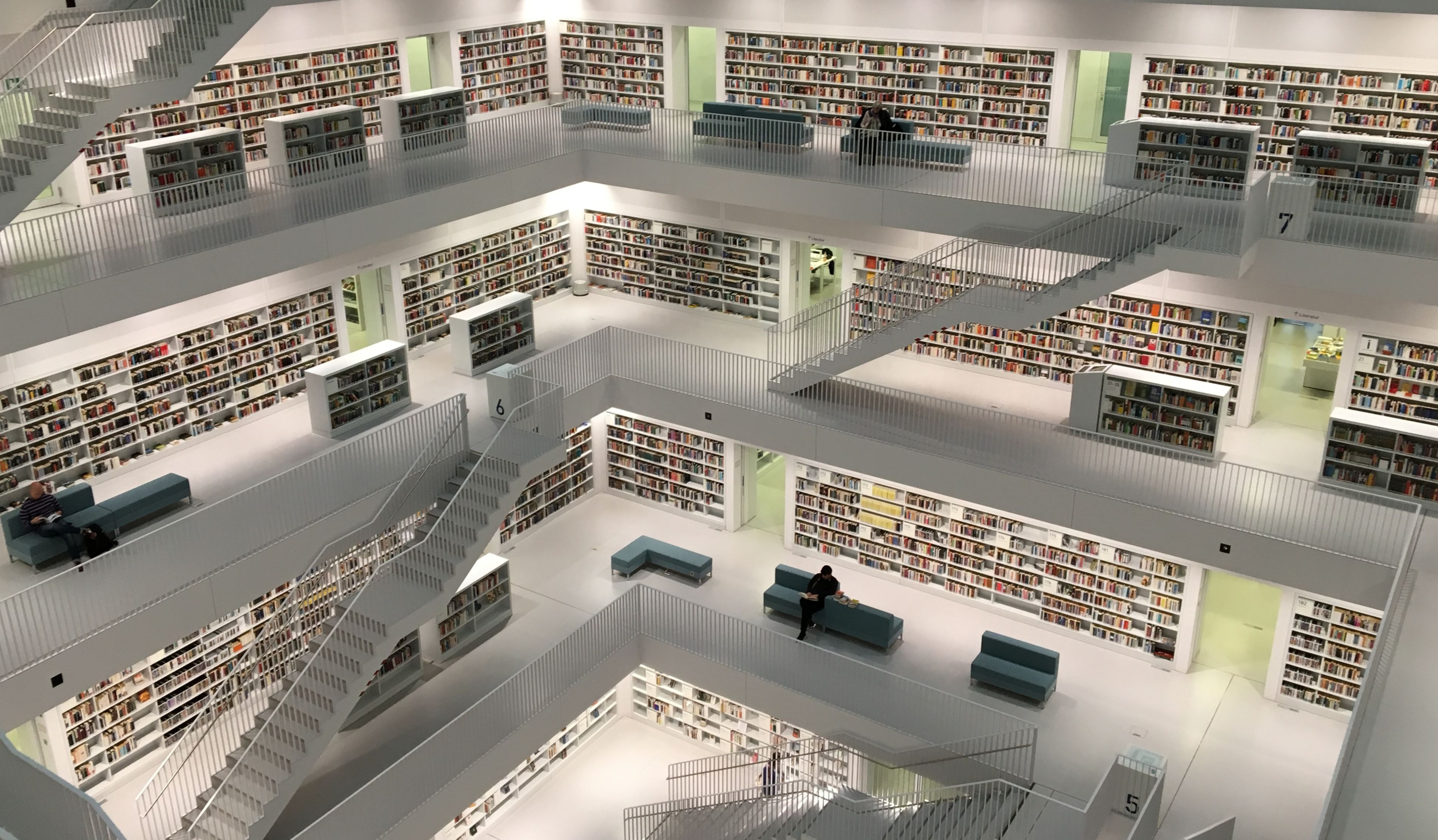今回は【小学生時代の学力は幻想? 中学で本当に伸びる子の共通点とは】と題し、お話をしていきます。
YouTube版
小学校で【優等生】と評価されていたのに、中学に進学すると成績が伸び悩み、思うような順位が取れない。
これは珍しい話ではありません。
一方で、小学校では特に目立たなかった子が、中学に入った途端に成績を伸ばし、学年上位に入ることもあります。
この差は、単なる努力量の違いでは説明できない部分があります。
よく考えると、小学生時代に評価されやすい【テストの点数】や【提出物の丁寧さ】は、親のサポートや短期的な詰め込みでカバーできてしまうことも多く、本質的な学力や思考力とは別物です。
中学では教科の難易度が上がり、応用力や自学自習の力、そして継続する力が求められます。
提出物の期限なども、中学生となり反抗期や思春期に突入した子どもが、親に言い忘れていたり、干渉を嫌うようになれば小学生時代のようにスムーズに事が運ぶわけでもなくなります。
つまり、そこではじめて子どもの本物の学力、実力が問われるのです。
そこで今回は、【中学で伸びる子】が小学生時代にどんな土台を築いていたのかを明らかにしながら、親が今どのように関わればよいか、勉強への向き合い方をどのように育てればよいかを、問題点・改善策を通してお伝えしていきます。
なぜ小学生の学力は中学で通用しなくなるのか
まず、小学校では成績優秀、先生からの信頼も厚く、【うちの子はこのままいけば安心】と思っていたのに、中学生になると急に成績が伸び悩み始めるという経験をする家庭は少なくありません。
子ども自身も【頑張っているのに結果が出ない】と焦りを感じ、親も戸惑いや不安を抱えることになります。
では、なぜ小学生時代に良い成績を取っていた子が、中学で思うように結果を出せなくなるのでしょうか?
それは、小学校の学習が知識を覚えることを中心としたシンプルな構造であるのに対し、中学では考えながら解く複数の条件を整理するといった思考力や応用力が求められるからです。
ここでは、小学生の【優等生】が中学で躓く原因について、3つの問題点から深掘りしていきます。
■問題点①:【覚える】だけで何とかなっていた学習習慣
小学生の学習では、中学、高校の勉強の根幹部分を担う土台です。
土台を蔑ろにできないものの、その中でも学力差は出来上がっていきます。
ただ、学年が上がって難易度はアップするにしても、テストの大半が基礎知識の確認や計算の正確性を問うものであるため、【暗記型】や【ドリルなどの問題集】を学習の軸にしてもある程度の成果が出やすいという特徴があります。
漢字や計算、理科社会の基本用語を繰り返し覚えるだけで高得点が取れるため、【覚えること=勉強】と思い込んでしまう子も少なくありません。
しかし中学生になると、文章問題や応用問題が急増し、単純な暗記では通用しなくなります。
小学生時代の土台がしっかりしていても、プラスアルファの力がないと中学の勉強に対応するのが難しくなります。
算数から数学へ、短文読解から長文読解へと進む中で、求められるのは【なぜそうなるのかを理解する力】や【与えられた情報をどう使うかを判断する力】です。
暗記型のまま中学に進むと、【わかっているはずなのに解けない】という壁に直面します。
これは決して子どもの努力不足ではなく、学び方そのものが中学の学習にフィットしていない可能性があります。
小学生のうちから、漢字練習、計算、覚えるだけでなく、理由を説明したり考えたりする習慣を育てる必要があります。
■問題点②:親が段取りをすべて用意していた
小学生のうちは、親が宿題の確認をし、塾の送迎をし、テスト前には計画を立ててサポートする家庭も多いでしょう。
たしかに、子どもが自分で管理できない間は、親の関与は必要不可欠です。
しかし、その【やってもらう】状態が長く続いてしまうと、子どもは自分から学習に向き合う力を身につける機会を失ってしまいます。
中学になると、部活動や友人関係、スマートフォンの使用など、生活面の選択肢が一気に広がり、自己管理能力が求められます。
にもかかわらず、【誰かに言われないと動けない】【どうやって勉強すればいいかわからない】状態では、学習面で大きく遅れを取ってしまいます。
つまり、小学生時代に【手厚くサポートしすぎた】ことが、かえって子どもの自立を妨げる要因になるのです。
親がやるべきことは、全てを整えることではなく、【任せる経験】を少しずつ増やしていくこと。
自分で考えて動く力が、長期的な学力の伸びを支える土台になります。
■問題点③:教科ごとの深さへの理解が乏しい
小学校では、教科ごとの学びの深さを十分に意識しないまま進んでしまうことがあります。
たとえば、国語では音読や語句の意味をなぞるだけ、算数では公式を覚えて機械的に問題を解くことで【できた気になっている】状態です。
しかしこのような表面的な理解は、中学の学習にはつながりません。
中学では、国語であれば登場人物の心情や筆者の主張を読み取る【読解の深さ】、数学であれば複数の条件を整理して論理的に解く【思考のプロセス】が求められます。
理科や社会も単なる暗記から一歩進んで、【なぜそうなるのか?】を問う問題が増えてきます。
つまり、小学校でなんとなくできていた子ほど、中学での【深く理解する】学びに移行できず、成績が頭打ちになりやすいのです。
大切なのは、小学生のうちから【なぜ?】【どうして?】と問いを立て、考える習慣を家庭でも育てていくこと。
これが、教科を使いこなす学力へとつながっていきます。
中学で伸びる子に育つために必要な子どもの改善習慣とは
さて、小学生のうちは【できる子】と言われていたのに、中学生になると成績が思うように伸びなくなる子がいる一方で、学年が進むほどに力を発揮していく子もいます。
この差を生むのは、小学生時代に何をどのように学んできたかに他なりません。
ただ正解を出すことや、テストで良い点を取ることを目的にしてきた子は、応用や思考力が問われる中学の学習で壁にぶつかります。
そこで重要になってくるのが、子ども自身が持つ【考える力】【学ぶ姿勢】【自走する力】の3つの基盤です。
これは、いわゆる地頭や才能ではなく、日々の学習の中で意識的に育てることができる力です。
とくに、小学生の段階からこの3つの力を鍛えておくことができれば、中学に入ってからも安定して成績を伸ばし、上位層に食い込んでいくことが可能になります。
ここでは、そんな【伸びる子】に共通する3つの学習習慣を具体的に紹介していきます。
■改善策①:間違いから学びを得る【振り返り力】
小学生のうちは、間違いを【恥ずかしい】【ダメなこと】と捉える傾向が強くあります。
しかし、学力を伸ばす上で本当に大切なのは、間違えたあとにどう振る舞うかです。
間違いをチャンスと捉え、【なぜ間違えたのか】【どこで思い違いをしたのか】【次に同じような問題に出会ったときはどうするか】を考える習慣が、確かな学力をつくります。
この【振り返り力】は、中学の学習で必要不可欠な自学自習の土台にもなります。
中学以降は先生が一つひとつ丁寧に解説してくれる時間は限られます。
自分の間違いを自分で分析し、解き直す力がなければ、同じパターンで繰り返し失点することになります。
日々の学習では、【○つけをして終わり】ではなく、【×の理由】をノートに書かせたり、親が子どもに問いかけたりして、学びの質を高める工夫を。
小学生の段階でこの力が習慣づけば、中学生になっても成績を伸ばせる自立した勉強ができる子に育っていきます。
■改善策②:【わかる】ではなく【説明できる】まで仕上げる習慣
テストで点が取れていると、つい【わかったつもり】になりがちですが、本当に理解できているかを見極めるには、【説明できるかどうか】が大きな鍵です。
誰かに自分の言葉で説明することで、記憶は整理され、思考の定着も深まります。
特に算数や理科では、【なぜそうなるのか】【なぜこの式を使うのか】といった背景を理解しているかどうかで、応用問題への対応力が変わります。
国語であれば、本文の要点をまとめたり、登場人物の気持ちを筋道立てて話す訓練が、【読み取る力】や【書く力】に直結します。
家庭でできる実践方法としては、今日習ったことを親に説明する、学習ノートにまとめ欄を設けて自分の言葉で再整理するなどが効果的です。
学校や塾ではできない、日常の中でのアウトプット機会を増やすことが、たしかな理解力と表現力を育てます。
■改善策③:長文・複数情報を処理する【読み解く力】を育てる
中学に進むと、すべての教科で文章量と情報量が一気に増加します。
国語の長文読解はもちろん、理科や社会でも複数の資料を読み解いたり、数学でも問題文が長く複雑になるのが特徴です。
そこで求められるのが、【読みながら考える】力、すなわち読み解く力です。
この力を小学生のうちから育てておくことが、中学以降の安定した学力につながります。
読書をするのも良いですが、特に効果的なのは【情報の整理が必要な読み物】に触れること。
新聞の子ども向けコーナーや、グラフ付きの図解本、資料読み取り型の問題などが有効です。
また、読んだ内容を要約する、ポイントを一言で説明する訓練も、【読む力】と【考える力】を同時に高めます。
テストで高得点を取る子は、例外なくこの処理力が高いのです。
毎日の少しの積み重ねで、この読み解く力は着実に育てることができます。
親ができる本当の学力を支える関わり方
ところで、中学に入ってからも成績を安定して伸ばしていく子どもには、本人の努力に加えて、家庭の関わり方が大きな影響を与えています。
とくに教育熱の高い家庭では、子どもの将来を思うあまり、【もっと頑張らせなければ】【できる子に育てなければ】と、知らず知らずのうちにプレッシャーをかけてしまっているケースが少なくありません。
もちろん、親が学習に関心を持ち、サポートする姿勢は非常に大切です。
しかし、その関わり方によっては、子どもの本来の伸びる力を奪ってしまうこともあります。
頑張る方向を間違えれば、せっかくの努力が空回りしてしまうのです。
ここでは、子どもを【潰さずに伸ばす】ために、親がどのようなスタンスで学習を支えるべきか、3つのポイントに分けて解説します。
学力の土台を強くし、将来にわたって自立した学習ができる子に育てるための、親のかかわり方の質を一緒に見直していきましょう。
■親の改善策①:正解よりも【考えた過程】を認める声かけ
成績が良くなる子どもは、間違えたことを怖がらず、粘り強く考える力を持っています。
この力を育てるために、親ができる最も効果的なアプローチの一つが、【結果】ではなく【思考の過程】を認める声かけです。
たとえば、テストを持ち帰った子どもに【何点だった?】と聞くのではなく、【どの問題が難しかった?】【どうやって答えを出したの?】と尋ねることで、子どもは自分の思考を言葉にする機会を持ちます。
これにより、自分の考え方に気づき、次回への改善策を自然と見出せるようになります。
さらに、【点数が良かったね】だけで終わらず、【この問題、工夫して解いたんだね】【最後まで考えたの、えらいね】といった具体的なプロセスへの評価が、子どもの内発的な学習意欲を高めます。
親の声かけが結果に偏ると、子どもは【失敗を避けよう】としがちですが、【考えたこと自体をほめられる】環境があれば、チャレンジを恐れず取り組めるようになります。
■親の改善策②:【勉強しなさい】よりも【どう学ぶか】を一緒に考える
多くの親がつい口にしてしまう【勉強しなさい】という言葉。
しかし、これは子どもにとっては漠然とした命令にすぎず、何をどう始めればよいのか判断できないことも多いです。
とくに小学生から中学生への移行期には、勉強のやり方を一緒に考えることが重要です。
たとえば、テスト前に【今日は何をどの順番でやる?】と問いかけることで、子ども自身が計画を立てる機会を持てます。
最初は上手くいかなくても、親が軌道修正をサポートすることで、少しずつ自分で学習の流れを組み立てられるようになります。
ここで大切なのは、親が【指示役】になるのではなく、【伴走者】の立場を取ることです。
アドバイスはしても、最終的な選択は子どもに任せる姿勢が、主体性の育成につながります。
自分で学ぶ方法を考えられるようになった子どもは、環境が変わっても、持続的に成績を伸ばすことが可能です。
小学生のうちからその力を育てていくことが、将来の学力の安定につながります。
■親の改善策③:結果ではなく【継続】を喜べる家庭づくり
【また100点だったの?すごいね!】と点数を褒めるのはよくあることですが、これは時にプレッシャーとして働いてしまいます。
とくに優等生タイプの子は、【次も良い点を取らなければ】【失敗できない】と感じてしまい、勉強が苦しさにつながることもあります。
それよりも意識したいのが、【継続していること】【日々の努力】に注目し、それを家族で喜べる文化をつくることです。
たとえば、【毎日机に向かって勉強しているの、すごいね】【昨日できなかった問題が、今日はできるようになったね】と声をかけることで、子どもは自分の中の変化に気づき、勉強そのものに自信を持てるようになります。
結果だけに注目する家庭では、成績が下がった瞬間にモチベーションが崩れやすくなりますが、【続ける力】に価値を置く家庭では、子どもは長期的な視点で努力を続けられるようになります。
勉強を【評価されるもの】から【自分の成長を感じられるもの】へ。
そんな家庭のあり方が、子どもの学力を底支えしていくのです。
【学び方を育てる】ことが、中学での飛躍につながる
小学生のうちに高得点を取っていると、【このまま中学でも順調にいけるだろう】と思いがちです。
しかし実際には、小学校での優等生が中学に入って急に成績が伸び悩むケースも少なくありません。
これは、点数や暗記に頼った表面的な学力だけでは、思考力・読解力・応用力が求められる中学内容に対応しきれないからです。
中学でも伸び続ける子どもたちに共通しているのは、日々の学習の中で【どうしてこうなるのか】【なぜ間違えたのか】と自ら考える習慣を持っていることです。
そしてそれを家庭で支えている親は、点数の上下ではなく学び方そのものに目を向けています。
中学での飛躍を見据えるなら、子どもの学力を【点数】ではなく【伸びる力】で捉え、継続と改善を喜べる家庭こそが、真に強い学習環境を育てていきます。